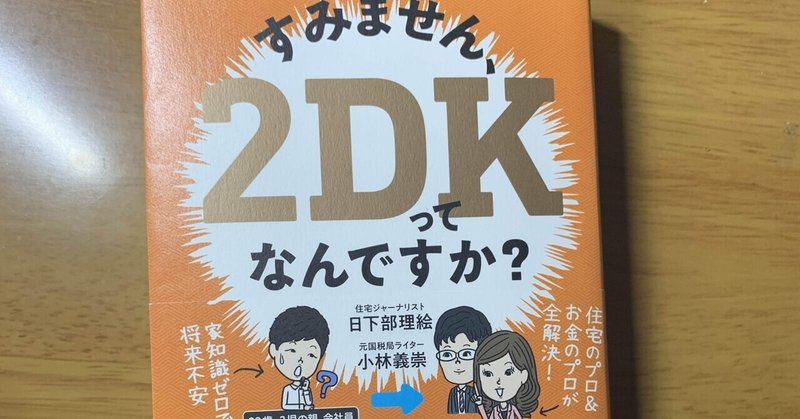
「すみません、2DKってなんですか?」を読んだ。
この前のシリーズの「金利ってなんですか?」がすごいわかりやすかったので本屋で見て購入しました。また、社会人として、住宅の知識は是非知っておきたかったこともあり、仕事に役立つ可能性を考えて読むことにしました。
要約をしていきます。
•一人暮らしでも結婚して2人で暮らすにも最初の家は賃貸が無難。いきなりマイホームはリスキー。
•日本では持ち家と賃貸の割合は6:4
•戸建て…一軒家。
•分譲住宅…広い土地を分割して同じような形で数多く作るとことでコストを低く抑えた住宅。
•分譲マンション…1つのマンションを何部屋かに分けてそれぞれ販売する。分譲割合に応じてその分の敷地利用権が得られる。
•戸建てとマンションではマンションの方が丈夫で耐用年数が長いこともあり固定資産税が高くなる。
•LDKとは居間を表すリビング、食事をするダイニング、キッチンの頭文字。2LDKだとすると、このLDKに窓や換気扇がある居室(寝室にできそうな部屋)が2つ加えられたもののこと。ただしLDKは居室が一部屋の場合は8畳以上、居室が2部屋の場合は10畳以上なければLDKと認められない。
•1kは一つの居室とキッチン。ワンルームは扉など仕切りがなく、キッチンと居室が繋がった部屋。
•屋根付きのものがベランダ、屋根なしものがバルコニー。テラスは庭付きの部屋。
•現時点で賃貸も持ち家もトータルでみるとコストにあまり差はない。賃貸は最後に物件が残らず、税金の優遇もないが気楽に引越せる。持ち家は逆。
•今、家を買うなら築浅•中古がおすすめ。設備も見た目も新しいのに価格が下がっているため。
•家の内見をする時は昼と夜のその地域の環境や近所の人の層をしっかり見ておく。ちなみに家の内見数は平均3件で決めるのが一般的。
•賃貸を借りたい時はその地元の不動産屋に行き、新築の家を買いたい時はデベロッパーやハウスメーカーへ行く。特にハウスメーカーは新築戸建てに特化している。
•マンションを買うとその区分所有者で管理組合に入り、外部の管理会社と委託契約を交わす。その管理会社がマンションの清掃や点検を行い、管理する。毎月、区分所有者が管理費を払う。つまり、マンションなら管理会社がしっかりしていれば自分でやらなくてもトラブルの処理やメンテナンスが楽。
•賃貸のメリット…移動しやすい、戸建ても借りれる、災害に対応しやすい。
賃貸のデメリット…自分のものにならない、分譲マンションの方が造りがしっかりしていて設備もいい、リフォームできない、高齢だと借りにくい、税金の優遇がない。
•持ち家のメリット…自分のものになる、好きにリフォームできる、住宅ローン控除など税金優遇有り、頑丈。
持ち家のデメリット…移動しにくい、維持管理にお金がかかる、売る時に手間もかかり買い手もあまりつかない。
•レインズ…不動産屋しか見られない物件データベース。物件情報が沢山のってる。
•片手仲介…売主、買主それぞれに別の不動産屋がついていて家の売買取引をすること。
•両手仲介…不動産の所有者から売却依頼を頼まれた不動産屋が自ら買い手を見つけてくること。不動産屋からすると売主、買主双方から仲介手数料が入る両手仲介の方がお得。
•分譲賃貸マンション…分譲マンションを所有者が住まずに貸し出している物件。住んでいた人が転勤で住めなくなり賃貸に出したりする。ただし、住める期間が限定されている定期借家である事が多い。その分相場よりも1.2割賃料が安い。
•UR…独立行政法人都市再生機構。URが管理する公的な賃貸住宅で建物の敷地が広く部屋も広めなことが多い。礼金、更新料など不要でU35など通常よりも家賃がお得になるプランもついている。
敷金…物件の担保代。家賃の滞納、修繕がなければ退去時に戻ってくる。家賃1、2ヶ月分。
礼金…オーナーへのお礼金。退去時に戻らない。オーナーから不動産屋への手数料に当てられることが多い。家賃の一ヶ月分。
共益費…マンションの維持管理に必要な費用。賃料の5〜10%前後に設定されている。家を借りる時は家賃だけでなく共益費の金額もみること。毎月払う金額は家賃と共益費の為。
専有部分が故障した場合は居住者が、専有部分が故障した場合はオーナーが原因とされる。
•デザイナーズマンション…名の知れた建築家がデザインしたもの。賃料は高め。
•網がかかっている部屋は鳩避けのためのネットの可能性あり。糞被害等があるので要注意。
•事故物件になるのを防ぐため60〜70歳になると賃貸は借りにくく、更新も難しくなる。そこで高齢者にはシニア向け賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅等の施設がある。生活相談員がついている。
•居候や同棲は契約違反。届出をしないといけない。
建売住宅…土地に建物が既に建っていて販売されている戸建て。
注文住宅…購入者が希望を注文してから作ってもらう住宅。間取り、構造、外観も自由に設計できる。その分値段が高くなる。
新築…建ってから一年以内のまだ誰も居住の用に供したことのないもの。新築と中古では値段に600〜900万の差がある。また、新築はハウスメーカーやデベロッパーから直接買うため仲介手数料がかからない。ただし、不動産屋で探して新築物件を買うと仲介手数料がかかる。法人から家を買う為、建物の対して消費税がかかる。土地にはかからない。
新築マンションの場合は最初に修繕積立金(マンションの維持、修繕の金)をまとめて払う。最初に50万程度払い、そこから毎月、一万円程度払う。
中古…個人が個人に対して住宅を売買しても課税されない決まりがある。よって、中古物件には消費税がかからない。ただ、不動産屋を介するための仲介手数料はかかり、売主が法人の場合には消費税がかかる。土地の購入には課税されない。
•床面積50m2以上の住宅で所得3000万以下なら住宅ローン控除が受けられる。
マンションと戸建てどちらが得か…
マンションのメリットは駅近で利便性に優れる、耐火性が強い、セキュリティが充実、24時間ゴミ出しできる、冬に暖かい。近隣との人間関係がドライなので楽。デメリットはペット禁止等マンションのルールがある、近隣の騒音、固定資産税が高い、使ってない設備等にも管理費の徴収がある。
戸建てのメリットは管理費等の徴収がない、リフォームが自由自在、子育て環境がいい、ペットを飼える、騒音が気になりにくい。デメリットは人間関係が意外と密、管理をすべて自分、防犯も自分、庭の手入れも自分。
ちなみに著者の人は断然マンションを進めている。
•住宅ローンで借りられる金額はその人の年収の5倍が目安。最初に頭金を多く払うことで後のローン返済額は少なく済み、利子を合わせた額も減る。頭金は物件価格の1.2割が目安。
•ローンの返済額は賃貸物件に住んでいたなら、その月額費用と同程度の金額を目安に。無理に住宅ローンを組むものでもない。
リバースモーゲージ…家を担保にしてその家の評価額の範囲内でお金を借りられる。亡くなったら物件が売却されて完済される。子供に家を遺さなくていい世帯にとってメリットが大きい。相続で家を譲られても赤字になる為。
住宅ローンの審査に通るポイントは勤続年数3年以上、80歳までに完済できるプラン、現在住宅ローン以外のローンを組んでいないこと、クレカのキャッシング枠は外す。
審査は取引が長い金融機関だと通りやすい傾向にある。ネット銀行は対面がない分審査基準が厳しく通りにくい。
フラット35…最長35年間の固定金利でローンが組め、職業や勤続年数の制限がなく、多くの人に貸すことを前提とした住宅ローン。変動金利よりも若干高めに設定されている。フラット35で組むよりも普通の住宅ローンで組んで方が有利なことが多い。
手付金…売買契約時に契約成立を示す証拠金として売主に支払うお金。最終的に住宅購入代金に充当されるので頭金になる。支払った後に買う側の都合で契約を止める時は手付金放棄となり返金されない。逆に売主の都合で契約を破棄したいとなったら手付金倍返しとなり支払った手付金の2倍の額を受け取れる。住宅購入代金の5〜10%が相場で相手を縛るためのもの。
住宅を購入するときは他にも契約書にかかる印紙税、登記費用、不動産取得税、仲介手数料等がかかる。
•住宅ローン特約は絶対つけておく。審査が通らなかった場合にペナルティなしで契約解除できる。
住宅ローンの変動金利…金利は半年ごとに見直されるが、返済金額については5年ルールで5年間変わらない。また、6年後の返済額を見直しよ時も前回返済額の125%を上限とする125%ルールがあり、見直し後の返済が見直し前の1.25倍を超えることはない。変動金利はあまり変わらない。
元利均等…元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定。最初のほうは金利ばかり払ってるイメージで中々元金が減らず元金均等に比べて返済額も期間も増える。
元金均等…元金だけが一定の返済。元金が減っていく分その元金につく金利も安くなっていく。最初の方は返済額が多いが毎月の負担はどんどん軽くなり早く返し終わり、返済額も元利均等よりも少なくてすむ。
•団信、火災保険、地震保険には入っておく。水漏れや天災等幅広くカバーしてくれる。ただし、損害割合によって金額も変わる。
•住宅ローンを組んだ家を人に貸して金をとるのら契約違反。ローンを完済したら抵当権をはずす。登記上ローン未返済となり、次のローン審査に影響が出るため。
•家を売りたい場合も不動産屋にいく。複数の不動産屋に行っていい。広告をはってもらえる。3ヶ月かけてうれないと長引いてるイメージ。
•売り出しの販売価格は値引きされてもいいようにやや高めに設定しておく。
•建物で新築な家を取得した場合、固定資産税評価額から1200万を引いて不動産取得税を計算する。
•住宅ローン控除を受ける場合、最初の年だけ確定申告をする。
住宅取得資金贈与の特例….両親、祖父母から住宅購入資金を援助してもらった場合に贈与税がゼロになる。
•家を売って譲渡所得がでれば税金が発生するがその利益から3,000万円の控除が受けられる。つまり、売却した家が3,000万円以下なら税金が発生しない。
•住宅ローン控除や3,000万円控除は同じタイミングで使えないので注意する。
すごい長くなりましたが要約するとこんな感じでした。住宅の基礎とはいえ、私自身知らないことばかりで少し複雑なこともあったけどすごい勉強になりました。また、とてもわかりやすく説明したされていて読みやすいです。
理解しにくいこともありましが、重要なのは家は購入しても、所有していても、売却しても税金はかかる。しかし、その都度使える税金対策がある。このことをしっかり覚えていることだと思います。
わたしが将来家を持ちたいと思うときの参考にしていきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
