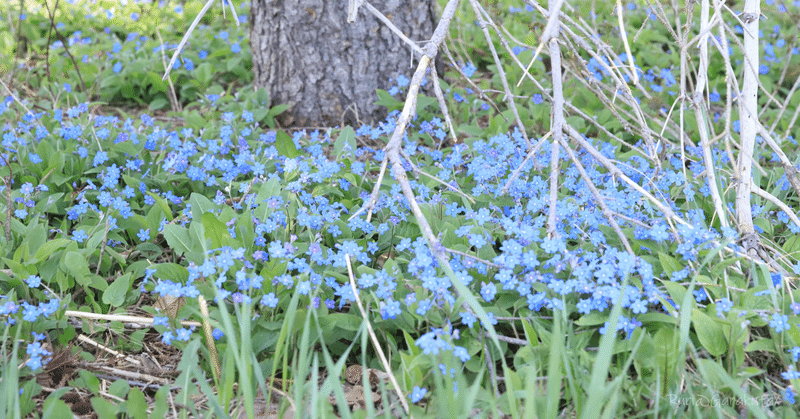
IPO準備/上場会社でひと工夫 Part.11 - 印章管理 -
IPO準備会社と上場会社。それぞれ立場は違いますが、意外にもその悩みどころや解決策に共通点があります。ここではその " ひと工夫 " をご紹介します。
今回は、印章管理についてのひと工夫です。
印章管理のルール整備で明暗が分かれる
皆さんの会社の印章管理は、しっかりとした運用を行なっていますか。
しっかりとした運用を行うためには、印章管理に関するルール作りをしっかり行うことが必要です。最近では契約書の電子契約サービス利用に伴い、印章管理規程を改定した会社も多いのではないでしょうか。
契約書に限らず様々な書類に会社の印鑑が押印されれば、それは会社として認めている証拠になります。特に契約書類は、稟議等で承認決裁を受けていないなど会社としては認めていないにも関わらず契約書類に押印されてしまうと、それが原因で民法上の無権代理/表見代理のトラブルに発展し、社内だけでなく顧客、取引先等に多大な損害と迷惑を被らせることになりますので、日本の会社にとってこの印章管理はとても大切です。
この印章管理ですが、規程としてはわずかな数条で構成されている程度で、内容としては印章の種類に始まり、その調製、登録、交付、保管、使用等に関する事項が定められています。そのため、ネット上にある雛形をそのまま流用している会社が少なからずあるかと思います。ただ、規程の条文自体は雛形のままでも構いませんが、印章の管理方法や押印手続き方法などのルールの整備は皆さんの会社の運用状況や社風に合わせることをお勧めします。逆に、そうでなければ、先にご紹介したようなトラブル発生の原因になりかねませんので、十分な注意が必要です。
前述のとおり、みなさんの会社で最近契約書の電子契約サービス利用に伴う印章管理規程の改定を行なったと思いますが、例えば電子印の調製と登録はお済みでしょうか。また、電子契約締結後の押印管理簿の記録方法は万全でしょうか。この点は、ルール自体はしっかり整備していると思っていても記録を残すところまでのルールを厳密に決めていないことや、その記録の確認、監査までをしっかりと行えるところまでルールを整備していないケースが見受けられます。以前の記事「" 発生事実(不祥事/不正行為) " が発生しない上場会社の内部監査 Part. 11 - モノ言う証憑 -」でご紹介した直近事例でも会社印鑑の不正行為が発覚しておりますので、管理系部門と内部監査としては、ぜひ印章管理の整備/運用状況の再確認をお勧めします。
それでは、IPO準備/上場会社でのひと工夫として2つご紹介します。一つは管理系部門としてのひと工夫、もう一つは内部監査としてのひと工夫です。
【ひと工夫1】管理系部門・印章の登録と押印記録簿の管理
管理系部門の皆さんが印章管理で押さえるポイントは、印章の登録と押印記録簿の管理です。この2つを押さえることで、印章の使用状況を把握することができますし、印章の不正使用の早期発見が可能です。
印章の登録では、印影(電子印を含む)、保管責任者及び代行者、保管場所が重要です。印影については、特に電子印の印影をどのように定め、誰が保管責任者なのか、誰が押印することができるのか。また押印記録については、どのように残すのかが重要です。このあたりは先のネット上にある印章管理規程の雛形を流用してしまうと「印影を登録する」、「保管責任者を定める」、「記録を残す」という条文になっており、具体的に印章登録簿の様式や保管責任者の資格(役職等)、押印記録簿の様式と記載内容などの詳細なルールが無い状態です。この整備のままで運用するのは、とても怖い状態ですし、内部統制の観点で評価するなら場合によっては「不備」に相当するケースもあるかもしれません。
多くの場合、会社の印鑑のなかで大切に取り扱われるのは、法務局に登録した印鑑(いわゆる「実印」)と銀行印ではないでしょうか。そのため、実印は社長が保管責任者となり、押印は社長のみが行う。銀行印は社長又はナンバー2の方が保管責任者及び押印者というケースが多いと思います。ここで見落としがちなのは、実印と銀行印以外の印、例えば社印(いわゆる「角印」)や役職印の印章管理です。これの多いケースとして見受けられるのは次のケースです。
社印・役職印の登録は行われているが、役職者の入社・退職の頻度が多い会社では保管責任者の変更が滞っているケース。
組織変更が多い会社では社印・役職印の登録/変更自体が滞っているケース。
さらに多いケースとして、社印・役職印の押印記録が正確に行われていない等管理手続の運用がルールどおりに行われていないケース。
社印・役職印は職務権限(決裁権限)に基づいて決裁権限者が承認したから押印しても良い、というものではありません。会社の印鑑なのですから、会社が認めていない限り押印できない印鑑です。職務権限とは、その権限者の自由な判断に委任している権限を定めているものではなく、あくまで会社が意思決定した経営・事業方針等に沿った行動を権限者が代わりに行う代行の権限を定めています。管理系部門の皆さんは、この点を十分に理解したうえで印章管理にあたることをお勧めします。
もうひとつ、 「印章管理は法務のお仕事」という固定観念は会社の実態に合わないかもしれません。印章の登録手続き自体は法務が担うとしても、登録簿の様式の設定や登録簿の保管管理(文書管理の意味での保管管理)は総務が担ったり、銀行印に限って言えば押印の手続き等の銀行印管理は経理が担うなど、印章管理における具体的な業務の多くは管理系部門全体に分担されます。分担されることで管理が煩雑になる懸念はありますが、お互いに管理が徹底されていることを確認し合える相互牽制機能が働きます。印章管理に必要なのは「効率性」ではなく「有効性」と「整合性」です。契約書の電子契約サービスについては効率性を求める声が多いですが、後に発生するトラブルの原因としては有効性と整合性が問われる点です。電子署名法(「電子署名及び認証業務に関する法律」の略称)の第3条は次のように定めています。
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
そもそも契約書の電子化は、デジタル改革関連法(デジタル社会の実現を目指すための5つ又は6つの法律の総称)の目的である社会課題を解決するためにデータ活用を促進することと、電子帳簿保存法の目的である国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減するために帳簿書類及び添付書類の電子化に伴って法的に認められた契約方法です。ムダを省く(効率化)を目的としているわけではありません。そのため、電子署名法ほか施行令施行規則等では利用促進に並行してリスクと想定する有効性と整合性に関する定めがあります。契約書の電子契約サービスで「タイムスタンプ」を発行しているのもそのためです。会社においても注目する点はリスク・コントロールの観点で、有効性と整合性に注目して有効性と整合性に関するリスクの低減をするためのルール整備を行うことをお勧めします。管理系部門の皆さんは有効性と整合性を証明するためにも①会社の印章管理のルール整備と完全な運用、②押印記録の徹底、この2つポイントを押さえてください。
【ひと工夫2】内部監査・印章保管状況の実査と押印記録の照合
内部監査の皆さんが印章管理の内部監査を行うときに押さえるポイントは、①ルールと運用状況の整合、②印章の保管状況の実査、③押印記録の照合(電子契約のタイムスタンプを含む)です。内部監査としては、印章管理の運用状況にポイントを絞って監査するイメージです。
通常は押印記録簿とその記録簿にある押印済書類との照合を行いますが、不正行為等に多いのはこの記録簿に記載の無い書類への押印です。そのため、押印記録簿のみに基づいて照合を行なっていても不正行為や誤った印章管理を行なっている状況等を検出することはできません。そこで注目する点は、次のとおりです。
印章が常に保管されている場所の確認(実査)
印章を使用している又は押印している従業員の確認(書面監査、ヒアリング)
社内ルールと異なった押印を行なっているかの確認(ヒアリング) など
印章の保管状況はとても重要です。施錠可能な書庫等で保管しているから大丈夫、というわけではありません。印章の保管の意味は、保管責任者及び押印者のみが利用できる範囲で保管することにより誤った印章の使用を防ぐことです。ですから、書庫の鍵は保管責任者及び押印者のみがお持ちになる方が良いでしょう。電子契約サービスについては、契約相手先から送信されてくる「契約確認メール」の送信先にご注意ください。印章管理に必要なのは「効率性」ではなく「有効性」と「整合性」です。この点を内部監査の皆さんは十分に理解して内部監査を行うことをお勧めします。また、実査と書面監査だけではなく、保管責任者及び押印者そして部門の皆さんへのヒアリングも行ってください。性悪説ではないのですが、記録保存と内部監査のためだけに印章の保管場所と押印記録簿を整えているかもしれません。会社における全業務の最大の目的は、最終的には会社の企業価値の向上です。会社はその目的を達成するために、内部統制の4つの目的である①業務の有効性及び効率性、②報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守④資産の保全を業務として遂行します。印章管理はこの業務遂行の一連の流れとして行う業務のひとつと考えられます。内部監査の皆さんとしては心苦しいですが、この印章管理に関する内部監査の際は性悪性を前提に監査することをお勧めします。そこで単に誤った印章管理が行われているのであれば、その状況を改善していただければ良いだけのことです。ぜひ思い切った内部監査の実施をお勧めします。
押印された書類は、社内外を問わず最終的に表に出ます。つまり印章管理は業務の最終地点を守る防御線です。会社として、押印された書類が有効性と整合性のある書類であることを担保できるようなルールを整備し、運用管理を実施することをお勧めします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
