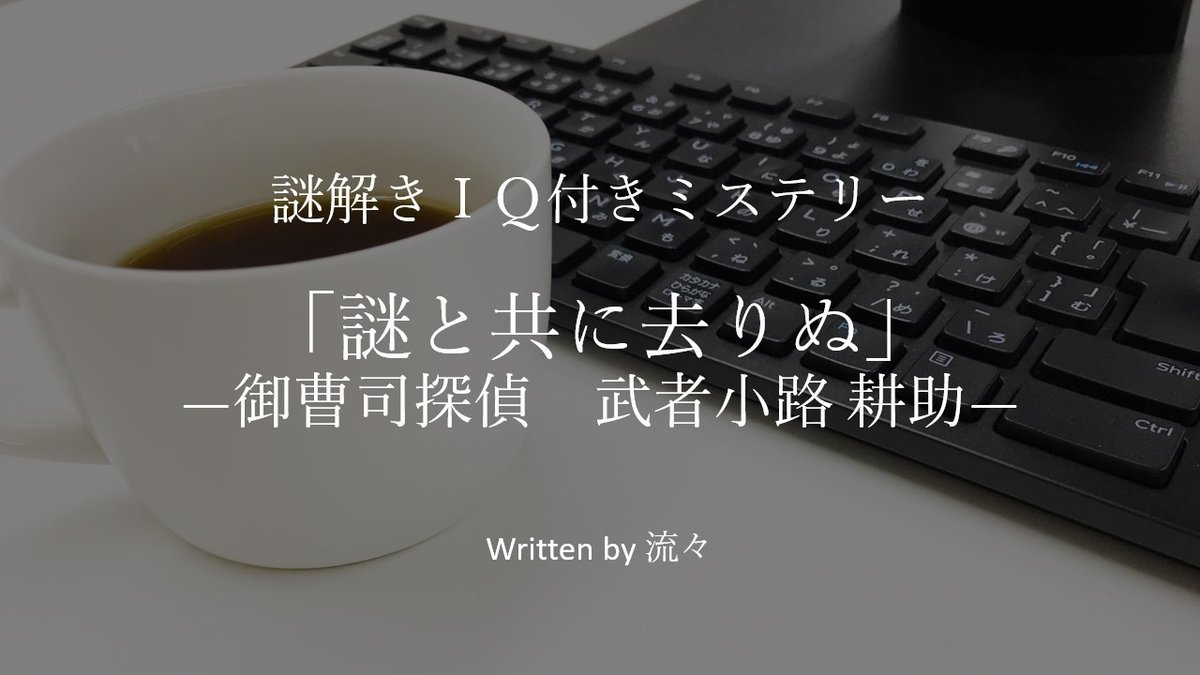君が解くべき謎①/3 謎解きIQ140
大事件のフラグが立ちました
ここは歴史と菜の花の街、百済菜(くだらな)市。
その昔、かの国から伝わったとされる仏像が古寺から見つかり、市の文化財に指定されたことがきっかけで改名した。
元々この街は食用の菜の花栽培が盛んだったが、今では観光資源としても一役買っている。早春に咲きわたる黄色い絨毯は僕にとっても自慢の一つだ。
市の中心部を南北に走る大通りから一本入った道を右に曲がり、しばらく行った十字路を左へ三ブロック進み、角の煙草屋のおしゃべり好きおばちゃんに見つからないようこっそり通り抜けた辺り、つまり街の外れに武者小路名探偵事務所がある。
ここの所長が僕の先輩、武者小路(むしゃのこうじ)耕助さんである。一度聞いたら忘れない名はミステリー好きなおじい様につけられたそうだ。その名の通り、僕らが生まれ育ったこの街を守るべく探偵事務所を開設した。
理由(わけ)あってここを手伝うようになったのが僕、鈴木涼。お世話になって一年ほどになるけれど、毎日をのんびりと過ごしている。
「前から気になってたことがあるんですけど」
ミルで手挽きしたキリマンジャロブレンドを味わっている先輩は、至福の表情を浮かべている。そこへ声を掛けたものだから、ちょっとだけムッとした感じ。
「そもそも、なんで【名】探偵事務所なんですか。先輩が難事件を解決したなんて話、聞いたことがないんですけど」
「せっかく美味しい珈琲の香りと酸味を楽しんでいたのに、何かと思えばそんなことかい? それくらい推理しなきゃ僕の助手とはいえないよ、鈴木くん」
お手伝いはしているけれど、先輩の助手になったつもりはないんだけどなぁ。
二十五歳の僕を快く中途採用してくれたのには感謝しているけれど。
「それに、先輩じゃなくて先生と呼びなさいと、いつも言ってるだろ」
「いーじゃないですか、先輩は先輩なんだから」
「もう、しょうがないなぁ」
就職難のご時世でフリーターをしていた僕を見かねた祖母が、先輩のおじい様と幼馴染ということもあり、紹介してくれたのがこの事務所。
二人はたまたま同じ大学出身で生まれも育ちもここ、生粋の百済菜っ子同士ということで気の置けない関係だ。
「鈴木くんがこの事務所に来てから、何か大きな事件はあったかい?」
「うーん、迷子の犬探しとか、お屋敷の中での探し物くらいですかね」
「連続殺人や怪盗が予告状を出すことなんて、この街で聞いたことがないだろ?」
「ありません」
「つまるところ、世間に轟く私の名声が犯罪への抑止力となっているのだ」
僕は黙ったまま目を細め、粘りつくような視線を浴びせた。
先輩は、その攻撃をマイセンのコーヒーカップで遮っている。
「初めてのお客様にも、すぐに名探偵だってわかってもらえるし。依頼主の立場になって物事を考えれば、何をアピールすべきかは自ずと分かるというもんだよ」
かなり強引な気がする。
単に名探偵と呼ばれたいだけなんじゃないかなぁ。
「まぁこうしてお給料をもらえてるだけでありがたいんですけど」
「そうだろう?」
「仕事も少ないのに、ねぇ」
さらに攻撃を仕掛けてみる。どう出る、先輩!
またカップの陰に顔を隠すようにしながら天井を見上げている。
「その辺は大人の事情と言うやつだよ。うん、そう。大人の事情だ」
「そういうことにしておきます。僕も百済菜っ子ですからね、事情は察しもつきますから」
「それにしても、今日も暇ですねー」
掃除も終えてしまい退屈なのでぼやいてしまった。
「もうお彼岸だな。ということは、鈴木くんがうちに来て一年になるから、何かお祝いでもしようか」
「え、何かプレゼントしてくれるんですか」
「欲しいものがあるのかい?」
一応言っておこうかな。
「そうですねぇ……。何か、こう、目の覚めるような事件をやってみたいです。いかにも探偵っぽいような」
「また無茶なことを言って。何も起きないに越したことはないのだよ」
先輩の言葉がフラグとなってしまったのか、突然、扉をノックする音が事務所に響いた。
「先生、お願いです! 力を貸してください!」
立派な身なりをした初老の男性が、取り乱した様子で入ってきた。
「分かりました、お引き受けしましょう」
「えぇっ! 先輩、まだ何も聞いていないじゃないですか」
あきれてしまい、まじまじと先輩の顔を見る。
「よく考えてみたまえ鈴木くん。この方は非常に焦っていらっしゃる。一刻を争う重大事件と言う訳だ。私を先生と呼んで入ってきたと言うことは、ここが探偵事務所だと言うことも分かっている。決して部屋を間違えたわけではない。ならば私が引き受けずに誰がやるのだ」
「流石、看板に偽りのない名探偵だ。ありがとうございます」
男性が深々とお辞儀をした。
「で、ご用件は」
先輩は応接セットのソファを勧めて、向き合うように座った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?