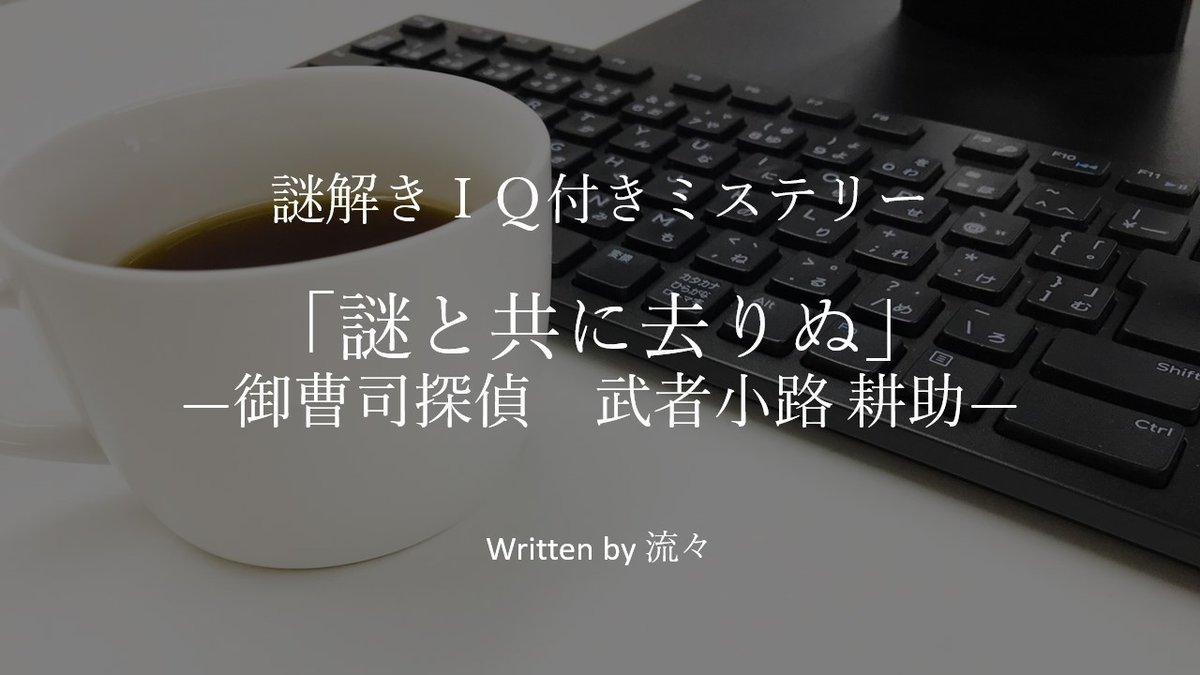怪盗ドキからの予告状①/2 謎解きIQ120
彼岸にて
ここ百済菜(くだらな)市で花見と言えば、桜ではなく菜の花だ。
市の外れにある弥勒寺の周辺は昔から菜の花栽培が盛んな地域で、この時期には辺り一面が黄色い絨毯で埋め尽くされる。
見頃は短いけれど多くの観光客が訪れている中、彼岸の墓参りを終えて寺を後にした。
「この花々を愛でながら、どこかでお茶でもしたいものだね」
のんびりとした調子で薄曇りの空を見上げたのは、僕が働いている探偵事務所の所長、武者小路 耕助さんだ。
僕の祖母と先輩のお祖父さんが旧知の中と言うこともあり、お世話になっている。今日もミステリー好きのお祖父さんが出した謎解きを兼ねて、朝から墓参りに付き合ってくれた。
「先輩が気に入るような珈琲を出す喫茶店なんて、この辺りにはありませんよ」
「百済菜っ子の鈴木くんが言うなら、間違いないな」
「そんなことで感心しないでください。先輩だって、百済菜っ子じゃないですか」
「私は外でお茶を飲むことが少なかったからねぇ。大抵、家で爺やが淹れてくれたから」
先輩はあの有名企業、エムケー商事の御曹司であるにもかかわらず、会長であるお祖父様のミステリー好きに影響されて探偵事務所を開いたという変わり者。ま、そのお陰で仕事が少なくてもきちんとお給料はもらえるし、いい就職先ではあるのだけれど。
「それじゃ、事務所に帰って自分で淹れるとするか」
「それが正解ですよ。先輩の入れる珈琲は美味しいですからね」
「ほぉ、鈴木くんも分かっているじゃないか」
この人にはお世辞と謙遜という概念がない。
確かに、先輩が淹れた珈琲は格別なのだけれど。
寺の駐車場でボルボV40の助手席に乗り込む。
この前、青い車と言ったらマジに怒られた。デニムブルーメタリックと言うそうだ。スポーティーなショートワゴンで確かにかっこいい。
何でも武者小路家では「車は頑丈であるべし」という家訓があり、ボルボを選んだらしい。
市の中心部を抜けて大通りを右に曲がり、しばらく行った十字路を左へ三ブロック進み、駐車場の向かいにある煙草屋のおばちゃんに挨拶をしてから事務所へ向かうと、建物の入り口前に人相の悪いおじさんとチャラそうな若い男が立っている。
どちらもスーツ姿だけれど、目つきが鋭い。
「やぁ、御手洗(みたらい)さん。何かありましたか?」
どうやら先輩の知り合いのようだ。
「先生、お待ちしてましたよ」
おじさんの方が笑みを浮かべて歩み寄ってきた。若い方は立ったまま、こちらを警戒している。
「連絡をくださればよかったのに」
「事務所へお電話したのですが、お留守だったので」
「スマホの番号もお教えしておきますね」
などと話をしながら二人は階段を上り始める。
相変わらず睨みつけている若い男へ「どうぞ」と進めると、無言で続いていった。
二人のお客がソファに腰を掛けると、おじさんの方が若い男を紹介した。
「私と組んでいる捜査一課の伊集院です」
えっ、と言うことは刑事さんたちなのか。
伊集院と紹介された若い男は敵意を隠さず、視線を先輩に向けたまま軽く頭を下げる仕草をした。
「どうも、はじめまして、武者小路です。こちらは助手の鈴木くん」
僕も黙って会釈をする。
「御手洗さんが部下を連れてお越しになったとなると、何か事件ですか?」
「これから事件になりそう、と言う案件なんですがね。ぜひ先生の知恵を借りたくて」
「やだなぁ、先生なんて呼ばなくていいですよ」
僕には、いつも「先輩じゃなく、先生と呼びなさい」と言ってるくせに。
「今日は仕事でお伺いしてますから、耕ちゃんと言う訳にはいきません」
後で聞いたところによると、御手洗刑事は先輩のお父さんの学生時代からの友達で、先輩が小さい頃からよく遊んでもらっていたそうだ。
「で、早速ですが」
御手洗刑事が一枚のコピー紙を取り出し、テーブルに広げた。
『四月三日、時計の針がDからEに変わる時 王の土器を頂戴する
怪盗ドキ』
「ほう、これは……」
「怪盗ドキからの予告状です」
無類の骨董マニアで、土器を中心として各地の博物館を狙う怪盗ドキ。あいつが百済菜市の宝を狙っているのか。
「これって、先輩が前にフラグ立てたからじゃないですか?」
刑事さんたちの様子を伺いながらささやく。
「フラグって?」
「ほら、『この街で怪盗が予告状を出すなんて、聞いたことがない』って言ってたじゃないですか」
「あぁ……覚えてない」
「えぇー!? あんなに自信満々で言い切ってたのに」
右斜め上を見上げて口笛を吹く真似をしている。とぼける仕草が子供かよ。
かと思えば急に真剣な表情で身を乗り出す。
「いたずらではない、ということですね」
「ええ。市立博物館にある『王の土器』をターゲットにしたようです」
「そうですか」
すっと先輩は立ち上がり、ミニキッチンへと向かう。
戸棚からマイセンのコーヒーカップを取り出した。
「おいっ! 何してんだよ」
腰を浮かせた伊集院さんが、怒気をはらんだ声を出す。
「今、美味しいコーヒーを淹れますから」
ここでも謙遜することなく、言い切っている。
「こっちはわざわざ時間を作って来てるんだ。御手洗部長の知り合いだか何だか知らないが、何が名探偵事務所だ! ふざけた名前つけやがって」
「うーん、でも事実ですからねぇ。それに名探偵って書いておいた方が依頼する方たちも分かりやすいし」
「それなら、さっさとこの謎を解いてみろよ!」
「もう解けましたよ」
フラスコにお湯を入れながら、先輩は当たり前のようにさらっと言った。
御手洗刑事も伊集院さんも、もちろん僕も一瞬言葉を失う。
その間に、楽しそうにこう続けた。
「予告の日まで一週間あるし、急がなくても大丈夫でしょう。コーヒーを淹れている間に、鈴木くんも解いてみて」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?