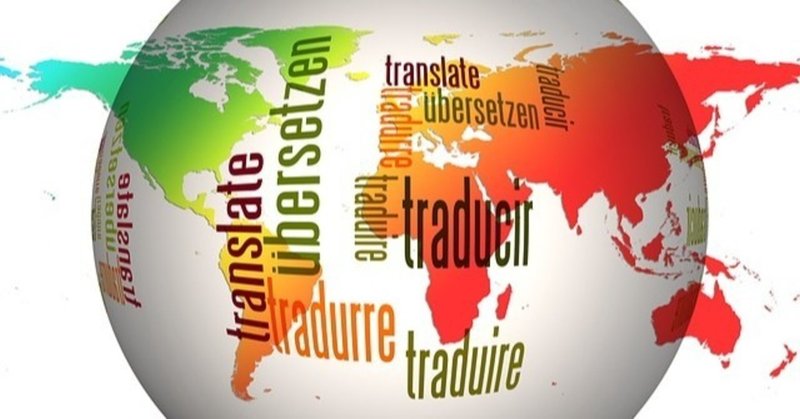
【Polyglotシリーズ】ロンブ・カトーとロンブ・カトーの外国語学習における10のルール
こんにちは。
読書が好きなヴィタリです。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。
今回もPolyglotsととその人たちの学習方法について紹介していきます。
念の為に復習しておきましょう。Polyglotとはたくさんの言葉が話せる人たちのことです。
このPolyglotシリーズの前の記事をまだお読みになってない方は以下のリンクからみてくださいね。
↓18ヶ国語が話せたシュリーマンの人生について↓
https://note.com/rudytskyi/n/n44e3d3735dbc?
↓18ヶ国語が話せたシュリーマンの学習方法↓
https://note.com/rudytskyi/n/n1a1fa83f5863
今回の記事では有名な翻訳者や通訳者の女性の外国語学習法が学べます。
短くロンブ・カトーについて
有名なハンガリー人といったら、僕は二人しか思い浮かべません。その二人は多くの外国語が話せていて、通訳・翻訳の仕事に関わってきた人物です。一人はIstvan Dabiです。もう一人は、今回紹介するロンブ・カトーです。
ロンブ・カトー(Kató Lomb)は1909年に生まれ、94歳で亡くなりました。彼女は大学で物理学と化学を専攻しましたが、若いころから外国語に興味を持って、独学で勉強していました。一応、大学で物理学と化学の学士号を取得しましたが、結局専攻に関する仕事に就かず、翻訳・通訳の仕事で生活費を得ていました。同時通訳の先駆者の一人とも言われています。全部で16カ国語ができていました。その言語とは、ブルガリア語、中国語、デンマーク語、英語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、イタリア語、日本語、ラテン語、ポーランド語、ルーマニア語、ロシア語、スロバキア語、スペイン語、ウクライナ語です。そのうちの8−10カ国語を流暢に通訳しました。残りの言語はどれぐらい流暢だったのかわかりませんが、仕事では16の言葉を使ったようです。
ロンブさんは『わたしの外国語学習法』という本の中に外国語学習における10のルールを書きました。紀伊国屋やジュンク堂などの大きな本屋、またアマゾンに日本語版があるので、ぜひ読んでみてください。
では、ロンブさんが記したルールを紹介したいと思います。
ルール1、外国語に毎日触れましょう。
1.当たり前かもしれないが、学習している外国語に毎日触れることです。脳は筋肉のようだから、強くなりたければシステマティックに練習しなければならないのです。
これを聞いて、「なんだ。これならとっくに知っているよ」と思って溜め息をついたでしょう。普通はそうなりますね。ところが、このルールを守っている人は非常に少ないのです。なぜかといいますと、人間はとても面倒くさがりな生き物だからです。(まさに僕のことなんだよな。最近スペイン語の勉強をサボってる)
何かを継続するということは努力するということです。確かに継続することはちょっと難しいかもしれません。しかし、継続しなければ何も上手くなりません。それは大昔の人でも知ってる事実でしたから、「継続は力なり」という言葉が作られたと思います。
毎日外国語に触れましょうね!

ルール2、モチベーション意地のために工夫しましょう
勉強している言語の勉強する気が薄れていったら、なんとか工夫してやる気を維持させなければなりません。
それは誰にでも起きる問題ですが、それを克服しなければその先はありません。人によってはその克服の仕方が全然違ってきます。例えば、学習法を変えたり、勉強している時に休憩を入れて音楽を聞いたり、散歩したり、彼女(彼氏)がいればラインしたりすることです。十人十色ですから、各自で探してくださいね。
2つ目のルールと1つ目のルールは非常に近い関係にあります。やる気を維持させなければ、継続できません。因に、私は今スペイン語を勉強していますが、なかなか毎日勉強できません。モチベーションのために色々模索中です。(笑)
ルール3、文脈が一番大事!孤立した単語より、連語や文の方が記憶に残りやすい!
日本では、英語などの単語帳が流行っています。確かに、文法の基礎が分かって、たくさんの単語が分かったら、小説や記事が読めるし、会話できます。目的が外国語をある程度話せるようになることならば、それで十分でしょう。
しかし、上級レベルやそれ以上になりたけば、孤立した単語だけを覚えることはいいことでしょうか。
答えは
NO!です。(たぶん)
なぜならば、一つの単語を覚えただけで、単語の使い方までわからず、たとえ文法的に正しくても、変な間違いをしてしまう恐れがあるからです。
たとえばもし「car」という英単語を覚えたい場合は、その単語だけじゃなく「a new car」というような連語で覚えた方が記憶に残りますし、冠詞や、形容詞をどこに置いたらいいのかもわかります。(自分を頭よく見せるために文法用語を使っちゃいました)
ルール4、覚えたモノをすぐに使いましょう
教科書の余白に決まり文句などを書き出して、出来るだけそのフレーズを使うことが大事です。
個人的には、このルールの前半は別に要らないと思っていますが、覚えようとしているフレーズをできるだけ使った方いいでしょう。
ルール5、頭の中で暇つぶしに見えるものを翻訳してみる。
本当になんでもいいです。例えば町を歩いている時に看板や、広告や、見たもの(テーブルを見たら頭の中で「table」と訳してみる)などを訳してみたりすることです。または、好きな歌の歌詞を訳してみるのもいいかもしれません。
ルール6、正しい文を暗記しよう
暗記する時は文が間違っていないことを確認してからです。
例えば、詩が好きでしたら詩を暗記したり、歌が好きでしたら歌詞を覚えたり、好きな映画から台詞を暗記したりすることが外国語の上達につながるでしょう。
ルール7、フレーズを覚えるなら一人称で
使いそうなフレーズ、または、慣用句などを一人称で覚えましょう。
説明しなくてもわかると思いますが、(1)「彼の名前はなんとかです」という形で覚えるのではなく、(2)「私の名前はなんとかです」という形で覚えた方がいいでしょう。日本語では、「私」でも「アナタ」でも「彼」でも、動詞の形が変わりません。(そういう意味では日本語の勉強は楽だった)しかし、他の外国語なら、「私」と「アナタ」の後の動詞が変化します。例えばスペイン語なら、(1)と(2)はこうなります。(1)「Usted llama なんとか」 となります。(2)は「Me llamoなんとか」となります。しかし、初心者なら(2)を使うことの方が多いでしょう。言い換えると、重要なものから勉強するということですね。
ルール8、「読む」「書く」「聞く」「話す」全部やりましょう!
ロンブさんは何を言いたかったのか、お分かりでしょうか。
外国語を勉強している人の中で一つか二つの分野しかやってない人がいますね。(日本の方でそう言う方は多いんじゃないかな)確かに、目的によってどういう分野に力を入れるのがちがってきます。外国語で本を読みたい!という目的の人ならば、リーディングに力を入れなければいけないとは思いますが、外国語はそんなにちょろいものではありません!本を読めるようになるには4つの能力を身につけるのが一番の近道です。なぜかといいますと、「読む」「書く」「聞く」「話す」というのは別々の分野ではなく、4つの能力は相互関係にあるからです。全部を練習しないと、外国語はなかなか身につけません。

ルール9、間違いは怖くない!直されていない間違いは怖い!
ここで「僕が色々知ってるよ」という自慢を兼ねて、ことわざと名言を紹介しようと思っています。この言葉を言った人の名前は覚えてませんが。「失敗しない人というのは何もしない人である」です。「失敗は成功のもと」ということわざなら知らない人はいないでしょう。
日本にはそういうことわざがあるのに、日本人は(日本人批判しているわけではありませんよ(笑))なぜか外国語を完璧にしてから外国人と話したいと思っているようです。それは日本人は完璧主義者が多いからかもしれません。高い志を持つのは素敵ですが、果たして人間は何かを完璧にできるでしょうか。
人間が作ったもので完璧な者はないし、完璧な人間もいないでしょう。
間違ってもいいです!むしろ、間違わない方がおかしいです。
間違いをすることによって僕たちは上達するのです!
ルール10、私は外国語がきっとできるようなると信じること。
自分は外国語なんてできるようにならない!
と思っていたら、どんなに素敵な先生に恵まれても、どんなに頑張っていても外国語ができるようにならないでしょう。
しかし!
自分を信じて、自分に合った学習法で勉強すれば、外国語はだれもできるようになります!
それでは、いかがだったでしょうか。
何かご質問がありましたらいつでも聞いてください。
これからもこういう人たちやそういう人たちの学習方法について書いていきますので、チェックしてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
