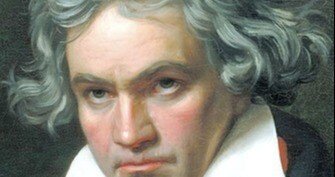#弾き語り

ベートーベン:ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 作品15
00:00 I. Allegro con brio 18:47 II. Largo 32:47 III. Rondo. Allegro scherzando ピアノ協奏曲第1番 (ベートーヴェン) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2%E7%AC%AC1%E7%95%AA_(%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3) Piano Concerto No. 1 (Beethoven) https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Concerto_No._1_(Beethoven) ベートーヴェン 再生リスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG (P)エミール・ギレリス:アンドレ・ヴァンデルノート指揮 パリ音楽院管弦楽団 1957年6月19日~20日録音 #ピアノ,#ピティナ,#beethoven,#ストリートピアノ,#弾いてみた,#ピアノカバー

ベートーヴェン:《弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調》作品130
00:00 – 08:30 Ⅰ. Adagio, ma non troppo – Allegro (B♭ major) 08:31 – 10:26 Ⅱ. Presto (B♭ minor) 10:27 – 16:35 Ⅲ. Andante con moto, ma non troppo. Poco scherzoso (D♭ major) 16:36 – 19:17 Ⅳ. Alla danza tedesca. Allegro assai (G major) 19:22 – 25:52 Ⅴ. Cavatina. Adagio molto espressivo (E♭ Major) 25:53 – 33:28 Ⅵ. Allegro in B♭ major ベートーヴェン『交響曲集』再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1wpquw9OxqNkW04ZYODRzFE ベートーヴェン再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1zT3TDzCFkYRGchw_08y2KG ベートーヴェン の7大ピアノ・ソナタ集 再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1xEY24t4_5KF0rgQSVYgejm ベートーヴェン 『ラズモフスキー弦楽四重奏曲』再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1xL6QgtPG5WdxCawuTAdAIC ベートーヴェン『後期弦楽四重奏四重奏曲』再生リスト https://youtube.com/playlist?list=PLTtHiFCVwL1z60arn0dXGzuFhbM2F4BwF 弦楽四重奏曲第13番 (ベートーヴェン) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A6%E6%A5%BD%E5%9B%9B%E9%87%8D%E5%A5%8F%E6%9B%B2%E7%AC%AC13%E7%95%AA_(%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3) String Quartet No. 13 (Beethoven) https://en.wikipedia.org/wiki/String_Quartet_No._13_(Beethoven)

『ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 Op 110』ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月26日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第31番 変イ長調 作品110は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1821年に完成したピアノソナタ。 概要 ベートーヴェンの最後のピアノソナタ3作品(第30番、第31番、第32番)は、『ミサ・ソレムニス』や『ディアベリ変奏曲』などの大作の仕事の合間を縫うように並行して進められていった[1]。途中、やがて彼の命を奪うことになる病に伏せることになるが[2]、健康を回復したベートーヴェンは旺盛な創作意欲をもってこの作品を書き上げた[3]。楽譜には1821年12月25日と書き入れられ、これが完成の日付と考えられるものの、その後1822年になってからも終楽章の手直しが行われたとされる[1]。こうして生まれた本作品には前作を超える抒情性に加え[1]、ユーモラスな洒落も盛り込まれており[3]、豊かな情感が表出されている。また、終楽章に記された数々のト書きは、しばしば作曲者を襲った病魔との関連で考察される[2][4]。 1822年2月18日付の書簡からは、このピアノソナタが続く第32番と共に、ベートーヴェンと親交の深かったアントニー・ブレンターノに献呈される予定であったことがわかる[1]。ところが、出版時には楽譜に献辞は掲げられておらず、献呈者なしとなった理由を決定づける証拠も見つかっていないため不明である。[1]。ブレンターノ夫人への献呈が検討される以前には、弟子のフェルディナント・リースへの恩義に報いるために彼に捧げられることになっていたとする説もある[1]。楽譜の出版は1822年7月、シュレジンガー、シュタイナー、ブージーなどから行われた。 作曲者はチェロソナタ第5番にみらるように、後期の作品ではフーガの応用に大きく傾いている。この曲の終楽章は、最後の3曲のピアノソナタの中では最も典型的にフーガを用いたものである。ドナルド・フランシス・トーヴィーは「ベートーヴェンの描くあらゆる幻想と同じく、このフーガは世界を飲み込み、超越するものである」と述べた[3]。 演奏時間 約18分[5]。 楽曲構成 第1楽章 Moderato cantabile molto espressivo 3/4拍子 変イ長調 ソナタ形式[6]。con amabilità(愛をもって)と付記されている。序奏はなく、冒頭から譜例1の第1主題が優しく奏でられる。 ベートーヴェンは譜例2に示される第1主題の後半楽節を好んでおり、自作に度々用いていた。ヴァイオリンソナタ第8番の第2楽章(譜例3)やその他の楽曲にも同じ旋律を見出すことが出来る[5]。また、この旋律がハイドンの交響曲第88番の第2楽章からの借用であるとする意見もある[2]。 第1主題に続いて特徴的なアルペッジョの走句が入り、変ホ長調の第2主題の提示へと移る(譜例4)。 ピアノソナタ第23番と同様提示部の反復は設けられておらず、そのまま展開部へと移行する。展開部はテノールとバスの音域を行き来する左手の音型の上で、転調を繰り返しながら譜例1冒頭2小節の動機要素が8回奏される。続く再現部では第1主題が細かな伴奏音型の上に姿を現し、第2主題は変イ長調となって戻ってくる[5]。コーダでは経過部のアルペッジョが奏でられ、譜例1の断片を回想しつつ弱音で楽章を終える[5]。 第2楽章 Allegro molto 2/4拍子 ヘ短調 三部形式[5]。スケルツォ的な性格を持ち[3]、軽やかな中にも全体的に不気味な雰囲気を漂わせる。第1の部分に使用されている旋律は当時の流行歌から採られている。譜例5は『Unsre Katz hat Katzerln gehabt』(うちの猫には子猫がいた)、続く譜例6は『Ich bin lüderlich, du bist lüderlich』(私は自堕落、君も自堕落)というコミカルなタイトルの楽曲に由来する[3][4][7]。 譜例5と譜例6がそれぞれ反復記号によって繰り返され、曲は中間部へと進む。中間部は下降する音型と上昇するシンコペーションの音型が交差する、譜例7に示される楽想が5回奏されるだけの簡素なものである[3][5]。 中間部が終わると第1部をほぼそのまま再現し、コーダで音量とテンポを落として切れ目なく終楽章へ続く[2][8]。 第3楽章 Adagio, ma non troppo - Fuga. Allegro, ma non troppo 6/8拍子 変イ長調 極めて斬新な構成と内容を備えた終楽章は、規模の大きな変ロ短調の序奏に始まる[5](譜例8)。この部分のベートーヴェンの手稿譜には例外的に数多くの修正の跡が残されており、作曲者が推敲を重ねて書き上げたことが窺われる[4]。レチタティーヴォと明記された楽想は頻繁にテンポを変更しながら進む[9]。この中でタイで繋がれた連続するイ音に作曲者自身が運指を指定している部分は、クラヴィコードで実現可能な演奏効果を想定して書かれたものである[5][9]。 続いて変イ短調の『嘆きの歌』(Klagender Gesang)が切々と歌い始められる(譜例9)。『嘆きの歌』の下降する哀切な旋律線は、バッハの『ヨハネ受難曲』の「Es ist vollbracht」との関連を指摘されている[4][10][11]。 次に変イ長調で3声のフーガが開始される[12]。フーガの主題は第1楽章第1主題に基づくもので[4][13]、この上昇する音列が全曲を統一する役割を果たしている[3]。フーガは自由に展開されてクライマックスを形成する。 盛り上がったところで再び『嘆きの歌』が現れる。「疲れ果て、嘆きつつ」(Ermattet, klagend)と記載されており[9][12]、ト短調で休符によって寸断された途切れ途切れの旋律が歌われる(譜例11)。 クレッシェンドを経て、再度3声のフーガとなる。ベートーヴェンはこのフーガ冒頭にイタリア語で「次第に元気を取り戻しながら」(Poi a poi di nuovo vivente)と記した[9][14]。譜例12の主題は譜例10のフーガ主題の反行によっており[13]、ト長調で開始される。 次第に譜例10の縮小形、拡大系が姿を現すようになり、さらにメノ・アレグロで4分の1の縮小形を出しつつト長調から主調である変イ長調に移行する。同時に、譜例10の主題が堂々とバスに回帰する。その後、対位法を離れて一層大きく歓喜を表しながら、最後に向かって徐々に速度と力を上げていき高らかに全曲を完結させる。 出典 1^ a b c d e f 大木 1980, p. 401. 2^ a b c d Cummings, Robert. ピアノソナタ第31番 - オールミュージック. 2015年2月7日閲覧。 3^ a b c d e f g “Beethoven: The Last Three Piano Sonatas”. Hyperion Records. 2015年2月7日閲覧。 4^ a b c d e “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 110 no 31”. The Guardian. 2015年2月7日閲覧。 5^ a b c d e f g h 大木 1980, p. 402. 6^ 大木, p. 402. 7^ Mauser 2008, p. 148. 8^ von Bülow, Hans. “Score, Beethoven: Piano Sonata No.31 (PDF)”. J. G. Cotta. 2015年2月7日閲覧。 9^ a b c d “Beethoven, Piano Sonata No.31 (PDF)”. Breitkopf & Härtel (1862年). 2015年2月7日閲覧。 10^ Mauser 2008, p. 114. 11^ Kaiser 1979, p. 583. 12^ a b 大木 1980, p. 403. 13^ a b 石桁真礼生『新版 楽式論』、音楽之友社、1966年、P.295-296 14^ 大木 1980, p. 404.

『ピアノソナタ 第26番 変ホ長調 作品81a 『告別』』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第26番 変ホ長調 作品81a 『告別』は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年から1810年にかけて作曲したピアノソナタ。 概要 本作にはベートーヴェン自身が標題を与えているが、そのようなピアノソナタはこの『告別』と『悲愴』としかない。その背景には彼のパトロン、弟子であり友人でもあったルドルフ大公のウィーン脱出が関係している[1]。 オーストリアは1809年4月9日にナポレオン率いるフランス軍と戦闘状態に陥った。ナポレオンの軍勢は5月12日までにウィーンへと侵攻しており、神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世の弟にあたり皇族の身分であったルドルフ大公は5月4日に同市を離れることになる。ベートーヴェンはピアノソナタの第1楽章の草稿に「Das Lebewohl(告別)」と記すとともに「1809年5月4日、ウィーンにて、敬愛するルドルフ大公殿下の出発に際して。」と書き入れた[1]。オーストリアの降伏により同年10月14日に終戦、フランス軍が撤退した後の1810年1月30日にルドルフ大公はウィーンへと戻った。第2楽章の「Die Abwesenheit(不在)」はこの期間のことを示しており、さらに第3楽章には「Das Wiedersehen(再会)」、「敬愛するルドルフ大公殿下帰還、1810年1月30日」と書き込まれている[2]。 この曲を出版したブライトコプフ・ウント・ヘルテル社は各楽章の表題をフランス語に置き換えて"les adieux"、"l'absence"、"le retour"と表記した[2]。親交の深かったルドルフ大公のために作曲されたこのピアノソナタの標題にはベートーヴェン自身もこだわりがあったらしく、「Das Lebewohlはles adieuxとは全く違うものである。前者は心から愛する人にだけ使う言葉であり、後者は集まった聴衆全体に対して述べる言葉だからである。」と手紙で抗議している。ただし、作曲者自身もスケッチ段階では第1楽章の「Das Lebewohl」を取り消して「Der Abschied(別れ)」、第3楽章は「Die Ankunft(到着)」としていたことが分かっている[2]。 出版社へと持ち込まれたのは第24番、第25番のソナタと同じ1810年2月10日であったが、このソナタのみ翌年に作曲者自身による修正を施され[3]、1811年7月に出版された[2]。ルドルフ大公へ献呈[4]。81aとなっている作品番号は、ジムロック社がブライトコプフ社に先駆けて六重奏曲を刊行していたため、ブライトコプフ社が自社の作品番号を混乱させないようピアノソナタを81a、六重奏曲を81bとしたことに由来している[2]。 演奏時間 約16分半[5]。 曲の構成 第1楽章 "Das Lebewohl" Adagio 2/4拍子 - Allegro 2/2拍子 変ホ長調 ソナタ形式[2]。『告別』の副題がつけられている。譜例1に示すとおり序奏の最初の3つの音符には"Lebewohl"と歌詞が与えられており[4]、楽章全体にこのモチーフが配されている[2]。 序奏に続くアレグロの第1主題にはLebewohlの動機が組み込まれており、テヌートで強調されている[6](譜例2)。一方、左手のバスの動きはLebewohl動機の反行形となっている[7]。 Lebewohl動機の反行形に始まる経過部を経ると変ロ長調の第2主題が提示されるが、これも拡大されたLebewohl動機に基づくものである[6](譜例3)。さらに下降する結尾句も同じ動機から構成される[6]。 提示部の繰り返しを終えると展開部となる。小規模な展開部では譜例2の下降する音型が扱われ[6]、これが8分音符2つの単位まで細かく分解されていく[7]。分解された音型からクレッシェンドして再現部となり、譜例2と譜例3が変ホ長調で現れる。コーダではまず譜例2が取り上げられて展開されるが[6]、続いてLebewohl動機と8分音符の走句が組み合わされていく。最後は大公の出立を見送るような情緒を見せつつ楽章を閉じる[7]。なお、ベートーヴェンは楽章の最後から4小節目の2分音符のハ音において、音を持続したままクレッシェンドするという特殊な指示をしている[4][注 1]。 第2楽章 "Die Abwesenheit" Andante espressivo 2/4拍子 ハ短調 2つの主題が繰り返される序奏的性格を持つ楽章[8]。『不在』の副題がつけられており、ドイツ語で「ゆるやかに、表情を込めて」(In gehender Bewegung, doch mit Ausdruck.)と指示されている[4][8]。ハ短調で奏でられる譜例4の第1主題の音型は譜例1の動きと関係している[8]。開始のハ短調に落ち着かず、不安げな様子が表現される[7]。 レチタティーヴォのような経過を経てト長調の第2主題へと移る(譜例5)。 間もなく変ロ短調で第1主題が回帰し、続いてヘ長調で第2主題が再現された後、譜例4の音型を静かに奏でながら終楽章に接続される。 第3楽章 "Das Wiedersehen" Vivacissimamente 変ホ長調 6/8拍子 ソナタ形式[8]。『再会』の副題とともに、ドイツ語による「非常に生き生きとした速度で」(Im lebhaftesten Zeitmaasse)という指示がある[4][8]。和音の一打に続き華麗なアルペッジョの序奏が現れる。第1主題はまず譜例6のように出されるが、主旋律が左手に移されると高音部は装飾的な彩りを添える。 きらびやかな経過部を終えると変ロ長調の第2主題が提示される(譜例7)。第2主題が繰り返される際に現れるフレーズには、同時期に作曲された『皇帝協奏曲』の第3楽章のものと極めて類似したパッセージが用いられている[7]。 勢いのあるコデッタにより結ばれ、提示部の反復に入る。展開部はごく短く、専ら第2主題が扱われる[8]。たちまち細かい分散和音の伴奏に乗ってオクターヴで第1主題が再現され、常法通り第2主題へと進む。コーダではポーコ・アンダンテとなって譜例6を穏やかに回想し、形を変えて繰り返す。最後は元のテンポに戻り、喜ばしく閉じられる。 脚注 注釈 1^ このクレッシェンドは鍵盤楽器では表現不能である。 2^ 譜例中では最後のイ音にかかるタイが省略されている。 出典 3^ a b 大木 1980, p. 384. 4^ a b c d e f g 大木 1980, p. 385. 5^ “Booklet, BEETHOVEN, L. van: Piano Sonatas, Vol. 9 (Biret)”. NAXOS. 2015年4月19日閲覧。 ^6 a b c d e “Beethoven Piano Sonata No.26 (PDF)”. Breitkopf & Härtel. 2015年4月16日閲覧。 7^ ピアノソナタ第26番 - オールミュージック. 2015年4月12日閲覧。 8^ a b c d e 大木 1980, p. 386. 9^ a b c d e “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 81a”. The Guardian. 2015年4月12日閲覧。 10^ a b c d e f 大木 1980, p. 387.

『ピアノソナタ第24番 『テレーゼ』嬰ヘ長調 作品78』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第24番 嬰ヘ長調 作品78は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年に作曲したピアノソナタ。 概要 ルドルフ大公の目録によれば、この作品の写譜が大公の元に届けられたのは1809年10月であったらしい[1]。当時は旺盛な創作活動を続けていたベートーヴェンであったが、ピアノソナタの分野では前作『熱情ソナタ』以来既に4年が経過していた[1]。1809年のナポレオン軍の侵攻はルドルフ大公がウィーンを離れるという事態を招き、この出来事に絡んで作曲された『告別ソナタ』によってベートーヴェンはこのジャンルに舞い戻る。そうした中、同時期に書かれたより規模の小さい本作が先に完成されて世に出されることとなった[2]。 楽譜は1810年9月にブライトコプフ・ウント・ヘルテルから出版され、伯爵令嬢テレーゼ・フォン・ブルンスヴィックに捧げられた[1]。そのため本作は『テレーゼ』と通称されることもある[1][2]。ベートーヴェンはブルンスヴィック家と親密な関係であり、ピアノの教え子でもあったテレーゼから贈られた彼女の肖像画を生涯大切にしていた[3]。なお、彼女は『エリーゼのために』の「エリーゼ」の正体として有力視されているテレーゼ・マルファッティとは別人である。アントン・シンドラーによれば、作曲者自身はこの作品に強い愛着を抱いていたということである[1][2][4]。 演奏時間 約10分[2]。 楽曲構成 第1楽章 Adagio cantabile 2/4拍子 - Allegro, ma non troppo 4/4拍子 嬰ヘ長調 ソナタ形式[5]。ハイドンの作品などに前例があるとはいえ、古典派音楽としては非常に珍しい調性が選択されている[4]。曲は4小節の優美な導入に始まる(譜例1)。この序奏は楽章中に現れる要素を予言するものであるが、曲中に再度現れることはない[4]。 続いてアレグロ・マ・ノン・トロッポの主部となり、譜例2の第1主題が提示される[5]。 16分音符による経過句を経て、第2主題が嬰ハ長調で出される(譜例3)。第2主題は右手に始まる16分音符の流れに受け継がれ、その音型が左手に引き渡されて結尾句を形成する。 提示部を反復した後、小ぢんまりとした展開部となる[5]。まず第1主題が嬰ヘ短調で出された後、16分音符の流れとこの主題冒頭のリズム素材が組み合わされて進められる。再現部では第1主題がやや拡大された形で再現され、続いて第2主題が嬰ヘ長調に現れる[5]。コーダでは16分音符の流れの上に譜例2を回想しながら音量を増していく。なお、展開部と再現部を反復するよう指示されている[6]。 第2楽章 Allegro vivace 2/4拍子 嬰ヘ長調 ソナタ形式とロンド形式を融合した形式とみなすことができる[4]。ユーモラスな性格を持ちながらも、繊細な感覚で貫かれている[5]。強弱が交代する第1主題に始まる(譜例4)。 続いて2音ずつスラーで結ばれた16分音符が上昇するパッセージが現れる(譜例5)。 譜例4、譜例5が繰り返されたのち、譜例5の音型から生成された第2主題に相当する楽想が嬰ニ長調で奏される[4][7](譜例6)。 再び16分音符のパッセージとなって進められると、譜例4がロ長調で、譜例6が嬰ヘ長調で順次再現される[5]。終わり近くに嬰ヘ長調で譜例4が出されるが、この際フレーズ後半にはスラーが付されて趣に変化が与えられている[4][6]。譜例4に基づくコーダとなり弱音に落ち着いていくが、上昇するアルペッジョが挿入された後、16分音符による音型に乗って勢いよく全曲の幕を閉じる。 出典 1^ a b c d e 大木 1980, p. 380. 2^ a b c d ピアノソナタ第24番 - オールミュージック. 2015年4月26日閲覧。 3^ 大木 1980, p. 377. 4^ a b c d e f “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 78”. The Guardian. 2015年4月25日閲覧。 5^ a b c d e f 大木 1980, p. 381. 6^ a b “Beethoven: Piano Sonata No.24”. Breitkopf & Härtel. 2015年4月26日閲覧。 7^ 大木 1980, p. 382. 参考文献 大木, 正興『最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I』音楽之友社、1980年。ISBN 978-4276010147。 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.24, Breitkopf & Härtel, Leiptig

『ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『悲愴』("Grande Sonate pathétique")』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
Sonata No 8 in C minor, Op 13, commonly known as Sonata Pathétique 1798年から翌年にかけて作曲されたらしい。 持ち前の非凡なピアノ演奏技工で立身出世のための貴重な武器だった頃のベートヴェンはピアノの作曲に力を入れた。"Grande Sonate pathétique"は初版時に彼自身が表題を付けたようである。 3楽章からなるが2楽章はフィナーレの文字通りの導入部とみて、全体を2楽章とする見方もあるようである。以上は、本からの知識に過ぎないが。

『ピアノソナタ第26番 『告別』変ホ長調 作品81a 』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音 ピアノソナタ第26番 変ホ長調 作品81a 『告別』は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年から1810年にかけて作曲したピアノソナタ。 概要 本作にはベートーヴェン自身が標題を与えているが、そのようなピアノソナタはこの『告別』と『悲愴』としかない。その背景には彼のパトロン、弟子であり友人でもあったルドルフ大公のウィーン脱出が関係している[1]。 オーストリアは1809年4月9日にナポレオン率いるフランス軍と戦闘状態に陥った。ナポレオンの軍勢は5月12日までにウィーンへと侵攻しており、神聖ローマ帝国皇帝フランツ2世の弟にあたり皇族の身分であったルドルフ大公は5月4日に同市を離れることになる。ベートーヴェンはピアノソナタの第1楽章の草稿に「Das Lebewohl(告別)」と記すとともに「1809年5月4日、ウィーンにて、敬愛するルドルフ大公殿下の出発に際して。」と書き入れた[1]。オーストリアの降伏により同年10月14日に終戦、フランス軍が撤退した後の1810年1月30日にルドルフ大公はウィーンへと戻った。第2楽章の「Die Abwesenheit(不在)」はこの期間のことを示しており、さらに第3楽章には「Das Wiedersehen(再会)」、「敬愛するルドルフ大公殿下帰還、1810年1月30日」と書き込まれている[2]。 この曲を出版したブライトコプフ・ウント・ヘルテル社は各楽章の表題をフランス語に置き換えて"les adieux"、"l'absence"、"le retour"と表記した[2]。親交の深かったルドルフ大公のために作曲されたこのピアノソナタの標題にはベートーヴェン自身もこだわりがあったらしく、「Das Lebewohlはles adieuxとは全く違うものである。前者は心から愛する人にだけ使う言葉であり、後者は集まった聴衆全体に対して述べる言葉だからである。」と手紙で抗議している。ただし、作曲者自身もスケッチ段階では第1楽章の「Das Lebewohl」を取り消して「Der Abschied(別れ)」、第3楽章は「Die Ankunft(到着)」としていたことが分かっている[2]。 出版社へと持ち込まれたのは第24番、第25番のソナタと同じ1810年2月10日であったが、このソナタのみ翌年に作曲者自身による修正を施され[3]、1811年7月に出版された[2]。ルドルフ大公へ献呈[4]。81aとなっている作品番号は、ジムロック社がブライトコプフ社に先駆けて六重奏曲を刊行していたため、ブライトコプフ社が自社の作品番号を混乱させないようピアノソナタを81a、六重奏曲を81bとしたことに由来している[2]。 演奏時間 約16分半[5]。 曲の構成 第1楽章 "Das Lebewohl" Adagio 2/4拍子 - Allegro 2/2拍子 変ホ長調 ソナタ形式[2]。『告別』の副題がつけられている。譜例1に示すとおり序奏の最初の3つの音符には"Lebewohl"と歌詞が与えられており[4]、楽章全体にこのモチーフが配されている[2]。 第2楽章 "Die Abwesenheit" Andante espressivo 2/4拍子 ハ短調 2つの主題が繰り返される序奏的性格を持つ楽章[8]。『不在』の副題がつけられており、ドイツ語で「ゆるやかに、表情を込めて」(In gehender Bewegung, doch mit Ausdruck.)と指示されている[4][8]。ハ短調で奏でられる譜例4の第1主題の音型は譜例1の動きと関係している[8]。開始のハ短調に落ち着かず、不安げな様子が表現される[7]。 第3楽章 "Das Wiedersehen" Vivacissimamente 変ホ長調 6/8拍子 ソナタ形式[8]。『再会』の副題とともに、ドイツ語による「非常に生き生きとした速度で」(Im lebhaftesten Zeitmaasse)という指示がある[4][8]。和音の一打に続き華麗なアルペッジョの序奏が現れる。第1主題はまず譜例6のように出されるが、主旋律が左手に移されると高音部は装飾的な彩りを添える。 脚注 注釈 ^ このクレッシェンドは鍵盤楽器では表現不能である。 ^ 譜例中では最後のイ音にかかるタイが省略されている。 出典 1^ a b 大木 1980, p. 384. 2^ a b c d e f g 大木 1980, p. 385. 3^ “Booklet, BEETHOVEN, L. van: Piano Sonatas, Vol. 9 (Biret)”. NAXOS. 2015年4月19日閲覧。 4^ a b c d e “Beethoven Piano Sonata No.26 (PDF)”. Breitkopf & Härtel. 2015年4月16日閲覧。 5^ ピアノソナタ第26番 - オールミュージック. 2015年4月12日閲覧。 6^ a b c d e 大木 1980, p. 386. 7^ a b c d e “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 81a”. The Guardian. 2015年4月12日閲覧。 8^ a b c d e f 大木 1980, p. 387. 参考文献 大木, 正興『最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I』音楽之友社、1980年。ISBN 978-4276010147。 CD解説 NAXOS, BEETHOVEN, L. van: Piano Sonatas, Vol. 9 (Biret), 8.571268 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.26, Breitkopf & Härtel, Leiptig

『ピアノソナタ第24番 『テレーゼ』 ヘ長調 作品』 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月13日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第24番 嬰ヘ長調 作品78は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1809年に作曲したピアノソナタ。 概要 ルドルフ大公の目録によれば、この作品の写譜が大公の元に届けられたのは1809年10月であったらしい[1]。当時は旺盛な創作活動を続けていたベートーヴェンであったが、ピアノソナタの分野では前作『熱情ソナタ』以来既に4年が経過していた[1]。1809年のナポレオン軍の侵攻はルドルフ大公がウィーンを離れるという事態を招き、この出来事に絡んで作曲された『告別ソナタ』によってベートーヴェンはこのジャンルに舞い戻る。そうした中、同時期に書かれたより規模の小さい本作が先に完成されて世に出されることとなった[2]。 楽譜は1810年9月にブライトコプフ・ウント・ヘルテルから出版され、伯爵令嬢テレーゼ・フォン・ブルンスヴィックに捧げられた[1]。そのため本作は『テレーゼ』と通称されることもある[1][2]。ベートーヴェンはブルンスヴィック家と親密な関係であり、ピアノの教え子でもあったテレーゼから贈られた彼女の肖像画を生涯大切にしていた[3]。なお、彼女は『エリーゼのために』の「エリーゼ」の正体として有力視されているテレーゼ・マルファッティとは別人である。アントン・シンドラーによれば、作曲者自身はこの作品に強い愛着を抱いていたということである[1][2][4]。 演奏時間 約10分[2]。 楽曲構成 第1楽章 Adagio cantabile 2/4拍子 - Allegro, ma non troppo 4/4拍子 嬰ヘ長調 ソナタ形式[5]。ハイドンの作品などに前例があるとはいえ、古典派音楽としては非常に珍しい調性が選択されている[4]。曲は4小節の優美な導入に始まる。この序奏は楽章中に現れる要素を予言するものであるが、曲中に再度現れることはない[4]。 第2楽章 Allegro vivace 2/4拍子 嬰ヘ長調 ソナタ形式とロンド形式を融合した形式とみなすことができる[4]。ユーモラスな性格を持ちながらも、繊細な感覚で貫かれている[5]。強弱が交代する第1主題に始まる。 出典 1^ a b c d e 大木 1980, p. 380. 2^ a b c d ピアノソナタ第24番 - オールミュージック. 2015年4月26日閲覧。 3^ 大木 1980, p. 377. 4^ a b c d e f “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 78”. The Guardian. 2015年4月25日閲覧。 5^ a b c d e f 大木 1980, p. 381. 6^ a b “Beethoven: Piano Sonata No.24”. Breitkopf & Härtel. 2015年4月26日閲覧。 7^ 大木 1980, p. 382.

ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 作品27-2 『幻想曲風ソナタ』("Sonata quasi una Fantasia") ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(P)フリードリヒ・グルダ 1953年11月1日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ナビゲーションに移動検索に移動 初版譜表紙 1802年 ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 作品27-2 『幻想曲風ソナタ』("Sonata quasi una Fantasia")は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1801年に作曲したピアノソナタ。『月光ソナタ』という通称とともに広く知られている。 概要 1801年、ベートーヴェンが30歳のときの作品。1802年3月のカッピによる出版が初版であり[2]、ピアノソナタ第13番と対になって作品27として発表された[3]。両曲ともに作曲者自身により「幻想曲風ソナタ」という題名を付されており[4]、これによって曲に与えられた性格が明確に表されている[2]。 『月光ソナタ』という愛称はドイツの音楽評論家、詩人であるルートヴィヒ・レルシュタープのコメントに由来する。ベートーヴェンの死後5年が経過した1832年、レルシュタープはこの曲の第1楽章がもたらす効果を指して「スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」と表現した[5][6]。以後10年経たぬうちに『月光ソナタ』という名称がドイツ語や英語による出版物において使用されるようになり[7][8]、19世紀終盤に至るとこの名称が世界的に知られるようになる[9]。一方、作曲者の弟子であったカール・ツェルニーもレルシュタープの言及に先駆けて「夜景、遥か彼方から魂の悲しげな声が聞こえる」と述べている[3]。このように『月光ソナタ』の愛称と共に広く知られる以前より人々の想像を掻き立て、人気を博した本作であったが、ベートーヴェン自身はそのことを快く思っていなかったとされる[5]。なお、後述の尋常小学校の物語が引用されることがあるが、作り話である。 曲は伯爵令嬢ジュリエッタ・グイチャルディに献呈された[1]。ベートーヴェンはブルンスヴィック家を介した縁で自らのピアノの弟子となったこの14歳年少の少女に夢中になる[注 1]。1801年11月16日に友人のフランツ・ベルハルト・ヴェーゲラーへ宛てた書簡には次のようにある。「このたびの変化は1人の可愛い魅力に富んだ娘のためなのです。彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。(中略)ただ、残念なことには身分が違うのです」[1]。その後、グイチャルディはヴェンゼル・ロベルト・フォン・ガレンベルクと結婚してベートーヴェンのもとを去っていく。この献呈は当初から意図されていたわけではなく、グイチャルディにはロンド ト長調 作品51-2が捧げられるはずであった。しかし、ロンドをヘンリエッテ・リヒノフスキー伯爵令嬢へ贈ることが決まり[注 2]、代わりにグイチャルディへと献呈されたのがこのソナタであったようである[1]。なお、ジュリエッタはアントン・シンドラーの伝記で「不滅の恋人」であるとされている。 曲の内容は『幻想曲風ソナタ』という表題が示すとおり、伝統的な古典派ソナタから離れてロマン的な表現に接近している[4]。速度の面では緩やかな第1楽章、軽快な第2楽章、急速な第3楽章と楽章が進行するごとにテンポが速くなる序破急的な展開となっている。また、形式的にはソナタ形式のフィナーレに重心が置かれた均衡の取れた楽章配置が取られ[12]、情動の変遷が強健な意志の下に揺るぎない帰結を迎えるというベートーヴェン特有の音楽が明瞭に立ち現われている[2]。 本作はピアノソナタ第8番『悲愴』、同第23番(熱情)と並んで3大ピアノソナタと呼ばれることもある。 演奏時間 約15-16分[1][4]。 楽曲構成 第1楽章 Adagio sostenuto 2/2拍子 嬰ハ短調 三部形式[1]。『月光の曲』として非常に有名な楽章である。冒頭に「全曲を通して可能な限り繊細に、またsordinoを使用せずに演奏すること」(Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino.)との指示がある(譜例1)。「sordino(弱音器)」とは「ダンパー」のことを指すとされ、冒頭の指示は現代のピアノにおいては「サステインペダルを踏み込んだ状態で」と解釈される 第2楽章 Allegretto 3/4拍子 変ニ長調 複合三部形式。スケルツォもしくはメヌエットに相当する楽章であるが、いずれであるとも明記されていない[13]。暗い両端楽章の間にあって効果的に両者を繋ぐ役割を果たしており、フランツ・リストはこの楽章を「2つの深淵の間の一輪の花」に例えた[3][12][13]。レガートとスタッカートが対比される譜例4により開始される[注 4]。 第3楽章 Presto agitato 4/4拍子 嬰ハ短調 ソナタ形式[13]。ピアノソナタ第14番としては、第3楽章のみソナタ形式となっている。堅牢な構築の上に激情がほとばしり、類稀なピアノ音楽となった[1][13]。急速に上昇するアルペッジョからなる譜例6の第1主題は、第1楽章の3連符の動機を急速に展開させたものである[4]。頂点のスフォルツァンドでダンパーが解放される[14]。

ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『大ソナタ悲愴』("Grande Sonate pathétique")ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月11日~12日録音 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『大ソナタ悲愴』("Grande Sonate pathétique")は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピアノソナタ。作曲者の創作の初期を代表する傑作として知られる。 概要 正確な作曲年は同定されていないものの1798年から1799年にかけて書かれたものと考えられており、スケッチ帳には作品9の弦楽三重奏曲と並ぶ形で着想が書き留められている[1]。楽譜は1799年にウィーンのエーダーから出版され、早くからベートーヴェンのパトロンであったカール・アロイス・フォン・リヒノフスキー侯爵へと献呈された[1][2]。本作は作曲者のピアノソナタの中で初めて高く、永続的な人気を勝ち得た作品である[3]。楽譜の売れ行きもよく[4]、気鋭のピアニストとしてだけでなく作曲家としてのベートーヴェンの名声を高める重要な成功作となる[5]。 『悲愴』という標題は初版譜の表紙に既に掲げられており[6]、これがベートーヴェン自身の発案であったのか否かは定かではないものの、作曲者本人の了解の下に付されたものであろうと考えることができる[7]。ベートーヴェンが自作に標題を与えることは珍しく、ピアノソナタの中では他に第26番『告別』があるのみとなっている[1]。『悲愴』が意味するところに関する作曲者自身による解説は知られていない[8]。標題についてパウル・ベッカーはそれまでの作品では垣間見られたに過ぎなかったベートーヴェンらしい性質が結晶化されたのであると解説を行っており[1]、ヴィルヤム・ビーアントは「(標題は)気高い情熱の表出という美的な概念の内に解されるべきである」と説いている[8]。 ミュージカル・タイムズ誌に1924年に掲載された論説は、本作の主題にはベートーヴェンも称賛を惜しまなかったルイジ・ケルビーニが1797年に発表したオペラ『メデア』の主題と、非常に似通った部分があるとしている[8]。他にも、同じくハ短調で本作と同様の楽章構成を持つヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトのピアノソナタ第14番の影響も取り沙汰される[3]。とりわけ、第2楽章アダージョ・カンタービレの主題はモーツァルトの作品の第2楽章に見られるものと著しく類似している[9]。また、未完に終わった交響曲第10番の冒頭主題が同主題に類似したものだったという研究成果が発表されている[注 1]。グスタフ・ノッテボームは本作の終楽章が構想段階ではヴァイオリンとピアノのための楽曲であった可能性を指摘している[1]。 このピアノソナタはベートーヴェンの「ロメオとジュリエット」期の心境[3]、すなわち「青春の哀傷感」を写し取ったものと表現される[10]。描かれているのは後年の作品に現れる深遠な悲劇性とは異なる次元の哀切さであるが、そうした情感を音楽により伝達しようという明確な意識が確立されてきた様子を窺い知ることが出来る[10]。劇的な曲調と美しい旋律は本作を初期ピアノソナタの最高峰たらしめ、今なお多くの人に親しまれている[1]。 イグナーツ・モシェレスは、1804年に図書館でこの作品を発見して写しを取って持ち帰ったところ、音楽教師から「もっと立派な手本を基にしてスタイルが出来上がるよりも先に、そんな奇矯な作品を弾いたり勉強してはならないと注意を受けた」と回想している[8][11]。ベートーヴェン自身は持ち前のレガート奏法を駆使し、あたかもその場で創造されたものであるかのように弾いたとアントン・シンドラーは証言している。その様子は既によく知られていた本作と同じ曲が演奏されているのかと耳を疑うほどであったとされる[11]。 本作はピアノソナタ第14番(月光)、第23番(熱情)と合わせてベートーヴェンの三大ピアノソナタと呼ばれることもある。約100年後にロシアの作曲家ピョートル・チャイコフスキーが交響曲第6番『悲愴』を作曲しているが、その第1楽章にはこのピアノソナタの冒頭主題とよく似たモチーフが使用されている[7][10]。 演奏時間 約17-19分[2][10]。 楽曲構成 第1楽章 Grave 4/4拍子 - Allegro di molto e con brio 2/2拍子 ハ短調 ソナタ形式[10]。譜例1に示されるグラーヴェの序奏が置かれ、展開部とコーダでも姿を見せる[10]。同様の手法は選帝侯ソナタ第2番 WoO.47-2(1782年-1783年)の第1楽章にも見られる。 第2楽章 Adagio cantabile 2/4拍子 変イ長調 ロンド形式[14]。ベートーヴェンの書いた最も有名な楽章のひとつである[12]。ヴィリバルト・ナーゲルはベートーヴェン全作品中でも指折りの音楽と評価しており[14]、マイケル・スタインバーグはこの楽章のために「ハープシコードの所有者は最寄りのピアノ屋に駆け込んだに違いない」と述べた[8]。美しく、物憂い主題が静かに奏で始められる[2](譜例5)。 第3楽章 Rondo, Allegro 2/2拍子 ハ短調 ロンド形式[14]。譜例8のロンド主題は譜例3から導かれているが[12][14]、第1楽章とは異なって劇的な表現を抑えて洗練された簡素さを感じさせる[8]。 その他 編曲例 ヤドカリ 「ベートーベン」 鈴木愛 「そっと。」(第2楽章) [GuiterFreaks&DrumMania] KOHTA 「RESONATE 1794」(第1楽章) [beatmaniaIIDX] ビリー・ジョエル 「THIS NIGHT」(第2楽章) 森田浩司 「愛のX」(第2楽章) 橋本祥路作曲 心の中にきらめいて(第2楽章) シンフォニー・エックス 「Sonata」- 『トワイライト・イン・オリンポス』の3曲目に収録(第2楽章) SMAP 「Theme of 008 (piano sonata no.8)」- 『SMAP 008 TACOMAX』の1曲目に収録 上田知華+KARYOBIN 「BGM」(第3楽章) 平原綾香&藤澤ノリマサ「Sailing my life」(第2楽章) ルネッサンス 「Island」- 1stアルバムの中の3曲目に収録 (第1楽章及び第3楽章) シジマサウンズ 「一番好きなあなたへ」(第2楽章) mihimaru GT「Love Letter」- メロディーを一部サンプリングしている(第2楽章) Joseph McManners [In Dreams] 09-Music of the Angles (第2楽章) ドラゴンハーフ 『Dragon Half』ドラマCD(1993年)中「戦え!サンハーフ」主題歌 作詞:松宮恭子 編曲:岸村正実 歌:坂井紀雄 (第3楽章) 上原ひろみ 「ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第8番《悲愴》第2楽章」 - 『ヴォイス』に収録 キッス 「Great Expectations」(地獄の軍団)(第2楽章) 渡辺直美 「見えないスタート」(2017年の競艇テーマソング)(第2楽章) ルイーズ・タッカー (Louise Tucker) - Midnight Blue (en) (第2楽章) 使用例 のだめカンタービレ(Lesson 1およびLesson67で、のだめが演奏している) るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- (第60話 「勝利を許されし者 志々雄対剣心 終幕!」で第2楽章がBGMとして使用されている) WXIII 機動警察パトレイバー (作品のクライマックスにおいて流される) HERO 第2期 (第7話のみ第2楽章がBGMとして使用) 心が叫びたがってるんだ。「心が叫びだす~あなたの名前を呼ぶよ」 (予告編のBGMのほか、作中でも重要な場面で使用されている) 遺留捜査 第1シーズン (第4話 「紅い石」で第2楽章がBGMとして使用されている) 銀河英雄伝説 (ゲーム) (スーパーファミコン版で、第1楽章をアレンジしたものが使用されている) スーパーカブ(アニメ) (第8話終末部で第2楽章をBGMとして使用)