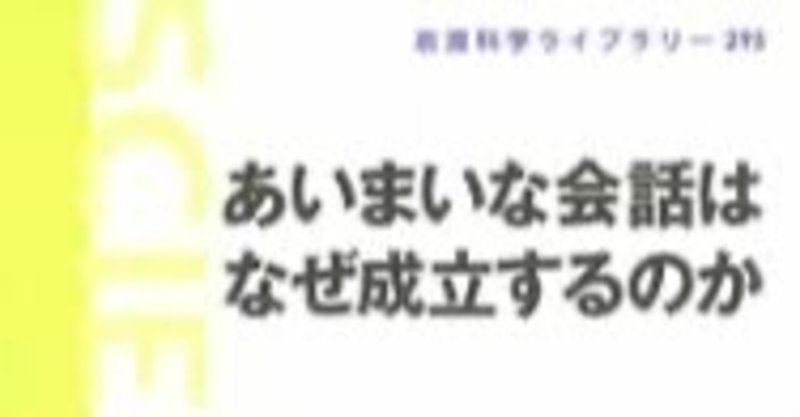
時本真吾『あいまいな会話はなぜ成立するのか』
私たちは日頃より何らかの言語を使って他者とコミュニケーションを行なっている。しかしながらそうしたコミュニケーションは、直接的というよりむしろ間接的であいまいな表現に埋め尽くされている。たとえば、他人から充電器を借りようとするときに、直接的な「充電器貸して」ではなく、「充電器持ってない?」といった回りくどい聞き方をすることがある。こうした迂回表現はいったい何のためになされるのか? そこに理由はあるのか? 本書『あいまいな会話はなぜ成立するのか』は、哲学、言語学、心理学、脳科学の知見を用いて、そのような謎を解明することを目指している。
三つのポイントの提示
まず次のような会話について考えよう。
A「コーヒー飲む?」
B「明日、朝が早いんだ」
ここにおいてAの問いかけは「yes/no」を求めるものだが、Bはそのようには応じていない。しかしながらそこに「no」が含意されていることを、私たちは容易に理解するだろう。つまりこの返答の背景には、「(コーヒーを飲んで眠れなくなったら困るので、遠慮しておくよ)」というメッセージが込められているのである。日常会話においてわれわれは、こうした言外の意味の適切な処理をほとんどストレスなしに行っている。
「なぜ」「いかにして」このようなことが行われているのだろうか。この問いかけは、より具体的な複数の問いかけとして、たとえば次のように切り分けることができる。人間はいかにしてメッセージを理解しているのか。また、そうした理解をなぜ容易におこなえるのか。あるいは、そもそもなぜ理解を要する間接的な表現方法をあえて選択するのか。著者は次の三つのポイントにまとめている。
【1】適切な文脈の検索
【2】推論の収束
【3】間接的表現の存在理由
結論から先に言えば、この本でこれらの問題が解決されることはない。この本が担う役割は、あくまでも様々な学問分野から集められた問題解決のアイデアをわずか120頁という分量でコンパクトに明快に記述することにある。
協調の原理
あいまいな表現を理解できるのはなぜだろうか。その問いに迫るためにまず紹介されるのは、ポール・グライスの「協調の原理」である。会話に参加する者はその会話の目的や方向性を踏まえつつ「当を得た発話」を行わなければならない。それがグライスによる協調の原理が意味するところである。お互いの発話が「当を得たものだ」という前提があるからこそ、われわれは(上に挙げたコーヒーの例のように)不完全とも思える発話であってもその意図を辿ることができる。文脈を想定し、含意を推論し、コミュニケーションの継続を促すのは、会話=協調作業という地盤なのだ。このように本書は、グライスの協調の原理を【1】適切な文脈の検索という問題への先駆的なアプローチとして位置付けている。
関連性理論
続いて紹介されるのがスペルベルとウィルソンによる「関連性理論」だ。こちらは、いささか哲学的とも言えるグライスの理論を、進化論の視点を取りいれて修正した理論だと言える。この理論の前提にあるのは、人間の心の働きが「適応的」にふるまうということである。それはつまり、コミュニケーションにおいても、その個体にとってより関連性の大きい事柄に注意を払うような、ある種の効率化が働く(そのように含意を解釈する)ということだ。あるメッセージを受け取ったとき、その個体は文脈のなかでもっとも効率的で無駄のない推論が解釈として採用するのだ。次の例を考えよう。
A「今度の日曜にホームパーティやるんだけど、鈴木君、呼んだら来るかな」
B「お姉さんの結婚式らしいよ」
ここでは、Aの問いかけに対して、Bが「お姉さんの結婚式」という新情報をもたらしている。これを受けてAの頭の中では「『お姉さん』というのは鈴木君のお姉さんのことだろう」、「姉の結婚式を欠席することはできないだろう」、「結婚式が行われるなら披露宴も同時に行われるだろう」、「その日はホームパーティーに参加できないほど忙しいだろう」といった思考がめぐらされ、最終的に「鈴木君は来ない」という解釈にたどりつく。ここで行われているのは、与えられた情報の価値(認知効果)を関連性の下に見定め、最小の処理コストで無駄なく解釈を引き出すことである。
このように関連性理論は、あいまいな発話でさえも瞬時にその意味を探り当てられるという、人の認知の仕組みをうまく説明している。しかしながらそこには限界もある。著者は関連性理論の枠組みの中では【2】推論の収束が今一つ説明できていないと指摘し、また【3】間接的表現の存在理由についても正面から応答できていないことを付け加えている。
ポライトネス理論
本書では、【3】間接的表現の存在理由に関して、二つの理論が紹介される。その一つ目がブラウンとレビンソンによるポライトネス理論である。これは、言語的コミュケーションにおける対人配慮に着目した理論である。一般的に直接的な言い方というのは、しばしば相手を傷つけたり、顔をつぶしたりするものである。そのためコミュケーションにおいては間接的な表現、つまり「ほのめかし」が用いられることが案外多い。たとえば「先生、寒いです(エアコンの設定温度を高くして)」、「もうちょっと早く相談してくれたらなあ(もう手遅れだ)」などがその例として挙げられる。前者は目上の人に命令することを避けており、また後者は手遅れの状態に陥った相手を気遣っていると理解できる。ポライトネス理論によれば、こうした対人配慮という機能こそが、間接的表現の存在理由なのである。先にあげたコーヒーの例に関しても、理由に言及することで、「いらない」という拒否が前面に押し出されるのを回避していると分析できるだろう。
戦略的話者の理論
しかしながら間接的表現は、対人配慮に発するものばかりではない。たとえば皮肉や嫌味を効果的に響かせるために間接的表現を用いることもあれば(ミスをした部下に対して上司が「いい仕事をしてくれたな」というケース)、相手を上手く出し抜くためにそれを用いることもある。そうした「非協調的な発話例」をも視野に入れつつ、間接的表現の存在理由について考察するのが、スティーブン・ピンカーの「戦略的話者の理論」である。(そしてこれが【3】間接的表現の存在理由に関する二つ目の理論ということになる。)
手短に言えばその内容は、ある種の状況下でははっきり言うよりも、あいまいな言い方をした方が得になることがある、というものだ。ピンカーは、スピード違反を犯した運転手と彼を呼び止めた警察官を例にあげる。罰金(罰則)を嫌がる運転手は、それ以下の額面を警察官に賄賂として渡すことで違反を見逃してもらえないかと考えている。もしも警察官が不真面目であれば、思惑どおり賄賂によって運転手は罰を免れることができる(無罪放免)。しかし、逆に警察官が真面目であれば、賄賂を持ちかけたことにより運転手は逮捕されるだろう。
素直に罰金を払うか、それとも賄賂を提案するか(その場合は、警官が真面目なら逮捕されるし、不真面目なら無罪放免になる)――これが運転手の直面している戦略的状況である。とはいえ運転手が取りうる行動は、実はもう一つある。それは賄賂を「ほのめかす」ことである。賄賂が単なるほのめかしに留まる限り、相手が真面目な警察官であればあるだけ逮捕の心配はない。なぜならば、あくまで賄賂はほのめかされているに過ぎず、決定的な証拠を欠くがゆえに、もし強引に逮捕でもすれば冤罪になる可能性があるからである。結果として運転手は、罰金(警官が真面目だったとき)か無罪放免(不真面目だったとき)かという最も有利な条件でゲームをプレイすることができる。
以上がピンカーの戦略的話者の理論の概要である。ここではほのめかし(間接的表現)が利得最大化のための戦略として採用されている。言質をとられずに意図を伝えること、いわゆる「相互知識」の回避により利得を最大化すること、ピンカーはそこに間接的表現の存在理由を見出すのである。
神経回路と連想ゲーム
最後に著者は脳科学の成果を紹介する。分量としてはこの部分が本書のなかで一番ページ数が割かれているトピックであるが、そこで個人的に最も興味深かったのは、(本書全体を通して繰り返し、扱いが難しいとされてきた)【2】推論の収束について考察される箇所である。とりあえずそれに関して簡単にまとめておきたい。
著者は90年代のバラエティ番組で行われていた、「マジカルバナナ」(!)を例にとって説明する。このゲームでは、複数の人間がある言葉からある言葉への連想を順番に行っていく。例えば「(Aさん)バナナと言ったら黄色」、「(Bさん)黄色と言ったらひまわり」、「(Cさん)ひまわりといったら夏」、「(Dさん)夏と言ったら暑い」、「(Gさん)暑いと言ったら…」といった具合に。不自然な連想が出た時点でその回答者が脱落していくという仕組みだ。
連想における自然/不自然の区別に合意がとれていることがこのゲームの前提である。それが難なくプレイされるためにはわれわれの脳の神経回路がよく似た形で安定している必要があると著者は指摘する。(そうしたありがちな形で安定する神経回路をもっていないことを発達障害や心的疾患の原因とする者もいるそうだ。)つまりこうした連想ゲームが合意の取れた形で行えることはすなわち、不完全な発話から突拍子のない解釈が引き出されることなく、ほどほどのところで推論が収束することと関係しているのではないか。そのように著者は示唆しているのである。
蛇足
以上がまあ全体の要旨と言ってよいのではないかと思う。それでは最後に、完全な蛇足ではあるが僕の感想というか妄想を書き留めておく。
本書で扱われていた、あいまいな表現やその解釈といった問題は、あんがい「詩的言語」や「ことばの文学性」について考える材料になるのではないか。そう僕は考えている。文学のことばを作るということは、簡単に言えば、現在の流通している普通のことば遣いのぎりぎり外にあるものをなかば強引に内部化していくことだ。それは難しい漢字や気取った言い回しを使うことではなく、また典型的に夢想的なイメージを書き連ねることでもない(それらは、もはや使い古されたもの、見る影もない文学的感動の残滓、噛みすぎたガム味のベビースターラーメンだ)。
ことばの常識的な使用法をあえて踏みはずし、伝わるか伝わらないかギリギリのところで、それを無理矢理にある種の「気持ちよさ」として流通させてしまうこと、それが文学の出発点にして終着点なのではないだろうか。それは、時の経過とその都度の実践によって自ずと変化していくことばの姿をいったん写し取ることであり、またその変化の傾向を人為的にねじ曲げることでもある。そして、もしもこのような文学観が成り立つならば、まだ掘り起こされていない「気持ちよさ」の源泉とは、たとえばこの本で言及された連想ゲームにおける自然/不自然の狭間、そのグレーゾーンに横たわっている。そんな気がしてならない。
……というようなことは『あいまいな会話はなぜ成立するのか』という本とはいっさい関係のないことだ。単に僕がこの本を読みながら勝手に考えたことに過ぎない。けれどもたぶんそれは僕にとっては掘り下げるに値するテーマなので、いつか気が向いたらまたそのことについて書いてみたいと思っている。
金には困ってません。
