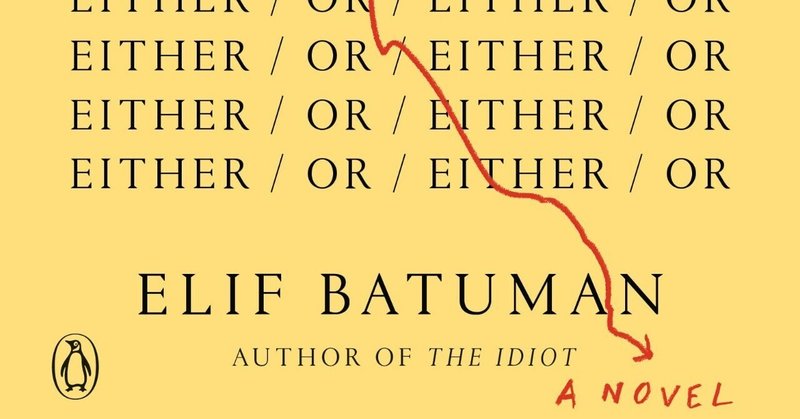
優雅な読書が最高の復讐である/Either/Or
読んでから少し時間が経ってしまったけれど、The idiotに続いて読んだエリフ・バトゥマンのEither/Orについて書いておこう。
The Idiotと同じく作者のアルター・エゴ、セリーンのハーバード大学2年目の物語だ。
「その人たちはHotmailというものの存在を知らないの?」という台詞やフージーズのKilling me softly with his songのシングルカセット(そういうものが存在した)をタワーレコードで買う描写が1996年という時代を感じさせる。
2年次になったら物語の顔ぶれも変わるものだと思っていたら、相変わらずイヴァンとの関係性は引きずっているし(メールや初期チャットの類でよく分からない関係がしばらく続行)、スヴェトラーナも出てくるし、前作からの地続きのような話かな、と最初は思っていた。当たり前ながら文体も雰囲気も変わらないし。
変わったのはセリーンの専攻である。言語学から文学へ。そこで彼女は(タイトルの基となっている)キルケゴールの「あれかこれか」の一部「誘惑者の日記」と出合い、これは自分の身に起きたことと一緒なのではと思う。
他に彼女が感情移入しながら、あるいは距離を置いて、疑問を抱きながらものめりこむテキストとしてプーシキンの「オネーギン」とブルトンの「ナジャ」が出てくる。
印象的なのは級友から勧められたマーティン・エイミスの「二十歳の時間割」を読むシーンだ。セリーンは主人公の恋人に対する残酷な描写を読んで、自分は物語を“書く側”でいようと決心する。
人生という物語の“主人公”であるべきか、それとも“語り部”であるべきか。自分のこれからの人生は既に本に書かれていることの繰り返しで、そこから脱するためには人生そのものから距離を置かなくてはならないのか。それが「あれか/これか」という二択の問題となってセリーンにのしかかる。体験と自分自身が乖離しているような青年期独特の感覚が、全編を貫く重要なムードになっている。
恋をして浮かれる周囲に影響されて、セリーンも前作では実体のないものだったセックスとロマンスに乗り出してみるが、彼女自身の体験の実感としても、話としても、不思議なくらい陳腐だ。
バトゥマンは30代まで男性と付き合っていたが、現在のパートナーは女性で、クィアとしての自分を見出すまでに苦労したと言っているから、このセリーンの性に関する違和感や不器用さは作者自身の紆余曲折の道のりを反映しているのだろう。
大学内の微妙な恋愛ゲームのルールに戸惑い、夏休み、ガイドブックの学生記者として派遣されたトルコで複数の男子と関係を結びながら(短いけどまともな交際と言えるのはカッパドキアで会った青年くらいだ)、彼女は常に自分の体験について自分自身に問いかけている。これは自分の物語においてどんな要素なのか? どのような意味があるのか? 読んでいると文章の5分の1くらいは疑問形で書かれているんじゃないかとさえ思えてくる。
主人公が自分のアイデンティティについて悩むこういうコミカルな思索小説といえば、近年はシーラ・へティのHow should person be?があり、バトゥマンのセリーン二部作やサリー・ルーニーの「カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ」はその影響下にある作品で、後続作品のヒットによってジャンル化しつつあるような気がする。オテッサ・モシュフェグのMy year of rest and relaxationもこの系譜に入るかもしれない。
ラスト、トルコを後にしてモスクワに向かうとき、セリーンはヘンリー・ジェイムズの「ある婦人の肖像」を読んでいる。そして物語のような人生を生きられない著者の男たちと、自分の物語を自分でコントロールできず、語ることができない物語のヒロインたちに想いを馳せる。
そしてここに来てようやく彼女自身の物語を取り戻したという感覚を得て、若い女性として、トルコ系移民二世として、エリート学生として、恋愛や人生に翻弄される身として定められたプロットから自分は脱出するとのだ確信するところで話は完結する。多分、セリーンの物語がビルドゥングスロマンとして書かれることはもうない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
