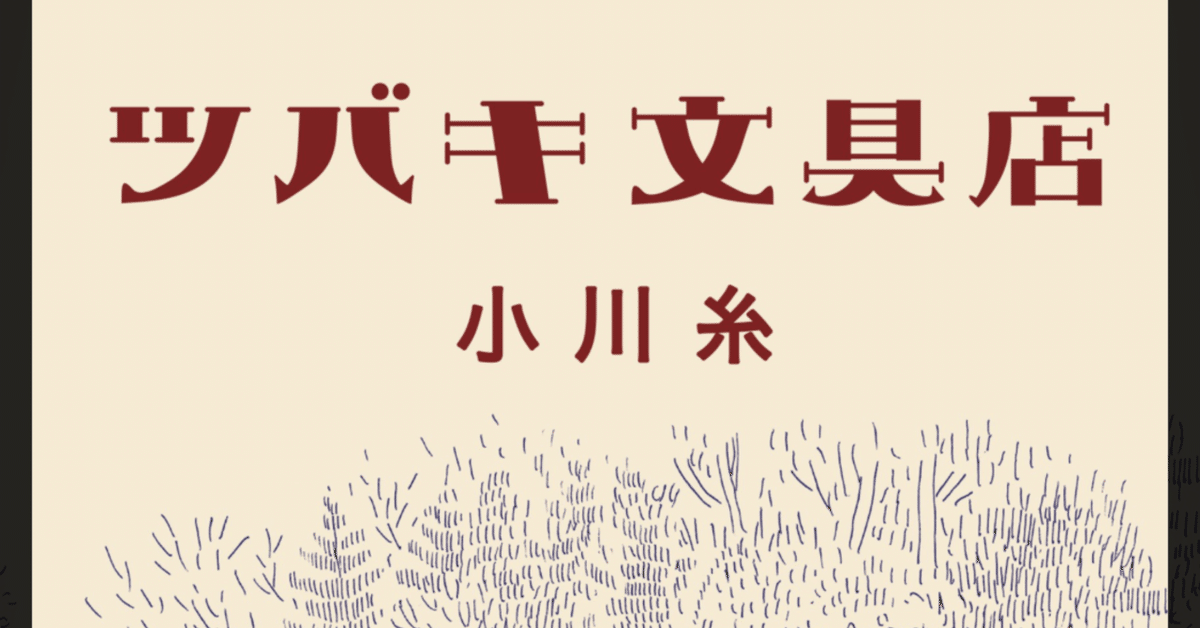
【読書感想文】小川糸/ツバキ文具店
*ネタバレを含みますのでご注意ください。
ツバキ文具店はNHKの夜ドラマで観たのが始まりだった。多部未華子さんはLiar Gameの映画で観たのが初めてだったが、このドラマの役柄は印象的だった気がする。
ドラマを観た時から少し時間は経って、小説は文庫本が出版された2019年に購入した。
ページ数は346、一般的なボリュームだ。
構成としては夏・秋・冬・春の四章から構成される。そして遊び心があるのか、ページの左下がパラパラマンガとなっていて可愛らしい。
主人公の雨宮鳩子は江戸時代から由緒正しく伝わる鎌倉の代書屋という設定だ。鎌倉という舞台がそうさせるのかもしれないが、どこか現代から少し離れた時代を想像させる。これが大正浪漫の時代であってもあまり違和感がないだろうというのが第一印象だ。その中で現代だと思わせる描写の一つが、鳩子が登場人物を「マダムカルピス」「バーバラ婦人」といった独特なあだ名でが語る場面だ。
設定の話はともかく、この物語は「代筆屋」という聴き慣れない職業を軸としているのだが、文字や文章にまつわる事柄をよく調べて鳩子というキャラクターを構築している。文章のマナーから鉛筆や筆の種類に加え、なぜその用具を選んだのかという理由のなかに、鳩子が依頼主に抱く想いが丁寧に描かれている。そのため一つひとつの場面が非常に読み応えがあるし、本書は物語が大きく動くことは少ない「日常小説」の要素が高いながらも、全体的に心に沁みる描写が多い良質な純文学だと感じる。
お気に入りの場面はいくつかあるが、
<夏>の「世界中の悲しみという悲しみを、瞬間、涙腺を磁石のようにして吸い集める。」という描写が特に共感を持てる。
誰かの悲しみを表現するための文章を書いている。そのためには自分が悲しいと思わないといけない。おばさんやペットが亡くなった時のことを思い出して、その瞬間、鳩子は依頼主の気持ちになりきっている。「嘘泣きをする時に悲しいことを思い出し、本当に涙が止まらなくなってしまった。」という現実でもよくある話を思い出す人は多いのではないだろうか。
文章は活字ではなく、実際に手で書かれた(であろう)ものが小説内に載せられている。これが心に刺さるポイントの一つだ。人の描く文字というのは活字とは違う感情を感じることが出来る。
<冬>の「叶うなら、私も愛する人からもらった手紙に埋もれるようにして天国へと旅立ちたい」という文章も気に入っている。とても乙女心のあるフレーズだが、これは依頼主の男性の母親が天国にいる父親からの手紙、ということで鳩子が代筆をした結果として鳩子が想っていた描写だ。
代書屋という職業は文章を書く瞬間、この人になりきる必要がある。その人になりきった時は、鳩子、そして読者にも熱が入る。しかし、その場面が終わった瞬間になぜか一種の虚しさを感じる。それは「代行」というものの宿命なのだろう。自分は何者かになる、そしてその勤めが終わった時、自分が何者なのか分からなくなる。これは全ての事柄に通じるものがある。虚しさの正体はこの感情に繋がるのではないだろうか。
そんな自我との闘いの結末は、今まで向き合ってこなかった「先代」と表現される祖母との手紙を通じた会話であった。物語が進み鳩子の悩む描写を見ていた中でおおよそ想像がついた結末であったが、今まで知らなかった祖母の弱い部分と向き合い、自分の思いのままを綴っていく。彼女がその文章を書き終えた時、「憑き物がとれた」と表現をした。今までの人生と向き合って、無我夢中に想いを放出した結果なのだろう。そしてその放出した想いは、何者でもない、鳩子自身の想いだ。
このように、鎌倉という風情のある街を舞台としつつ、依頼主に寄り添っていく満足感の裏にある虚しさを感じながらも、最後は自分自身を形成するものに向かっていく力強い物語だと感じた。綺麗な最後であったが、続編「キラキラ共和国」が刊行されている。こちらも時間が出来たら読みたいと思う。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
