
秋草の美学②:文化と絵画と言語
今回も、前記事「秋草の美学①:ゆりかごから棺桶まで」と同じく、源豊宗『日本美術の流れ』の言葉に反応したところを取り上げていきたいと思う。
この書籍の序章で源は西洋・中国・日本美術の三つを比較し、それぞれの象徴をヴィーナス・龍・秋草としながら特徴を述べていった。その中で「日本の絵画は線の絵画」と言及し、具体例をあげていく箇所がある。そこについて思うことがあり、一つの記事として書き残しておくことにした。
◆私の線の描き方は、日本訛り?
前記事でも書いたとおり、私は幼少期にアメリカへ引っ越したのだが、現地でみんなで絵を描く機会を重ねていくうちに、自分の絵がどこか異質なことに気づいていった。子どもは当然ながら見たものをそのまま描く技術がないので、アウトプットする際に何かしらのポイントを押さえた上でデフォルメした形を描くことになる。教室に並んだ絵を見るにつけ、個々人の独創性や絵の上手い下手以前の大前提が、自分だけ根本的に違っているように感じた。
そこから少しずつ観察と修正をくり返してすり合わせていったのだが、最後まで抜けきらなかったクセが線の描き方だった。自分の描く絵は、周りの友人たちと描きだす線の質がそもそも違っていたのだ。そして、その異質な線をもとに絵を描いてしまうから、結果としてアメリカ仕様の絵にならない……。色々と工夫しながら脱却を試みたものの上手くいかず、最終的に妥協した記憶がある。
たとえば色の使い方などは、比較的簡単に自分の中に取り込むことができた。それまで赤で描いていた太陽を黄色で描くようになった時のことは、今でも何となく覚えている。(ちなみに家では親の手前、赤で描き続けていた。)赤い太陽と黄色い太陽の違いに若干の困惑を抱きつつ、私の目から見て実物の太陽は黄色にも赤色にも見えないことが印象的だった。
それでも、これは一種の文化的なシンボルなのだとは理解していた。だから実際に太陽が何色なのかは関係ない。記号化されたシンボルを描くことで、受け取り側の中で実物の太陽のイメージに変換される。文化によってコードが異なるので表現を適宜変える必要はあるが、私は太陽そのものを絵で再現する必要はなかった。それは「太陽」と「the sun」という二言語間の関係性に似ている。

◆日本絵画は線の絵画
ここでいったん、話を『日本美術の流れ』に戻そう。
源は、日本絵画は対象をマッスとして描かないで輪郭として描く線の芸術になると言っていた。その内容について詳細を述べている箇所を、一部引用したい。
日本の絵画は線の絵画です。それは筆を使うからというだけではないのです。本質的には日本人はものを平面的に見るということそのことが、つまりものを輪郭的に見るということが、ものを線においてとらえるということになるのです。それが日本の絵画の線的表現とさせているのですね。同じく筆で描いても中国の絵画は、中国的人格主義はその筆の運動に、作家の主体的な芸術的生命の鼓動を表現しようとする。いったい中国では、筆は線を表現する道具ではなく、生命のリズムを奏でる器なのです。その意味で中国の絵画はまさに筆の芸術なのです。それが筆意というものです。
そんなことをいうと日本の絵画には筆意はないかと反問されそうですが、もちろん芸術家の手の動きなのですから、西洋画にだってタッチの勢いというものがあるのですが、問題はその事実を認めた上での様式的性格として、日本の絵画は本質的に線による造形という所に特色があるといえるのです。(略)それは書においても同じです。中国の書は単なる線の造形ではなく、筆の芸術なのですが、日本の仮名は、その特色が連綿遊糸にあるように、それはまさに線の芸術といってよいと思います。
私はこれを読んで、幼いころの私にとって「線」がネックになっていたことを唐突に思い出した。日本語訛りの英語とは無縁だった当時の私だが、絵については強めの「日本訛り」をもっていたのではないか?という考えがよぎる。
色彩感覚はローカライズに成功したのに、線は長いあいだ苦戦した……。その原因が何に由来するものなのか、自分でもいまだに分からない。でも、源の指す日本絵画の特徴である「線の造形」をもって絵を構築していたことはハッキリしている。源はもっと高次元な芸術的絵画について言及していたはずなのに、その萌芽が幼児の時点で見られるようになっていたことに、私はギョッとしてしまった。これは日本にいた時は一度も感じたことのない違和感だったので、少なくとも私の通っていた幼稚園では集団的に見られた傾向と推測できる。
◆言語に影響されない絵について
ちょうど同じくらいの時期、面白い動画に出会った。
「ゆる学徒ハウス」というプロジェクトのオーディション動画だ。こちらは2次選考動画の一つで、「ゆる美学ラジオ」という企画で応募されたナターシャさんのもの。
ナターシャさんは今年3月に東京藝術大学大学院(油画)を卒業された経歴をお持ちなのだが、ご自身の第一言語は絵だとおっしゃっていた。彼女は父親がアメリカ人、母親が日本人で、それぞれ自分の言語しか話せない家庭環境だったそうだ。こういった状況の子どもは、モノリンガル家庭の子と比較して言語発達が遅くなる傾向にある。そのため、彼女は言語を話すよりも先に絵を描き始め、0歳から親子三人のコミュニケーション手段として絵を活用していたとお話されていた。そこから解釈を広げ、「絵を描くには言語が必須だ」という学説に異論を呈している。彼女にとって絵は言語に依存しないものだからだ。
私にとっても、絵を描く行為は言語に依存しない。しかし、文化には依存すると思っている。前記事でも繰り返し述べた「自分を取り巻く膨大な量の情報を、どのように抽出・認知し、どのように輪郭を与え、どのように表出していくか」の規範は文化によって与えられるものであり、絵画と言語は「どのように表出していくか」の部分で分岐するという認識だ。絵にしろ言語にしろ音楽にしろ、共同体の中で受け渡ししやすい情報の形があり、共同体の一員として生きるにはまずそこを理解していなくてはならない。どのような個性があっても、世界へのまなざし方、要するに情報の抽出と認知はある程度文化に依存せざるを得ない。(これは、その母文化が自分の気質に合うか合わないかとは全く関係なしに刻み込まれてしまうものだ。生まれる場所や母語を自分で選べないように。)
この考えに基づくと、絵を描くには言語と同じシステムが土台として必要となるため、「絵を描くには言語が必須だ」という説に同意する結果となる。
しかし、ナターシャさんは十分な文化的影響を受ける前に絵を描き始めた。私にとって、そこが非常に興味深い点である。その後も成長していく過程で、文化の影響を内面化させることなく独自に絵画表現を発展させていったとするならば、これは大変面白いなと思った。率直にいうと、そんなことって可能なのだろうか?と少し懐疑的なのだが、それ以上にもっと深堀りして聞いてみたいと興味津々だ。私にとって思いもよらない世界が広がっている可能性も高く、それを知ることが出来るならばより嬉しい発見となるからである。
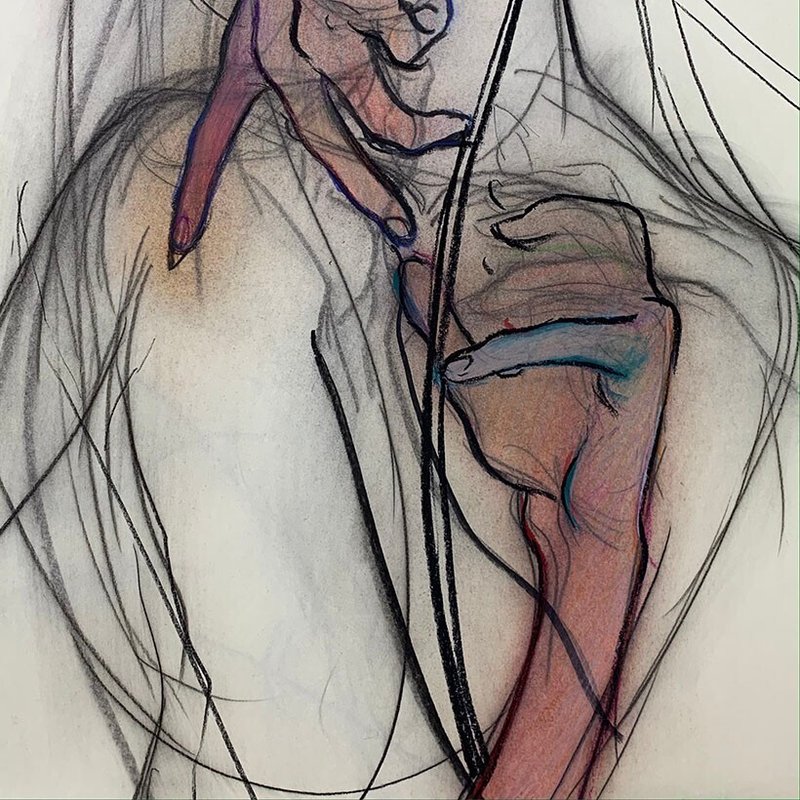
◆知らぬ間に内面化する母文化
なぜ私が「文化に依存しない絵」について懐疑的なのか。それは私たち人間は、自分たちで思っている以上に母文化の影響を受ける生き物だと考えているからだ。
たとえば、聴覚のための「脳と感覚のメカニズム」が誕生前から機能していることは、今では広く知られている。研究者により数字は多少変動するが、胎児は大体妊娠18週目ほどから耳が聞こえ始めるようになり、35週目頃には大人の聴覚レベルに近づくとされている。更に胎児は妊娠最後の10週の間に母親の話を聞くことで言語を学び始め、出生時には母語(≒母親の話す言語)と外国語を区別するようになっていることまで実証されている。
しかも、1歳(12.8ヵ月)で母語への接触を完全に断たれた国際養子(育った国であるフランスの言語のみを話す)は、音声を処理するときの脳活動がフランス語の母語話者とは異なると報告されている。彼らの脳の活性化パターンは、出生国の母語話者と一致したのである。これは人生の初期段階での経験が、神経レベルで永続的な影響を及ぼすことを示唆している。
ちなみに音楽も言語のリズム、パタンは反映される。マサチューセッツ州タフツ大学のアニ・パテルによる研究では、二つの音楽サンプルの演奏を聴いた大方の聴衆は、どの国の作曲家か当てることができたと報告されている。そこから言語と音楽の認知的処理には重複部分があり、形態と機能において多くの違いがあるにも関わらず、神経結合を共有しているとの主張が展開された。個人的にはこれは大変納得のいく内容で、私自身も作曲者や演奏者の言語による影響が音楽にあらわれているのを常々体感していた。しかも言語のリズム、パタンのみならず、音に対する情報の抽出と認知の傾向、表出の際の変換の仕方、美意識や感性への訴えかけ方も、作曲者や演奏者の文化的背景が色濃く見られると感じている。そしてこれは音楽にとどまらず、あらゆる芸術作品に通ずる傾向だとも私は思う。

「母文化が自分の気質に合うか合わないかとは全く関係なしに刻み込まれてしまう」と先述したが、様々な理由でそこから解放されよう・超越しようとする表現者は沢山いる。しかし皮肉なことに、それを意識すればするほどにその人の無意識の部分での文化的背景が透けて見えてしまうことが多い。(だから無意味だと言っているのではない。)
しかし出生時から二つの言語の影響を受けた同時性バイリンガルであるナターシャさんと、幼児期に二つ目の言語を身につける後続性バイリンガルであった私とでは、言語発達における影響は違った様相を呈することになる。この辺はまだ目ぼしい研究結果を引用できる段階ではなく、だからこそ一人一人の感じてきた・見えてきた世界の違いが如実に違って面白い部分なのではないかと思っている。
◆終わりに
前記事も今記事も、これは完全に私の体験(n=1)が出発点の話になる。自分の感じたことを俯瞰して見た時に見受けられた傾向を紐解く作業だ。そこには過度な一般化も含まれているだろう。しかし、個人の体感ではそうだった、というふうに理解していただければと思う。
バイカルチュラル(マルチカルチュラル)な子どもが受ける影響は、二つの文化を習得する過程や環境、習得状況などによって様々な違いがあるうえ、その人自身の生まれもった気質によっても大きく異なる。ある人に見られたからと言って、別の人に見られるとも限らない。私はどちらかというと神経質かつ要領が悪い慎重派だったのではないかと思う。こんなことにつまづくまでもなく、自然と適応していった友人も多く知っている。
私の場合は帰国の年齢もそこそこ早めだったため、言葉の方は現在では保持されていない。しかし表からの見えやすい部分ではなく、もっと根本的な認知の部分に刻まれた影響はいまだに感じることがある。それはどのように言語化したら良いか分からない、人と共有することが難しい部分だ。(そこには帰国時のカルチャーショック+母文化への再適応も含まれる。)
長いあいだ自分の中で感じていた「言いあらわしがたいもの」を、こういう流れで客観的に分析することになるとは、まったく想定していなかった。正直に打ち明けると、書いていく内に、しょうもない自分語りに自分でもウンザリしてきてしまった。だんだんどうでも良くなってきて止めようと思ったところで、ナターシャさんの動画と出くわすことになった。彼女の内容も、言ってしまえばただのn=1に過ぎない。しかし、統計や一般論では言い表すことのできない、個人がn=1をn=1として抱えたまま提示することの大切さを感じた。結局は自分の体験を真摯に語ることが、自分に対して一番誠実で大事なように思えてきたのだ。
その試みが成功したかどうかは、自分でもよく分からない。しかし、これはこれで、何かしら個人的なマイルストーンと位置づけることはできるような気がしている。
<主要参考文献>
エレナ・マネス(2012)『音楽と人間と宇宙 : 世界の共鳴を科学する』柏野牧夫監修, 佐々木千恵訳, ヤマハミュージックメディア
Christine Moon, Hugo Lagercrantz, Patricia K Kuhl, "Language experienced in utero affects vowel perception after birth: a two-country study" Acta Paediatrica, Volume 102, Issue 2 (2013).
Lara J. Pierce, Jen-Kai Chen, Audrey Delcenserie, Fred Genesee, Denise Klein, "Past experience shapes ongoing neural patterns for language" Nature Communications, 6, 10073 (2015).
Megha Sundara,Nancy Ward,Barbara Conboy, Patricia K Kuhl, "Exposure to a second language in infancy alters speech production" Bilingualism: Language and Cognition, Volume 23, Issue 5 (2020).
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
