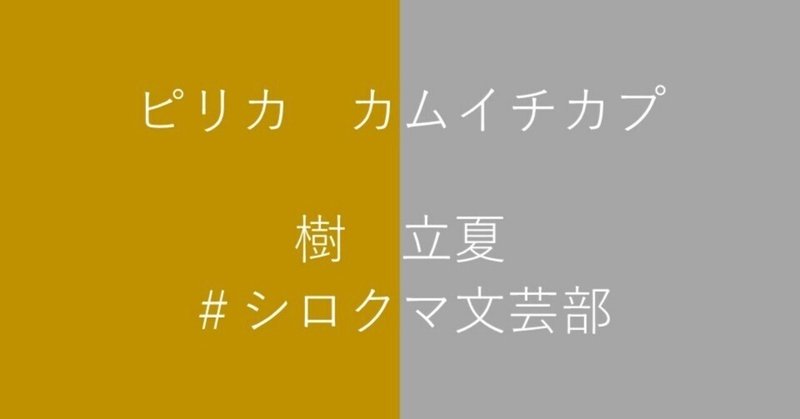
ピリカ カムイチカプ【#シロクマ文芸部】
新しい雪が、柔らかに僕の体温を奪う。凍り付いた冬の夜空に、金と銀の星々が瞬いていた。父さんが、僕の髪を掴んで腕を振る。瞼の傷からしみ出した血が、視界に入り込む。
またお酒を飲みすぎたんだろう。いいんだ。僕が耐えればいい。そのうち、父さんは僕を放り投げて寝てしまうんだから。お酒が抜けたら、いつもの気が弱い父さんに、ちゃんと戻るんだから。
「言え! どうして俺に黙って、あんな奴らの家に出入りしていた?」
——あんな奴ら?
「どうしてあいつらの家に入り浸っていたのか、俺には言えないのかあ?」
——あいつら?
頭にかっと血が上る。
黙って耐えていた僕は、初めて父さんに殴りかかった。
「どうしてそんなことが言えるの? 海の家族は僕に優しくしてくれた! 本当の家族のように接してくれたんだ! だけどこの家は、みんな嘘で、全部作りものじゃないか!」
一瞬、意識が飛んだ。僕は、父さんに殴り飛ばされていた。雪に埋もれたおかげで、頭を打たずに済んだ。肩で息をする。厳冬の冷気が、体中を凍らせていく。
父さんが、ぞっとするほど血走った目をして、足を上げる。青ざめた母さんが僕に走り寄り、震えながら僕の背を庇った。父さんは、舌打ちをして、「寝る」と言い、奥の部屋に引っ込んだ。
「サクラ」
母さんは、僕の額の血を優しく撫でるように拭うと、感情のない声で、囁いた。
「母さんと、逃げましょう」
父さんが眠っているうちに、最小限の荷物をまとめ、僕たちは家を出た。最後に、どうしても、幼馴染の海に会いたい。海の家は、この温泉街にある土産物屋だ。年の瀬の深夜、人などいるはずもなく、どの店にもシャッターが下りている。逃げる僕たちは、孤独だ。
ふらつく母さんの手を取り、白い息を吐きながら、海が暮らす土産物屋に辿り着いた。裏口の前に立ち、海の部屋の窓に雪玉をぶつけた。祈るように待っていると、鍵が開く音がして、懐中電灯を片手に、海が戸を開けた。僕の傷だらけの顔に驚いたのか、海は一瞬、漆黒の瞳を大きく見開き、僕と母さんを何度か交互に見た。
海は、状況を察するとすぐに踵を返し、足音を立てずに自分の部屋に駆け上がり、ぼろぼろの文庫本と、小さな木彫りを持ってきた。
「お守りにして」
知里幸惠というアイヌの女性が日本語訳をした、『アイヌ神謡集』と、梟の木彫りだった。
「これ、海が大切にしてた……僕、もらえないよ」
「いいから。お守りにして」
海は、本と木彫りを僕の鞄の中に押し込むと、僕の両手を取った。
「いい? おまじない」
海の瞳が、僕をまっすぐに見つめ、口が魔法の言葉を紡ぐ。
「シロカニペ ランラン ピシカン、コンカニペ ランラン ピシカン」
海がいつも諳んじていた、梟の神様の神謡だ。
「銀の滴 降る降る まわりに、金の滴 降る降る まわりに……」
僕は日本語で追いかけながら、ぼろぼろと泣いた。
「カムイチカプは、かならずあんたを助けて幸せにしてくれる。私はそう信じてる」
カムイチカプは、梟の神様だ。
海は、温かな指で僕の涙を拭った。
「また必ず会えるよ。カリンパニ」
海は、最後に優しく呟いた。僕の名前、「サクラ」という意味の、アイヌ語だった。
雪原の彼方、地平線が、群青色に変わっていく。夜明けだ。もうすぐ、父さんが起き出して、僕たちを探し回るだろう。
海に背を向け、母さんと手を繋いで走る。始発の列車に乗らなければ。ぜえぜえと白い息を吐きながら、僕たちは、声さえも出すことができずに泣いた。
僕と海は、春になったら、一緒に高校生になるはずだったのに。
僕達は、父さんが追ってくることを恐れ、北海道を離れた。シェルターや遠い親戚の家などを転々としながら、僕は、高校に行く代わりにアルバイトに明け暮れ、気づくと、十八歳になっていた。
辿り着いた関西の田舎で迎えた年の瀬に、僕たちは初めて、アパートの一室を借りた。古くて狭くて、隙間風が冷たかったけれど、僕たちはその部屋をこざっぱりと片付け、母さんのパート先のスーパーで分けてもらった蕎麦を食べ、二人だけで年を越した。
健康でいられるだけで、幸せだった。自分たちの足で立って生活できることが嬉しかった。窓辺には、海にもらったお守りの本とカムイチカプの木彫りを、いつも飾っておいた。カムイチカプの木彫りを見る度に、海との思い出が、僕を呼んだ。
「サクラには、辛い思いばかりさせてしまって……」
「母さん、またその話? 父さんと一緒にいるより、今の暮らしの方が絶対にましだって!」
正月の早朝にもかかわらず、僕を送り出してくれる母さんに、僕は笑って、新聞配達のアルバイトに出かけた。ふと、配達予定の新聞を見る。文字の羅列から浮かび上がってきた名前を見て、心臓が大きく脈打った。
——秋辺 海。
海だ。夢中で記事を読む。海は、十八歳にして、若手の登竜門とされる文学賞を受賞し、この新聞で、アイヌの民話とその解説の連載を決めた。
思わず、新聞を握りしめる。
『今月の民話は、知里幸惠さんが訳された、梟の神様、カムイチカプのお話です。シロカニペ ランラン ピシカン……』
「銀の滴 降る降る まわりに」
本にある、あの神謡だ。懐かしい記憶と共に、涙があふれる。海は、クジラが仲間を呼ぶように、ずっと僕に向けて信号を発していた。彼女が放った言葉が、ようやく僕に届いたのだ。
僕は、決意した。必ず、海に会いに行く。僕だって、海に届けたいものがあるのだから。
正月休みが明けると、僕は、母さんに断って、彫刻刀を買った。アルバイト先の材木店に頼んで、廃材を分けてもらい、我流で彫刻を始めた。
海のお父さんは、温泉街の土産物屋で、熊の置物を彫っていた。サケを捕まえた熊や、母熊と子熊の像。おじさんが彫った熊は、触れば温かそうで、今にも動き出しそうで、本当に、生きているようだった。
『いいかサクラ。全ての生き物は、皆カムイなんだ』
おじさんの優しい声が頭に蘇り、僕を奮い立たせた。
アルバイトの合間や夜に、僕はひたすら、木と向き合った。その木の中には何が存在するのか。その木の中から外に出たがっているものは何なのか。木の声に耳を傾け、彫り続けた。
季節が春から夏、夏から秋へと移ろい、木彫りを百体ほど彫り上げ、指にタコができたころ、父さんが交通事故で死んだと知った。母さんは、どこか少しだけ、ほっとしているようにも見えた。
彫刻を始めて一年になる年の瀬の日、家のポストに、一通のハガキが入っていた。
『日本彫刻コンクール 金賞 清沢サクラ様』
一瞬、思考が止まった。
「金賞……?」
僕がぽかんと口を開けていると、母さんが走り寄ってきて、ハガキを覗き込む。
「金賞! 金賞ですって、サクラ! 母さん、わかってたの。あなたには才能があるって。母さんの目は確かなんだから!」
母さんは、僕が習作のつもりで彫り上げて置いておいた梟の木彫りを、僕に言わずにコンクールに応募していたのだ。
嬉し泣きする母さんを横目に、ハガキに再度目を落とした。
『賞金 百万円』
「この彫刻を持って、海さんに会いに行きなさい」
母さんは、僕の額を優しく撫でた。
夜のうちに積もった新雪を踏みしめ、朝日がさす雪原を進む。凍てつく空気の中、雪の結晶が太陽の光を反射して、ダイヤモンドのようにあちこちできらめく。
飛行機のチケットは高価で買えなかったから、鉄道と船を乗り継いで、北海道へ帰ってきた。寒さで耳たぶが痛い。懐かしい冬の匂いの中、久しぶりの雪に足を取られながら、駆け出したい気持ちを抑え、それでも、心は黒い森を越えて、あの風景へと飛んでいく。
空に、鳥を探した。梟。カムイチカプ。神様の鳥。リュックの中には、コンクールで受賞した作品だけをつめこんできた。僕が彫ったカムイチカプは、おじさんが彫った熊——キムンカムイのように、ちゃんと生きているだろうか。
黒い森の木々を仰ぎ見る。古くからの友人と再会したようで、とても懐かしい。
森を抜け、温泉街に入る。今日は平日で、街は、お年寄りと外国人の団体客で混み合っていた。一時は深刻な客不足に悩まされていたと聞くが、状況は少し良くなっているようだ。人波をかき分け、海の土産物屋を目指す。
海のお父さんは、店の前で黙々と木彫りをしていた。以前とちっとも変わらない優しい瞳が、驚くこともなく、僕をとらえた。
「お帰り」
おじさんは、にっと笑うと、店の奥を指差した。
海が、難しそうな顔をして、ノートパソコンの画面を凝視していた。執筆中なのだろう。しばらく見ない間に、艶やかな黒髪は腰のあたりにまで伸び、もともと透明感のある肌は、雪のように白くなっていた。
海、と言おうとして、声を飲み込む。
違う違う、そうじゃない。勇気を出して、声をかける。
「アトゥイ!」
突然アイヌ語で呼ばれたことに、よほど驚いたのだろう。海は、飛び上がるように顔を上げた。輝きを増した宝石のような瞳が、涙に飲み込まれていく。
「カリンパニ?」
震える声で僕を呼ぶと、ふらふらと立ち上がり、こちらへ歩いてくる。
「これ、僕が彫ったカムイチカプ。君に見せにきた」
リュックの中から、木彫りを取り出した。
「子供の頃にさ、二人で、冬の森でカムイチカプを見つけたこと、覚えてる? 音も立てずに、大きな翼を広げて、あっという間に獲物を捕まえたよね。あの瞬間をどうしても切り取りたくて、彫ってみたんだけど……どうかな?」
海は、何も言わず、じっと木彫りを見つめた。
沈黙に耐えきれず、僕は口を開いた。
「これ、母さんが、勝手にコンクールに応募しちゃって。賞をもらったんだ。まぐれだよ。おじさんのキムンカムイに比べたら、まだまだ拙いし。でも、うち、貧乏だからさ、賞金はありがたかったんだ」
海は、ぴくりとも動かない。
「海、文学賞とったんだね。僕、スマホもパソコンもないから、検索できなくて。テレビもないから、海が受賞したっていうニュースも知らなくて。新聞配達のバイトの時に、記事を読んで知ったんだ。海って、昔から本ばっかり読んでたもんね。……どうしたの? なんか言ってよ!」
ふざけて笑ってみせても、海は黙ったままだった。
「ピリカ」
——綺麗。
静かに、優しくそう言うと、海は、天を仰ぎ、息を吸って、笑った。直後、海は、思い切り僕に抱きついた。
「ほらね、言った通りでしょ? カムイチカプは、絶対あんたを幸せにするって!」
海は、僕を抱きしめて、大きな声を上げ、笑いながら泣いた。
僕たちは、目を合わせると、おまじないの言葉を唱えた。
「シロカニペ ランラン ピシカン」
「銀の滴 降る降る まわりに」
額に、海の額の温かさを感じた。
海の漆黒の瞳から、銀の滴が次々とこぼれ、白い頬をとめどなく伝った。
冬の空気には、いつしか、生命の香りが混じっていた。
<終>
この小説は、小牧幸助さまの下記企画に参加しております。
小牧部長、今年最初の小説、書けました!
発表の場を頂き、深く感謝申し上げます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
