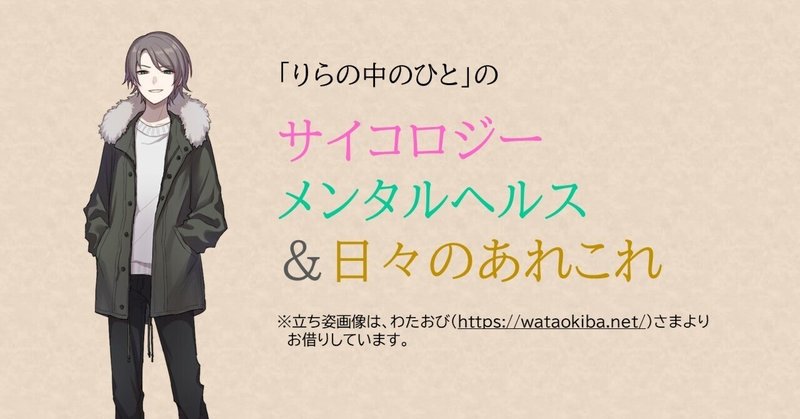
【シリーズ摂食障害Ⅱ・#5】 「内的知覚の混乱」をめぐって
【シリーズ摂食障害Ⅱ・#5】 「内的知覚の混乱」をめぐって
「サイコロジー・メンタルヘルス&日々のあれこれ」
摂食障害への理解を深めていく連載は、シーズンⅡに入っています。摂食障害と関連する心理面の特徴について、理解を深めています。今回は、摂食障害における心理的特徴の一つとされる「内的知覚の混乱」について取り上げます。
1.外的情報だけでなく、内的情報を覚知できることが必要
私たちは、目(視覚)、鼻(嗅覚)、舌(味覚)、皮膚(触覚や痛覚など)といった、全身のさまざまな感覚器から外界の情報を覚知し、必要な処理を行った上で表出・行動しています。私たちが環境に適合して生活する上で、外界の情報を正しく覚知できることは、とても大切です。
ところで、私たちの生存のために必要な情報は、外界だけにあるわけではありません。食欲に関わる空腹感・満腹感や睡眠欲、疲労、性的興奮、女性であれば生理周期における体調変化などの、生存や繁殖に関わる内的情報を覚知し、適切に対応する(空腹なら食べる、眠いのなら睡眠をとるなど)ことも大切なのです。
同じ意味で、喜怒哀楽といった自身の気分・感情状態を把握し適切に処理できることも大切です。“恐怖”という感情を例にすれば、そのような対象(例えば、散歩中にばったり出会ったヒグマ)に対しそれ(“恐怖”)を感じることができれば、急いで退避するなどの適応的な行動をとることができるのです(蛇足ですが、ばったりヒグマに出会ってしまった時、あわてて逃げ出すと追いかけられてしまうので、相手を刺激しないよう、静かに語りかけながら後ずさりにゆっくり移動するのがよいようです)。
生存や生殖に関わる内的情報や、気分・感情状態を覚知することを、総じて「内的知覚」と表現します(気分や感情も、内外の刺激に強く影響されるとはいえ、それが生じるのは個体の内部です)。
2.心身症におけるアレキシサイミア概念
発症や経過が、心理社会的要因に強く影響を受ける身体疾患を「心身症」といいます。私たちの心理的なプロセスと身体的なプロセスとは、互いに影響し合うもの(心身相関、といいます)ですが、心身相関が強く見られる病態を、特に心身症というのです。職場でのストレス(心理的なストレス)により、気晴らし食い(身体的ストレス)がやめられず、その結果罹患してしまった「胃潰瘍」(身体疾患)などは、心身症の代表例といえます。
ところで、心身症患者では、経験的に、自身の気分・感情状態への気づきや表出が乏しい場合が多いことが見出されていました。この特徴をアレキシサイミア alexithymia といいます。さまざまに発せられているストレスサインに気づかず対処が遅れる(ないしは不適切なやり方で対処してしまう)ことによって、ストレス反応をこじらせ疾病化してしまうものを「心身症」と考えるわけです。先の「胃潰瘍」の例では、この患者は自分自身では、疲れや心理的ストレスに気づかず、疲労に対する適切な対処(休息)をとらず、身体的にストレスとなる対処(気晴らし食い)を続けた結果、ある時突然、体調を崩してしまうことになるのです。
3.摂食障害における「内的知覚の混乱」
摂食障害は、精神疾患ですが、心身医学的には「心身症」のひとつと考えることもできます。摂食障害でも、アレキシサイミアのような心理的特徴を認めることが多いのですが、近年はアレキシサイミアという語を用いず、「内的知覚の混乱(障害)」というようになっています(考え方の中身はほぼ同一)。
次回、摂食障害における「内的知覚の混乱」の様子を、具体的に見てみたいと思います。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
