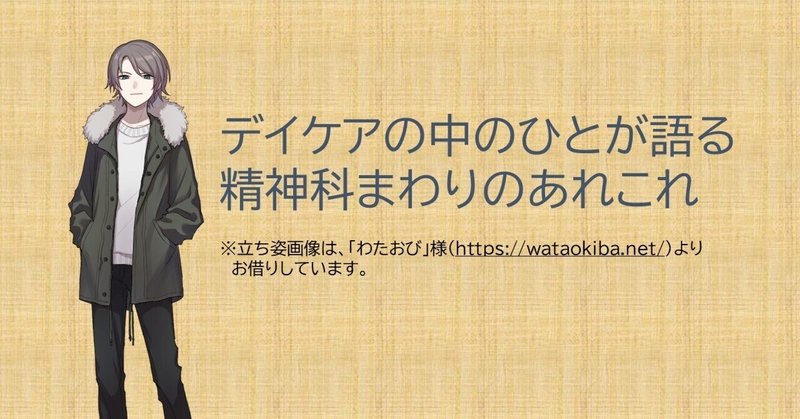
デイケアの“マンネリズム”をどう考えるか
デイケアの“マンネリズム”をどう考えるか
「デイケアの中のひとが語る、精神科まわりのあれこれ」#120
精神科デイケアで働いていた(退職予定)心理士が、精神科医療や心理支援についてあれこれ語る大人気シリーズ。
これまで私は、精神科デイケアがより治療的に機能するためには、いろいろと学び工夫することが必要だよ、と口を酸っぱくして繰り返してきました(すみません、何か偉そうだったな、と謝りたい気持ちではあります)。デイケアの“マンネリズム”をどう考えるのか、一度まとめておこうと思います。
***
1.“マンネリで何が悪い!”説
私たちの生活は、概して“マンネリ”です。連日“奇想天外な”ことが頻発する生活では、疲れてしまいますよね。“マンネリ”とは概ね、“安定”とか“平和”を意味するものです。
デイケアには、一定の期間(数か月から数年、それ以上)、一定の頻度(週に数回)通うものです。ほとんど“生活の一部”となるわけですから、“マンネリ”でもいいのです。
精神疾患や障がいの特徴に、「病状の波、生活のしづらさの波がある」「刺激に弱く、環境の影響を受けやすい」というものがあります。その結果、安定した生活を続けることが難しい場合もあるために、デイケアに通い続けながらリズムを保つ、という治療が成り立つのです。「マンネリズムの治療的効果」とでもいえましょう。一部の患者様にとって、“マンネリ”であること自体が難しいのです。
2.“マンネリ”であり続ける難しさ
ところで、矛盾しているようですが、変わらずにいるためには、常に変わり続けなければなりません。
そのことを、私たちはコロナ禍で身に染みるように理解しました。デイケアがふだん通り回っている(スタッフ側からは「ふだん通り開室させている」、患者様からは「安心して通える」)裏では、絶えざる努力と工夫が必要である、と。市中の感染状況に応じて、対策を変化させ、プログラムの見直しを行うこと(最強の感染対策を漫然と続けるのは、安全ではあっても、治療的ではない。対策を怠り“なすがまま”なのは、言わずもがなである)。これは実に難しいことです。
3.その上での“マンネリズムの打破”
デイケアをしっかりと継続する、それが“マンネリ”であったとしても。その上で、患者様のリカバリーに向けた試行錯誤をしっかり行っていく必要があります。この点は、これまで語ってきたことの繰り返しになります。
”マンネリ“を大事にしましょう。その上で、変えなければならないものを変えましょう。私の退職(と、”大人の都合“で、治療構造そのものを転換させなくてはならない)を控えているので、この機会に旧弊を一掃したい気持ちが、残されるスタッフたちにはあると思います。慎重に進めましょう。
***
これまで、「デイケアの中のひとが語る、精神科まわりのあれこれ」として、一連の投稿を行って参りました。
私が病院を退職することにより、「デイケアの中のひと」でなくなること、投稿を重ねること120回(!)で、区切りがいいことなどを考慮し、この投稿をもって「デイケアの中のひとが語る、精神科まわりのあれこれ」シリーズを終了させていただきます。
これまでのご愛顧、誠にありがたく御礼申し上げます。(タイトルや内容を変えつつ)投稿自体は続けて参りますので、引き続きご贔屓賜りますよう、お願い申し上げます。
りらの中の人 拝
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
