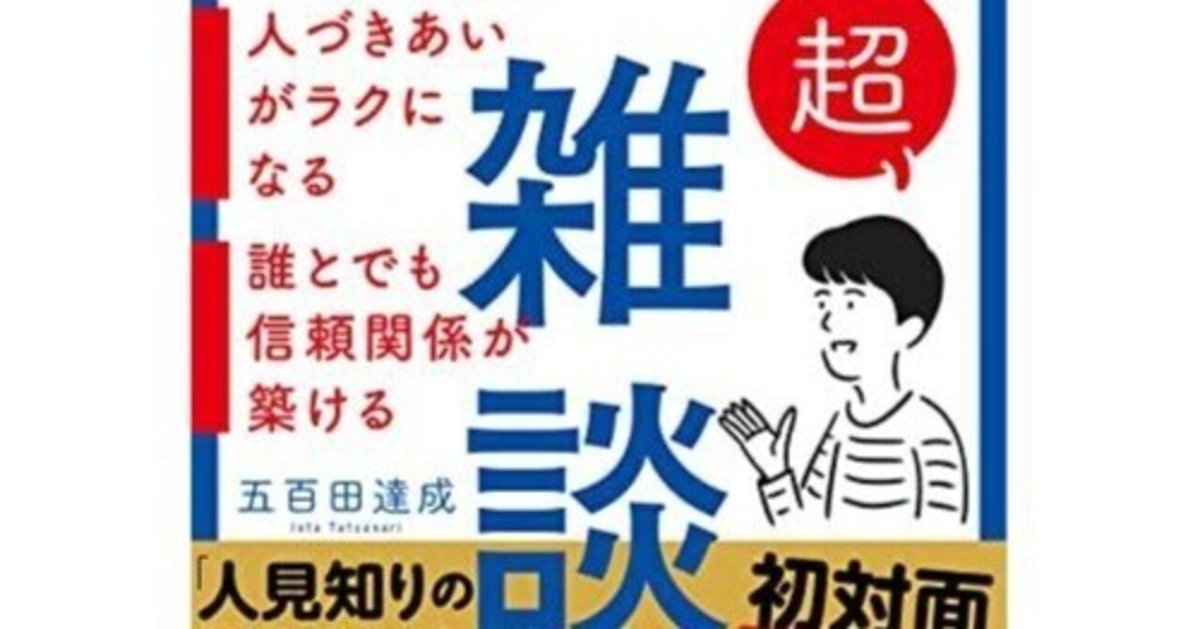
【本の要約】雑談ニガテな僕が、誰とでも信頼関係を築けるコツをまとめた『超雑談力』を読んでみた
今回の記事も僕が気になった本の要約です。紹介するのは、五百田達成さんの書かれた『超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける』という本です。100万部以上売れたベストセラーです。
内向的な人や発達障害の人にとって雑談は厄介な課題ですよね。
「雑談って一体何を話したらいいんだ?」
「適切な相づちの仕方は?」
「天気の話はアウトと聞くけど本当なの?」、等々。
雑談に関する疑問や悩みごとは枚挙にいとまがありません。
もちろん僕も例外ではなく、雑談は自分にとって大きな壁となっています。ついには、雑談に対する苦手意識が頂点に達するあまり、雑談に参加することすら諦めました。「コミュニケーション下手」のレッテルをはられ、職場では浮いた存在になった時期もありました。
特に、発達障害の僕にとっては、一見「意味のない内容」の話をする雑談は心理的に受け入れられません。ASDの僕にとって「意味のない・目的のない物ごと」は恐怖対象そのものであり、雑談の時間は気持ち悪い・不気味な存在と言っても過言ではありません。
そんな雑談アレルギーの僕にとって、この本は新たな気づきや学びをたくさん与えてくれました。雑談に関する本は既に巷に多く溢れています。僕もいくつか手に取ったことがあります。
雑談の本というと、「リアクションには『さしすせそ』が大事だ」のような、どれも同じようなテクニックを羅列したものばかりだ、という印象をもっていた僕にとって、この本は衝撃を与えてくれました。役立つ情報ばかりで1,400円(ソフトカバー版)の価格でもお釣りが返ってくるほどの良書でした。
具体的にこの本は下記の4点で優れています。
✔︎ 最初に「雑談の目的」を明確に提示してくれる
✔︎ 紹介されているテクニックはなんと35個
✔︎ どのテクニックも練習で習得できるものばかり
✔︎ 会話例が豊富でシチェーションがイメージしやすい
雑談の目的を明文化してくれることは、何事にも目的や意味がないと気が済まないという僕のようなASDの人にとってすごく助かります。また、目的を理解することでゴールを達成する意欲が湧き上がり、雑談を頑張ろうという気持ちにさせてくれます。
ちなみに、著者の五百田達成さんは心理カウンセラーの方で「コミュニケーション×心理」を軸に恋愛や結婚に関する本を多く出されています。米国のキャリアカウンセラーの資格を持っているすごい方のようです。
さて、前置きが長くなりましたが、下記から本の中身に入っていきます。
本のなかで紹介しているテクニックは35個ですが、今回は特に僕が良いと思ったものを選りすぐり9個だけ紹介しています。
気になった方はぜひリンクからお買い求めください。
◇◇◇
1.雑談の目的とは
著者は一番最初に雑談の目的を提示してくれています。
雑談の目的はズバリ「人間関係の構築」にあります。
職場の給湯室での同僚との雑談、幼稚園の送り迎え時のママ友との雑談、バーの店主との雑談。状況は各々ですが、全ての雑談は、会話を通じてお互いの警戒心を解き、スムーズで円滑な関係にシフトするのが目的であると著者は言っています。
実際に、この本の中で、著者は雑談による成功談の具体例を提示してくれています。
「初対面の相手と、どうでもいい話で盛り上がってすっかり意気投合した」
「堅物の取引先と、長々と世間話をしているうちに商談がまとまった」
余談ですが、オードリーの若林さんは雑談についてご自身のラジオでこんなことを言っていました。
若林正恭:天気の話するとかじゃなくて、「集団の一員として、エレベーターが来るまで毛づくろいしようや」ってことなわけじゃない。
春日俊彰:なるへそ、なるへそ。
若林正恭:だから、「私たち集団の一員ですよね?」ってことの確認が大事なわけで、実際、天気の話をしてるようでしてないっていうか。
春日俊彰:ああ、はいはい。そこで何かをとりにきてないってことね。
若林正恭:天気の話、ガチでしてないのよ。天気の話30%、集団の一員ですよの確認70%だな、あれは。
雑談は「私たち、集団の一員ですよね?」の確認。つまりお猿さんたちの毛繕い(グルーミング)と同じような働きを果たしていると若林は言っています。
2.明日から使える雑談のテクニック集
ここからは書籍で紹介している雑談のテクニックのシェアに入ります。書籍の35個のテクニックのうち、特に「僕が良いと感じたもの」・「他の雑談本では見かけなかったもの」をピックアップさせてもらいました。
① 情報交換ではなく、気持ちをやり取りする
著者の五百田さんによれば「仲良くなりやすい雑談」というものが存在するらしいです。「雑談の内容は何でも構わない」「天気の話自体は重要でない」と上で述べましたが、雑談の目的が人間関係の円滑化であることを考えるとより目的達成に近い雑談をすべきことは明らかです。
まずは下記の2つの雑談を比べてみましょう。
A:「最近いいゴルフのドライバーを買いまして」
B:「どこ製ですか」
A:「◎◎製です」
B:「どうしてそれにしたんですか」
A:「飛びが違うと聞いて」
B:「なるほど、私も検討します」
A:「最近いいドライバーを買ったので気持ちよく打てるんです」
B:「わかります!しっくりくるクラブって貴重ですよね」
A:「一旦『これだ』と思っても、すぐにわからなくなるから困ったもんですよ」
B:「でもまあ、難しいからこそ、ゴルフは楽しいんですよね」
A:「そうなんです。やめられませんね!」
どちらが「良い雑談」か一目瞭然ですよね。
前者は情報のみを伝えていますが、後者は「情報」ではなく「気持ち」をやり取りしていますね。後者の方が話が盛り上がっていることが文字からも読み取れます。
調べればわかる冷たい情報ではなく、人それぞれが持っている生の情報やその人の感情を共有することが大事だ、と五百田さんは仰っています。関係が親密になること間違いありません。
②肯定して共感する
雑談で大事なポイントは下記の2点です。
✔︎ 会話のラリーをひたすら続ける
✔︎ 相手が自分の気持ちを発しやすいように会話をつなげていく
雑談はある意味で、何もない「間」の時間を埋めるためのもの。すぐに終わってしまっては気まずい時間が流れるばかりです。また、人間関係円滑化のために相手を知ったり相手と仲良くなるために相手の気持ちや意見を聞き出すことが重要です。
そのためにやってはいけないことが2つあります。
✔︎ 相手の発言を否定/訂正する
✔︎ 良かれと思って、アドバイスをする
良くない雑談の例を実際に見てみましょう。
A:「最近、寒くなりましたね」
B:「あ、でも、来週は暖かいみたいですよ」(訂正)
A:「あ、そうなんですね…。急な気温の変化で風邪をひいちゃいました」
B:「手洗いをしていますか。気をつけたほうがいいですよ」(アドバイス)
このような返しをされたらAは雑談を続ける気が消失します。ラリーも続かないし、自己開示をしようとは思わなくってしまいます。
肯定されると、人は気持ちを打ち明けてくれるようになります。(よく「心理的安全性」と言われる環境です)
A:「最近寒くなりましたね」
B:「そうですね。朝晩とかめっきり冷え込みますね。」(肯定)
A:「急な気温の変化で風邪を引いちゃいましたよ」
B:「うわ、それは大変だ」(共感)
聞き手は、「とにかく肯定する・共感する」を実践してください。仮に、相手が好き勝手に話をした場合でも、イライラせずに否定したりアドバイスをしたりしない忍耐力も必要かもしれません。
雑談においてアドバイスは禁物とされています。
「ちょっと困ったことがあって…」「最近、悩んでいてね」などという相手の言葉は一見、相談かのように見えます。しかし、ほとんどの場合、相手はただ話を聞いてほしいだけだったりします。
このような愚痴や雑談に対しても、ひたすら肯定・共感することで、相手に気持ちよく話してもらうことが大事です。これが正しい雑談力です。
ちなみに、五百田さんによれば、語尾に「~よね」をつけると、それだけで共感度の高い雑談口調になります。
×「ほうっておけばいいよ」 ○「ほうっておけばいいよね」
×「苦手なんです」 ○「苦手なんですよね」
僕が執筆したこちらの記事でも「正論より共感が大事」ということに触れています。
③ 「趣味はなんですか」より「最近ハマっているものはありますか」
相手の趣味を聞くのは初対面の時には定番ですね。相手を知るための手がかりになり、場合によっては共通点が見つかるなんていうラッキーがあるかもしれません。
しかし、「趣味」という言葉はハードルが高い言葉です。聞かれた方は「”趣味”はどのレベルのものを指すんだろう」「”趣味”と胸を張って誇れるほどのものがないな」と余計なことを考えてしまうのです。
ところが、質問の仕方を工夫するだけで話がぐんと進んでいます。「最近ハマっていること(もの)はありますか」と聞きます。
「趣味」と言われると身構えてしまいますが、「ハマっていること」と言われると、好きなことや気になっている分野について語れます。質問が具体的なうえに、「どう思われるか」と他人の評価を気にしなくて済みます。
④「過去/未来/現在」で質問する
自分が知らないことを相手から教えてもらううえで、話が広がりやすい質問の視点は「過去/未来/現在」で質問することです。
先ほど触れた「最近ハマっていること」について聞くうえでも、この視点は効果的でしょう。
・過去 「昔からお好きなんですか」「いつから始めたんですか」
・現在 「今でもよく作るんですか」「最近は何がおすすめですか」
・未来 「じゃぁ今週末も?」「次に狙っている場所とかあるんですか?」
このように時系列に沿って質問を投げかけると、話が広がりやすいです。
過去は最初の質問として使いやすく、現在について聞くとお互いの心の距離が広まり、未来の話はスムーズに次の話題に移るステップになります。
相手がよく知らない話題を持ち出したら、「困った」ではなく「ラッキー」と思って、いろいろ教えてもらうと良いかもしれません。
⑤ 適度に「自己開示」を行う
まったく自分の話をせず、ひたすら質問ばかりしていると相手は不安になります。「自分ばかり話していて気まずい」「なんだか腹の内を探られているようで疲れる」という気持ちが湧いてきてしまいます。
雑談で自分の話をしすぎることはNGとされていますが、適度に自己開示を行うとよいです。
ここでオススメのコツを紹介します。
「自分が聞いてばかりだな」という自分に気づいたら、「少しだけ自分の話をしてから、再び相手に会話のバトンを戻す」を実践することです。
ここで大事な言い回しが、「私はよく~しちゃうんですけど、そういうことってないですか?」「僕、最近~だなあ。そう思いませんか?」のようなものです。
五百田さんは「3割自分の話、7割相手の話」がベストバランスと言っています。
⑥ 視線は相手の目ではなく口元に
コミュニケーションが苦手な人や内向的な人にとって、「視線をどこに置くか」問題は非常に大事ですね。この本ではその正解も教えてくれます。
正解は、「相手の口元」だそうです。これは程よく目を合わせているのに緊張を強いない、というベストな場所です。
相手の目を見ずに話すと相手の不安をかきたて、「どこか信用がおけない」という評価につながります。一方で、欧米人のように目を直視すると相手を戸惑わせてしまいます。
「目線を会話の途中で外すべきかどうか」というのも難しい問題ですが、会話の途中に時おり外す方が楽かもしれません。この辺りは好みの問題ですが、「視線に気をつけなきゃ」と考えすぎると緊張しすぎてしまい、それは相手にもつながってしまいます。
⑦「なぜ(Why)?」で理由を尋ねるのではなく、「どう(How)?」で状況や気持ちを尋ねる
良かれと思ってやってしまうNG雑談の一つに、「『なぜ?』と理由を尋ねる」があります。下の会話例を見てみましょう。
A:「この間、うっかり電車の中で寝過ごして終点まで行っちゃったんだよ」
B:「どうして寝過ごしたんですか?」
A:「え?ああ、えーっと…ちょっと飲みすぎて」
B:「なぜ、そんなに飲んだんですか」
A:「あ、いえ、久しぶりに学生時代の友人と会って…」
質問した方に悪気はありませんし、むしろ興味があって質問しています。しかし、質問された方としてはうまく話せなくてストレスが溜まります。
理由を尋ねられた瞬間、人の気持ちはすっと冷めるものです。「なぜだろう」と理由を考えて、頭が冷静になるからです。だから、「気持ちをやりとりする雑談」には、とても不向きな質問です。
また、「理由を尋ねる」という行為には、詰問のように批判的に聞こえてしまうリスクもあります。これでは相手は良い気分になりません。
質問するなら「Why」ではなく「How」を使うことが効果的です。
「ピーマンが苦手なんだよね」に対しては「どうして嫌いなの?」ではなく「どれくらい?」と質問します。先ほどの会話では「一度も目が覚めなかったの?」「目が覚めたとき、びっくりした?」と尋ねます。
⑧褒められたら謙遜ではなく素直にお礼を言う
「素敵なお洋服ですね」と褒められたら「いえいえ、そんな…」と謙遜したくなりますよね。日本人は謙遜することが美徳であるとされています。
しかし、この受け答えも著者はNGとしています。なぜなら、そこで会話が終わってしまうからです。
ここで、素直に「ありがとうございます」とお礼を言うと、好印象を抱かれ距離が縮まるとのことです。
また慣れてきたら、お礼だけでなく「+ひと言」加えると良いようです。
「ありがとうございます + お気に入りのブラウスで色違いも持っています」と返せば、「どこで買ったんですか?」と更なる会話のきっかけにもなります。
ちなみに、雑談とは違いますが、嫌味を言われた時も「ありがとう」と返すとカウンターとして機能するようです。
⑨ 立ち入った質問には「一般論」で返す
「年収、いくらなの?」「お子さんのご予定は?」というストレートで失礼な質問をする人がいますが、本当のことを真面目に答える必要はありません。自分の心が傷ついたり、相手はさらに深掘りした質問を投げかけてくる可能性があるからです。
そこで使えるテクニックが、「一般論で話を逸らす」ということです。
「僕の年齢だと500万円から800万円くらいが相場ですかね」「普通は何歳ぐらいで産むんでしょうか」
一般論で回答すれば一応、質問には答えていますし、暗に「自分ことは言いたくないアピール」につながります。
「それって少ないよね、私たちの時代は~」「だいたい、そういう相場っていうのは~」と、相手が食いついてきて、話が逸れたらこちらの勝ちです。
「仲良くなりたい人にはパーソナルな話を、距離を置きたい人には一般論を」。これが大事です。
3.さいごに
ここまで、9個の雑談テクニックを紹介させていただきました。今回紹介したのはほんの一部であり、この本には全部で35個のテクニックが載っています。
興味を持たれた方はぜひ書籍の方もご購入してみてください。Kindle Unlimitedでも読めるようです(2023年6月時点)。
雑談は意味のない時間のように見えて、実は人間関係をより良くする、距離をぐっと縮めるチャンスに溢れています。苦手意識のある人ほどこれらのテクニックを習得し、雑談を意義のある時間に変えてみてください。練習すればするほど、意識することなく自然とこれらのテクニックを使えるようになります。
僕もまだ道なかばですが、一緒に頑張っていきましょう。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が良いと思われた方は、♡ボタンまたは下の「オススメする」よりシェアの方をお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
