
ZARD 坂井泉水〜約束の歌はまだここにある〜
点滴の薬剤を取り替えた看護師が病室から出ていくと、自然とふーっと長い息が漏れた。無意識に入っていた身体の力が抜け、頭が枕に沈んでいく感じがした。
個室の病室のベッドで、仰向けのまま天井を眺める。天井にはランダムな縦長の歪な模様のデザインが施されていて、じっと眺めていたら、プロデューサーの長戸の顔が浮かんで、思わず苦笑する。
彼とは、何もなかった。わたしが一方的に何かを期待して、何かを失った気になっていただけだ。そのことが、今ならわかるし、認められる。その上で、彼のことが気になっていた当時の自分を愛しくも思える。彼自身よりもずっと。
午後はもう、見舞い客の予定もない。
窓際に置いてもらったベッドから外を見ると、楓が風に葉を揺らしている。大きな楓で、5階のこの病室からだと、木の上部のこんもり茂った梢と視線が並行になる。たくさんの葉が揺れる、ザワワ、という音が、耳元で聞こえる気がする。
目を凝らすと、楓の葉越しに小さな桃色が見える。病院のフェンス越しに植えられた桜の花だろう。
きっと窓を開けたら、少し肌寒い、けれどたくさんの生命(いのち)の気配を纏った春の風が、この腕を撫でてくれる。けれどそれは叶わない。癌に侵されたこの身にとって、感染症は命取りだ。目を瞑って、全身の産毛の先端に神経を集中したら、誰かに優しく撫でられた気がした。
------------------------------------------------------
入院してから、あまりニュースも見ないが、世の中はわたしのことなど構わず進んでいっているのだろう。
そのことに寂しさはない。むしろ少しだけ、ほっとしている。ZARDの坂井泉水でなく、久しぶりに長く、蒲池幸子でいられる。
歌手になりたいという小さい頃からの夢のため、突き進んだ今日までの道のりに、悔いはない。
色んなことがあったし、時には悔しさに眠れぬ夜もあったけれど、それ含めて、わたしの道だったと思うし、わたしが選んだ道だから。
先日、お忍びで摩季(大黒摩季)ちゃんが来てくれたのは嬉しかった。摩季ちゃんには、デビュー前からずっと甘えてばかりだ。元来、わたしは人見知りなのだが、なぜか摩季ちゃんの前だと、心がふにゃっと解けてしまう。
彼女の言葉や仕草、表情には、人を安心させ、包むオーラがある。その空気に、わたしは出会った頃から包まれて、安心させられている。摩季ちゃん、そう心の中で呟くだけで何故か、ふっと笑みが溢れる。そういう素敵な女性なのだ、摩季ちゃんは。
「早く元気になって、また歌声を聴かせて。約束だよ」
去り際、そう言われて、わたしは上手く頷けただろうか。
きっと、ぎこちなくなってしまっていたんだろうな。
摩季ちゃんは、そんな些細な仕草を見逃さない。
だから何も言わずにこっちをじっと見つめて、それから、またあのいつもの豪快で優しい笑顔で、じゃあまたね、そう言って帰っていった。
何も言わずに見つめられたあの数秒に、たくさんの言葉をもらった気がして、摩季ちゃんが帰ったあと、少し泣いてしまった。こんな自分が不甲斐なくて、悔しくて、早く元気になりたくて。また、歌いたい。そう、それだけ、そのことだけ、いつも思ってる。願ってる。
------------------------------------------------------
午前中、見舞いに来たスタッフと、新曲のレコーディングについて話した。まだまだわたしは歌えるし、歌う気もある。
けれど…軽く、パジャマの上から右手で左腕をさする。自分でも、細くなったのがわかる。
抗がん剤の副作用の吐き気がひどく、食べられない日が続いたせいだ。
顔はむくみ、髪も抜けた。鏡を見るたび、ため息が漏れそうになる。
最近は、立ち上がると身体がふらつくようになった。
こんな身体で、また、いや、まだ、坂井泉水をやらなきゃいけないのだろうか、やれるのだろうか。わかってる。世間が求めているのは、こんな下膨れた顔の、髪もボサボサの40才のおばさんではない。
憂いを秘めた横顔で、澄んだ歌声を響かせる彼女だ。
誰か。
最近、気づくとどこにもいるはずのない、誰かを求めている。
わたしは今まで、人に恵まれてきた方だと思う。仕事絡みで、とくにデビュー前後は色々、嫌なこともあったし、されたし、させられたけれど、それ以外では、基本的に、たくさんの人にサポートされ、守られてきた。
それなのに、心も体も弱った時に、誰か、誰かと、求めなくてはならないほど、誰もいないなんて、滑稽な話だと思う。
でもその一方で、誰もいないから、坂井泉水なんだ。
そうも思う。
誰か、今、わたしが思うような、絶対の味方がそばにいて、この細くなった腕を撫でてくれるような誰かがいたら、それはもう、坂井泉水ではないだろう。
朝霧の煙る、森の奥の湖の水面を、1人歩くような孤独。
わたしはぐっと全身に力を入れると、体を起こし、ベッドから足を下ろして、立ち上がった。
---------------------------------------------------
短大を卒業してOLをしていた時に、街でスカウトされた。原宿で友達とクレープを食べている時で、最初はナンパかと思った。
言われるままに連絡先を伝え、名刺をもらい、その時はそれで終わった。あまり現実味がなかったし、こんなことで、歌手になれるとも思えなかった。
だけど、そのあと、一緒にいた友達が少しだけ、よそよそしかったことを覚えてる。
良かったね、凄いね、サッチは美人だから。絶対電話した方が良いって、チャンスだよ、デビューしたら絶対コンサート行くよ、その言葉が全部何故か、小さな棘となって腕や太ももに刺さった。
やめてよ、そんなんじゃないって、勝手に盛り上がらないでよ、こんなのよくある話だよ、ただのナンパかもしれないし…必死に否定すればするほど、すぐそばにいる友達が遠ざかって行く気がした。誰か。やめてよ、1人にしないでよ。その時からかもしれない。わたしのそばにぴとっと、張り付いて、わたしを見張るようになったのは、孤独が。
------------------------------------------------------
言っても信じてもらえないだろうけど、わたしは自分が美人だとか綺麗だとか思ったことはあまりない。
学生の時から、それなりに異性から好意を向けられることはあったけど、クラスにはわたしより断然可愛い子が必ず数人はいた。いや、もっといた。
学校では、できれば目立たずにいたかったけれど、歌が好きという思いもあって、歌手への憧れもあった。目立ちたくないことと、歌手になりたいことは、矛盾していた。
高校生くらいの時、そうしたことに悩んで、父に相談した。友達に相談しようと思ったけど、相談できる相手がいなかった。わたしの悩みは、わたし以外の友達に相談した途端、「美人の贅沢な悩み」という一番嫌われる類の相談にすり替わってしまう代物だった。そのことを、自覚していた。
父が夜遅く仕事から帰ってきた日を見計らって、相談した。母も、兄弟も既に寝ていた。
わたしは自分の部屋にいて、父がそっと玄関の戸を開ける音を聞くと、一階に降りて行った。
急に現れたわたしに父は少しびっくりして、おぅ、とだけ言った。
「あのさ、少し、話あるんだけど」
父はネクタイを緩めていた手を止めると、軽く頷いた。
台所のテーブルで父と向かい合って座った。
「ごめんね、疲れてるのに」
「いや、それよりどうした?ちゃんと飯は食ってるのか、少し痩せたんじゃないのか?」
父は、わたしを見ると、必ず「飯を食ってるか」聞いてくる。そのお決まりな感じが鬱陶しくもあり、けれど安心できた。この人は、いつだってこう、同じように同じ温度でわたしと接し、わたしを心配してくれる。わたしに何があろうと、なかろうと。遠ざけたり、羨んだり、馬鹿にしたり、嫉妬せずに。
父はわたしの話を少し俯いて黙って聞いていた。
話終わっても何も言わないので、どう思う? とこちらから尋ねてみた。父は言葉を探すようになおも少し黙っていたが、どっちでもいいんじゃないか、と言った。
「俺にとっては、お前が歌手になろうが、ならなかろうが、変わらない。大切な娘だ。それ以上も以下もない。だからな、何もアドバイスなんてできん」
「そんな…」
わたしがあからさまに不満そうな声を出すと父は苦笑した。
「歌手になりたいなら、人前に出るしかないだろ。夢を掴みに行くには、勇気も痛みも必要だ。それができないなら、諦めるしかない。歌手を諦めても、人生には違う形の幸せがたくさんある。どちらを選ぶかは、お前次第なんだよ」
父と話した少しあとから、わたしは自分の中で1つの割り切りをした。
なりふり構わず、歌手という夢を掴みに行く。
そのために、自分にある使えるものは何でも使う。
それがクラスで4番目くらいに「美人」と思ってもらえる、見た目だとしても。
------------------------------------------------------
OLを辞めて、事務所に所属した後は、レースクイーンやモデルをやって、人前に出て、知名度を稼ぎながら、歌手になるチャンスを伺い続けた。
その日々を今、愛おしいと思う。
頑張ったな、自分、と思う。
辛いことも多かったけど、楽しいこともあった。
レースクイーンは女同士の蹴落とし合いの世界だったが、その中で、夏生ちゃん(岡本夏生)は名前の通り、真夏のひまわりのように明るい子だった。
どこそこの社長と一晩一緒にいれば幾らもらえるとか、優先的に仕事を回してもらえるとか、そういう話をあっけらかんとする子だった。
「マジで?夏生ちゃん、やったの?」
そんなふうに聞くと「いやそれがさ、金もらったらグアム行こうかなとか考えて気が抜けてさ、気づいたら鼻くそほじってたわけ。そんで台無しよ、いる?そんな奴?あ、いたわ、ここに。あっは!」
バシバシ肩を叩かれ、その痛さと、彼女の笑顔に、わたしはいつも、生き返った気がした。その痛さに、身を捩らせて笑ってる時だけ、ちゃんと呼吸できてる気がした。
ある晩、わたしの部屋で彼女と飲んだことがある。
「サッチは、これからどうするの?」
「わたし、歌手になりたいんだ」
そう言うと、彼女は頷いて、サワーの入ったグラスを握ってしばらく黙っていた。
「サッチ、歌上手いもんね。カラオケ機械の仕事もやってるんでしょ?」
「うん…機械のPRでね、どさ回りだけど、色んなところで歌わせてもらってる」

「そっか。楽しい?」
そう尋ねられて、わたしは少し考えて、苦笑した。
「どうかな…」
この間、PRイベントで泊まりで地方に行った時、マネージャーがいないところで、同行したメーカーの担当者から、「今夜、付き合ってよ」そう言われた。
やんわり断ると、担当者は、「そっかー。他にもこの仕事やりたいっていう歌手志望の子、たくさんいるんだよ。でも僕が君を推してるの。君には才能があると思うから」そう言って革靴でトントン壁を蹴った。
「すみません」
小さく謝ると、担当者はあからさまに舌打ちして、去っていった。去り際、衣装のミニスカートの中に手を入れられた。
「まぁ、色々あるよね」
夏生はとりなすように笑うと、飲もっ!と言って、わたしのグラスにビールを注いだ。
さんざん飲んで、酔い潰れてしまった彼女を、何とか立たせてベッドに寝かせると、わたしは床に横になった。
部屋の明かりを消して、しばらくすると、
「サッちゃん」
と小さな声が聞こえた。
「何?」
問い返して、しばらく待ったけれど、返事はなかった。わたしの聞き間違えか、寝言かと思って、わたしも寝ようと思って寝返りを打った時、小さな独り言のような声が背中から聞こえた。
「サッちゃんは、夢をかなえるんだよ。わたしのぶんまで」
わたしは、何も返事ができなかった。
------------------------------------------------------
午後は、病室の廊下を歩くことが日課になっている。
体力を落とさないための、リハビリの一環だ。
こういうルーティンは頑張れる方だ。
地道に努力するのは嫌いじゃない。
中学の時は陸上部で、200mで県記録を作った。
その時、努力の楽しさを知った。
やればやるだけ、記録が伸びる。
身体は正直だ。
苦しいことには必ず見返りがある。
では、この抗がん剤の苦しさの先にも、楽しさはあるのだろうか。きっとあるはずだ。グロリアスデイ。そう信じるしかない。
たくさんの人たちが、わたしの歌で希望を感じてくれている。わたしが諦めるわけにはいかない。諦めるつもりもない。たしかに病状は思わしくないけれど、だからって投げやりになったら、約束を破ることになる。
誰との?
誰との約束だろうか。
病院の廊下の手すりにつかまって、立ち止まった。
------------------------------------------------------
部活帰り、正門を出ようとしたところで声をかけられた。
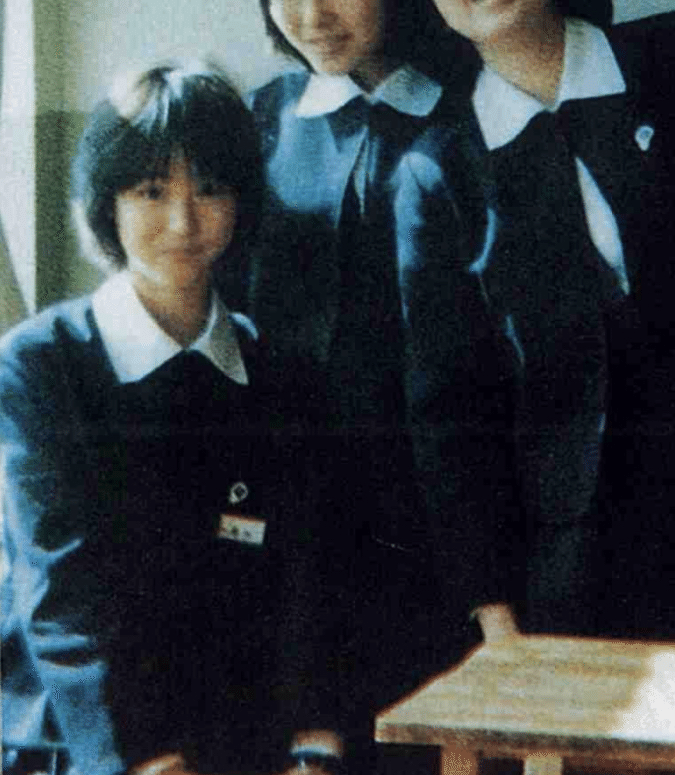
振り返ると、同じ陸上部の男子だった。
「今帰り?」
「うん」
そう返事をして、少し、ドギマギした。
同じ部活だったけれど、ほとんど話したことがない男子だった。
確か、名前は瀬尾で、種目は長距離だったはずだ。
「この前の記録会、すげかったじゃん」
わたしが自己新を出したことを言ってるのだろう。わたしは黙って軽く頷く。
そのあと彼は自分は今スランプで記録が伸びないことや、陸上ではなくて、本当は音楽をやりたいことなどを話した。わたしはそれを黙って聞いていた。
「なぁ蒲池」
名前を呼ばれて、初めて彼をしっかり見た。
短髪で、少し寝癖がついてる。
眉は少し上がっていて、鼻筋がスッと伸びている。
奥二重の目は優しそうだった。
「またこうして、タイミングが合ったら、一緒に帰ってくれないか?」
突然の提案に驚いて、なんて答えようか考えながら彼を見ていた。彼もわたしを見ていた。
「でもわたし、瀬尾君のこと何も知らないし」
そう言うと彼は苦笑して言った。
「そうだよな。変なこと言って悪かったな。気をつけて帰れよ」
そう言って、走って行ってしまった。
「蒲池」
そのあとも、何度も彼はそうやってわたしに呼びかけ、一緒に帰ろうと誘ってきた。
時には、周りに他の生徒がいる時もあって、恥ずかしかった。でも、そんなふうに、堂々と誘ってくる男子は他にいなくて、わたしは迷惑に感じながらも、彼のことがそんなに嫌いではなかった。
「蒲池」
そう呼びかけられると、わたしはいつも一呼吸おいて振り返った。その一瞬に、わたしはいつも、彼のラブラドールのような優しい目を思い浮かべていた。そして、振り返ると答え合わせのように、その瞳で、わたしを見ている彼がいた。そのことがおかしくて…今思えば、たぶん、嬉しかったんだと思う。
でも、一緒に帰ってもわたしが何か話すことはほとんどなかった。彼の低い、でもよく通る声を聞いて、時々笑ったり、頷いたりしていた。
ある時、いつも別れるT字路で彼が言った。
「俺、引っ越すことになったわ」
驚いて彼を見ると、何故か少し笑っていた。たぶん、泣きそうになるのをこらえていたんだと、これも、今ならわかる。でもその時のわたしは、ただ驚くことしかできなかった。
「いつ?」
「来週。残念だな、蒲池ともせっかく少し、仲良く慣れたのに」
わたしは黙って、俯いた。頷けばいいのか、首を振ればいいのか、わからなかった。
「蒲池」
そう呼ばれて、わたしは顔をあげて彼を見た。
「またいつか、会おうな」
わたしは今度ははっきり頷いた。
「俺、その時までに、お前がさ、いいなって、一緒に帰りたいなって思えるような男になるから。ありがとな、いつも、付き合ってくれて」
今度は、はっきり首を振った。嫌だったことなんて、ない。確かに恥ずかしかったことはあったけど。嫌だと思ったことはない。でも、そのことをどう伝えればいいのか、わからなかった。
「じゃあ、また」
そう言って、彼が背を向けようとするのを、わたしは呼び止めた。
「瀬尾君」
わたしから、彼を呼び止めたのは初めてな気がした。
もっと早く、こうして、彼の名前を呼べば良かった。
再びわたしを見た彼を見つめ返して、ゆっくりと言った。
「明日、たぶん、練習17時には上がれると思う」
彼はニカっと笑うと、「オッケ。約束な」そう言うと、いつものように走って行ってしまった。
次の日、彼は学校に来なかった。噂で、彼の家族は借金を抱えており、夜逃げしたと聞いた。わたしは全部、信じなかった。「約束な」その彼の声だけ、頭に残っていた。
------------------------------------------------------
今まで生きてきて、たくさんの人と約束して、守れた約束も、守れなかった約束もあった。
守れなかった約束と、その人達のために、わたしは歌い続けている。わたしが歌うのをやめたら、果たせなかった約束は、なかったことになってしまう気がして。
肯定したいんだ。
自分の人生と、自分の人生にわずかでも関わってくれた全ての人の人生を。そういう歌を歌い続けたい。生命ある限り。
なのに、身体が言うことを聞かない。そのことが、もどかしかった。
------------------------------------------------------
子宮がんが肺に転移していると聞かされ、再入院してから、お気に入りの場所があった。
病院の廊下の端の非常扉から出られる、非常用のスロープだ。医師からは止められているが、時々ここで、外の空気を吸ったり、空を眺めている。
そうしていると、昔のことをよく思い出す。おそらく、もう2度と会うことのない人たちのことだ。
その朝は、数十年ぶりに樹希のことを思い出した。彼とは、湘南の小さなアパートで2年間だけ同棲をした。短大を卒業するころに出会い、OLとして働いている時に別れた。
樹希は出会った頃はヤンチャな性格で、悪いこともしていたようだった。けれど、わたしと付き合ってからは人が変わったように真面目に働いていた。
わたしは短大を卒業後、不動産会社で働きながらも、歌手になる夢を諦め切れず、いつも持ち歩いているノートに、時間があれば思いついた歌詞を書き付けていた。
ある休みの日、海までドライブに出かけた。
風が強い日で、浜には出ずに、車から2人で海を眺めていた。
「サチは、歌手になりたいんだよな?」
「うん」
「きっとなれると思うわ。だってすげぇ歌、上手いもん」
「ありがと」
「でもさ、サチが歌手になって、どんどん有名になったら、俺のことなんてあっという間に忘れちゃうんだろうなって、それが怖いんだ」
「何それ?考えすぎだよ」
そう言って笑ったわたしの肩を掴み、樹希は真剣な表情で言った。
「俺さ、サチを幸せにしたい。だから、喧嘩もやめたし、髪も黒くしたし、仕事もやってる」
「うん」
「俺、頑張るから」
「わかってるよ、頑張ってるのも知ってるよ」
「いや、そうじゃなくて、俺、俺さ、本当にちゃんと、サチを…」
「わかってる。大丈夫」
そう言って、わたしは樹希を抱き寄せた。抱きしめたら、わたしより大きな肩が、小さく震えているのが伝わってきた。
「ねぇ、待って。何で泣いてるの」
「泣いてないよ。俺、凄い奴に出会えたんだって、感激してるんだよ」
「大袈裟だなぁ。樹希はいつも大袈裟なんだよ、わたし、ただのフツーのOLだよ?」
樹希はわたしから体を離すと、わたしの目を見て言った。
「ありがとう」
------------------------------------------------------
また、みんなに会いたいなと思う。
みんなというのが、具体的に誰なのかはわからないけれど、今まで出会った、すれちがった、みんなに。
だけどそれは叶わない。だから代わりに届けたい。わたしの歌を。ねぇ聞いてる?聞こえてる?わたし、ここにいるよ。そう知らせたい。ありがとうよりもう少し深く、大嫌いよりもっと複雑で、大好きといえるほどにはまだ固まりきらないこの気持ちを。あぁ届けたい。自分の声で、体を震わせて。その力が、わたしにあとどれだけ、残っているだろうか。
スロープに腰をかけて、空を見上げたら、有明の月がうっすらと見えた。
「グロリアスマインド…」自然と新しいメロディと歌詞が口をついた(終)
-------------------------------------------------------
みなさん、お久しぶりです。
ふでねこです。
久しぶり過ぎて、忘れられてる気がしないでもないですが…ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。
不定期ですが、また自分が心揺さぶられるアーティストを紹介していけたらと思っております。
読んでいただけたら嬉しいです。
感想をもらえると小躍りします。
これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。
