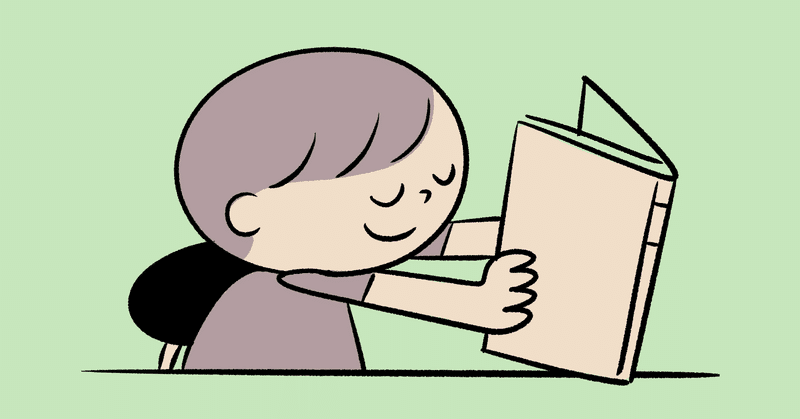
【中2英語】WPMを測って、英語を速く正確に読む力をつける
英語を英語のまま理解し、高校入試などの長文問題をある程度のスピード感をもって読んでいく力をつけるために、どのような活動に取り組んでいますか?
先日、中学2年生の授業で、教科書の読解教材を使って、WPM (words per minute:1分間に何語読めたか ) を測る活動を行いました。以前勤務していた学校の先生に教わり、生徒も集中して取り組めていたので、効果があると感じています。そのやり方を紹介いたします。
①WPMを測る活動を取り入れた指導とは
東京都教育委員会が発行している「中学校英語科教師のための指導資料」という冊子に、WPMに関する記述があります。PDFでダウンロードができますので、その一部を引用いたします。
読解のスピードを 上げるためには、教科書の読解を扱ったセクションなどを使って速読の練習を行うとよいでしょう。 WPM (words per minute:1分間に何語読めたか ) を測る活動を取り入れて生徒の学習への意欲を持続させる取組も効果的な指導の一つです。計算式は以下のようになります。
WPM=語数×60/読むのにかかった秒数
目安となる目標は、2学期末で、習熟の程度の遅い生徒で150語から200語、中程度の生徒では 200語から300語、早い生徒では300語以上です。
目安となる目標については、いろいろな考えがあるように思います。また、②でも記述しますが、上の計算式に、理解度チェックの問題の正答率も加えることを、以前教えていただいた先生から教わりました。生徒の実態に合わせて、設定していけばよいと思います。
②実際の指導の流れとワークシート
今回は、光村図書の『Here We Go! 2』Let’s Read 2 Meet Hanyu Yuzuru という教材を使用しました。400語弱の、インタビュー記事を扱った英文です。
⑴新出語句はリストであらかじめチェックしておく
⑵(必要であれば)題材についてオーラルイントロダクションをおこなったり、イラストや写真を用いて基礎知識を導入したりする
これをすることにより、読むことへのハードルはかなり下がります。今回は以前記事にしたような形で、導入の活動を事前に行っておきました。
⑶タイマーを設定し、読み始める
生徒には、慌てなくていいので、英語を頭から読んで意味がわかるスピードで読んでいくように伝えます。和訳をしようとするとどうしても、返り読みをしてしまって、英語をそのまま理解する練習になりません。決して戻らないように、と意識をさせます。最後まで読んだら、タイマー(デジタル教科書やiPadのタイマーなど大きくて分かりやすいものを使用)を見て、読み終わった時間をメモさせます。
⑷内容理解チェックの問題に取り組ませる
速く読めても、内容を理解できなければ意味がありません。ですので、読み終わった生徒から、内容理解チェックのワークシートに取り組ませます。その正答率を、WPMの計算式に加えると、生徒はスピードだけを意識するのではなく、内容を理解しながら読むというところも訓練することができます。
⑸答え合わせ、WPMを計算する
内容理解問題の答え合わせをし、計算をさせます。継続的に取り組ませると、生徒は自分の成長を感じることができると思います。今回は単発での指導となりましたが、集中して英文を読んでいく姿は、頼もしいものを感じました。
③指導の結果
まだ慣れていない生徒が多く、結果にはばらつきがありました。また、読むのは速いけれど内容理解ができておらず、結果的にWPMが遅くなってしまうという生徒も見られました。70語から100語くらいに入る生徒が1番多かったように思います。中には180という生徒もいました。数字で結果が出ることによって、自分の実力を客観視できるというのは生徒にとって励みになると思います。
④まとめ
WPMを測る活動でリーディング指導を行うと、生徒は意欲的に内容を理解しようとします。これは、生徒の能動的な学びだと思います。先生は最低限の知識や新しい単語を確認し、後は生徒を信じて英語の世界に飛び込ませ、その中で自分で情報を読み取らせます。英語が苦手だと思われる生徒も、その時間は集中して英文をなぞりながら読んでいる姿を見られます。未知なものに挑戦したいという気持ちは、どんな子どもももっているのだなと感じます。
ただ英文を読み、先生から重要な文法事項を説明される、といったような訳読式の授業は、生徒は受け身になり、何も面白くありません。もちろん精読して英文を丁寧に読んでいく授業も必要ですから、教科書の教材をうまく使いながら、英文を読む力を養ってあげられたらと思っています。参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
