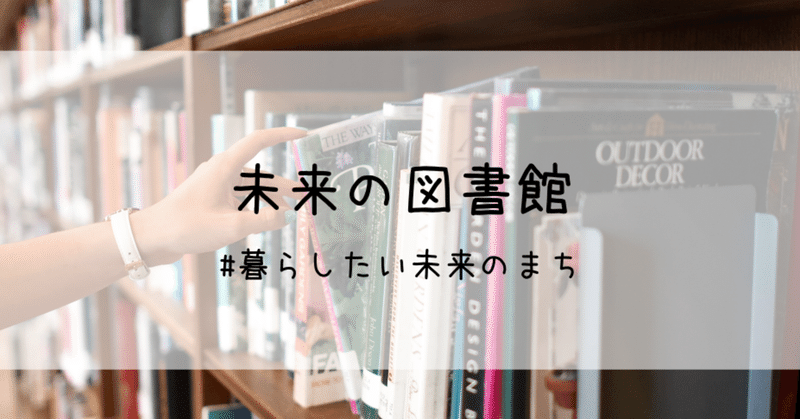
未来の図書館。#暮らしたい未来のまち
「#暮らしたい未来のまち」というテーマをみて、私は図書館の中の人なので、未来の図書館について考えています。
未来のまちでも、図書館が輝いていればいいな、と思うのです。
私自身は、小さな分館の責任者として勤めているのですが、本館は移転したばかりでピカピカの図書館です。
自動貸出機があって、予約棚も無人で、利用者さんが自分で端末を操作して貸し出します。
電子書籍の貸し出しも始まりました。
目新しい図書館は、たくさんの利用者さんが来館されているようで、図書館の課題であったティーンエイジャー(Teen-ager)たちも利用しているようです。
中学生以上になると、途端に図書館に来なくなってしまうのですよね。
最初は盛況であった新館も、だんだんと落ち着き、やっぱり分館の方が良いわと言って戻ってくる方々もチラホラ。
ご年配の方が使い方に困り、予約本を人間が受け渡してくれる分館の方が助かるというわけです。
分館の存在意義は、地域密着型であると考えているので、親切な対応をこころがけてはいますが、このまま分断された姿では、図書館としていかがなものか、と考えさせられました。
未来の図書館というと、司書もAIにとって代わり、なんでも自動化されたものになるのでしょうか。
ついていけない人たちは置き去りになってしまいます。
インターネットによって情報が溢れる今、情報インフラとして図書館の重要性は高まるはずです。
「図書館に未来がないと思うのは、図書館を単なる書籍倉庫と思っている人だけだ」
2019年に日本でも公開された、ニューヨーク公共図書館を描いたドキュメンタリー映画「エクス・リブリス」、オランダの建築家フランシーン・ホウベンの言葉です。
私自身かなり衝撃を受けたこの映画は、ニューヨーク公共図書館が図書の貸出しサービスを越え、就職支援プログラムや障害者住宅の手配、ディナーパーティー、シニアダンス教室、ファッションショーなど、社会インフラとして市民生活に密着した多様なサービスを提供する様子が映し出されています。
図書館がみんなの繋がる場所になる。
そんなハブ的な役割を担っていけたらなと思うのです。
図書館の未来は、私たちの未来は、やっぱり人と人をつなげていきたいなと。
図書館はあなたと本との出会いを演出し、新たなる関係を創造する場でありたいと願っています。
個人的には、ご近所同士の和みの場で良いと思うのです。
ちょっとおしゃべりしたって良いのです。
図書館にぜひ立ち寄ってみてください!
サポート頂けると飛んで喜びます! 本を買う代金に充てさせて頂きますね〜 感謝の気持ちいっぱいです!!
