
今SEOじゃない
今SEOじゃない
「今SEOじゃない」 検索エンジン最適化について今回は記述します。近年、インターネット上でのビジネスはますます重要視されていますが、Googleはユーザーエクスペリエンス(UX)さらなる向上のため、Search Engine Optimization(SEO)をSearch Generative Experience(SGE)に変更し、ウェブサイトのコンテンツマーケティングや文章作成に、(E-E-A-T)が上位表示に欠かせないようになりました。つまり、最近のトレンド(ニーズ)である「AI」にシフトしたワケです。

つまり、今後のSEOはAIが選ぶWebサイトになることを念頭に、E-E-A-T(経験知)を重視し、視覚的な画像や根拠を示せるデータなど、体験知や根拠を示せる視覚物が記載されているウェブサイトが上位になるようです。
WordPressで書いた私のブログ(https://www.aya199166.com/)の中の〖ブログ初心者に優しい〗というブログ記事のユーザー&読者の目を疲れさせない方法が記述してあります。
まず、検索エンジン最適化(SEO)とは、ウェブサイトの上位表示を目指すための施策のことです。GoogleやYahoo!などの検索エンジンでユーザーがキーワードを使って検索する際に、自社(己)のウェブサイトが上位に表示されることで、多くの流入を促すことができます。しかし、近年のアルゴリズムの変更や競争の激化により、SEOの効果は徐々に減少していると指摘されていますから、文字数のボリュームにも拘りが出てきました。
では、なぜSEOが効果を失っているのでしょうか? それは、検索エンジンのアルゴリズムが進化し、ユーザーのニーズや行動に合わせて変化しているからです。検索エンジンは、ユーザーの検索意図を理解し、最適なコンテンツを提供することを目指しています。そのため、キーワードだけに頼った最適化ではなく、ユーザーのニーズに応える価値のあるコンテンツを作成することが重要です。そして、、今は価値のあるコンテンツをAIが瞬時の撰んでくれます。
従来の豊富は重要視が必要な対策として、まず、ユーザーの行動やインタラクションデータを分析し、改善点を把握することが必要です。ツールやデータの活用により、内部のウェブサイトの問題点や改善のポイントを見つけ出しましょう。また、外部の要素も重要であり、他のウェブサイトやSNSでの評価やシェアが上位表示に影響を与えることも考慮しましょう。
次に、コンテンツの質を重視しましょう。ユーザーが求める情報や解説を提供することで、ウェブサイトの評価が向上します。タイトルや文章のタイトルや文章のクオリティも重要です。タイトルはユーザーの興味を引きつける役割を果たしますので、魅力的でわかりやすいタイトルを考えましょう。また、文章は読みやすく、情報を的確に伝えることが求められます。適切なキーワードを使いながら、ユーザーが求める情報を的確に解説しましょう。
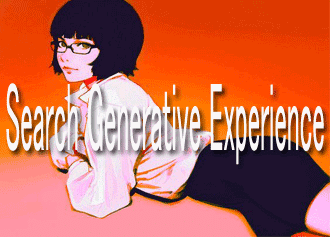
また、ビジュアルコンテンツの活用も重要です。画像や動画はユーザーの興味を引きつけ、情報をわかりやすく伝える手段です。 適切な画像や動画を選び、ウェブサイトの魅力を高めましょう。更に、画像や動画のファイル名やalt属性にもキーワードを活用することで、検索エンジンに対して情報を提供しやすくなります。
また、ユーザーエクスペリエンス(UX)を重視することも大切です。Webサイトの表示速度やレスポンシブデザインなど、ユーザーが快適に利用できる環境を整えましょう。ユーザーがウェブサイト上で求める情報を簡単に見つけられるようにすることで、ユーザーエンゲージメントを向上させることができます。
また、SEO(SGE)だけにこだわらず、総合的なマーケティング戦略を考えることも非常に重要です。ウェブサイト(ブログ)の検索エンジン上での順位を追求するだけでなく、ソーシャルメディアやメールマーケティング、コンテンツマーケティングや内部・外部リンクなど、様々なチャネルや方法を組み合わせて、アクセスを増やしましょう。 また、ユーザーとの関係を構築し、リピーターを増やすことも大切です。
「今SEOじゃない」という分析でも、SEOの基本的な要素や戦略を理解し、適切に取り入れることは依然として重要です。 検索エンジンのアルゴリズムが進化しても、ユーザーニーズの理解や把握や情報検索の行動は変わることはありません。なので、ユーザーを重視し、分析して、ユーザーエクスペリエンスに焦点を当てたウェブサイト作りを心掛けることが重要です。
Googleの評価向上は、データの分析を行いながら改善を行うこともSEO(SGE)において重要な要素です。ウェブサイトのアクセスデータやユーザーの行動データを分析し、どのページがより多くの流入を生み出しているのか、ユーザーが離脱する原因は何なのかなどを把握しましょう。 これにより、Webサイト内の改善点や弱点を特定し、改善施策を立てることができます。
また、基本である外部の要素も重視することは忘れてはなりません。 他のWebサイトやソーシャルメディアでの評価やリンクバックは、検索エンジンにとってウエブサイトの信頼性や重要性を示す重要な要素です。他のウェブサイトとのコラボレーションやソーシャルメディアでのシェアを積極的に行い、外部からの注目を集めましょう。
自分が運営するWebサイトの信頼性や重要性を改善向上させたければ…目的は,どーあれ、他サイトや読者・ユーザーからクリックされるような、外部からの注目を集めれるような、検索フォームで高い順位表示を目指せなければいけません。
さらに、インデックスの最適化も忘れてはなりません。検索エンジンがウェブサイトを正しくクロールし、インデックスに登録されることが重要です。Webサイトのロボット.txtファイルやsitemap.xmlファイルを適切に設定し、検索エンジンがWebサイトの全てのページを正確に把握できるようにしましょう。アフェリエイトなどで稼ぐつもりなら、(やはり、独自ドメインとレンタルサーバーの方が効果が大きいです。)
そして、ユーザーの目的を理解し、コンテンツを作成することが重要です。ユーザーが求める情報や解決したい問題に焦点を当て、具体的で有用なコンテンツを提供しましょう。 キーワードの選定やコンテンツの作成においても、ユーザーのニーズと検索エンジンの基準を両立させることが求められます。
「今SEOじゃない」という声がある一方で、検索エンジン最適化はWebサイトの成功に欠かせない要素です。SEOの基本を押さえつつ、ユーザーのニーズと検索エンジンの進化に合わせた戦略を取り入れ、Webサイトの流入や改善を目指しましょう。継続的な努力と探求心も忘れづに・・・
くわえて、情報の更新が重要です。検索エンジンは常に新しい情報を求めています。 定期的なコンテンツの更新や追加は欠かせません。新しいトピックやトレンドに関する記事を作成し、ユーザーの興味を引きつけましょう。なので、過去のコンテンツも定期的に見直し、必要な場合はアップデートや改訂を行いましょう。
さらに、ユーザーとのコミュニケーションを大切にしましょう。コメントやフィードバックへの返信や、ソーシャルメディア上でのユーザーとの対話を積極的に行いましょう。ユーザーの意見や要望に耳を傾け、それを元にコンテンツやWebサイトの改善を行うことで、ユーザーの満足度を高めることができます。
最後に、Webサイトの成功を図るために分析と評価を行いましょう。Webサイトのアクセス解析やキーワードの分析を通じて、トラフィックの状況やユーザーの行動を把握しましょう。さらに、ウェブサイトの評価や順位を定期的にモニタリングし、必要な対策や改善を図りましょう。データに基づく意思決定は、効果的なマーケティング戦略の立案や実行に不可欠です。
「今SEOじゃない」という声があるかもしれませんが、SEOは依然としてWebサイトの成功には重要な要素です。 検索エンジンのアルゴリズムやユーザーニーズが変化していく中で、柔軟に対応し、ユーザーエクスペリエンスを重視したコンテンツと最適化を行いましょう。継続的な努力と改善を通じて、Webサイトの上位表示と成功が実現します。

ところで「ブログ好きが仕事」という意味は、私にとって数年前は非常に特別なものでした。ブログを通じて情報発信を行いながら、自分自身も成長し続けることができました。そして、同じようにブログを日課にする人々と繋がり、成長していけることに喜びを感じました。
マズローの「五段階欲求説」の最上位である自己実現欲求は、第一階層から第四階層まで全ての欲求が満たされた場合に至る最後の人間の欲求(欲望)ですが、「ブログ好きが仕事」の意味は「自己実現欲求」そのものです。

今SEOじゃない
この欲求は、自分が得た人生観・価値観などに基づいて「自身らしく生きてきた時間」や「経験知」を伝えたい訴求願望とも云えます。これまでの欲求と違い、「自分の生き方や人生を知ってほしい」という希望です。
この欲求を満たすためにはGoogleが決めたblogランキングのセオリーを知らねばと思いましたが、何処をどう探しても解るワケもありません。が、猪突猛進でブログの要素を調べた結果の一端が当ブログ記事のに「ブログスキルとは」の中のテキストリンクの「ブログには11項目の絶対がある」です。
最後に、皆さんも自分の好きなことに向かって一歩踏み出してみてください。ブログを通じて、新たな可能性に巡り合うことはザラです。まさに私がそうです。読者の皆さん、今日は私が大切に思っているテーマについてお話ししたいと思います。それは、「ブログ好きが仕事」ということです。
閉じる
キャンセル一時保存公開設定

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
