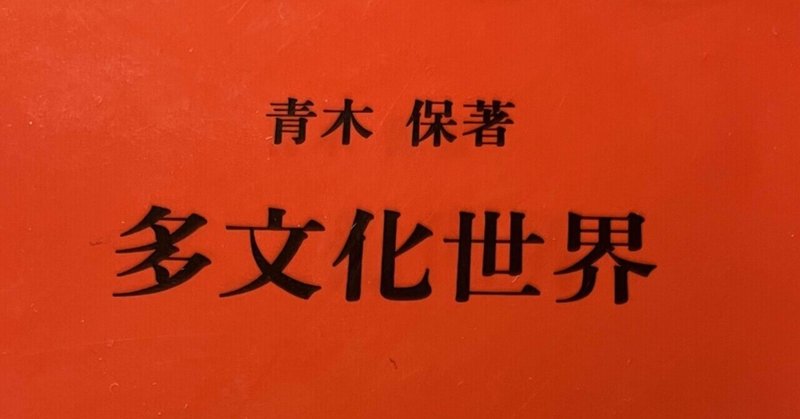
青木保氏の『多文化世界』5
さて、多文化共生について色々考えてきましたが、もちろんのこと自分たちの国の文化も絶やす訳にはいきません。青木保氏は「歩ける街」を強く主張しますが、その訳を考えます。
文化や歴史は形として残って後世に伝えられていく訳だが、筆者は街の景観そのものが文化を表すと考える。それはつまり、歴史的建造物が残っているかどうかという話かと思うが、どうやらそれだけではないらしい。
筆者は「歩ける街」を主張する。文字通り、歩くことが可能かということだ。その国の文化や歴史を知る一つの方法として、街を歩くということがある。もちろんそれによって歴史的建造物を見つけられるからという理由もあるが、それによって市民たちの暮らしも見ることができる。せっかく歴史的建造物があっても、歩くことが不可能なら意味がない。確かにそうである。
この本は2003年に刊行されたもので、少し情報は古いのだが、当時日本は世界的に見て人気な観光地ではなかった。具体的な数値で言うと35位くらいで、中国は5位だった。なぜ歴史的建造物が多いと思われる日本がこんなにも低い順位であったかというと、当時の日本の街の景観がまばらであったからだと筆者は言う。
わかりやすく言えば、ゴチャゴチャしすぎていたということだ。日本で最も人気のある街は昔から変わらず東京だが、その東京ですら北京に劣っていた。当時は経済面を重視していたので、東京においては道路は特に広く取られ、人が歩くスペースはなく、歴史的建造物は取り壊され、こぞって高層ビルが建てられた。歩けないということは、その街の魅力を知ってもらえないということである。
震災も空襲もあったからというのは言い訳にはならないと筆者は主張する。破壊されたものを修復するという執念は、西欧都市に見習う必要があるという。確かに、日本は色々な建物を復元する技術は持ち合わせている。今までにもいくつかの歴史的建造物の修復はしてきた。修復しようと思えば出来るはずだ。それをしないのに、嘆くだけ嘆くのは言い訳にすらならないという筆者の考えはもっともである。
日本だけでなく、そもそもアジア圏の都市は歩くように作られていないと筆者は考えるが、筆者は2001年に5年ぶりに上海へ訪れて、その変わり様に驚いたという。かつての上海は、交通網は充分でなく、空港、建物、商店街、文化施設その他もバラバラな感じであり、都市の利用勝手としてはとても悪かったらしい。ところが、再び訪れた時、街には十分な照明が取り付けられ、地下鉄も利便性が増し、外国人に非常にわかりやすいように街区がつくられていた。開放感が増して「歩ける都市」に進化した。
上海は、経済発展をしようとすればするほど、文化力を上げなければならないことに気がついたのではないかと考える。上海は、イギリスやフランスの近代先進国が租界してきて拠点をつくり、自分たちの西欧文化を傾注して、近代的建造物を建てた。それは現代の上海に残り、一部は文化財に指定された。さらに、当時の近代的なアパートなどは文化財であると同時に今なお人が住んでおり現役の建物として残っている。他にもホテルや銀行なども活用され、ただ残すだけでなく、実際に今も役割を全うし続けているというのが、上海の街の特徴だ。
今でも、東京は真新しいものこそあるが、古いものを見るために我々日本人だって行かない。それは京都のような街の役目だろう。京都が今なお世界的に人気のある観光地であり続けている理由は、単に歴史的建造物が残るだけでなく、京都という街がそれらの魅力をフルに発揮出来るように努力しているからだろうと、筆者の考えを読んでわかった。京都はあえて、建物の高さに上限を設けて、経済面より歴史面を優先した。碁盤の目も現代に残り、日本の中であれ以上に「歩ける街」はないだろうと思う。全ての歴史的建造物が埋没することなく、等しく光が浴びられる様にしている。いくら歴史的建造物が残っても、誰かに見つけられなければ意味がない。でも、歴史的建造物はその国の歴史と文化を探るには、とても重要な資料だ。我々の文化を知ってもらうためにはとても大事なものである。
今の日本は、東京が「最新」を担い、京都が「歴史」を担っており、うまく分担出来ていると私は思う。それによって、どの街もそれなりに等しく光が浴びられる様になっているのかもしれない。では、京都に住んでいるからといって「最新」を追いかけることが不可能かというとそうでもない。逆に言うと、東京はもう「歴史」を追いかけることはできないのかもしれない。街そのものが歴史を表すという筆者の考えに沿えば、今の東京から歴史を感じとれる場所は減ってきているように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
