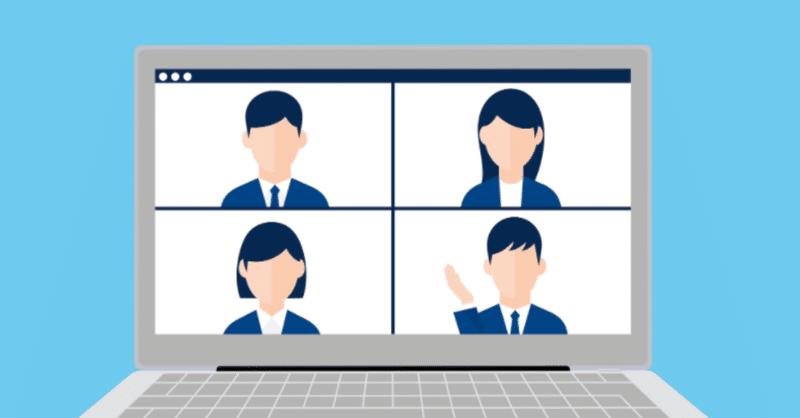
【最新】オンライン商談で売りきる術
こんばんは。
本日は、オンライン商談でも売れる営業の商談の進め方についてお話します。
肌感がつかみにくいようなオンライン商談ですぐに実施できる内容です。
もちろん、対面での商談でも有効です。
オンライン・オフライン問わず売れる営業は、商談でなにを話しているのか、何を考えているのか、どのように進めているのかをお話します。
すぐにでも実施できる簡単な内容ですが、これは効果絶大です!
これを実践することで、以下のことができるようになります。
・商談の確度設定の精度が上がる
・いつ受注できるのか、根拠を持って説明できる
・受注のためになにをすればいいのかが分かる
・次の商談までに行うこと、商談で行うことが明確になる
・受注率が向上し、売れる営業になる
では早速ですが本題に入ります。
営業をすると初回商談後
「検討します」「前向きに考えます」となるケース、一度は経験があると思います。
カウンターの方の反応は上々。しかし次回日程が決まらない、決まっても次の商談の進め方がわからない…
そんな時、みなさんはどのように対応しますか?
「また伺います、連絡します」や「みなさんやってます!今だけ〇〇円です」等押したり引いたりすることもありますよね?
押したり引いたり、効果が出る場合もありますが、ギャンブルのようなものです。
断るために、帰ってもらうために
「めっちゃいいね!うちも検討しないとって思っていたから検討して連絡するよ!」というお客様もいます。
そういった見込みのない案件に時間を割くのは無駄です。ときには見極めも必要です。
そんな商談の整理、管理をし、高受注率を維持するための初回商談の進め方についてお話します。
商談を進めるために初回商談で合意すべき事項
①検討する価値のあるものであったか(コンペリングイベント)
②導入スケジュール
③決済プロセス
④導入から逆算し、必要な条件・懸念点 ※失注リスク
最低限これらについては初回商談でヒアリングし合意すべき事項になります。
なぜこれをヒアリングするのか、合意するのか?
受注までの道筋「受注プラン」を立てるためです。
これらをヒアリングすると、以下のような受注プランが出来上がります。
株式会社A様:受注プラン
ゴール:8/10から導入、稼働開始
→8/1までに価格合意、支払い完了、契約書記載
→7/25までに代表者よりサービス内容合意、利用部署特定
→7/15までに担当者と概算見積もり作成、導入スケジュール合意
→7/2までに現行システムからのデータ移行について懸念払拭
→7/5までに次回商談を実施し、業務フロー・お困り事聴取
受注までのスケジュール、やるべきことが明確になります。
上記は簡単な例ですが、このように考えることで受注までにやるべきことが明確になります。
いつまでに、誰に、なにをするのか。
そのために自分(社内)はどのような準備が必要なのか。
この受注までの道筋を立てるため、初回商談でヒアリングすべき事項が
①検討する価値のあるものであったか(コンペリングイベント)
②導入スケジュール
③決済プロセス
④導入から逆算し、必要な条件・懸念点 ※失注リスク
この4つになります。では、一つづつ見ていきましょう。

①検討する価値のあるものであったか(コンペリングイベント)
提案内容は検討する価値のある内容であったかについて。
「へー、いいね!」で終わる案件は、感触の良い商談とは言えません。
先方から検討する価値のあったか、課題解決・ビジネス成長に寄与できるものであったかをお客様の声でヒアリングします。
また、課題解決ができる、検討する価値のある場合でも要注意です。
導入によってお客様のビジネスは具体的にどのように変わるのか、課題解決によってどのような効果が得られると思うのか。
価値を感じた=OK ではなく、「どのように価値を感じていただけたのか」をしっかりとヒアリングしましょう。
商談全般におけるヒアリングについては、是非こちらも参考に
あわせて、コンペリングイベントが重要です。
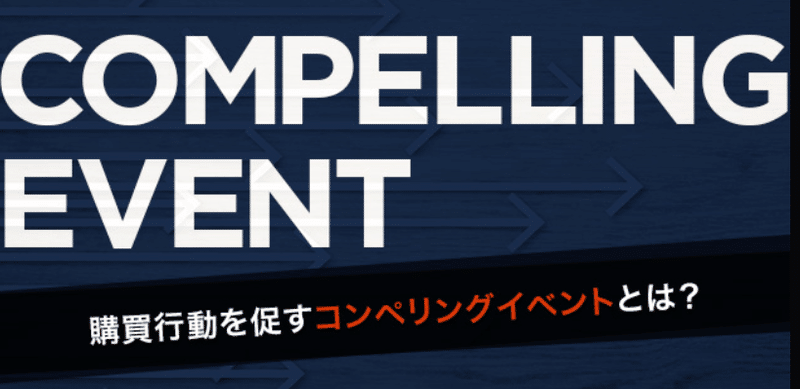
これは、導入のために差し迫った状況のことだとご理解下さい。
9月からテレワークを始めるので、ビデオ会議システムが必要だ。
新入社員研修用に、Eラーニングシステムが必要だ。
来期の売上比率を上げるために、営業支援システムが必要だ。
感染対策のために、非接触で決済をするIC・QR決済システムが必要だ。
などですね。
いつから(いつまでに)なにをするため、〇〇(自社製品)が必要という、導入が必要になる理由をしっかりとヒアリングしましょう。

コンペリングイベントがない場合は、作りましょう。
以前、お客様の課題、未来のギャップ=課題とお話しました。
有名なAs is To beのフレームワークですね。

そのギャップ=課題がわかれば、それを埋める施策こそがコンペリングイベントになります。
ただの時期を待つようなプロダクトセリングは時代遅れです。
お客様の潜在的な要望、ニーズを引き出し、製品価値を最大化させた上で営業をしましょう。
仮説思考については以下記事でも少し触れていますので是非
コンペリングイベントについては詳しく書くと止まらないので、今回はこの辺にしておきます。

②導入スケジュール
これは文字通り、導入の場合、いつからどのように導入頂けるかの確認です。
コンペリングイベントにも繋がりますが、いつからどのように導入するのかのスケジュール感が握れていないと商談が間延びします。
いつかは受注できる、受注するのは確実。
でも…導入は三年後でした。
導入には繋がっていますが、今月、今期の成果にはなりません。
具体的な理由があるならまだしも、意味なく相手のいうがまま待つ営業はナンセンスです。
いつから動いていくのか、スケジュール感さえつかめればあとは簡単です。
スケジュールに合わせて逆算していくことで、クロージングまでのプランが作れます。
これが明確になると、商談の進め方が変わります。
スケジュールはおおよそでもいいので、合意する癖をつけましょう。

③決済プロセス
これは②にも繋がります。
スケジュール感の合意のため、お客様の中で誰に推進してもらい誰を納得させる必要があるのかを把握するためです。
スケジュール感の把握と、今後の商談を誰あてに進めるべきかの把握のために抑えておきましょう。

④導入に必要な条件・懸念点 ※失注リスク
これは重要です。
導入の条件ともいっていいでしょう。
スケジュールとともにヒアリングするのがベストです。
「○月導入で一緒に進めて行きたいのですが、いかがですか?」と聞けば
「んーいまは判断できないな」等のYesでもNoでもない回答が来ることが多いですね。
Yesであれば油断は禁物ですが、受注に向けて話を詰めればいいですし、
明確な理由があってのNoであれば理由の解決で検討する余地があるのか、検討すらNGなのかの確認で済みます。
この、YesでもNoでもない回答の際にヒアリングを実施しましょう。
「では、どのような条件(状況)であれば検討可能でしょうか?」
聞き方はいろいろありますが、こういった趣旨の質問を投げかけます。
明確な回答がいただけなければ、残念ながら受注可能性は低いです。
抱えている案件の数、お客様規模等様々な状況を勘案し、見極めることも出来ます。
※念の為言っておきますが、明確な回答がないからといって、諦めるのは違いますよ…!
しかし、YesでもNoでもない回答の場合はなにかしらの条件や懸念が隠れています。
このYesでもNoでもない理由を深堀りしていき、商談の見極めと同時に次の段階に進むための材料探しをしましょう。
ここでヒアリングした条件や懸念が、受注までに越えるべき壁となります。
当然、条件クリアのみで受注できる案件ばかりではありませんが、商談初期でヒアリングすることによってその後の商談の進め方が大きく変わってきます。
以上、初回商談でヒアリングするポイントです。
これらをヒアリングし、受注プランを立てて商談を進めましょう。
株式会社A様:受注プラン
ゴール:8/10から導入、稼働開始
→8/1までに価格合意、支払い完了、契約書記載
→7/25までに代表者よりサービス内容合意、利用部署特定
→7/15までに担当者と概算見積もり作成、導入スケジュール合意
→7/12までに現行システムからのデータ移行について懸念払拭
→7/5までに次回商談を実施し、業務フロー・お困り事聴取
済:7/2 初回商談(データ移行懸念、スケジュール感OK)
これは一例なので、ご自身で管理しやすい形式で管理するのが良いと思います。
このようにプランを立てると「次に何をするべきか」が明確になるとともに、商談の確度がある程度見えるようになってきます。
Aランクです、Cランクですという主観的な商談判断に根拠を持たせることが出来ます。
また、今期・今月の見込みがあるのかないのか、いつであれば受注できるのか、受注条件はクリアできるのか等、分析をすることが出来ます。
分析ができると、自分の着地予測や予算管理もできますね。
このように商談を分析して管理するために、初回商談でヒアリングすべき事項をお話しました。

こちらを参考にし、曖昧な案件管理から、受注のための商談管理をしていきましょう。
案件管理の精度は確実に上がります!
では、このへんで。
お疲れさまでした。
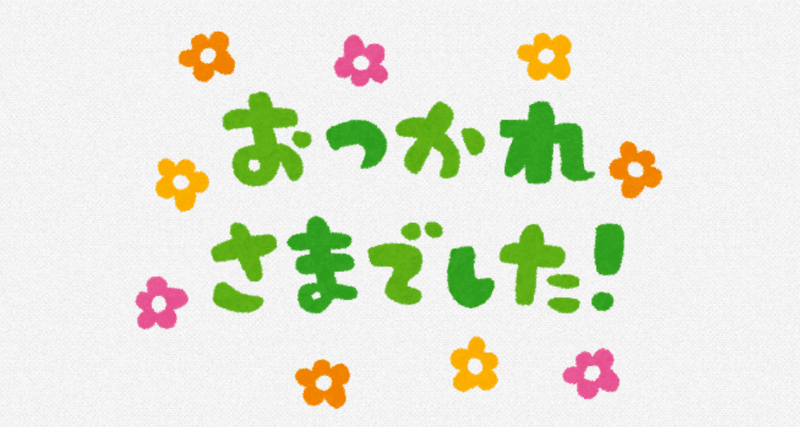
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
