
かつて魂の番人でいてくれた人達よ
先日、町田そのこさんの『52ヘルツのクジラたち』を読了した。
これまでに読了した町田さんの本は「星を掬う」「宙ごはん」など。どちらも筆者読みではなく、タイトルや、背表紙のあらすじに惹かれて読んだため、どうやら私は“町田さんが執筆した”と知らずしても魅力に惹かれ、つい読んでしまうらしい。
そんな中、『52ヘルツのクジラたち』は、これよかったよ、という母からのおすすめの言葉と共に手渡された。
映画化された際に予告を何度か目にしていたことや、本屋大賞を受賞し、書店でもかなりコーナーが設けられていたこともあって著者名、タイトル共にな本の存在は知っていた。
こうした“周囲が評価している”作品を読むときは少し緊張する。
いや、なんで私が緊張してんねんとも思うだろうが、周りの思う“面白い”と自分の“面白い”の尺度が果たして一致するのかソワソワしてしまうのだ。
それらを踏まえて読み始めた、作品。
一言目にまず、よかった。
とても、良かった。
電車で、カフェで、自宅で、普段なら携帯を開いてしまう場でも読みたさが上回り、気付けばいつの間にか読み終えてしまっていた。
最終的に読み終えたのは、アルバイトへと向かうバスの車内。そして、その後のアルバイトをしている間もずっと頭の中では余韻が残っていた。
そして誰かに問うてみたい
「ねえ、貴方が発する52ヘルツの音はどんな音?どんな色?」という質問が頭の中を駆け回っていた。
特に印象的だったのが“魂の番人”という表現。
自分の過去に照らし合わせても、あぁいいなあ、分かるなあ。
そんな風に思えるこの表現が浮かぶ町田さんは一体どんな経験をこれまでにしてきたのだろう。
『52ヘルツのクジラたち』は簡潔に言えば、キナコ、というあだ名の女性と、「ムシ」と呼ばれる少年の物語。
あまりネタバレ的な表現はしたくないが、これまで私自身が触れてきた誰かの人生と比較して相対的に考えてもこの2人の今生きている世界。
特に「ムシ」と呼ばれる少年が生きる世界は〈絶望〉と表現しても大袈裟ではない。
そうした中で、“魂の番人”という表現は、絶望的状況の中にいる人の魂のそばにいる相手。そんな意味合いで用いられている。
それは少年にとっての、キナコであり。
かつてのキナコにとってのアンさんと呼ばれる登場人物なのだろう。
なぜこれほど、この表現に惹かれたのだろうか。
おそらく、“魂の”という表現が心にストンと落ちてきたからだと思う。
誰かを救うとか、助けるとか、支えることが決して物質的な、金銭的な“何か”に限らないと気付き始めたからだと思う。そばにいる、魂に寄り添う。それが誰かの人生にとって、とてつもなく支えになることが、ある。
そう気づき始めたからだと思う。
キナコは別に少年にお金を渡したわけではなかった。
話せない少年とボードでやり取りを交わし、一緒にアイスを食べた。話せないことに対して、たとえば「話して欲しい」と相手のできないことを無理やり克服させることもなく。
アイスを「何も食べてないだろうし、食べさせてあげる」と押し付けがましく振る舞うこともなく。ただ「自分がアイスを食べたいから」と一緒にいる理由を作った。
そうやって少年のそばにいて。
きっと少年にとっての“魂の番人”となっていた。
あくまで私個人の解釈だが、魂の番人的存在が側いるときはその存在に気づくことはできない。
その渦中にいるときは、目の前を追うことにあまりにも必死で、後々振り返った時に“あの人が”とその存在を思い起こすのだと思う。
そうして本から、
少しだけ自分の人生に視点を戻してみる。
現在進行形で、私の番人になってくれている人達の存在は、きっともう少し未来にならないとわからない。だから、かつての私にとっての魂の番人的存在について考えてみる。
就活の時、たった1人。
たった1人だけ「筧さんはきっと、就職じゃないのかもね」と私の心の底の本音を真正面からぶつけてくれた面接官がいた。
嘘ではないけれど、100%本音でもない志望理由を幾度となく面接をする中で「本当にそう思っている」かのように演じるのが上手くなっていたタイミング。その時期にも関わらず私の心の本音を見透かしたその人。
私が内定をとりあえず辞退して、インターンという意思決定をした時も。インターンで少しだけ成果を出せた時も、静かに見守っていてくれた。
多分、静かに応援してくれていた。
そして、何かお礼を返そうとする私に「恩は返すものではなくて、送るもの。恩送りだよ」と教えてくれた。
そうだ。
インターンで身体を壊した時に、社内で1人だけ私の仕事とか、成果とか、仕事とか。そんなこと抜きに私の体調を、身体を心配してくれた人がそういえば、いた。
「今日元気なさそうだけど、大丈夫?」とか
「サーモン食べれたの良かった!」とか。
(その時の私の食欲は壊滅的で、サーモン2貫を30分かかったけど食べれたことを報告した時に喜んでくれた)
会社にいつ復帰するかとか、そんなことを一切聞かず、ただ私の身を案じてくれていた。
そして時折zoomを繋げてくれた。
そして、にいちゃん的存在として番人でいてくれた。
そうそう。とうとう何も食べられなくなった時。
就活で出会った、とある企業のかつての面接官の方がご夫婦で自宅に招いてくれた。
今の自分の状況とか、心を一通り話した時。
「すぐにそのインターンをやめよう」と言った。
当時の私は、インターンをお休みしてはいたけれど、やめるなんてもってのほかと思っていた。
だから“何を言っているんだ”と思った。
しかし後にその選択肢をとった自分を振り返ると、やはり番人として導いてくれていたんだなと思う。
その後も、事あるごとに相談やら、人生逃亡やらした時。
ヨシタケシンスケさんの「にげてさがして」を薦めてくれた。映画化した辻村深月さんの「かがみの孤城」を観てごらんと言ってくれた。素直に読んで、観た私。今ではどちらも私の心を支える人生のバイブルとなっている。
そうだ、営業時間前でもいつでもおいでねと言ってくれたカフェのご夫婦がいた。
お水だけ飲みに行った私を咎めることもなく、受け入れてくれた。
引っ越しの時に、荷物を運ぶのを手伝って欲しいと言った私に、車を出して運搬をほぼ全て助けてくれた。
あぁ、そうだ。
居場所がないと思っていた時に受け入れてくれた、お蕎麦屋のおじちゃんも然りだ。
営業前に、夜明け前の3時4時に泣きじゃくる私に「お店の中で本を読んでいていいからね」と静かに私の魂を支えてくれていた。
私の人生にはこれほどまでに番人がいたのか。
今こうして夏空を見上げて文章を描きながら思う。
そして現在進行形で、私の魂は誰かによって支えられているのだと思う。
少年にとってのキナコのように。
かつてのキナコにとってのアンさんのように。
番人は決して分かりやすく
助けてくれるわけではない。
けれど確かに私のことを頭の片隅で考えて、
そして静かに見守ってくれている。
あぁ、そんな存在を“魂の番人”とつけた町田さんは一体どんな人生を、何をどこまで経験した方なのだろう。少しだけプロフィールを調べてしまった。
美容専門学校に入ったものの、全く仕事が合わずに1年足らずで辞めました。その後はファミレスやエステ、和菓子屋など職を転々とし、24歳で当時付き合っていた人と結婚、のちに出産。
なかなか波瀾万丈な人生を歩んできた彼女。きっとたくさんの場所を浮遊し、さまざまな経験をし。その上でその時々で思考し、小説という形で表現している方なのだ、と思った。
そんな彼女にもきっと番人が過去の様々なタイミングでいたのだろう。
“魂の番人”という心震える表現と出会えたこと。かつて私の魂の番人でいてくれた存在を思い返せたこと。そして現在進行形で私を見守ってくれている番人の存在に、きっともう少し先の未来で気づけること。
それを嬉しいと思える、そんな小説だった。
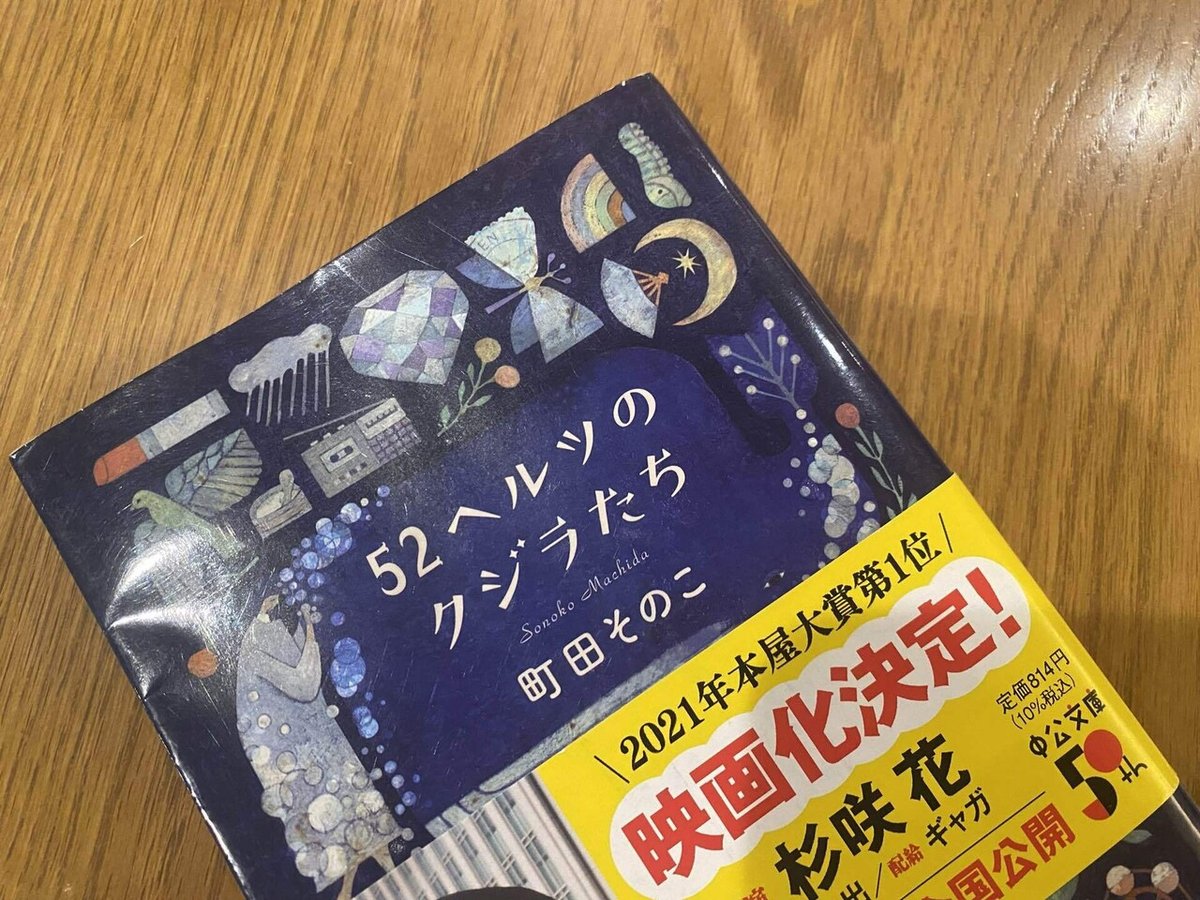
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
