
長編 Fragmentary color No.3〜No.4
※この小説は3回に分けて掲載しています。第1章からお読みください。
第3章 Heliotrope's night

「一緒にシャワーを浴びる?」
彼女の目が黒豹のように濡れている。
そんな時の彼女は震い付きたいほどにいい女だ。 わたしは返事をせずにカウチにごろりと横になった。
「ふふ 危険を感じた? 今。」
「充分感じた。一瞬鳥肌たったみたいに。」
「そう、それは良い傾向よ。鳥肌立つのも一種の快感のひとつ。わたしの波動があなたに少し近づいたってことね。」
ゆるやかな笑みで、彼女はわたしの目を捉える。
部屋の中に漂う香り。薄紫の香り。
人が動く方向になだらかに流れる。
ヘリオトロープの花の香り。
この人のような。
高潔でそのくせとても淫靡で。
この人がシャワーを浴びる裸身を、一瞬のうちにクロッキーしてみたい気がした。
薄紫の色鉛筆で。
柔らかな体の線に沿って膨れ縮まりながら滑り落ちる水しぶき。
頬や背中に絡み貼りつく長い黒髪。
しなやかに動く細い指。
それは冷たい彫刻のようで。
けれどその肌に触れると、燃えたぎる情欲の血流が、青く細い静脈に激しく流れているのを感じるだろう。
妖しいまでの美しき淫らな裸身。
でも。わたしの体はこの人を欲してはいない。唯、眺めていたいだけだ。
「正直な人ね、あなたは。今はわたしを欲しくないって顔に書いてある。」
この人もわたしと同じ。
すぐに人のこころが読めてしまう。
こわいくらいにみごとに。
嬉しいことでも哀しいことでもなんでも。
だから先回りして答えが用意できる。
予想通りの答えに小さく微笑みながらやり過ごせる。
それが元から何もなかったかのように。
胸の中に三角の薄黄緑の氷のかけら、ひとつ抱えて。

わたしは彼のあの静謐な笑みを思い出している。この世のすべての矛盾と絶望とを深緑の湖に沈めたような、染透るような笑み。
彼女は赤いアセロラジュースを眺めている。
ルビーように透き通った赤いアセロラの色。
「か、な、し、み」 の色はそれぞれに違う。
彼のかなしみ、彼女のかなしみ、そしてわたしの。
彼女はわたしを後ろから羽のような薄さで抱きしめる。
すべての色を滲ませて、ゆっくりとかき混ぜて、不透明でそれなのに澄んでいる、無彩色な熱が彼女の肌からわたしの肌へと沁み込んでゆく。
いつでもそうだ。いつでもそう思う。
この部屋にいて彼女といると、必ず彼に会いたくなる。
彼の柔らかい子犬の巻き毛のようなくせ毛に、指を入れて握り締めたくなる。
深い森の中の彼といると、彼女の細い指がすべるように黒髪を通りぬける、そのなめらかな感触を感じたくなる。
その時わたしは、自分が押し寄せる満潮のようでもあり、手繰り寄せられる引潮になるようにも思えた。
オーディオから流れる曲は、止まったような空気を震わすようにゆっくりとつぶやき漂う。
Celine Dion ーTo Love You Moreー
I'll be waiting for you
Here inside my heart
I'm the one who wants to love you more
You will see I can give you
Everything you need
Let me be the one to love you more
And some way all the love that we had can be saved
Whatever it takes we'll find a way
第4章 White Hotel
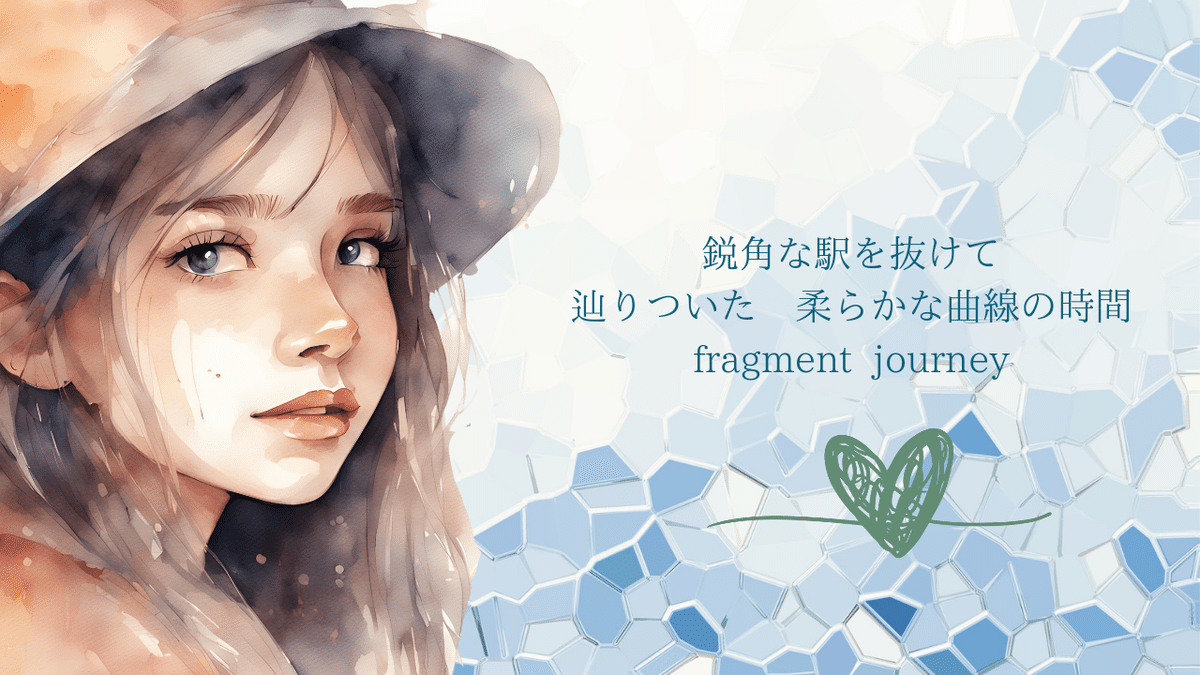
ホテルの部屋は程よい適温に保たれていた。
シャワーを浴びた後の少し火照った体に心地よい涼しさ。
べットに腹這いになって、彼の仕事をしている姿を後ろから眺めている。
何ヶ月かの内の何週間か、彼はあのゆうすげの丘を降りて、この街のこのホテルのこの部屋で仕事をする。
どんな内容の仕事なのか、そこからどのくらいの報酬を得ているのか、詳しく聞いたことはない。 興味もあまり持てなかった。
PCとSmartphone。それが仕事の武器なのだと彼は言った。
彼のPCを打つ指ひとつで、わたしが予想出来ないくらいのお金が動くのだとも。
横文字の長い名前を聞いたような気がするけれど。よく覚えていない。
その時、首をかしげたわたしに彼は笑いながら、博打打ち だよと言った。
一夜にして巨額の富を得ることも可能だけれど、その指ひとつですべてを失うこともあるのだと。
「すべてを無くしたら どうするつもりなの?」
そう聞くわたしに苦笑しながら、それでもさらりと彼は言う。
「そうだな。 コンビニでアルバイトでもするかな。」
「あの原色の制服を着て?」
「そう 朝早くからね。」
「じゃあ、わたしは早起きをしてパンを買いにいかなきゃ。あなたの店に。」
彼が楽しそうに笑う。
「そしてレジのあなたにパンとお金差し出して お・は・よ・うって言うのね。 」
「いいね。お前が笑顔でおはようを言いに来るのを、毎朝待ちながらレジに立っているのも。」
そんな光景も少しも不自然じゃなかった。
真剣な顔でPCを見つめながら、気ぜわしく指を動かす彼と、原色の制服を着て、コンビニのレジに立つ彼の間には、どこにも不都合なつぎはぎなど見当たらない。
毎朝彼の店に、パンとおはようの挨拶をしに行くのも楽しい気がした。

PCの指を止めて、ふと振り向いて彼が言う。
「たいくつなんじゃないのか?」
静かで深いいつもの微笑が、ホワイトイエローの綿毛のように、ふうわりと前を通りすぎる。わたしはゆっくり首を振る。
厚い壁で仕切られた四角い空間。
音もなく涼しい空気を吐き出すエアーコントロール。
彼の指がはじき出すリズミカルなキーボートの音階。
素肌に触れる白い清潔なシーツの感触。
気ぜわしく動く外側の時間が、ここでは見事に遮断されていた。
まるで宇宙の空間に浮遊する、透明なタイムカプセルの中に二人いるような錯覚。
しばらくして彼はわたしの横にゆっくりと体を横たえる。
少し疲れた横顔。 戦い終えた戦士のようだ。
「彼女とはどうなったの? 」
笑わずに向けた顔に蒼い影が走る。
「 どうにも 」
わたしは彼の胸に顔を寄せて、彼の体に腕を回す。 暖かい・・。 それだけ感じた。
「誘いには乗らなかった、ってことか。」
わたしのまだ湿った髪を指で掬いながら彼がつぶやく。
「男は鍵を持っていて、女は鍵穴を隠し持っている。誰の言葉だったのかしら。
どれにでも合うってものじゃないらしい。
沢山の鍵穴と沢山の鍵があって、その中でふと合致するときがある。
そのときだけこころと体の扉が開くって。
でも。ねえ、扉を開くことは必要なこと?
扉を開いてそこに見るものは何?
わたしには聞こえるのよ。
開いた扉の前で、呆然と立ち尽す男や女達の音のない乾いた呟きが。」
彼のこころに蒼い影が広がるのを、見た。
わたしが広げた蒼い影。
コバルト・ブルーに墨色をかき混ぜたような、蒼い影。 彼の指に力が入る。

(あなたは自分の鍵をなくしたまま。
いつでもあなたは自分の鍵を探している。
手に入れることなどできないと分かっているのに。 いつでもどこかに忘れてきたのだと、ちょっと入れ忘れただけなのだと、そんなふうな顔しか見せないあなた。
いくつも、いくつも、どんなに強く、強く、握り締めても、いつもその手をすりぬけて滑り落ちてゆく。
そうなることを知っていながら、あなたはいつでもそれを唯じっと見ている。)
言えない言葉。 口に出来ない言葉。
口に出してしまえば、紙屑のように丸めて捨ててしまいそうな言葉。
彼との届かない距離を、カミソリの切り後のような薄い痛みのように感じながら、その空白のような距離を、ゆらゆらと漂う青藻のような距離を、大切に抱え込むわたしがいる。
「ね。 ゆうすげ はまだ咲いている? 」
そう聞くわたしに彼は、羊歯のような湿り気のある、ぬくもりを含んだ三日月型の微笑みを少しだけ見せた。
「ちらほらだろうな。 森の秋は深まるのが早い。」
彼の胸は深い深い緑の森。
倒れ掛かるようなわたしを、受け入れもせず、突き放すこともなく、その胸に埋めたわたしのこころに、冷たくそして震えるような疼きを与えて、それでも、そっとそこに留まらせてくれる。 いつでも。
それ以上でもなく、それ以下にもならない、やさしさで。
Cocoon Yarn
あなたは わたしの髪を いとおしむ
蚕の糸を 紡ぐように
わたしの体の芯の繭
あなたの指に絡む絹の細糸
ゆるやかに しなやかに
そして きりきり と
記憶の彼方で まわる 糸車
カラカラ と 乾いた木製の音をたてて
わたしの こころを 巻き取ってゆく
あなたは わたしの髪を いつくしむ
縺れた糸を 均すように
― 第5章へー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
