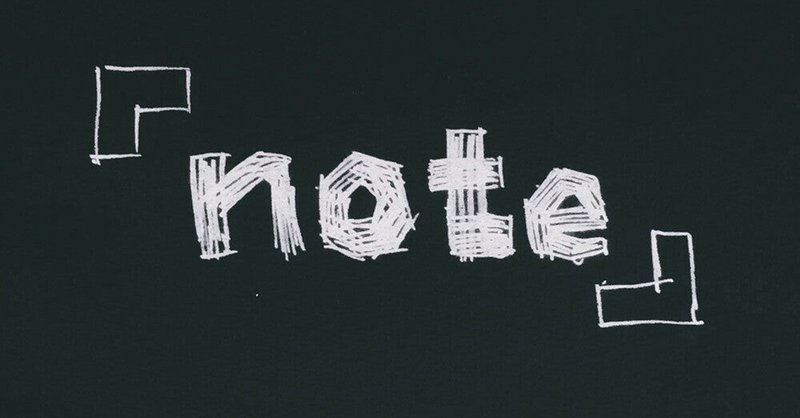
note創作大賞2022に参加します!
必勝法はないけれど、必敗法はあります。今の時代に、電話ボックスは必要ありません。よって、どんなにデザインの優れたテレフォンカードをつくったところで「負け」です。できれば勝ちたいと思っているのに負け戦に挑むことはやめた方が良いので、勝ちに行くんだったら、僕なら短い物語を書く
【#145】20211119
人生は物語。
どうも横山黎です。
作家を目指す大学生が思ったこと、考えたことを物語っていきます。是非、最後まで読んでいってください。
今回は、「note創作大賞2022に参加します!」というテーマで話していこうと思います。
☆note創作大賞2022が開催!
現在、note創作大賞2022が開催されています。ジャンル不問、形式不問のなんでもありコンテストです。第一回目ということで、傾向を掴めないし、対策もできないしで、打ち手が無いように思えますが、そんな状況下でも個人的に戦略を立てて臨もうと思います。
僕の戦略は大きく分けて、2つです。
一つ目は、「短い物語を書く」ってこと。
規定をみると、字数制限がありません。どれだけ長い物語で勝負しようが構わないわけですが、僕は短い物語で勝負しようと思っています。少なくとも長編は書きません。noteという場所を考えても、時代の流れを見つめても、長い物語は好ましくありません。noteだから、今だから求められる物語を追求した方がいいなあと思っているので、僕は短い物語で勝負しようと考えています。
必勝法はないけれど、必敗法はあります。
今の時代に、電話ボックスは必要ありません。よって、どんなにデザインの優れたテレフォンカードをつくったところで「負け」です。できれば勝ちたいと思っているのに負け戦に挑むことはやめた方が良いので、勝ちに行くんだったら、僕なら短い物語を書くよってことです。
それから二つ目。
「noteに適した、新しい創作の形を追求する」ってこと。
応募要項をご覧になられたでしょうか?
以下は、審査員となる各社のコメントから抜粋したものです。
KADOKAWA
今回の「創作大賞」はジャンルも形式も問わない賞ですから、既存のフォーマットにとらわれない自由な作品が応募されてくることと思います。
幻冬舎
募集作品にジャンルやフォーマットの制約はありません。自由でオープンな発想から生み出された作品に巡り会えることを楽しみにしております。
ダイヤモンド社
どんな人でも、オリジナルでユニークな「知識、経験、物の見方」があるはずです。ぜひ、それを最大限、魅力的に伝えてみてください。きっと多くの人の心を動かせる「ベストセラーのタネ」が眠っているはず。(中略)みなさまの唯一無二の作品を期待しています!
note
文字数や枚数などの細かい規定も設けませんし、テキスト×映像のような表現方法の組み合わせも可能です。インターネット時代ならではの自由であたらしい創作のかたちに出会えることをたのしみにしています。
テレビ東京さんのコメントは映像に関する内容がメインでした。この際、二次利用のことは二の次で、あくまで「優れたnote作品」を追求したいので、テレ東さんのコメントはスルーでいきます。
他の企業のコメントに共通しているのは「既存のフォーマットに囚われない新しい創作の形」を求めていることであると分かると思います。
「既存の形」=「本」「電子書籍」「文章だけ」とすれば、「新しい形」を追求するということは、そこから外れる、というより一歩進めばいいというわけです。
「本」と「note作品」の違いは分かりやすいです。
重さがあるか、ないか。
ページをめくるの、スクロールか。
日本の「本」は縦書きがほとんどですが、noteでは横書き。
などなど。
違う点は目立っています。ぶっちゃけ、noteで作品作りをするってだけで「新しい形」で表現することになるんですよね。
ではでは、「電子書籍」と「note作品」の違いは何でしょうか。通じるものがありますが、少なからず違いはあります。
あるいは、従来の小説は「文章だけ」の割合が多くを占めますが、一歩進むためにはどうすればいいのか。
☆僕なりの「新しい創作の形」はこれ
これらのことを踏まえ、今のところ僕が考えていることを共有します。
前回、前々回の記事をご覧になられた方はご存じだと思いますが、僕はnote創作大賞2022に出品する作品は、「noteで共同制作してつくる新しい『桃太郎』」です。
初めて目にした方は情報量が多くて戸惑うかもしれませんが、一応ここには僕なりの考えがあって、さっきまで語っていた戦略に通じています。
Noteの特性を考えた場合、文章や作品を通じてコミュニケーションできる点が魅力の一つだと思っています。SNS的機能の有無が、「電子書籍」と「note作品」の違いといえるのではないでしょうか?
「電子書籍」は作品自体でコンテンツが完結していますが、「note作品」は「スキ」したり「コメント」したりコミュニケーションすることもコンテンツの一部になっています。
つまり、「既存の形」から一歩進む方法の一つに、「作品作りにコミュニケーションを取り込むこと」が挙げられるわけです。
したがって、僕は共同制作でつくった作品で勝負しよう!と思い至ったわけです。それをやるだけで他の作品と差別化が図れますし、悪くない選択だと考えています。あとは中身次第って感じです。
それから、「文章だけ」のコンテンツからの脱却についても述べておきます。今のところ確定した具体的なアイデアはありませんが、ぼんやり考えていることを書いておきます。
noteでは画像を挿入することができたり、動画を挿入することができたりします。あくまで「note作品」で勝負するわけですから、できることならそれらを上手く駆使したいと考えています。
文章中に適度に、適切に、写真かイラストを挿むと良い感じになりそう。
とはいえ、僕が一番こだわりたいのは物語で、そこに時間と労力を割きたいので、僕一人であれもこれも手を出すのはキツそうです。まだはっきりとは言えませんが、写真やイラストをみなさんから集めて、そしてみなさんと一緒に決めていけたら楽しそうだなあ、そんな未来があったらステキだなあって思っています。
このあたりも意見がある方は、コメントしていただけると幸いです。
☆メインはnoteで共同制作
最後になりますが、僕が今回一番大切にしたいのは、「note創作大賞2022で結果を残すこと」ではなく、「noteで共同制作してステキな作品をつくること」です。
長々と、「こうしよう!」「これやったら負ける!」「新しい創作の形を追求するんだ!」と、作戦を熱く語ってきましたが、とはいえ、勝負事よりもみんなでつくることに興味があるので、勝ちにこだわりすぎないようにします。
なんか、保険をかけているようでかっこ悪いですが、やるからにはクオリティーもちゃんと追求したいので、共に旅する仲間になってくれませんか??
興味を持たれた方は、是非、下のマガジンをフォローしていってください。ただいま、『桃太郎』に対する疑問、新しい『桃太郎』への意見を募集中です。思ったことや、気になったことをコメントしていってください!
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
横山黎でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
