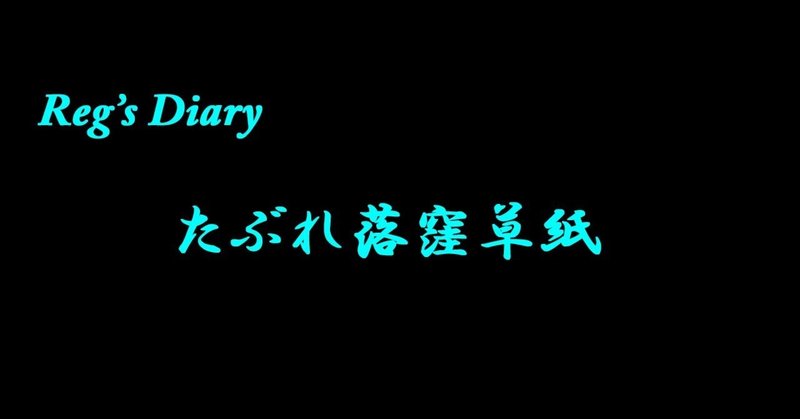
日本のルーツは記紀にあり
日本の成り立ちは「古事記」や「日本書紀」に記されています。日本の原点を著した二つの書物を「記紀」と呼びます。
「古事記」は現存する最古の書物とされ、歴史書ですが神話を含んでおり、序文と上中下の三巻から成っています。
天武天皇(在位673年~686年)が日本の正史と天皇の系譜を後世に伝える史書の編纂を臣下に命じます。これを受けて国家運営の根本に関わるプロジェクト「日本書紀」編纂が始まります。
また古事記の序文には、天武天皇が28歳の聡明な稗田阿礼(ひえだのあれ)に帝紀と旧辞を誦習せよと命じたとあります。帝紀は天皇や皇室の系譜に関する歴史書物、旧辞とは各氏族に伝わる説話を集めた歴史書物ですが共に現存しておらず、詳細は不明です。しかし、記紀はこれを情報源に作成されたと伝えられています。誦習とは声に出して繰り返し読むこと、後に稗田阿礼が諳んじた内容を太安万侶が筆録し、これが712年に「古事記」となります。
稗田阿礼という人物も謎が多く、天鈿女命の末裔猿女君の一族説、女性説、藤原不比等説、実在してない説まであります。
日本書紀によると推古天皇時代に聖徳太子と蘇我馬子が「天皇記」「国記」等の史書を編纂してますが、現存はしておりません。乙巳の変で蘇我蝦夷が自宅に火を放ち自害し、その際に焼失したとも、天智天皇に一部が献上されたとも言われますが・・・。
古事記と日本書紀が同時代に作られた意図は不明ですが、どちらも天皇家の支配の正当性を示しています。30巻という膨大な漢文で様々な説を掲載した『日本書紀』が多くの臣下で編纂されたのに対し、短く首尾一貫した『古事記』は天武天皇の個人的な意図がかなり入ったとも言われます。また古事記には出雲に関する内容が多く含まれていることも指摘されています。日本書紀は古事記に遅れること8年後の720年に完成しています。
ただ686年に亡くなった天武天皇はどちらも読むことは叶いませんでした。
【REG's Diary たぶれ落窪草紙 5月13日(月)】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
