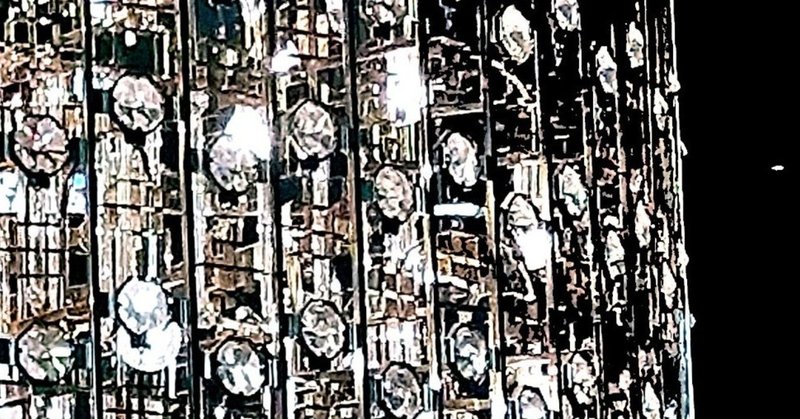
小説【船は故郷へ】4回目 (文字数11907 全4回 無料)
第3回からの続きです
船には静寂が戻った。
わたしはギリスがいつも座っていた椅子を見た。
そこには、やはり誰かが座っていた。
背もたれからはみ出しているのは、傾げたような後頭部だけだ。これだけの騒ぎにも関わらず、姿勢はまるで変わっていないのだから、死んでいるのだろう。
問題は果たして誰か、ということだ。
近づく。
インフルエンザで急遽休むことになったウィンディだったら大いに驚くところだ。
喉が乾いていた。
まだシャワーを浴びていないのを思い出した。
ギリスはわたしの荷物に入っていたビールをどこへやったのだろうか。
銃を持ったまま、その椅子の前に回り込んだ。
髪を短く切っていたので、後ろから頭の一部を見ただけでは判らなかったが、座っているのは見知らぬ若い女性だった。場違いな薄い黄色の室内着を着ている。まるでわたしの方が彼女の部屋に入り込んだ異分子というふうだ。
その女性には銃創が見られなかった。少なくともいまこの船のあちこちに転がっている宇宙飛行士のようなひどい状態にはなっていない。ただ、顔色が相当ひどく、死んでからかなり時間がたっているように見えた。
誰だろうか。
今度の一連の事件と、どんな関係があるのか判らなかった。
とにかく、事の顛末を会社に報告しなければならない。付近の宇宙管制塔にもその旨を通達してもらう必要があるのだろうか。オペレーション関係は業務ではないので、勝手がわからない。一番頼りになる人間はわたしが撃ち殺してしまった。
通信室のコントロールパネルはディスプレイに穴が開いており、どのボタンも使いものにならなかった。これもギリスの仕業なのだろうか。自分が長年にわたって指揮した船に対して、こんなことをしたのか。
タラップを降りて通路に戻る。
横たわっているノエルの死体。
空調の音だけの静かな船内。
このタラップを登っていったときと同じ光景だった。
ただ、いまはゆっくりと見て、考えることができる。
あの女性はなぜあそこにいたのだろうか。
いや、とにかく、まず管制塔へ報告をしなければ。ホワイトが首を長くして待っているに違いない。
わたしは1-Dの倉庫へと戻った。いまとなっては、どの倉庫の通信機を使ってもよいのだが、いまの状況をどう説明すればいいのか、考えをまとめる時間が欲しかった。
1-Dの倉庫へたどり着いても考えはまるでまとまらない。
そのまま素通りして廊下を歩き続ける。
いまこの船で生きているのはわたし一人のはずだが、銃は手放せなかった。
本当に他の誰もいないのか、いま一つ不安だ。
現に、見知らぬ人物が船長の椅子で死んでいたではないか。
船のハッチの前を通りかかる。
そこには乗組員の札がかかっていた。
クォート・ウィーゼル
ノエル・ロゼ
ギリス・ノートン
ハイダ・ルジッチ
リュウ・オラフ
わたしは文字が消えかかっていた自分の札を裏返してその横に並べた。黒い方はまだくっきりと名前が残っていた。
ロイド・グルーク
どうしてわたしが生き残ったのだろうか。
鍵の掛からないカプセルで寝ていたのだから、それこそ蓋を開けて楽に殺せたはずだ。ハイダと同様に。
そういえば、睡眠装置のランプが点灯していなかった。
しかし、わたしが乗り込んだことはみんな知っていたはずだ。こうしてここに札を下げていたのだから。
途端に、いろいろなことが思い出される。
横の睡眠装置で殺されていたハイダ。廊下で撃たれていたリュウ。タラップの下で死んでいたノエル。
アイスクリームの中で死んでいたクォート。私服で殺されていた。胸からはまだ血が流れていた。
わたしを殺そうとしたギリス船長。
何故、彼はわたしが寝ている時に殺さなかったのか。
さあ、いまここで何が必要か。
考えることだ。駄目だと思っても諦めず、さらにその先へ行こうと考えることだ。
凡人故、それがいままでできなかった。だが、いまのこの特殊な状況でならそれも可能ではないかと思う。
あの女性が何故あそこで死んでいるのか。それを解き明かせるのはわたししかいないのだ。
ようやく1-Dの倉庫にたどり着いた。
あることを試してみた。十分ほど様子を見てみたが、結果は思った通りだった。
次に船の中をいろいろと捜索した。
結果は思った通りだった。
暗い倉庫内のコントロールパネルから管制塔を呼び出す。
ホワイトの青白い顔が現れる。
「ヴィーナス221だ」
「わかってるって。経過はどうだ? どうなった?」
「船長を撃った。彼は死んだ」
そう言うと、さすがにしばらく黙り込んだ。
「……そうか。よくがんばったな。もちろん、この事件の特異な経緯に関しては僕も証言するから、君の行動が非難されることはないだろう」
「そういう後始末のことを考えると、そちらへ帰るのも少し億劫だな。このまま漂っているのも悪くないかもしれない。少なくとも地球では望むべくもない静かな環境に居られる」
「軽口を叩く気力があるとわかって安心したよ」
「ああ。まあ、こんな状況でふさぎ込んでいては、やっていられないからな。それでだな、その静寂を活かして、ちょっと事件についていろいろと整理したんで、聞いてくれるか?」
「……いまさら力になれるとは思えないが」
「そんなことはないだろう。君のおかげで僕は生き残ることができたんだ」
「わかった。聞こうじゃないか」
「そうだな。僕の身に起こったことを最初から順に説明しよう。まず最初に僕の目が覚めたのは睡眠装置の中だった。その隣でハイダが殺されていた。彼は寝ているところを撃たれたと思われる。睡眠装置は事故があった場合に備えていつでも外から開けられるようになっているんだ。彼は僕と同じで遅番だったからな」
「なるほど」
「だけど、ここでなぜ僕はそのまま寝ていることが許されて、彼が殺されたのか、という疑問が出てくる」
「単に忘れられたのかもな」
「僕は船長になったつもりで考えてみたんだ。彼の行動をなぞってその根拠を探ってみた。まず、僕が知っている状況から事件を組み立てると、彼は睡眠装置に入っているハイダを殺し、廊下でリュウを殺し、操縦室の下でノエルを殺した。順番は不定だ。なぜか、かなりたってから1-Cの倉庫でリュウを殺して、その際に負傷したらしい。僕が見つけた時にリュウの血はまだ固まっていなかったから、殺されたのが他の乗組員よりもかなり後だと判断したんだが、まあ、これは船長とリュウが組んで皆を殺し、最終的に仲間割れで、ということも考えられなくもない。とにかくその後で1-Dの倉庫へやって来て僕を発見して撃ってきた。撃った後は操縦室に逃げ込んで、僕に殺された」
「それが奇妙だと言いたいんだな」
「船長は僕のロッカーに入っていた僕の荷物や、他の船員の荷物もまとめて持っていた。操縦室にバッグが置いてあったし、彼が最後に持っていたのは僕の銃だった。それにも関わらず、彼はなぜ僕を撃った後に操縦室に逃げ込んだのだろうか。これはどうも辻褄が合わない。まるで僕が武器を持っていることを用心していたようじゃないか」
「負傷していたから、形勢不利と考えたんじゃないのかな」
「だけど倉庫までは来ているんだ。そこまで傷が酷いのだったらそもそも倉庫に入ってこなければいい。少なくとも彼は本気で僕を撃とうとしていた。それに、ここで彼はおかしなことを口走っているんだ。『貴様か』ってね。彼にしてみれば殺していない残りが僕だってことはいくら何でもわかってただろう。なにしろ船長だからな。勤務表を受け取っているだろうし、それを元に出航申請書や関税申告書を書いているはずだ。そもそもインフルエンザにかかったウィンディの替わりに僕を指名し、乗組員の勤務スケジュールを作成したのは船長なんだ」
「……なるほど」
「といった諸々のことから生まれてくる疑問があった。もっとも、船長を撃ってしまったいまとなっては手遅れなんだけど、それはつまり、こういうことだ。彼は本当にこの一連の事件の犯人だったのだろうか?」
「これも落ち着いて考えればある程度予想できたことなんだ。つまり、そもそも何故僕がここにこうしているのか、ということを考えればね」
「我考える故に我在りってことか?」
「ああ、結局はそれに近いのかもしれない。つまり、何故僕が殺されずに済んだかという、原点の謎だ。
結局、つまらない偶然のおかげだと思うんだけどね、僕が使っていた睡眠装置のランプが壊れてて、使用中を示す灯りがつかなかったんだ。犯人はランプの点灯した装置に入っていたハイダだけを撃って、他の確認をしなかったんだ」
「急いでいたのかな」
「まあ、それもあるかもしれない。でもそれぐらいの手間を惜しんで人を見逃すとも思えない。結局、犯人は僕が乗っていたことを知らなかったのではないだろうか。だからもう全員を殺したと思ってしまったんだ」
「なぜ、そんなことを思ったんだ?」
「札だ。乗組員は全員入り口のところにネームプレートをぶら下げる。当直は黒で、非番は赤い文字になっている。僕も船に乗って最初に札を下げた。非番の方でね。ところが、使い古しの札だったので、ほとんど文字が消えかけていたんだ。だから犯人はそれを見ても僕が乗っていることに気が付かなかったんだよ」
「ずいぶんと迂闊な話だな」
「この考えが根本なんだ。もし、船長が犯人だとしたら、乗組員の数を知らないはずはないから、札がどうであれ僕を見逃すはずがない。遅番になっている二人が睡眠装置で眠っているということなど十分に考えられることだから。最初は一人だけ放っておいて、後から僕を攻撃してくるというのはどう考えてもつじつまが合わないんだよ」
「確かにそうだ」
「だけど、僕が船長を恐れたように、彼も僕を恐れていたんじゃないだろうか。そう思えば倉庫での一撃離脱も説明がつく。こちらが武器を持っているのではないかと用心していたわけだ」
「つまり、君達はお互いに相手を殺人鬼だと思っていたんだ」
「ああ。不幸なことだった。もし僕がもう少し冷静に考えることができれば、きっと力を合わせてこの状況を乗り越えることができただろう。船長はおそらく他の乗組員と同様に撃たれた。そのときに犯人の顔を見ることができなかったんだ。きっと背中からやられたんだろうな。そのまま気を失っていたかもしれない。とにかく、僕が睡眠装置から出てくる前に意識を取り戻したんだ。そして、船内を探索する。他の死体を見つけてさぞ驚いたろう。しかし、彼は抵抗するすべを考えた。きっと用心しながらロッカーまで行き、武器を取り出して犯人を追いつめようとしたんだ。そこへ僕がのこのこと、彼のターゲットとして舞台に登場してしまった」
「残念だったな。本当に」
「ああ……そのことに気がついたのはつい先ほどだ。だけど、もしこの仮定が合っているのなら、犯人は別にいることになる。僕はさっきこの部屋から操作してすべての倉庫の温度を下げたんだ。カメラを自動反応モードにしてね」
「どうだった」
「出てくる者は誰もいなかったよ」
「それは少なくとも倉庫にいない、ということだね。まだどこかに隠れているのかもしれない、という可能性は消せないんじゃないかな」
「ロケットに詳しい者なら、搭乗口のすぐ下にある機関室などの存在を知っているかもしれない。でも、それは僕も同じだ。この船のことなら相当に詳しいつもりだよ。一通り見て回ったけど、誰もいなかった」
「だったら、そういうことなんだろうな」
「ここで、一つ問題になるのが倉庫で死んでいたクォートだ。僕が発見したとき、彼は殺されたばかりのように見えた。まだ血が固まっていなかったからね。船長と撃ちあって死んだのかもしれないと思ったけど、それだったら、船長は少なくとも犯人を殺したと思っていただろうから、僕を闇雲に撃ってくるというのはおかしい。まあ、安心しているところに僕を発見して驚いたのかもしれないけどね。それはそれで構わない。クォートは船長が殺したってことでもね。でも、もう一つもっと自然な可能性があるんだ。それはつまり……」
わたしはこの長い説明に自分でも疲れていた。
「クォートの死体を見たときから、なにかが引っ掛かっていたんだけど、ついにさっき思い当たった。彼は私服で死んでいたんだ。これはつまり、彼が殺されたのがきわめて最初の段階だということを強く示唆している」
こんなことをして何になるというのだろう。どのみち結果は自分で選べないのだ。この行為の意味はなんだろうか。
「つまり、実際にはクォートもずいぶん前に殺されていたということだ。おそらくは他の乗組員と一緒にね。彼の血が固まっていなかったのはアイスのある冷凍庫にいたからだよ。銃を持っていたということは、船内で起こっている事態に気が付いていたのだろう。実際に弾が一発無くなっていたから、犯人と撃ちあったとは思うけどね。そして低温の倉庫に逃げ込み、ついに撃たれてしまった。あるいは撃たれてから倉庫に逃げ込んだのか。その辺りはもうわからない。倒れた彼の身体は急速に冷やされ、流れた血も凍ってしまったんだ」
「なるほど」
「その後、僕と船長が撃ちあっている間に倉庫の温度が上がり、新鮮な死体のできあがりってわけだ」
「なぜそんなことになったと思う?」
「それが問題だ。はっきり言ってわからない……この犯罪の根本的なところが、よくわからないんだ」
ホワイトは肩をすくめた。
そして、わたしは最大の謎を打ち明けた。
「実は操縦席に見知らぬ女性が一人座っていた。死後ずいぶん経っているようなんで、この事件の犯人とはなり得ないけどね。いままでなんだかんだ言ってきたけど、結局最後にそれを見た時からこの事件が船長の手によるものではないとわかってきたんだ。もちろん……」
別にこうして話すことにそれほど意味があるわけではない。心の準備というやつだろうか。
「君には説明する必要もないだろうけど」
終章 故郷へ向かう船
ホワイトは弱々しくほほえんだ。
わたしは聞かなければならなかった。
「あれは君の妹だね」
彼は視線を逸らした。否定はしなかった。
わたしは続けた。
「犯人は船内にいないし、死体はどれも数時間以上前のものだ。ということは、ロケットの発射前に殺されていても構わないわけだ。でも、通常はそんなことをすればすぐにばれてしまう。なにしろ打ち上げ時に管制塔との交信があるからね。ところが、その管制官がすべてを承知で死体の乗っているロケットを打ち上げれば、それも可能だ。まあ、ロケットの操縦をすべて外から行えるのか、ということになると、やったことがないのでなんとも言えないが……」
「できるよ」
彼は静かにそう言った。
わたしはこの告発の行く末を考えると憂鬱になった。
「出発の少し前に、君は船のところまで車でやってきた。おそらく僕が船に入った直後ぐらいだろう。妹の亡骸を抱えて、操縦室に行った。そして、彼女を座席に座らせたんだ。後はどこかタラップの見えるところに隠れて乗組員がやってくるのを待ったというところか」
「皆がまとまって宇宙船に乗り込むものだと思っていた。いつも出発前に船長から『全員配置についている』と連絡を受けているからかな。まさか、ああもバラバラで乗ってくるとは思いもよらなかった。最初に来たのはノエルだ。彼は操縦室に行って、妹の死体を見て、慌てて戻ってきた。そこを撃ったんだ」
口調は変わらなかった。
「本当は全員に操縦室を覗いて欲しかったんだが、そううまくはいかなかった。奴の死体を隠そうとしているときにリュウがそこに現れた。慌てて後を追ってロッカーのところで撃ち殺した。そのとき、後ろから銃声が聞こえて、見るとクォートが銃を持って立っていた。撃ち返すと弾は彼の胸に当たった。倉庫に逃げこんだので後を追うと、中で死んでいたよ」
「外へ出ると船長がリュウの身体を揺さぶっていた。後ろから撃つと、そのまま倒れた。まさか死んでいないとは思わなかった。船の名札を確認すると、まだ殺していないハイダの赤字の札がぶら下がっていた。つまり、もう乗っているということだ。おそらくわたしが妹を運んでいる時にでも乗り込んでいたんだろう。
そこでわたしは睡眠装置のある部屋に向かった。本当は規則違反だけど非番の人間が打ち上げ前に寝ていることがあると、以前飲んでいるときに君から聞いて知っていたからな」
これほど距離の隔たりがあるのに、わたしはひどく緊張していた。
「真ん中の装置が使用中のようだった。どうやって中から出てきてもらおうか、少し考えたけど、あっさり手で蓋を開けられたので驚いたよ。とにかく、寝ている彼の頭をこづいて、目を覚ましたところで胸に一発打ち込んだ。自分が誰に殺されたのかを、知ってもらいたかったからな。奴を殺すのが一番簡単だった。しかし、君がその横にいたとは……」
そのときこそ、わたしが一番死に近づいた瞬間だったのだ。もしかすると、カプセルの中で銃声を聞いたがために、西部劇の夢なんかを見てしまったのかもしれない。
「白い札がぶら下がっているのは知っていたが、予備の名札かなにかだろうと見過ごしてしまった。とにかく、すべての乗組員を殺したと思ったわたしは船を出て、管制室へ急いだ。最近人手不足なのはアストロノウツも管制官も同じでね、今回のように一日にロケットが一台しか飛ばないときには一人で打ち上げのオペレーションをすべてこなすんだ。勝手に乗組員全員集合、燃料、計器以上なし、積み荷個数確認済みという報告を船長から受けたことにして、宇宙へさようならだ」
彼は満足そうだった。
わたしは無駄だと思いつつも、やはり尋ねずにはいられなかった。
「何故だ? どうしてこんなことをしたんだ?」
彼は首を振った。
「妹が五日前に自殺した。その罪を彼等に償ってもらう必要があった。それだけさ」
「他の奴等は知らないが、船長にまで責任があったのか?」
「彼には済まないことをした。しかし、この計画を実行するには船長に生きていてもらっては困るんだ。邪魔だから殺さざるを得なかった。君は遠慮なくわたしを殺人者呼ばわりしてくれて構わない。わたしだって自分の行為を正当化しようなんて気はまるでないんだから。まあ、死んでいった奴等よりは正しいところにいると思うけどね」
「だったら船なんか選ばなければ船長を巻き込まずにすんだじゃないか」
「船だから、こうしたんだよ……奴等が、そしてわたしが船に関係した職業でなければこんなことはしなかっただろう」
初めて彼の口調が乱れた。感情の起伏を抑え込んだ平静。すぐにそのことを後悔するように、彼は首を振って黙り込んだ。
「船だからってどういうことだ。君の犯行をごまかすためなのか。船が目的地に着いた時に、殺されたばかりに見えるクォートの死体があれば、船が打ち上げられてからの犯行だとごまかせるからか」
彼は意外そうな顔をした。
「ははあ。おもしろいことを言うね。あのクォートの一件はね、もっと別の目的なんだ。ロケットが打ち上げられた後もわたしはここで勤務を続けなければならなかった。明日にこちらへ到着する貨物船からの定期連絡も受けなければならなかったしね。だけど、乗組員を全て殺したと信じていたロケットから突然送信を受け取った時の驚きを想像できるかい? あれが今回の中で一番恐ろしい瞬間だったよ」
「そう、僕が最初に連絡を入れたときずいぶん驚いていた。管制官である君が僕の存在を知らないのはおかしいのでは、ということに思い当たったのが決定的だったんだよ。正常な発射であれば、船長から乗組員の人数と氏名が告げられるはずだからね」
「そうか……それはそうだな。とにかく、わたしは君が船に乗り込んでいたことを知った。勤務表が変更になっていたんだな。確かにその旨を書いた書類があった。机から落ちたと思われる床の上にね。相変わらずそういった伝達事項が徹底していないだらしない組織だよ。どっちにしろ当日にそんなことを確認する余裕はなかったけど……おまけに、君の話がいきなり途切れた。まるで誰かに邪魔されたように。そこでわたしは不安になったんだ。誰かを殺し損ねたのではないかと。だとしたらわたしに何ができるだろうかと必死に考えた。そのとき、クォートの死体が温度の低い部屋に転がっているのを思い出して、1-Cの温度を上げたんだ」
「だから、それが保身のためだろ。犯行時間をごまかすための」
「ちがうよ。わからないか。わたしは自分のやったことを隠そうとは思っていない」
確かにそれはそうだろう。現に妹の死体を操縦席に座らせている。これは自ら名乗りを上げているようなものだ。
「だとしたら、なぜ温度を操作したんだ」
「それはもう単に生き残りを無くすためだよ。生き残っている奴はどうせかなり負傷しているし、放っておいても君と殺し合いになるであろうことは予想できたけどね。無傷の君がケリをつけてくれる可能性はとても高い。どうだい、君は殺されたばかりに見えたクォートを見てこの一連の犯人がまだ船内にいると思っただろ? なんとしても相手をやっつけなければと思ったろ? まさにそれだよ。わたしが望んだのは」
「しかし、それは船長だったんだぞ。彼は関係ないんじゃないのか?」
「……そうだ。つくづく済まないことをした。どのみち君が生き残っていることが発覚した時点で、この計画がうまくいく可能性はかなり低くなってしまった。船長を巻き込んだこと自体が無駄になってしまったんだ」
「どういうことだ」
「……ロイド」
彼は目を細めた。
「前に酒の席でわたしが地球人ではないということを話しただろう」
「ああ。どこかのコロニー出身だってな」
「ブランクーシだ。まさに君がいま向かっている、宇宙船の中継基地として造られたところだ」
彼の声が奇妙に震えている。
「言ってみれば小さな田舎町だよ。決められた天候、季節、昼と夜。そこには人工でないものはない。そこでわたしは子供の頃から地球の事を聞いて育った。ここを人類発祥の地として崇めている者は、地球には母なる自然があると言うんだ。こんな人口過剰の薄汚い星の濁った海に憧れる人間はとても多いんだよ。わたしも妹もそうだった。幼い頃から。偽物の狭い海辺で、砂遊びをしながら地球の海には波があるという話をしたものさ」
こうして彼の話を聞くのは構わない。しかし、その後で、彼はどうするつもりなんだろうか。
「わたしはブランクーシに一番近いエクバスの大学を卒業してこの会社で働くようになった。勤務希望地はもちろん地球だ。晴れて次の年からここに来ることができたんだ」
彼の目が、遠くを見ている。わたしには見えない光景を。
「妹をつれてこの星に来た。わたしはすぐにこの星に慣れることができた。思っていたほど自然が残っていない、治安の悪いこの有様にも何も思わなくなった。だけど妹はどうもだめだったみたいだな。帰りたいと言うように……」
彼は中途半端に言葉を止めてしまった。
「どうでもいい話だ。わたし以外の人間にとっては。そもそもわたしがうっかりと自分の会社の船がブランクーシに向かうことを教えてしまったのが始まりだった。乗組員の中に以前から付き合いのある人間がいた。奴等は彼女をこっそり運んでやると言ったらしい。もちろん、そんなことが簡単にできるわけはないし、彼等にそんな大それたことをやるつもりがあったとも思えない。とにかく、どんなことをしても帰りたいと願っていた妹はあっさりと引っかかり、金も巻き上げられた。騙されたことに気がついた彼女は故郷を思って死んだ。その辺りは日記に書いてあったよ。妹の死体を通常の荷物としてコロニーへ送るのは不可能だ。検疫に引っかかる。でも、この仕事を利用してなんとかできないかと考えたんだ。妹が死ぬ原因となった奴等も同時に片づけるこの計画を思いついた時には何もかもが素晴らしく思えた」
わたしは言葉も無かった。
わからないではない。
しかし、彼の行為は破滅的だ。後先など考えていないのか。
「わたしの目的は果たすことができた。後は君の好きにするといい。警備隊に連絡したというのは嘘だ。まだ君の窮地を知っているのはわたしだけなんだ。思いがけない危険に曝して悪かった。操縦席の通信装置も完全に壊したと思っていたのに、倉庫にも同じ設備があったとはな」
「少し大きな船なら絶対にそうなっている」
「覚えておこう」
「ホワイト、君はどうするんだ」
尋ねると彼は力無く笑った。
「そうだな。最初から捕まるのは覚悟していたが、どうやらその心配もなくなったようだ」
「どういうことだ」
「倉庫で死んでいたクォートの撃った弾は、もちろん船長にあたっていない。クォートに傷を負わせたのはわたしだからな。彼が撃ち返した弾はわたしの腹に当たった。うまい具合に骨は避けてくれたようだし、出血もさほどひどくはない。ここで妹を乗せた船がブランクーシへ向かうのを見ていようと思っていたが、そろそろきつくなってきた。もし、君が望郷を理解してくれるのなら……いや、もう過ぎたことだ。死者はものを考えないだろう。悪いが通信を切るぞ」
彼が苦しそうに手を伸ばそうとして、うめくのが聞こえた。
「なんだっけ、あのくだらない台詞。ああ、そうだ。ちょっとワニを探しに行ってくるよ」
画面が暗くなった。
「おい」
通信終了という文字だけが白く浮かんでいる。
空調の低いうなりだけの世界にわたしは残された。
十日後。
操縦室の座席に座っていた。
通信機のスイッチを入れた。壊れているユニットを丸ごと取り外して、倉庫に転がっていた予備と入れ替えたのだ。動くかどうか不安だったが、なんとかなった。
「こちら貨物船ヴィーナス221」
呼びかけにすぐ応答があった。
「こちら第一宇宙港だ。ブランクーシへようこそ」
「本社から連絡があったと思うが、いろいろとごたごたがあった」
「聞いている。医者は必要か?」
「いや、大丈夫だ。二時間後に到着予定だ」
「了解。念のために聞くが、乗員の死体はどうした」
「ああ、すべて船外投棄したよ」
「了解。困難を切り抜けて荷物を届けてくれた君の行動に、このコロニーのすべての住民が感謝するだろう」
「ああ、残念ながらアイスに関してはほとんど溶けてしまったが、コンテナが一つだけ別の倉庫に入っていて無事だった」
「それは何よりだ。子供達が喜ぶだろう」
通信を切って、わたしは椅子に深く座って珈琲を飲んだ。この一杯のために『船内の銃撃戦により、貨物の一部が破損して珈琲の入っているコンテナが損傷。幸いにも被害は一箱だけに留まった』という一文を報告書に付け足しておいた。
吐き出した息が白く漂い、やがて消える。
室内の温度は0度近かった。
この部屋だけ暖房を入れていない。
別に寒いのが特別好きなわけではない。ホワイトの妹の腐敗を少しでもくい止めるためだ。おかげで、あまり長時間この部屋にはいられなくなってしまった。
他の死体はすべて投棄したが、彼女だけはここまで連れてきた。
なぜ、ホワイトがこの座席に妹を座らせたのか。
もちろん、乗組員が揃ってこの部屋にやってくることを期待していたのだろう。そして、なぜ自分達が殺されるのか、その訳を思い知らせてから殺そうとしていたのだろう。
でも、もしかすると、別の理由もあったかもしれない。
一時間ほどでそれをスクリーンにとらえることができた。
これといった特徴のない、ありきたりの人工居住地。それを大きなスクリーンで見ることができる唯一の場所がこの操縦席だ。
「さあ、名も知らぬお嬢さん、あなたの生まれたところですよ」
目を閉じた彼女に話しかける。魂なんてものを信じてはいない。だが、死んだ人間にだって慰めはあってもいい。
わたしは彼女を抱きかかえた。
廃棄用ダクトを開ける。宇宙にゴミなどをまき散らすのは御法度だが、古い船にはこういうものがついているのだ。
計算は大きく違っていないと思うが、ハイスクールでの物理学の成績を思うと心許ないばかりだ。この船の進行方向と射出の勢い、アステロイド軌道を回るブランクーシの速度。太陽の引力。
彼女の体をダクトへ押し込む。ステンレスの扉が閉ざされる。排出と書かれた赤いボタンを押す。
ランプがつく。一瞬船体が軋む。気圧計の針が一気に下がり、耳がおかしくなる。
すぐにランプは消えて、ゆっくりと針は元に戻る。確認のため、ダストボックスを開く。
もうそこにはなにもなかった。
船はやがてブランクーシの周りを回る軌道に乗った。
レーザーの照射ポイントの調整。減速、制御ロケット点火。すべて機械任せだ。
長い旅だった。
近づいてくるコロニーの明かりを見ながら、わたしは自分の故郷である地球のことを思った。生まれた町の家並みや近くの草原や家族。地球に比べて、あまりにここは小さい。このコロニーを生まれた土地と思うことができるだろうか。
しかし、少なくとも彼女はここに帰りたがっていた。
船外へ打ち出した体は、しばらくこの船と同じ方向へと進んでいるはずだ。うまくアステロイドの軌道に乗ればいいのだが。
モニターには小さく輝くブランクーシの姿が映し出されていたが、遠い地で命を落とした女性の姿はもうわからなかった。
頼りない星の瞬きに目を凝らしながら、ふと思う。
彼女は地球で海を見ただろうかと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
