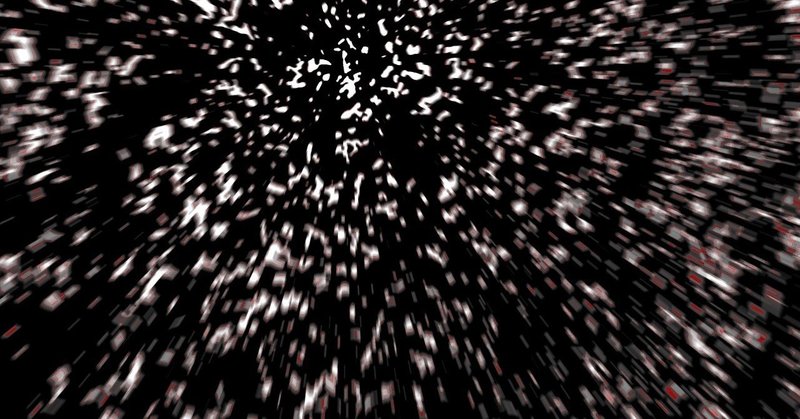
雪の降る夜 前半(9765文字 無料)
あの日、わたしは走っていた。
夜の闇と雪を踏みしめる音。乱れる呼吸。
月明かりに照らされた新雪の上に一筋の足跡が続いている。その先に何があるのか。
待ち受ける未来を恐れながら足跡をたどっていた。
わたしは疲れきっていた。
大学生活が始まって、長く苦しかった受験時代が如何に無意味なものだったかを知った。親の金を使って遊び呆け、車を買ってもらい、異性の尻ばかり追いかける男。それを意識して喜んでいる女。この目で見るまではそんな奴等が実在するなんて信じられなかった。わたしのように他人とほとんどコミュニケーションをとらないような女は彼等の視野に入らないのがありがたかった。
生物学にも特に興味を持てなかったのは、『合格できそう』を最優先にして学科の選択を誤った自分のせいだが、結果として大学からは足が遠のくことになってしまった。
わたしはただ、自分の進むべき道を探そうとしているだけだ。だけど、それがあまりに困難で、どうすればいいのかいつもわからなくなってしまうのだ。安住の地を求めているのに、方向さえわからない。何もない暗闇に放り出されたような感覚の日々味わっていた。
意味もなく追いつめられていると思ってしまう。眠る時に明かりを消せなくなった。これはきっと単なる自己憐憫なのだろうとわかっていてもどうしようもない。
お酒を飲む事ができればもっと生き方が変わっていたかもしれない。酒が他人とのコミュニケーションにこれほど重要な意味を持つとは予想もしていなかった。特に大学という、特殊な環境においてそれは顕著だ。
高校生の頃に知ったのだが、わたしはビールをコップに一センチも飲むと歩けなくなり、気持ち悪くなる。大学生になってからはコンパに出ると無理にでも飲まされると聞いていたのでいつも断り続けていた。
でも、それはわたしがお酒を飲んで苦しくなることが嫌なのではなく、酔いつぶれたわたしの面倒を見ることになる人に悪くて断っているのだ。
サークルや同好会にも入らなかったのはそんなことも原因の一つだ。
中学の頃からたくさんの本を読むようになり、その中でも推理小説が好きになった。しかし、大学にはミステリ研究会などの類は存在せず、気に入った作品について誰かと論じ合うことなど夢のまた夢だった。
きっと同じように孤独を噛みしめ、己の存在の意味などという、どこにもないものの答えを見つけようともがいている人がたくさんいるのだろう。わたしはその孤立した無数の点の一つだ。
やるせない日々が続き、過去の思い出に浸ることが多くなった。
気が付くと、わたしは子供時代のある夜のことを繰り返し繰り返し考えるようになっていた。部屋をうっすらと照らすオレンジの常夜灯を何時間も見つめながら、すぐ側に誰かが眠っているような気がしてしょうがなかった。
目をそらし続けてきたある疑問。
あの時の記憶は今でもはっきりと残っていた。
クリスマスを前にして、わたしは天井を見つめながら布団の中で思った。
あの夜の謎を解きに行こう。
十年前のクリスマスイブの晩に何が起こったのか、確かめる。
わたしを縛り続けている疑問の答えを見つけるために。
それは久しぶりの決意だった。
=============
列車は山間を縫うようにくぐり抜け、風仙寺駅に停止した。ディーゼル車に引かれる客車は暖房を使う冬の間は、乗降時に手でドアを開けなければならない。
頬に触れる空気の冷たさを最初に感じた。息を吸うと、少しのぼせていた頭がクリアになる。
ホームには僅かに雪が残っていた。スキーで有名な雲間岳から距離にすればそれほど離れていない場所で、交通の便は悪く、観光の対象となるようなものは特にない。
駅は集落から離れた山の中腹にあり、線路の向こうに小さな町が広がっているのが見下ろせる。懐かしい風景は過去をわたしの胸によみがえらせた。最初にこの光景を見たときには山に囲まれた箱庭のような家並みが、むかし科学館で見た鉄道模型のようだと思ったものだ。いつか鉄道模型をやりたいと思っていたものだが、女の子がそんなことを言い出すのはどうかと思って遠慮していた。いつか自分でお金を稼ぐようになったら好きなだけ買おうと一時期は思っていたけれど、やがてそんな情熱も忘れてしまった。
訪問はあらかじめ電話で知らせてあり、叔父が四輪駆動の大きな車で迎えに来てくれるとのことだった。あの事故以来会っていないので十年ぶりだ。わかるだろうかと心配していたが、駐車場には数台の車がいるだけで、迷ったりする余地はなかった。懐かしい笑顔がわたしを見た。
「お久しぶりです」
思った以上に叔父は歳をとっていた。山の男を連想させた逞しい印象は薄れ、なんだか一回り以上小さくなって、白髪と皺が目立つ人になっていた。まるで抜け殻のようだ、と何故か思う。
「ああ、久しぶり。香苗ちゃん、もう大学生なんだって?」
「ええ」
曖昧な返事をする。学校へ行かない者は学生を名乗って良いのか。
叔父の経営するペンションまで車に揺られて三十分。ますます人気のない山の中へ。
「それにしても香苗ちゃん大きくなったね」
「ええ」
「どうしてまたここに?いや、もちろん大歓迎だけどね。シーズンオフだから、今日は客は君をあわせて二組だ」
叔父の横顔からその気持ちまで推測するのは困難だ。
わたしは彼の表情を見逃すまいとして言う。
「わかりません。でも今年で十年です……区切り、というか……」
「そうか……そうだな」
会話ははずまなかった。
窓の外を過ぎる木々、日の当たらない場所に取り残された山道の雪を眺めながら、わたしはクゥシェットのことを思い出していた。
もう遠い記憶だ。
十二月二十四日の夜。
わたしは九歳だった。
=======================
クリスマスイブ。夜空にちらつきはじめた雪。
わたしは独りで電車を乗り継いで叔父さんの山荘へ遊びに来ていた。小学生なのに一人でこんなところまでやってくるのだからたいしたものだ、と叔父さんが感心したのももっともだと思う。
こんな日に降ってくる雪はロマンチックというやつらしい。さっき叔父さんがギターを弾きながらわたしに教えてくれた。それから、雪のもっと多い地方ではそれどころじゃないってことを話してくれた。
クゥシェットは叔父さんのところのスプーマムだ。二人でここに暮らしている。スプーマムとしては三歳。人間にするとわたしとほぼ同じ歳だという。
ここにいる間、クゥシェットとわたしは同じ客室の二段ベッドを使っている。もちろんわたしが上だ。おっちょこちょいのクゥシェットがハシゴを上り下りするのは危険だから。
わたしはテレビを見ているクゥシェットに言う。
「雪がただきれいだっていうのはぜんぜん嘘なんだよ」
番組の内容はおそらくクゥシェットにはわからない。テレビから観客の笑い声がするとそれだけで楽しくなるらしく、一緒に笑うのだった。わたしが側にいるときにはいつも横を向いてから笑顔を見せる。わたしが笑っているのを確認するように。
クゥシェットが理解できていないようだったので、もう一度同じセリフを繰り返した。クゥシェットはようやくわたしを見た。そして言葉を発した。
「どうして?」
素直にそう訊ねてくる。いつだってそうだ。クゥシェットはわたしの説明を聞くのが好きなのだ。わたしはクゥシェットに向かって少しばかり偉そうに説明をする。
「いい?クゥシェットが住んでいるここでも雪はけっこう積もるけど、もっとたくさん降る雪国の人にとっては……雪国ってのは雪がたくさん降る地方のこと。わかる?北の方はそうなんだよ。そこに住む人にとっては恐ろしいものなんだって。怖い怖いものなんだってさ」
「どうして?」
「屋根の上にたまる雪の重さで家がつぶれる事もあるらしいの。しょうがないからみんなで雪をどけるんだって。それを雪かきって言うんだけど。ここではめったに雪かきなんてしないでしょ。せいぜい玄関の前の雪を退けるぐらいで」
わかっているのかいないのか、クゥシェットは笑いながらうなずいている。そして例によって手を振りながら舌足らずに答える。
「でも、わたしは聞いたよ。雪はね、何もかも消すよ。山も川も木も。雪はね。すごいんだよ。手品みたいだって父さんが言ってたよ。手品っていうのは不思議なこと。父さんにもわからない不思議なこと」
その答えも少し的が外れているのが常だった。
「だから、みんなが『雪はきれいだ』って言うけど、本当は違うんだってことを説明したんじゃない」
「どうして?」
わたしは大きくため息をつく。
ふと思った。もしかすると、クゥシェットは得意げにしゃべるわたしを見て、さらに喜ばせようと何度も『どうして』を繰り返しているのかもしれない。
でも、まさかね。
そして、わたしは邪気のないクゥシェットの笑顔にまた同じ説明を始めるのだった。
クゥシェットは少しとろい。三年前に初めて会ったときにはまったく手を焼いた。叔父さんは『香苗ちゃん、辛抱強く相手してやってね』て言ったけど、トランプ遊びはぜんぜん覚えないし、キャッチボールは下投げでもロクに受けられないし、川に入れば転んでずぶ濡れになるし。まったく一緒に遊んでいるこちらは心が落ち着く暇がない。
ある夏の日、わたしが木に登ってお気に入りの枝でくつろいでいるとき、よせと言ったのにクゥシェットも太い幹にしがみついて登りはじめたことがあった。まあ、一番低い枝なら何とかなるかな、と思った瞬間に落ちた。別に大した高さではなかったけど、肘と膝を大きくすりむいて血が出ているのが見えた。クゥシェットは座り込んで大声で泣き出す始末。
わたしは慌てて飛び降りた。
「だから言ったじゃない。下手すると死んでたよ。親より先に死ぬってのは親不孝なんだよ」
以前、わたしが車に轢かれそうになったときに、父に言われたセリフだったけど、それはとても大切なことのように思えたので、何度も繰り返し、自分に言い聞かせていた。クゥシェットはひどくしゃくり上げながらも質問することを忘れなかった。
「どうして?」
説明するのはとても難しかった。というか、改めて聞かれると自分でもよくわからなかった。とにかく、そうなんだ、という結論にしてしまった。
そんな感じであったから、休みが終わって家へ帰るときにはいつも心配でたまらなかった。わたしがいない一年の大部分をどうやってクゥシェットは過ごしているのだろうか。
クゥシェットは近所の小学校に通っているという。他にスプーマムはいないという。虐められていないのだろうか。
とにかく、クゥシェットはわたしが来ると無闇に嬉しそうにするものだから、世話が焼けると知りつつ一緒に遊んでいたのだ。
雪に覆われたクリスマスの日、わたし達は銀世界の中『秘密基地』へと急いだ。山荘から森を抜ける道の先に崖があり、その下に近所のホテルの大きな看板がある。その裏が恰好の隠れ家になっていた。冬には雪が崩れる恐れがあるのでその辺りには近づくな、と叔父さんに注意されていたのも秘密基地に相応しい条件だった。
驚いた事にクゥシェットが最初にこの気の利いた場所を教えてくれたのだ。わたしはその件で彼女を褒めた。ただ、クゥシェットが嫌っている大きな岩がそこへ向かう道の途中にあるのが、彼女には災難だった。それは「地蔵岩」と呼ばれていて、おそらく山の上の方から落ちてきたものなのだろうけど、大きな岩の表面にお地蔵さんの顔のような模様が浮かびあがっているものだった。わたしにはどうしてもその白っぽい染みがお地蔵さんには見えなかったが、クゥシェットは「なんだか恐いもの」としてなるべく見ないように側を通り過ぎようとするのだった。その緊張した様子がおかしいので、側に来ると、わたしはわざと「あ、あれなんだ」とか言って彼女に岩を見せようとしたものだった。
その日は雪が積っていたので、地蔵岩もすっかり白く覆われていた。クゥシェットもにこにこしながら側を通りすぎた。
わたし達は秘密基地の側に大きな雪だるまを作った。それは会心の作で、叔父さんにもらった炭で両目を、薪で鼻をつくり、小さな熊手を両手に見立てて、という素晴らしい雪だるまとなった。側で見ていたクゥシェットも最後に雪だるまの頭にバケツを被せるという重要な仕事を成し遂げて大喜びだった。わたしはクゥシェットにクリスマスのプレゼントとして持ってきた鬼のお面をこの雪だるまにつけてみたくなった。お面は部屋に置いてあるが、もう遅いので明日の最初の計画に加えることにした。きっとクゥシェットは驚くに違いない。
「よし、これは歴史に残る名作だ。このまま残しておこう」
わたし達は二人で大きく手をたたいた。
その夜、例によって遅くまでテレビを見たりトランプをしたりして、夜更かしをした。
寝るときには、小さな電球を点けたままにしておく。わたしはもともと真っ暗にしないと眠れなかったのだけど、クゥシェットが暗闇を怖がるので、しょうがなくそれに合わせた。
次の日に目を覚ますと、すっかり窓の外は明るくなっていた。わたしは寝坊してしまったのだ。
部屋の中にクゥシェットの姿が見当たらないので、例のお面を持って一人で森を抜けて秘密基地に行ってみると、驚いたことに巨大な雪だるまは消えていた。
跡には小さな雪の山があるのみだった。
がっかりして戻ってくると山荘の道具小屋の隅には雪だるまに使った熊手とバケツが隠すように置いてあった。もうそれだけで誰が犯人かは明白だった。
わたしはクゥシェットの部屋に行った。わたしがいるときには山荘の客室に一緒に寝ているが、普段の彼女は自分の部屋にベッドがある。
彼女はテレビを見ていた。が、雪で濡れた彼のズボンとセーターがすべてを物語っていた。
「クゥシェット、あの雪だるま壊したでしょ」
彼女はテレビを見たまま首を振った。
「知らない。知らない」
泣き出しそうな顔を見てわたしにはおおよその察しがついた。
きっと、午前中にクゥシェットは昨日作った大作を見にいったのだろう。そして雪だるまの手や顔に触ったに違いない。そんなことをすれば雪に埋め込んだだけの炭の目や口、あるいは薪の鼻など簡単に取れてしまうだろう。あるいは彼女は本当に無実で夜のうちに勝手に落ちたのかもれない。とにかくクゥシェットはびっくりしてそれらを戻そうとした。加減を知らずに力いっぱい頭を押す。その挙げ句に雪だるまの頭は落ちて壊れてしまったに違いない。
動転したクゥシェットは頭をつくりなおすことなど思いもよらずに雪だるま全部を壊してしまい、熊手やバケツを戻し、びくびくしながらここでテレビを見てわたしが来るのを待っていた。
そんなところだろう。
わたしは彼女の努力に免じてだまされてやることにした。
「そうか。だとすると、きっと溶けちゃったんだ。天気もよかったからなあ。雪は温度が上がると溶けちゃうんだ。それじゃあしょうがないね。こんどもっとすごいやつを一緒に作ろう」
わたしがそう言うと彼女は途端にニコニコと満足そうに笑った。
「壊してないよ。溶けた溶けた」
そう、わたし達はすごく仲がよかった。
=======================
森は空より深く暗い闇に沈んでいた。
午前零時。見上げれば星もない夜空を背景に木々の枝が浮かび上がっている。
もうわたしの目は闇に慣れていた。僅かに残る雪が木々の間に見えた。白く吐く息が凍てついた空気に散る。十年前を思い出す寒さだ。
振り向くと道の向こうに叔父の山荘の窓明かりが小さく光っていた。夜中でも居間の明かりはずっと燈しておくのだそうだ。もともとは暗闇を怖がるクゥシェットのための習慣だったはずだ。十年経っても彼女の為につけているのだろうか。あるいは、意味はもう失われ、単に習慣だけが残ったのか。
雪に囲まれたこの場所から眺めると、実に暖かそうな灯だ。
わたしも先ほどまで毛布にくるまってベッドの中にいた。
しかし、わざわざこの時間に出歩くのには重要な意味があった。
黙々とわたしは歩き続ける。懐中電灯の明かりはあまりにも頼りなげで心細かった。
風が強く吹きつけ、細かい雪片が流れる空気の形になり、体を撫でていった。小降りになっているが、もう十五センチほど積もっている。
背を丸めながら歩いていたわたしは硬い石に足を取られて転倒した。
衝撃。すりむいた掌の痛み。間近にある雪の大地。地面の匂い。懐かしい感覚が子供の頃を思い出させる。わたしはおてんばという柄ではなかったが、クゥシェットと遊ぶときには彼女にいろいろな体験をさせるために川に行ったり虫を追いかけたりして、実によく動き回った。
きっと一人だったらそんなことはなかっただろう。いまのわたしがそうだ。何をしたらいいのかまるでわからない。
この山はわたしが純粋になることができる場所だった。
あの日までは。
雪に頬を付けたまま眺める手のひら。転がった懐中電灯に照らされている。はらはらと雪が落ちて、すぐに血に溶けていく。
静かな雪だった。
十年前にも雪は降っていた。あの夜にも。
わたしは立ち上がる。歩き続ける。いまはもう見えない足跡をたどって。
クゥシェットが死んだあの夜の謎を解くために。
=======================
目が覚めるとクゥシェットがいなかった。まるで朝の繰り返しみたいだった。でも、窓の外は真っ暗だ。
わたしは部屋の明かりをつけて、しばらく待っていたけど、クゥシェットはなかなか戻ってこなかった。時計を見ると十一時だ。夜中近くの部屋で一人きりで待っているのは少し怖い。
クリスマスイブの夜。サンタクロースなんていないことはわかっていた。
しばらくして、わたしは下に降りていった。叔父さんは居間でテレビを見てお酒を飲んでいた。普段はお酒を飲まない人だったので、わたしは少し驚いた。
「叔父さん、クゥシェットがいない」
叔父さんはトイレにでも行ったのだろうと笑っただけだった。
わたしはトイレにはいなかったと答えた。叔父さんは肩をすくめて探してみようと言った。
山荘の部屋はそれほど多くない。客室を含めて全部回るのに時間はかからなかった。
探す場所を失った叔父さんは玄関を見て声を上げた。
「長靴がない」
玄関はお客さんが使うのでクゥシェットやわたしの長靴は山荘の裏口においてある。泊まっているお客さんはいなかったが、もちろんその規則は守られていた。例外としていろいろな雑用をこなす叔父さんの長靴だけが玄関に置くことを許されていたのだが、それがなくなっていた。
階段の下の木箱から別の長靴を出し、外へ駆けていく叔父さんの後をわたしも慌てて追う。わたしのつかんだ長靴は大きくて走りにくかった。
外はあまりに静かで、それがいつまでも続くことに恐怖を感じ始めていた。
雪はもう止んでいる。月明かりの中に地面も森もぼうっと浮かび上がっている。
新雪の上に一筋の足跡が続いていた。
「クゥシェット」
叔父さんとわたしは走った。よく見ると、足跡の傍らには時々小さな赤い染みがあった。それはもしかして血じゃないのか、と思ったけど、わたしは何も言わなかった。叔父さんもわかっているに違いない。
雪は十センチ程しか積もってはいなかった。わたしと叔父さんは森へと続く小道をたどっていった。
走りながらわたしの唇は震えていた。激しい動悸で目がくらみそうだった。
闇の底を柔らかく照らす雪面。一筋の足跡。その先に何があるのか。
わたしは待ち受ける未来を恐れていた。
五分ほど走っただろうか。前方で雪が盛り上がっているのが見えた。叔父さんがクゥシェットの名前を叫んだ。
近づくにつれてわたしの鼓動はますます激しくなっていった。
うつぶせに、雪に半ば埋もれた小さな体。両手は投げ出されている。足に合わない大きな長靴。服装はわたしが最後に見たときのまま、上着も着ていない。
叔父さんは雪を払い、動かない体を抱きかかえた。クゥシェットの顔は白くなっていた。そして何故かうっすらと笑みを浮かべていた。その安らかな顔がわたしの脳裏に焼き付いた。
髪の毛の間から雪がはらはらと落ちた。それはクゥシェットの血で赤く染まっていた。
叔父さんはクゥシェットの頬を何度も叩いた。でも何も起こらなかった。わたしにはわかっていた。クゥシェットが二度とわたしの手を焼かせることはないのだ。煩わせることはないのだ。
恐くて目をそらした。地蔵岩が視界に入った。見慣れた景色は闇の中で得体の知れないものに化けていた。雪を被った巨大な岩がわたしに迫ってくるような気がした。
やがて何も言わずに叔父さんは立ち上がり、山荘へ向かって大急ぎで走り出した。わたしはその後を追った。黙って泣きながら走った。声を出してしまうと全てが本当のことになってしまいそうで恐かった。
山荘に戻って町の病院へ運んだ時にはもう手後れだったのだけど、叔父さんはなかなかあきらめようとしなかった。輸血が必要なら自分の血をいくらでも、と医者に詰め寄っている横でわたしはクゥシェットが突然この世界から消えてしまったことを受け入れられなくて呆然としていた。
=======================
そう、十年前のクリスマスイブだ。
あの後で警察の人もやってきて状況を調べた。
クゥシェットは頭に大きな怪我があったが、それ自体は致命的なものではなかった。死因は雪の中へ飛び出していったため体温が低下して凍死に至った、ということだ。調べてみると山荘の階段の下にわずかに血の跡があった。このことから警察は、クゥシェットが階段から足を踏み外して転げ落ち、自分の血に驚いて気が動転してしまったため外へ駆け出し、その挙げ句に凍死してしまったのだろうという結論を出した。
わたしは当時、その結論どころかクゥシェットの死さえ納得できなくて、葬式が終わった後でも、次の年の夏休みになったらまた会えるのだと心のどこかで信じていた。
あの夜のクゥシェットの安らかな死に顔が何度もわたしの夢に出てきた。目を覚まして事故を思い出しては呆然としていた。
クゥシェットを発見した雪道の光景が忘れられなかった。
叔父の山荘へは葬式以来訪れなかった。
そして十年だ。
いまわたしは積もった雪の中を歩いている。あの日クゥシェットが歩いた場所を目指して。
そう。ちょうどこれぐらいの時間だった。
わたしの中にはクゥシェットの死に対するわだかまりがずっと残っていた。警察があのような短絡的な結論を出したとしてもそれは仕方がない。彼等はクゥシェットと遊んだことがないのだから。でも、わたしは違う。わたしはクゥシェットと共に過ごした時間がある。だからどうしても納得がいかないのだ。
スプーマムの血は人とほぼ同じ成分で、同じように赤い。人からスプーマムへなら輸血も可能だ。
わたしのさまざまな思惑はただ一つの疑問から発していた。すなわち『自分の血に驚いたクゥシェットが果たして外へ行くだろうか』ということである。
わたしの見てきたクゥシェットの行動からするとそれはまずありえないのだ。わたしと遊んでいるときにも彼女はよく転んだり頭をぶつけたりしており、時々は血も流した。そんな時、自分の血を見るとたちどころに腰を抜かして座り込んでしまうのが常だった。そして大声で泣き出すのだ。ましてや、彼女は暗闇を恐れていた。
そう。それがわたしの知るクゥシェットだ。そんな彼女の性質は身近な者しか知らないだろう。
わたし。あるいはもっと身近な彼女の父親だ。
たどりついた。
道の右手に大きな暗がりがある。目を凝らすと巨大な岩の存在が確認できる。半ば雪に覆われている。
木々の様子はかなり変わっているが地蔵岩だけはそのままだ。
クゥシェットはこの辺りに倒れていた。十年前、葬儀が終わってこの地を去る前の日、わたしはここを一人で訪れている。
突然この世界から知っている者が消えてしまうという残酷な現実に為す術がないということを知って泣いた。
その時、この岩をクゥシェットの墓標だと思うことにした。
立ち止まり上空を仰ぐ。
暗く沈んだ空には月も星も見えない。
振り返る。
わたしのたどってきた暗く長い道が雪に覆われて見えない闇へと延びていた。
暗がりから、足音が聞こえてきた。
後半へ続きます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
