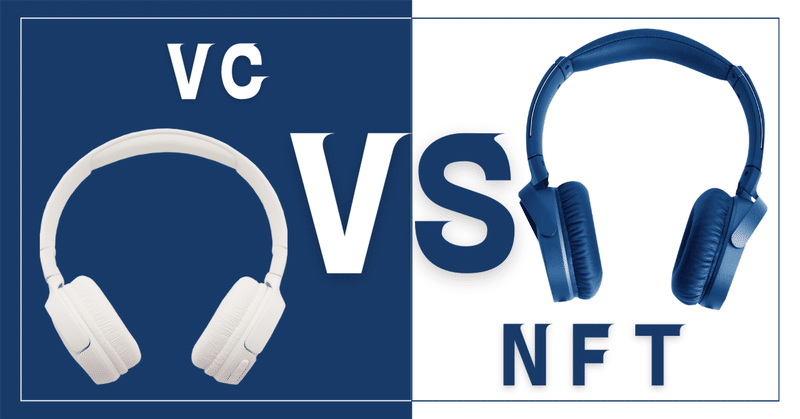
VCとNFTの類似点・相違点
こんにちは。
Recept 大島です。
私はWeb3業界、特にNFTと深くかかわってきました。
個人で一時期やっていたWeb3アセットの売買もNFTを中心にやっていましたし、銀行でプロジェクトリーダーを務めた施策もNFT関連でした。
そして今、起業して取り組んでいる領域が「DID/VC」という技術です。
DID/VCはWeb3のムーブメントの中心にいる技術ではありませんが(親戚くらいの感覚)、NFTとの共通点も多いと個人的には思っています。
もっと言うと、
私がNFTに可能性を思っていた点の多くを引き継ぎ
私がNFTに限界を感じてしまっていた点を回避している
のがDID/VCだと思いこの技術にかけています。
今日はその話をしていきます。
NFTとは
NFTは「Non Fungible Token=非代替性トークン」の頭文字をとったものです。

ブロックチェーン上ではトークンという形式でデータが流通しています。
(トークンもまた抽象的な用語ですが、Web3においては「保有者が何らかの権利を有していることを証明するデータ」と覚えるのが最良だと私は思っています。)
で、非代替性のトークン=同じものが二つとないトークン=NFTとなります。
分かりやすい比較で言うと、暗号資産は「代替可能なトークン(Fungible Token=FT)」です。
ビットコインというトークンを考えると、あるビットコインと別のビットコインはどちらも「1ビットコイン」です。
Web3上で利用するときも、法定通貨と交換するときも、それらのビットコインは同様の用途・価値で利用できます。
つまりこれらのビットコインは等価で交換可能=代替可能、というわけです。
少し脱線しましたが、NFTはそうではないということです。
仮にあるアート作品がNFTになったとして、それらには一意の情報(シリアルナンバーと例えると分かりやすいですかね)が付与されています。
仮に同じアート作品がNFTになっていたら
①作者が自分のアート作品でNFTを発行したら、誰かがそのアート画像を拾ってきて勝手にNFTを発行した
②同一人物、例えば作者が二つ同一のNFTを発行した
といったパターンが考えられます。
①に問題がありそうなのは自明ですし、おそらく誰かが勝手に発行したNFTは偽物のような扱いをうけ価値がないものとみなされるでしょう。
②にもなんだか問題がありそうです。(例えばその作家が好きでアートNFTを買ったとして、次の日に同じアート作品がまたNFTにされていたら嫌ですよね。)
このように、同じアート作品をNFTにした場合でもそれぞれは等価ではないということになります。
NFT最大の価値
そして、ここまで記してきた特徴はNFTがもたらす革新性の一番大きい要素となっています。
これまでの世界では、基本デジタルデータはコピーし放題でした。
フォルダに入っているデータも右クリックで簡単にコピーできてしまいますよね。

データの作成日時等をログ管理するなどしてバージョン管理することも出来ますが、そのログ化記録されているデータベースにアクセスできる人しかバージョンを確かめられなかったりして、使い勝手がいいモノではありませんでした。
NFTでは、情報がブロックチェーン上に記録されるため、誰でもデータの発行者や所有者を確かめることが出来ます。
デジタルデータに「本物と偽物という概念(それによってデータの所有、唯一無二性などの概念も生まれる)」をもたらしたのがNFTの革新的なところです。
NFTがもたらす革新点
これでもまだ抽象的だったかもしれません。
もっとかみ砕いて、実世界にどんな便利さをもたらし、これまで出来なかったどんなことが可能になるのか、という観点で列挙していきます。
①管理者を必要とせずにデジタルデータの売買が可能となった
⇒ここまで話してきた内容でご理解いただけると思います。
②ユーザーが真に決定権を持ちデータのコントロールが可能となった
⇒これはWeb3上でユーザーがどのようにトークン(暗号資産やNFT)を保有するのかという方式の話になってきます。
ここで書くと長くなりすぎるので端折りますが、「ユーザーが自らのデバイスに秘密鍵というデータを保管し、それを介さないとデータに指図が出来ないためユーザーが真にデータのコントロール権を有した状態になっている」という方式です。
過去近しい内容を書いたので、もし気になる方はこちらを・・・
③事業者やサービスを超えた互換性がもたらされる
NFTは共通の規格が決められており、例えばウォレット⇔NFT、Dapps(ブロックチェーン上の各種アプリ)⇔NFT間には基本的に互換性があります。
規格が共通であるという条件の他に、ブロックチェーンという共有のインフラ基盤を共有しているという点も寄与しています。
④保有状況が公開される
NFTの保有者情報(ウォレットアドレス)や移転の記録はブロックチェーン上に公開されています。
⑤スマートコントラクトで扱える
スマートコントラクトとは、自動化(コード化)された契約という意味です。
例えば暗号資産とNFTを絡めることで、金流と商流の結びつきを自動化することが出来ます。
あるトリガーが引かれたら強制的にNFTが暗号資産で購入される、といった。
この「強制的に」というのが強烈です。
これまでだと例えば
・相手が約束を破ってお金を払わないリスク
・それを第三者が仲介することでリスクは減るがその第三者に支払う手数料が発生する
などのコストがありましたが、自動化されることで払拭できます。
他にもありますが、代表的なところだとこんなところだと思います。
NFTの限界
やっと戻ってきました。
ここからようやく、冒頭に書いた
私がNFTに可能性を思っていた点の多くを引き継ぎ
私がNFTに限界を感じてしまっていた点を回避している
のがDID/VCだと思いこの技術にかけています。
の真意について説明していきます。
私が感じていたNFTの可能性
先ほど挙げた五点すべてに革新性はあると思います。
※再掲
①管理者を必要とせずにデジタルデータの売買が可能となった
②ユーザーが真に決定権を持ちデータのコントロールが可能となった
③事業者やサービスを超えた互換性がもたらされる
④保有状況が可視化される
⑤スマートコントラクトで扱える
特に②と③に関して、これまでのインターネット世界での当たり前を根本から変えてしまう可能性があると感じ注目していました。
NFTに限界を感じてしまった点①
これだけ私はNFTの可能性に魅了されたわけですが、現状NFTは大して普及していません。
その要因として、NFTの用途がマーケティング用途に偏ってしまったことが一つ大きいと私は思っています。
前述したNFTの性質において、例えば①と④あたりはNFTをマーケティング用途で使う動きを生み出します。
デジタルデータの売買やトレードという市場をつくり、誰がどんなNFTを持っているかによって事業者がプッシュ型で営業するなどの手法が思い浮かびやすいからです。
ただ、デジタルデータを保有するという体験は多くの人にとって分かりづらいモノです。NFTを持っている人に特典を与えるという後づけ的な施策も考えられますが、それもクーポンアプリと体験は変わらないわけで。。。
(その特典を金融資産や高度なモノに変えるとまた可能性が出てくるのですが、ここでは割愛します。RWAと呼ばれるこの辺は最近盛り上がっているようで、NFTを復活させるムーブメントとなる可能性があると見ています。)
また「誰がどんなNFTを持っているかによって事業者がプッシュ型で営業する」と先ほど書きましたが、これはWeb広告や営業電話と同じく事業者の押しかけ的な側面が大きいです。
もちろんユーザーが欲している情報をダイレクトに届けられれば事業者もユーザーもハッピーですが、ユーザーにとって価値のないNFTが次々と送られてきてもウザい広告と同じです。
個人関連情報の共有が規制される世の中において、「NFTを勝手に送りつけて後継施策につなげていく」というのは時代の流れに反しています。

NFTに限界を感じてしまった点②
先ほど私は、NFTの五つの特徴のうち特に以下二点に可能性を感じたと書きました。
②ユーザーが真に決定権を持ちデータのコントロールが可能となった
③事業者やサービスを超えた互換性がもたらされる
これらの条件に相性のいいデータは、ユーザーにとって
・自分で管理したいと思う情報で
・あちこちで提示するシーンがある
なものになると考えられます。
そして、私はここに最もよく当てはまる情報は「個人情報」だと思っています。
プライバシー意識も高まる中で、出来れば自分の情報は自分で管理していたい。そんな中で、本人確認プロセスを要求するサービスが増えて自分の情報を提示するシーンは増加していく。
そういった背景からです。
ところがNFTで個人情報を扱うのは適していません。なぜならNFTは多くの場合公開された情報であるからです。
一応、パブリックではないブロックチェーン上にNFTを置くことで閲覧制限はかけられますが、そうすると一般的なNFTの仕様と異なるものになったり、中央集権型のデータベースに大事な情報は置くなどの対応となってNFTを使う意味が薄れてしまいます。
VCについて
そして、当社が使っているDID/VCです。
DID/VCとは何の略で、どういった特徴があって、というのは代表の中瀬が蓄積していってるので気になる方はこちらのマガジンをご覧ください。
(NFTについてこんだけ詳しく書いておいてという突っ込みは無しで…)
VCとNFTの共通点
VCとNFTの共通点は、ユーザーに情報のコントロール権があることです。
NFTでは、ウォレットのアドレスが識別子となり、そこに保有するNFT情報が紐づいていきます。
ウォレットのアドレスに関する操作はウォレットの持ち主しか出来ないため、NFTのコントロール権はユーザーが有しています。
DID/VCでは、DID識別子があり、そこに保有するVC情報が紐づいていきます。
DID識別子に関する操作はNFT同様にウォレットの持ち主しか出来ないため、VCのコントロール権はユーザーが有しています。
特定のサービスや運営者に管理が依存されない識別子があり、それに紐づく情報があるという構造が類似していると感じます。
私がNFTに革新性を感じた
②ユーザーが真に決定権を持ちデータのコントロールが可能となった
③事業者やサービスを超えた互換性がもたらされる
はVCにおいても達成され得ると考えています。
VCとNFTの相違点
VCにあってNFTにないもの、それは「情報が秘匿される前提」です。
VCはユーザーのスマートフォンに保管され、ユーザーの操作によってのみ外部に公開されます。
前章で、個人情報こそ②と③の特徴と相性がいいのではないかと書きました。そしてNFTは公開を前提とした仕様であるから個人情報は扱いづらいのだとも。
VCでは情報が公開されることはないため、個人情報の取り扱いにも適しています。
こうなると、ユーザー主権や高い互換性を実現し、これらが真に価値を発揮する情報(=個人情報)を扱えるDID/VCに期待を抱いた理由も分かっていただけると思います。
NFTが嫌いなわけではないけれど
ここまでNFTとDID/VCについて書いてきました。
今更なんだという感じですが、私はNFTが価値のない技術だとは思っていません。
ただ時代の流れに沿っていない用途に使い道が依ってしまったとは感じています。
ユーザーがあちこちでNFT(デジタルデータ)を保有し、その情報は透明性高く管理され、その情報を元に第三者がサービスを提供する。
革新性は十分にあったと思います。
しかし、事業者による行き過ぎた営業が社会問題となり、個人情報の取得や共有に関する規制が厳しくなる昨今。
NFTだけが治外法権的に、事業者がユーザーの情報を自由に取得し、一方的にマーケティングする手段にはなりづらいと思っています。
NFTがマーケティングに依ってしまい失速した中で、DID/VCは個人情報を始めとするセキュアな情報を扱う「IDテック」としてこれから成長する技術です。
DID/VC技術がもたらす価値については疑念の余地を抱いていません。
まだ黎明期の本技術が、社会の流れに迎合した「本物のムーブメント」を起こせるようコントロールする。それもまた当社にとって重要な役割だと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
