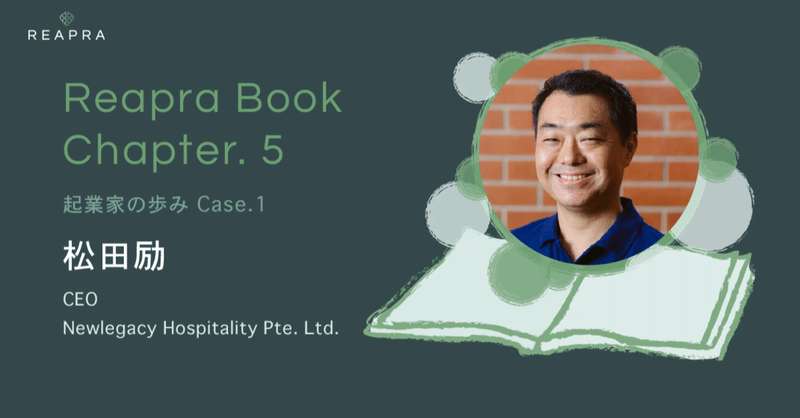
【Reapra Book連載シリーズ】第5章:社会と共創する熟達への道
昨年、Reapraで研究と実践の過程や得られた知識をまとめるためのプロジェクトが始まりました。それが"Reapra Book"。
Reapra Book連載シリーズも第5回目となりました。過去の記事はこちらからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
ここまではじめにから4章まで読まれた方の中には、「理論的な話ばかりで難しい」「実際のビジネスとどう繋がっているのかわからない」といった感想を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
第5章1節では、Reapraが支援する起業家の方々へのインタビューを通じて、社会と共創するマスタリーとは何かについて、より具体的に伝えていきます。 様々なエピソードから、1-4章で触れたReapraの研究実践との関連性を感じていただければ幸いです。
本章2節では、Reapra社員の社会と共創するマスタリーの歩みと題して、テクノロジー・セールス・ガバナンスをそれぞれ深めるReapra社員が執筆した文章を掲載しています。
今回インタビューにご協力いただいた起業家の方々は、現在様々な状況・ステータスにありますが、どの起業家の方も、日々変化する状況の中で産業創造を目指し、社会と共創するマスタリーを歩み続けている方々です。
また、Reapra社員も、概念構築という営みを通じて社会と共創するマスタリーを歩み続けています。 是非、ご自身と照らし合わせながら、多種多様な状況にある起業家の葛藤や変化、各Reapra社員のマスタリーへの想いに注目して読み進めていただきたいです。 何か1つでも、得るものがあれば幸いです。
起業家の歩み
2015年からタイにてホテル経営を行なってきたNewlegacy Hospitality Pte. Ltd.のCEO松田励氏(以下、“松田”として敬称略)。起業のタイミングや業界選択の理由から、今後の事業拡大の展望までのインタビューを行いました。タイという日本とは違った環境の選択や、そこにおける人との関わり方の変遷など、ユニークな環境がゆえの葛藤や自我の変容を中心に深掘りさせていただきました。
起業のきっかけ
編集 2015年のタイミングで起業をされたきっかけについて教えてください。
松田 2009年にホテルスクールを卒業してからずっとホテルの仕事ができていませんでした。「ホテルの仕事がしたいな」とウズウズしてるようなところで2014年後半に諸藤さんとシンガポールで再会して、食事をご一緒しました。それは単なる会食だったのですが、僕の記憶が確かなら、諸藤さんの方から「新しい業界を創っていく構想の中にホスピタリティ業界も入っているが、やる気ありますか?」とメールが来たと思います。
僕の方から諸藤さんに「起業したいです」とか「投資してください」と言葉にしたわけではないのですが、会食の中の会話でホテルの仕事したいという思いが凄くにじみ出ていたのではないかなと思います。そのメールをいただいた後に私の方で事業計画を作成して、数週間後には実際に投資しよう、という話になりました。
当時、中国ではエコノミーホテルのチェーンがトレンドで。すごいビジネスが中国ではあるんだなと感じていました。逆に、東南アジアでやっている人はいないなというのは同時に考えていました。中国のエコノミーホテルを見てこれを東南アジアでやりたいと思ったのと、諸藤さんとの再会が重なって起業する流れになったという感じです。
編集 元々は、どこかのタイミングで起業しようと考えられていたのですか?
松田 起業しようというのは、昔からあまり考えていなかったですね。自分とは関係無いことだと思っていました。2014年当時も、日本のホテル会社の外国法人で働くとかがいいなと思っていました。ただ、あまりそういうチャンスがなくて。そもそも日本のホテル会社で海外に法人のある会社がなくて。シンガポールのホテル会社で働くのも、トライはしたのですが、仕事が見つかりませんでした。
当時すでに30歳過ぎていて妻と子供2人もいて、フロントデスクの仕事から再スタート、というわけにもいかなかったという個人的な事情もあります。
また、シンガポールでホテルスクールを卒業したのがリーマンショックの直後で、採用が非常に細かったというのも影響が大きいですね。卒業した時が通常時であったら、シンガポールで大手ホテルオペレーターのアジア本社に普通に就職していたと思います。一年早かったり遅かったりしたら、普通に大手ホテルオペレーターで働いていて、全然違う人生だったでしょうね。
起業してからの葛藤
編集 なるほど、そのような背景があったのですね。では、実際に起業されてみて、葛藤されたことはたくさんあると思うのですが、いくつかお伺いしてもよろしいでしょうか?
松田 日本のコンサル業界で働いていたり、シンガポールの金融業界で働いてた経験が長かったので、それらとタイのホテル業界とのギャップがあまりにも大きかったというのが一言で言えば葛藤だと思います。タイに対するカルチャーショックとホテル業界に対するカルチャーショックの両方があって、実際のところ自分でもどちらのショックなのかわからないんですね。日本のコンサル業界から日本のホテル業界に移っても、カルチャーショックはあると思うんですけど、私の場合は業界とか、国が本当に180度違った。頭では分かっているけど身体がついて行かないということが結構ありました。
「普通」の違い
編集 具体的にどのような事が起こったのでしょうか?
松田 例えば、一番最初のホテルを開くときに、電話の内線の設定をしないといけなくて。何の番号をどこの電話に繋いで、その電話に誰かが出なかった時どこにどういう順番で転送するか、あるスタッフが僕に聞いてきたんです。僕としたらその時点で、「それくらい自分で考えてくれよ」って思ったのですが、しょうがないなので細かい内線の設計を手書きで紙に書いて渡しました。でも、何週間かしてもそれが設定されなくて。本人ははっきり言わないんですけど、その紙自体をなくしたようで。その紙の存在自体も覚えていたかどうかも怪しい感じがあって、ありえないなと思いました。こっちももう書いたこと覚えてないから、また一から考え直しなんですよ。普通に考えたら指示されたタスクはすぐにやるでしょとか、普通に考えたら社長が書いた紙無くさないでしょ、と。そのような問題が1日に何件も起こるわけです。ただ、こういう「普通に考えれば」と勝手に考えるのがとても良くないのです。向こうの方が「普通」なので。今考えれば、その人には手書きで指示をだして「よろしく」と言うこと自体が乱暴だったわけです。今なら、自分の手書きのメモを自分でも写真にとっておいて、定期的にフォローアップします。
編集 想像するに、様々な方法で問題を乗り越えられてきたと思うのですが、実際にどのようなことをされてきたのでしょうか?
松田 できない人に「なんでできないんだ」という風に言わないで、できるような方法を考えて、コミュニケーションするようにしたっていうのが一番の工夫だと思います。一応指示は出しておくけど、過度な期待はせず、実行されなかった時になぜされなかったのかを考えようということがよくありますね。
かつ、実行されなかった時に、イライラするのをやめたということですね。出来ない時にちょっととげのある言い方をしても、その人のプライドを傷つけるだけで、ますます事が進まなくなります。自分が1イライラすると向こうが3イライラするので、そういうことはあまりしなくなりましたね。自分の感情が動くと、それに輪を掛けて相手の感情が動いてしまう。仮に言っていることが正しくても、伝わらなくなっちゃうので。特にタイの文化では感情を表に出すということはすごく嫌われるので。「正しいことを熱心に雄弁に語る熱い人」が嫌われがちです。
人向き合いにおける葛藤
編集 文化が違うと価値観も違うのでさらに大変ですね。事前に記入いただいた資料では、2017年10月から12月のジャッキーによる社員ヒアリングというところでも人向き合いという観点で葛藤があったと記入されていましたが、これは具体的にどんな事象があり、何を感じられたのですか?
松田 Reapraのジャッキーさんが本社の社員全員にヒアリングするという機会がありました。その時は日本人の幹部が自分を入れて3人いたので、僕個人に対してのフィードバックもあれば、日本人の幹部全体に対するものもありました。全体として、ネガティブフィードバックが多かったんです。僕個人へのフィードバックとしては、僕が社員のことを機能としてしか見ていないというのがありました。目標達成したいと強く思っている人だから、あまり社員のことを人として見てくれてない人だと。思い返してみれば、僕も過去の職場で「機能として見られているな」と感じた経験があったので、当時の同僚のことを回想しながら、あの人みたいな感じに見られているのかとか考えていましたね。
編集 フィードバックを受けて、そんな風には接してるつもりはなかったのだけどというギャップが大きかったのか、確かにという感覚だったのか。どういう感覚で受け止められたのですか?
松田 「そんなつもりじゃなかったのに」とは思わなかったですね。それよりも、わりと指摘が根本的すぎて、どういうふうに改善したらいいか分からないみたいな感じでした。社員に向き合っていないと言われても、向き合うにはどうしたらいいのか?というレベルだったと思います。
編集 その後、どういった形で社員と関わられていたとか、そこからどのような変化があったのかお伺いしたいです。
松田 自分自身が機能として見られているか、人間として見られてるかというところを感じていた時期を思い出して、機能としてではなく、人として見るような接し方を心掛けました。
でも、改めて過去を振り返った時に、自分自身が機能として見られてるか、人間として見られてるかというところで深く悩んだ経験はあまりなくて。何となくあの人とは働きやすかったな、あの人はちょっと苦手だったなとかはあったのですけど、自分の中でその視点はあまり重要でなかったというか。そう考えた時に、元々相手のことを見つめるということが苦手なのだなと思いました。自分自身は、自分が他者を見るよりも、他者に自分を見て欲しい人なのだということに気づけたのが出発点でした。
自我への新たな気づき
編集 ご自身のそのような特徴について、気付くきっかけとなった出来事は何かあるのでしょうか?
松田 ちょうどその時にそのコーチングを受けていたコーチから、自分自身も「機能」として見ているという指摘を受けました。「何かを実行して何かを達成するから価値がある。何かを達成しなかったら価値がない。」という見方を自分自身にもしてるから、相手に対してもそういう見方をするのが前提になっている、ということです。自分自身に対しても、相手に対しても、条件付きの愛じゃなくて、無条件の愛というのですかね。そういうのを出すべきなのだと言われたのは気づくきっかけにはありましたね。
編集 気づきを受けてご自身が変化された中で、周囲の反応に変化はありましたか?
松田 そんなに劇的に変わるわけではないですけど、いい方向に向かっている感覚はありました。お互いもう少し仕事以外の部分でも繋がってるような感覚が出てきたというか。会社がだんだん大きくなってくるとそういう感覚って薄くなっていくんだと思うんですけど、逆に強くなっていった感じはある。あと、感情的に断裂することは減ったと思います。2018年の7月に、日本人が2人辞めてから、管理職では辞めた人はいないと思うので。コアなメンバーはあまり変わらなくなりました。
ただ、これは僕の社員に対する接し方が変わったから全部変わったということではないと思っています。事業をスタートした当時、僕があまりにも事業、ホテル、タイに関する知識がなかったので、夢だけ大きくて、実際に起きていることについては本当に理解していなかったんです。なので、何が大きく変わったかで言ったら、単純に自分の知識が大きく変わったのが1つ目。次に、社員への接し方が変わった。最後に、会社も大きくなって会社にいる人材も優秀になってきた。この3つが同時に起こったのだと思います。
利益マインドにおける葛藤
編集 いろいろな変化が同時並行で起こっていたんですね。事前資料では、利益マインドの低さというのも葛藤の1つとして記載いただいていますが、これは、どのように現れたのでしょうか。ご自身の葛藤だったのでしょうか。
松田 葛藤ともレベル感が違うかもしれません。一言で言えば、自分でもびっくりするぐらい商売が下手だったんです。今はReapraの矢野さんがRM(起業家を伴走支援するReapra社員)なのですが、初期の頃は今よりも諸藤さんと深く関わっていて。日常的に利益やキャッシュについて細かく聞かれるということってなかったのです。それは別に利益が大事じゃないと切り捨てるのとは違い、会社を経営する上では、それがいつも頭にあることがまあ前提だよね、ということだったと思います。その前提に追いつけずに金勘定が自分でもびっくりするぐらいできなかった。
これは生い立ちからきている部分もあるとも思います。加えて、昔自分がいたコンサルの業界はどんぶり勘定なんですよね。もしPLをきちんと見る会社であれば多少そういう感覚を持てたりするのかなと思うんですけど。それ自体がそんなに難しいものだと思ってなかったし、苦手だということにすら気づいていなかったというところからのスタートでした。2018年にお金が無くなった時にリストラで10人くらい辞めてもらったんですが、その時に強く利益マインドの低さを感じました。当然部下とのコミュニケーションの仕方だったり、信頼関係に問題があるというのもあると思いますが、そのいろんな複合要因をひっくるめて苦手であることを体で実感しました。
自我の変容
編集 改めて、五年前のご自身と現在を見比べて、ご自身の自我が変容した部分を教えてください。
松田 あんまり腹を立てなくなったというのが一番大きいんじゃないかなと思います。イライラしづらくなったし、気が長くなった。もともとせっかちではあるんですけど、うまくいかないことに対してイライラしたりとかすることがだいぶ減った思うんですよね。家族内でも末っ子でしたし、自分から積極的に話しかけたり、飲み会に誘ったりとかは友達にすらしなかったです。最近はそういった受け身に愛されたいという側から、積極的に愛する側に多少は変わってきたという感じはありますね。
今後の展望
編集 ありがとうございます。最後に、松田さんの今後の展望についてお聞かせください。
松田 事業の広がりとしては色んな側面があるんですけど、規模が大きくなることがまず重要と考えています。どんどん規模が大きくなって店舗が増えていって、それが他の国にも増えているっていう形にしたい。昨日ちょうど社員と話した時にも、規模が重要だよな、という話をしていたんです。それを実行していくには当然色んなレベルでボトルネックがあるのですが、オペレーションがまだまだ弱いので、仕組み化が大きな課題です。属人的でないやり方でもっと効率の良いやり方ができるはずのところが、できていないのです。
ホテル業界の常識を変えたいと言いつつ、いまだに普通のホテルのレベルにすら行ってない部分がある。きちんとオペレーションが強い会社で、きちんと規模も取れる会社にしていきたい。様々な国での事業展開をしていきたいというのがコロナの前からのイメージでした。これを65歳までにやりたいと思っていて、今44歳。創業からもう5年ぐらいたっちゃったんですけど、目標まであと20年以上あるので、5年ごとにフォーカスする国を変えながらずっと事業の広げていきたい。そう考えると、あと、何回転かできるんじゃないかなと思っていて、それをやりたいです。
僕自身はずっとタイの本社にいるというよりは、自身が移って次の国の立ち上げっていうのをやっていくっていうのをやりたい。むしろもう今頃それをやってるはずだったのに、思ったようにはならずに遅くなっているというのが現実です。
編集 タイという日本と全く異なる環境での葛藤と、それに対する向き合い、そしてご自身の変容についてお話いただきました。私たちが日常で感じるものとは毛色の違う悩みや課題に挑む松田さんの姿勢は、まさに「社会との共創」そのものだと思います。新型コロナウイルスの影響により、松田さんの事業は大きな変容の途中だと思いますが、これからもReapraとして、松田さんのよりよい自己変容や事業成長を伴走させていただきたいと感じました。 本日はありがとうございました。
------------------------------------------
Reapra Bookはこちらから全文ご覧いただけます。フィードバックフォームもありますので、ぜひご感想、ご意見をいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
