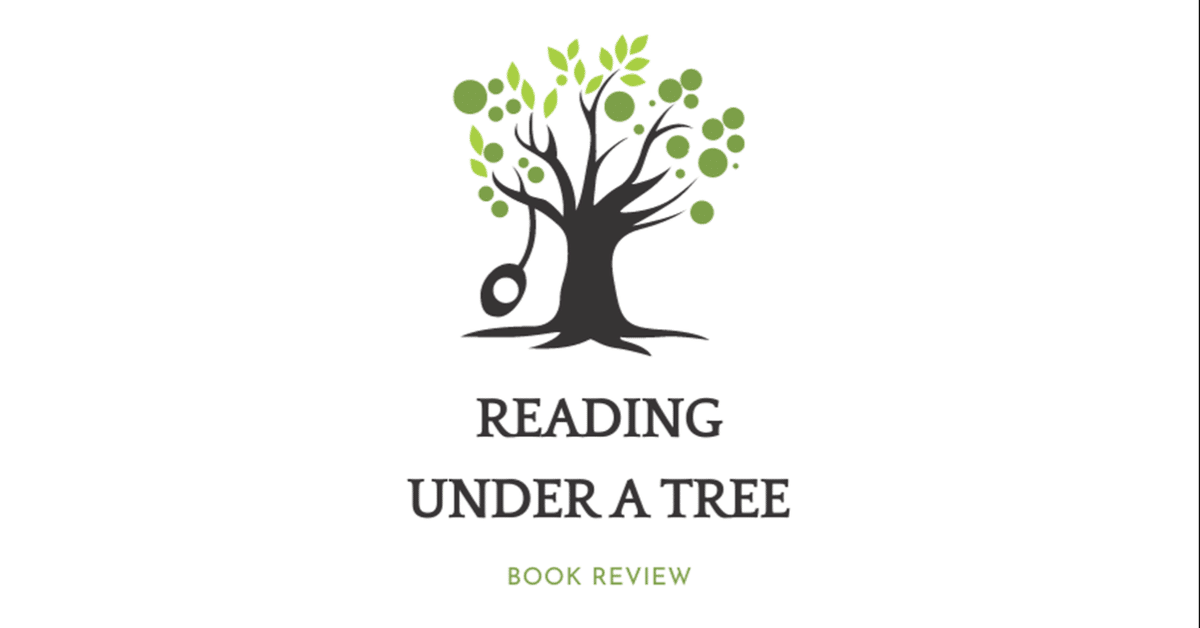
「門」夏目漱石
「門」もやはり初めて読んだ時よりも、今回の方が面白かった。私は常に一読ではきちんと読み込むことができず、それはそれで面白かったとしても、二度三度と読むたびに面白さが積み重なっていくことが多い。
夏目漱石の登場人物というと「高等遊民」が印象的だが、「門」の主人公・宗助は役所勤めである。この宗助が職業だけではなく、普通の、庶民的というか非凡さは感じられない気質を有している点が、私にとってはとても共感できる人物像となっている。解説(新潮文庫)の柄谷行人は「中年の日常をはじめてとらえた作品」と表現しており、そして「門」の新しさはそういうところにある、とも言っている。ただ、私としては夏目漱石の新しさを見出すことができたわけではなく、単に――時間を越えて――リアルさを共有したというところである。
例えば、宗助が参禅して、何も得られずに帰ってくるという点はこのリアルの一つであり、この作品の良さにつながっていると思った。柄谷行人の解説によると、鎌倉への急な参禅はこの作品の欠点とされているという。しかし、私にとっては、この唐突さもリアルに感じるのだ。そして御米に隠して参禅に行ったことも――つらい過去を共有し、緊密な関係にある二人であるにもかかわらず――自分になぞらえてもよくわかるところである。
こうした宗助への同一視的な親密感は、彼と御米との関係にも波及する。「門」は「それから」でもそうであったように、主人公と男女一組の三角関係という設定がある。しかし、私は宗助と御米の関係への好感、そしてふたりと周囲の人たちや社会との関係性に対して、より興味がひかれた。宗助の御米に対する言動には、彼女に対する真の優しさを感じる。時々冷たい反応であるように見える宗助の態度も、「尋常の夫婦に見出し難い親和と飽満と、倦怠とを兼ね具えていた」ことの一面だろうと受け取れる。
「彼等は、日常の必要品を供給する以上の意味に於て、社会の存在をほとんど認めていなかった。彼等に取って絶対に必要なものは御互だけで、その御互だけが、彼等にはまた充分であった」「彼等は親を棄てた。親類を棄てた。友達を棄てた。大きく云えば一般の社会を棄てた。もしくはそれ等から棄てられた」
この辺りは繰り返し読むことが止まらない。そして「我々は、そんな好い事を予期する権利のない人間じゃないか」という宗助の発言を、また読み返してしまうのだ。
彼らが直面した厳しい社会の仕打ちの数々によって、二人の心は折れ、関係が壊れてしまってもおかしくなかった。でも、二人はより一体化する。「道義上切り離す事の出来ない一つの有機体になった」という表現は気持ちに突き刺さる。
だからこそなのか、こんな二人の深い内面世界(もしくは過去)とは対照的に、物語の日常は「希望もないが絶望もない。激しいものは何もない(柄谷行人)」まま終わる。
こういう物語を物足りなく感じる人は多いだろうか。私は、様々な感情が揺さぶられた。新潮文庫のコピーにあった「この感情は何だろう」という状態を体感した作品となった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
