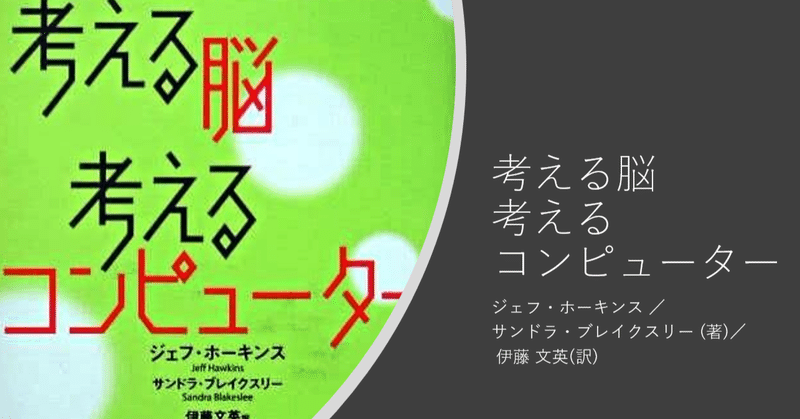
『考える脳 考えるコンピューター』レビュー
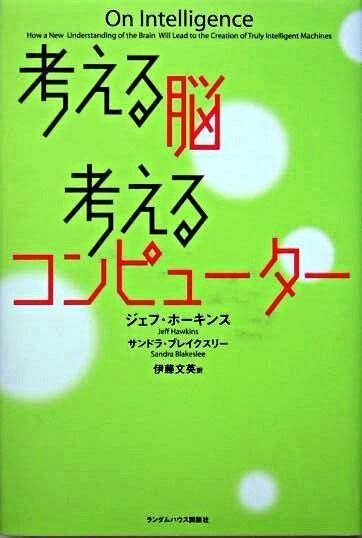
『考える脳 考えるコンピューター』
ジェフ・ホーキンス / サンドラ・ブレイクスリー (著)/ 伊藤 文英(訳)
◇
著者は、スマホが生まれる前、Palm(パームパイロット)というモバイルコンピュータを生み出した、ハンドヘルドコンピュータの父と呼ばれる方です。

下の四角い枠でグラフィティの入力ができました
氏はもともと、知能の仕組みを解明したいと、人間の『脳』がどう働いているかについての研究をしたかったのですが、当時コンピュータサイエンスの世界は生体の脳の研究なぞよりも、どうやって人工知能を造り出すかといった方向を志向していて、大学の研究室には居場所がなく、予算もとれなかったそうです。
で、仕方なく(?)IT企業を立ち上げ、Palmを開発して一発当てて大金持ちになってから、改めて本来の興味の方向だった『脳』と『知能』の研究に本腰を入れた。というなかなかすごい経歴の持ち主さまなのです。
もちろん、IT企業の社長さんやられているときも知能については独自の研究を進められていました。実際、Palmの特徴的な文字入力システム(グラフィティ)は、その知見を活かし、人間には人間の得意な『慣れ』を要求するけれど、コンピュータのほうにはコンピュータの得意な『定型処理』を担当させるという仕組みを採用。
今から見れば低いスペックの当時のハンドヘルドコンピュータでも十分実用的な手書き文字認識入力システムとして一世を風靡したそうです。
(その後、コンピュータの性能があがってスマホが現れてしまうのですが、まあそれはおいといて。)
さてさて、人間が得意な『慣れ』。それこそが実は知能の根源であると本書では語られています。(なお、そのまま『慣れ』とは書かれていません、これはワタシ的なおおざっぱな言い換えなのでご注意w)
外界に接している身体のセンサーから入力刺激は、あれこれ処理された後、最終的に人間の脳の、特に新皮質と呼ばれている薄い膜状の組織(脳の表面を覆っているしわしわのアレ)に伝達されるわけですが、新皮質はごく薄い積層構造になっていて、シナプスのネットワークを通じて情報がその層を上り下りする時、各層でかんたんな学習が行われ、「もうその層が知っている」情報はその時点で情報を処理します。下層で判断できることは下層で、より時間のかかる上層への伝達を行うより先に現場で判断して迅速に行動に移れるというわけ。
そして、何度も繰り返し、ゆっくり上層へ伝達された情報が『慣れ』といえる状態になるわけですね。
この『慣れ』こそが、知能の根源であり、人間の脳のすごいところなのだ。と、本書では繰り返し語られています(おかげで読むという刺激が繰り返されて慣れちゃいましたw)
※なぜその『慣れ』が知性や知能につながっていくのか、は、ぜひ本書をごらんください☆
ただ、デジタルコンピュータが生体の脳の構造を模倣したニューラルネットワークはまだまだ簡易的なものなので、それを使って人工の知性が作られるのは当分先になるだろうとも本書では語られています。この本が書かれたのは2004年なので、ワタクシ的には、もうそろそろ、真に実用的な知性あるコンピュータが生まれても良いころなんじゃないかなーなんておもう今日この頃なのでした。
―――
続編(?)のレビュー書きましたー
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費にさせていただきます!感謝!,,Ծ‸Ծ,,
