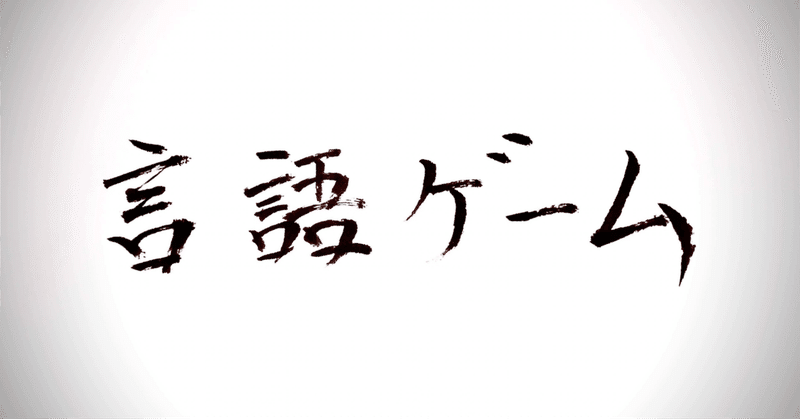
ジェノサイドに至る「言語ゲーム」
こんにちは、らるです。
今日は、ちょっと怖い話をします。
ジェノサイド…というのは
ジェノサイド(英: genocide)は、政治共同体、人種、民族、または宗教集団を意図的に破壊することである。
という意味で、集団殺害とも
訳されるそうです。
実は、これを起こさせるような言葉の使い方がある
というのが、今日の話です。
普通に考えて
「殺せ」と言われたからと言って
人はすぐに人を殺すか…といったら
そうはならないですよね。
ですが、実際にはそういうことが
起きてしまっていたわけです。
ティレルによれば、ルワンダにおけるジェノサイドの言語ゲームは三つの段階を経ていました。
①ことばを与える……「フツ」「ツチ」という呼称(概念)が与えられ、それらが公式に流通し、四十年をかけてそれぞれが自分のボキャブラリーとしてそれを引き受ける。
②言語内での推論/「言い換え」……独立後、多数派「フツ」のあいだで少数派「ツチ」への侮蔑語が浸透。「あいつらはゴキブリだ」「あいつらはヘビだ」など。
③行動を呼びかけ、正当化する……侮蔑語を経由して心理的抵抗を減じられた婉曲表現(「ゴキブリを駆除しよう」など)によって、具体的なジェノサイドが呼びかけられ、実行に移される。
①ことばを与える
②言語内での言い換え
③行動の呼びかけ、正当化
この3ステップで
人は人を殺すようになる…
というんですね。
各段階を詳しく見ていきましょう。①の段階で、たとえば「Xはツチである。だからXを殺せ」と呼びかけられたとして、「わかった、殺そう」とは普通はなりません。ただ、そこに②と③のプロセスが入ってくると結果は異なってきます。
名前がついただけでは
まだダメです。
まず、プロパガンダとして「ツチはゴキブリだ」という言い換えが入ってきます。言い換えの論理は、「ゴキブリは夜に這いずり回る害虫で、次々と繁殖する」→「反政府ゲリラは夜間に暗躍して、どこからでも湧いてくる」→「反政府ゲリラはゴキブリである」というものです。
類似性を並べての言い換えが入ってきます。
ツチ…というのは部族の名前なので
実際は人間なのですが
「夜に暗躍する、どこからでも沸く」という意味で
ゴキブリのようなもの…
だから、ツチ=ゴキブリである
と言い切ってしまうわけです。
本当はイコールでないものがイコールで結ばれました。
一気に怖い感じになってきました。
そこに、「ゴキブリとは駆除すべきものである」というすでに是認された推論(社会通念)が加わります。これらが合成されることで、「ゴキブリを駆除しよう」イコール「ツチを殺そう」という推論が成り立つ。こうなることで、実質的に「殺せ」という呼びかけに応答するハードルが下がるというメカニズムがあるとティレルは言っています。
ゴキブリ⇒殺す は自然なことですよね。
そこで、先ほど成り立ってしまった
ツチ=ゴキブリと合わさって
ツチ⇒殺す が成り立ってしまう
というメカニズムなわけです。
ルワンダでは直接的な「殺せ」という扇動はあまりなかったと言われています。虐殺を呼びかけたラジオ局であるフツ系の「千の丘ラジオ」でも、それは「ゴキブリを駆除しよう」といった一見カジュアルなことばとして呼びかけられている。しかし、それは字義通りのゴキブリの駆除とはけっして受け取られない言語的環境がすでに出来上がっていたなかで呼びかけられていました。だからこそ、その結果は大変悲惨だったわけです。このように、ジェノサイドにおいては「単なる言い換えでした」では済まない惨事につながるということを、この分析は物語っています。
こんな簡単なこと(ことば、概念を定着させるところは
簡単では無いですが…)で
人を殺すハードルが下がるのか…と
驚いてしまう話でした。
安易に蔑称を使うのも危険なものなんだ…という気が
してきますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
