
なぜ、私たちの「道徳」は一致するのか? J.S.ミル『功利主義』第一章 概論より
こんにちは、らるです。
今日はJ.Sミル『功利主義』の
第一章 概論 を紹介していきます。
この本で言いたいことを
まとめて話しているのがこの章になります。
結論としては
「功利主義を否定する道徳論者ですら
功利主義的な考えをしている部分がある」
と言う話になります。
…
冒頭の段落を
簡単に紹介します。
正と不正の判断基準をめぐる論争は、
解決に向けた進展が少しも見られない。
(中略)
最高善に関する問題、
あるいは同じことになるが、
道徳の基礎に関する問題は、
抽象的な思想の中での主要問題と
考えられてきた。
(中略)
思想家も世間一般の人々も、
この問題に関する意見の一致には
近づいていない。
P11
正と不正の問題
つまり、道徳の問題と言うのは
最重要なテーマにも関わらず
大昔からずっと進展しないままである。
ということを訴えています。
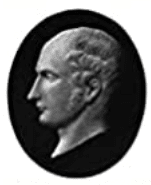
道徳論はいつまで経っても進まないね
どうしてだろうね?
というわけです。
道徳論者の方々の主張はこうです。
道徳能力を使っても
個々の行為に関して何が道徳的かは
直感的にはわからないよ。
結局、個々の事例に対しては
『道徳の原理』から
個別に考えて判断していくしかないよ。
…というわけで、次に気になるのは
『道徳の原理』の前提になるものって何?
という話になるわけですが…
そんなものは「無い」訳です。
だから、いつまで経っても
道徳論は決着がつかないわけですね。
万人が納得する道徳は
いつまで経っても生まれないのです。
ただ、
道徳論者たちがバトルしてる間も
私たちの中で道徳的な感覚って、
ある程度は一致してますよね?
それは、どうしてでしょうか?
ミルはこう答えるわけです。
道徳的信条が曲がりなりに
何らかの確実性や一貫性を獲得しているとすれば、
そうなっているのは、気づかれていない基準が
それとなく影響しているためである。
(中略)
人々の感情は、好意的感情にせよ
嫌悪の感情にせよ、自分たちの幸福に作用していると
思われる物事に大きく影響されている。
そういうわけで、効用の原理、あるいは、
ベンサムがのちになって最大幸福原理と呼ぶように
なったものは、この原理を大いに軽蔑して
その説得力を認めない人々の場合ですら、
自らの道徳理論を作り上げる際に大きな役割を
果たしてきている。
P16
なぜ、基本的原理が欠けているのに
道徳がある程度一貫性を持つのか…の答えは
効用の原理=最大幸福原理…つまり
功利主義が、働いているからである
ということです。

道徳論者の人たちは功利主義を否定するけど
アナタたちの考えの中でも
功利主義は欠かせないものになってるよね?
と、ミルは言っているわけです。
…
まとめ
正と不正の話=道徳の話は
最重要テーマにもかかわらず
昔から全く決着がつかない。
それは「道徳の原理」が
ハッキリしないままだから。
「道徳の原理」がなくとも
概ね一貫した道徳のイメージがあるのは
功利主義が大きな役割を
果たしているから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
