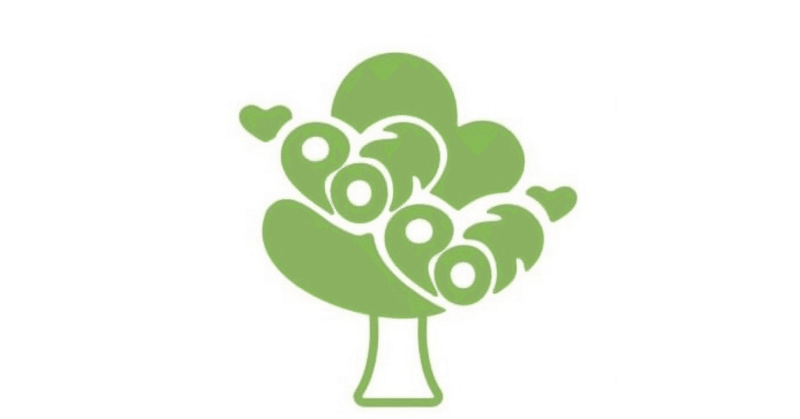
最近思うこと/徒然に備忘録-vol1
はじめに
2020.12.03
この記事は、北海道教育大学岩見沢校の授業に関するお話です。(トピックス:北海道/岩見沢/地域プロジェクト/デザイン/ビジネス×アート)
これは地域プロジェクトという授業で、僕も美術班で携わっています。今年は美術専攻とビジネス専攻合同での授業で、全40名近い学生で4班に分かれて構成されています。

(上写真1)リモート授業の様子

(上写真2)プロジェクトロゴとコンセプト

(上写真3) 中間発表 プレゼンスライド
//岩見沢のソウルフード「てんぐ饅頭」を対象にしたwithコロナにおける美術的アプローチについて
班を同じくするビジネス専攻の子達はなんと1年生!ビジネスの学生達は「政策学概論」というの授業で今回美術の地域プロジェクトⅡと合同で取り組んでいます。1年生達は中々土地勘もない中での授業。その上コロナで多くの1年生は岩見沢に来ることも出来ず、リモート。とかく大変な時勢の中でプロジェクトを進めています。
大学の本懐「美術”文化”」
この大学の本懐である「美術文化専攻では美術文化を地域社会に広め,美術による地域の活性化を促すことができ,表現者としても美術に関する深い造詣…(割愛)」。
「 美術文化の実践と発信 」
ここが他の美術大学、教育・学芸系の美術科と違うところ。ビジネスも同様にポリシーがあるのですが、時たま過去のキャンパスガイドで目にする「学科横断的」という考えが、やっと改組6年越しに日の目を浴びているように感じます。制作者に関わらずですが、人は一人で生きているわけではありません。色々な関わりの中で生きています。その中で、このコロナ禍でのプロジェクト授業はそういった繋がりを強く感じさせます。繋がりが希薄になりつつも、私達は大学生として、その学びを全うせねばなりません。ましてや、大学に入っておきながら、文科省が用意した「学生の生徒化(大学生の高校生化)」に甘んじてるようでは行けない、と最近思つています。
大学で学ぶということ
大学で教育を受けること、学問をしたり制作をするという事、が家畜にされ搾取されない一個の人間になるためにやることだと僕は思います。ゆえに、この大学の本懐である、制作のみならず美術文化の実践や発進をする事、はそういう意味で学府の徒として大事だと思うわけです。
それらを推進してるにも関わらず、文科省は一般の大学に「椅子に座っていること(出席)を学問であるとみなして単位出す基準にしなさい」とか「大学は学生が友達を作る手助けをしなさい」とか言って今があるけれども、その先には経団連が言っているような人間家畜化プログラムがあるわけですよね。👉偏向的かつきつい言い方と戒しつつも。
案の定脱線しましたが、ですから、こういう取り組みは改めて意義があるし、継続的に行えばこそ意味のあるものになると思います。
どうぞ温かい目で見守って頂くと共に、今後とも岩教生へのご理解ご協力を頂ければと思います。
国立大学法人 北海道教育大学岩見沢校 2020年度 美術文化専攻 地域プロジェクトⅡ (美術ビジネス合同) 新コロPONPONプロジ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
