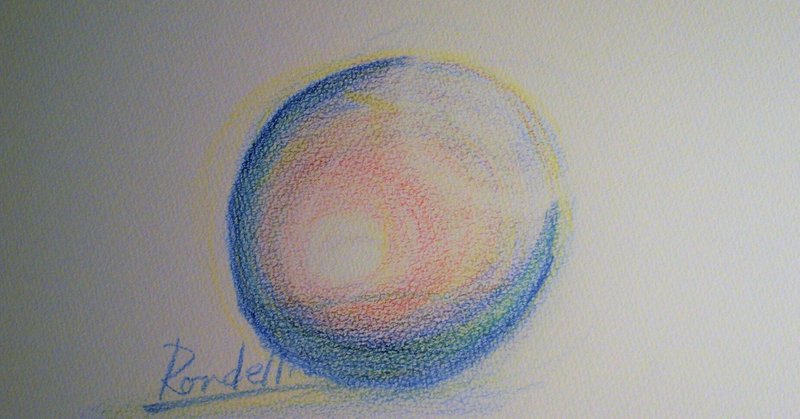
連載小説 星のクラフト 7章 #2
夕食には近くの川で獲れた魚と山で採れた山菜、マッシュルームのスープ、生ハムとポテトの乗ったサラダ、フルーツ、パンが用意されていた。
「豪華ね。専属のシェフが居るのかしら」
私はさっそくマッシュルームのスープを一匙口に入れた。
さきほどの老人が一人で給仕をしてくれる。厨房に誰かが居る気配はなかった。
「全部私が作りました」
独り言を聞いていたのか、老人がそう答え、私達のグラスに水を注ぎ足してくれる。
「シェフなの?」
「もともとはお嬢様のお城で食事を担当させて頂いておりました。それから、地球に派遣されたのです。こういったホテルがいくつか必要になるということで」
ローモンドはあまり話ができない設定になっていることを忘れず、耳をそばだてつつも黙ってサラダを突いている。
「どうりで、なにもかもが一流の料理だわ」
川魚のフリットはカリっと仕上がっていた。掛けてあるトマトのソースの香りも品がいい。
「ところで――」
老人はローモンドをちらりと見た後、私の耳に口を近付けた。「カオリさんは地球外から来た我々のことを知っているのですか?」
私は咳き込みそうになる。そう質問された場合に、どう答えるかを考えていなかった。
「いいえ」
ひとまずそう言う。
「じゃあ、地球に派遣されたとか、そういう話題はマズいのでは?」
まだ耳元でひそひそした声だった。
「大丈夫よ」
動揺を隠して平然と答えた。
「本当に?」
疑いのトーンで言い、さきほどと同じように顎を引き、斜め下から右目を突き刺すように私の顔を伺った。
「ええ」
バレそうな嘘を重ねないことにした。
「それより、どこのホテルでもこんなに美味しい料理が食べられるのかしら」
山菜のソテーを口に放り込む。話題を変えたいのもあるし、実際に聞いてみたいのもある。
「それはもちろん。全員、お嬢様のお城で厨房を担当していた者が仕切っているはずですから」
耳元で囁くのを止めて、背筋を伸ばして得意気に言う。
「それなら、早々と目的地に着くよりも、わざとゆっくり進めて、可能な限りのホテルに泊まって行った方が楽しそうだけど」
「仰る通りです。でも、お嬢様の話では、なるべく早く、例の村に辿り着いて欲しいようでしたよ」
「それね、何か、知らない? どういうことなのか」
村ひとつ分、人間がいなくなっている。建物ひとつが崩壊している。それがどこなのか、どうしてそんなことになったのか、調べるのがミッションだ。そしてそのことが、私の故郷であるお嬢様のいる星で管理していた宇宙の全記憶が書き込まれた装置の破壊事故につながっているかもしれないのだ。
「私の方では何も」
老人は首を横に振った。
「ところで、お名前は?」
老人の名前をまだ聞いていなかった。
「シェフでいいですよ。名前なんて、ございませんから」
深く刻み込まれた表情皺をもっと深くして微笑む。
「それでは、失礼なのではないかしら」
「いいえ、どのホテルでも、シェフがお迎えします。それが我々のミッションですから」
シェフはそう言うと、深々と頭を下げて奥に入って行った。
すっかり夕食を平らげると、部屋に戻ってベッドに寝転がった。
「ローラン、私が来ることは知られていないはずなのに、ちゃんと二人分のシーツやパジャマが用意されてるって変じゃない?」
ローモンドが言う。
「車に乗り込んだから、私の他にもう一人居ることはバレているはずよ。盗聴までされているかどうかはわからないけど、カオリはカオリだと言い張れば、向こうでも調べようがないはず。気にしなくて大丈夫」
もちろん、既にローモンドがローモンドであることがバレている可能性は高い。だからと言って、追及するために遠い星から追いかけても来ないだろう。お嬢様はとにかく、人がいなくなった村について調べたいのだから。
「あ、鳥がいる!」
ローモンドは窓に駆け寄った。
「こんな時間に窓辺に来るなんて珍しいわね」
野鳥は夕方以降は秘密にしている巣に戻るはずだ。
「綺麗な鳥。クリーム色よ」
ローモンドはガラスに鼻をくっつけて、鳥が止まっている窓枠を見た。クリーム色の鳥は逃げもしない。
「このホテルで飼っているのかしら。慣れていそう」
それでも、ローモンドが窓を開けようとすると、鳥は忙しそうに羽根をはばたかせて庭に植えられた樹木の中に消えていった。
つづく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
