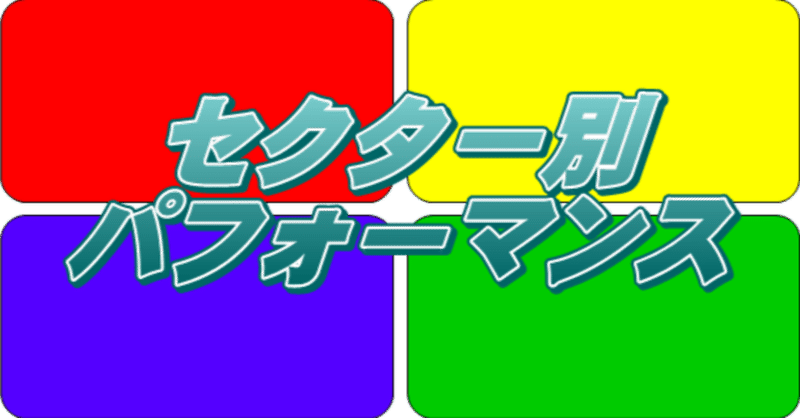
2023年12月末米国株セクター別パフォーマンス結果



2022年の負け組セクター(情報技術セクター、通信サービスセクター、一般消費財セクター)が2023年の勝ち組セクターになりました。
2023年はこの3セクターに大きくウェイトをかけていたら大笑いでしたが、2021年末からのパフォーマンスを見ると景色が違って見えてきます。




2021年末から大勝ちできたのはエネルギーセクターのみ。勝ち組3セクターでは情報技術だけが唯一のプラス。
S&P500にいたってはほぼ変化なし。2021末に一括投資してたらこの2年間は何だったの?ですが、つみたて投資をしてたら平均購入単価が下がっているでしょうから、一括投資よりは多少はパフォーマンスが良かったかもしれません(検証はしてません)。
右肩上がりしか経験してないと強気になりますが、1,2年下落相場を体験するとそれに耐えられるかはかなり難しいのではないかと。長期投資といいながらも1,2年の下落に耐えられないのは「えーっと、長期投資って何だったんですか?」とか「長期って何年くらいを言ってましたか?」なんてことを思ってしまいます。
「底を打ったら突っ込む」という言葉もたまに見られますが、いつ底なのか分かるという超能力を持ち合わせていたら今頃左うちわで暮らせているでしょうし、年ごとのプラスマイナスはあったとしても、底と言っている場所が数年前にはもっと下で買えたら底を待つ意味があるのか謎です。
結局どうするのがいいのかはいまだに分かっていませんが、100mを10秒以内で走れるような人でないとできないようなことを目指すよりは、誰でもできるようなことで資産を増やす方が投資にかける時間も労力も少なくて済み、他のことに時間を割けていいのではないかと思います。1日中パソコンの前に張り付いているのが楽しいのならいいでしょうが、全ての人がそうではないでしょうし、あとは自分が何に重きをおいているか次第なのかなという気がします。
支離滅裂な文章になりましたが、2023年単年だけではなく、毎年パフォーマンスを測定して、過去とつなげてどうだったかまで見た方が「今年はこのセクター(銘柄)だ!」といった、年末に振り返ってどうだったかまでフォローされない情報に振り回されなくて済むように思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
