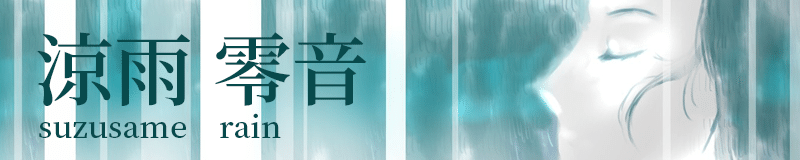食べる を少し、考えた
ホテルの中国料理店で担々麺を食べて、食べるということを考えた。食事について考えたと言ったほうが良いかもしれない。あるいは「うまい」を考えたのかも。
ホテルの中国料理店と言ってもいわゆる高級店ではない。でもスタッフさんは皆さん正装をされているといった感じのお店だ。格式張っているわけではなく子連れで入れるような雰囲気ではあるものの、少し整った空気の漂うお店を想像してほしい。味はさすがに間違いなく、何を食べてもおいしい。
このお店に、毎年足を運ぶ。理由はシンプルで、人間ドックを受けるとここの無料ランチ券をくれるからだ。
今年もここへ出向いたのだけれど、今回は何を思ったのか(思ったのはわたしなのに理由が定かでない)選べるメニューの中から担々麺を選択した。なぜこのようなお店で担々麺なのか。今もって理由はよくわからないが、何かに導かれるようにしてわたしは担々麺を選んだ。
ほどなくしてわたしの前に用意された担々麺は、深めの白い器に入り、均一な色のスープと丁寧に盛られた青梗菜に彩られ、淡い香りを漂わせていた。
なんて上品な料理なんだ。
わたしは目の前のそれが担々麺であることをしばし忘れた。これが。中国料理店の。担々麺。
レンゲを差し、スープを口に運ぶ。
ふわぁっと口腔に広がるごまの香り。どんなガーゼをも素通りするんじゃないかと思えるほど細かく擂られたごまはスープと一体化していてもはや不可分と思われるほどだ。ざらつきさえもほとんど感じられないのに、たしかに存在している。
スープは口当たりが柔らかく、ちりばめられたごまの風味を伴って広がり、複雑な味を残して通り抜けてゆく。わずかに刺激を残す辛み。なんということだ。こんな担々麺が存在していたのか。
箸で麺を取り上げると、ごまと一体化して粘度を増したスープが適度に絡みつく。口へと運ぶわずかな時間で絡んだスープは最適と思われる量を残して落ち、絶妙なバランスで届く。
なんなんだこの担々麺は。
まるっきりインパクトがない。
すばらしい技術で作られていることは疑いない。緻密なレシピと妥協のないし下ごしらえがあってこそ実現される味だ。申し分ない仕事だし、その割に安すぎる。
しかし。担々麺がこのようなものである必要はあるのだろうか。
ここでわたしは考えた。食べるとはいったいなんなのか。
食べる。何を食べるのか。どこで食べるのか。どんなふうに食べるのか。
食べる。誰が食べるのか。何を食べるのか。誰と食べるのか。
いくつもの要素があつまって「食べる」が構成され、いくつもの要素が絡み合って「うまい」が生まれる。
中国料理店で食べた担々麺はうまいのかと言えば、うまくないはずはない。きわめて上品で、見事なバランスを持った逸品であった。
が。わたしは担々麺にそういうものを求めていなかったのだ。そもそもなぜこのような店で担々麺などというものを注文したのか。その理由は今もわからない。わたしは「食べる」について考えるために、わざわざ担々麺を選んだとしか思えないのである。中国料理店の担々麺はこれまで食べたどの担々麺とも違うものだった。おそらくどの担々麺よりも手間がかかっているであろう感じがした。どの担々麺よりも上品であった。
そしてわたしは、担々麺に上品さをまったく求めていなかったということを知った。
実はわたしは担々麺が大好きだ。あちこちで食べている。市内にも好きな店がある。その店で麻婆豆腐を食べた話を以前書いた。
あまりのパンチ力に物語まで生まれてしまうほどの麻婆豆腐であった。ここで垣間見えるように、この店はホテルの中国料理店の対局にあるような店だ。にぎやかな地下街にあり、店内もにぎやかだ。麺の上に麻婆豆腐をかけた料理にライスまでついていたりして、何かが間違っているような気がする。この店には担々麺のメニューがいくつもある。黒いの、赤いの、白いのという三種がメインだ。どれも、一口目で必ずむせるほど辛い。
写真の麻婆豆腐は辛党のわたしもびっくりするほど辛く、思わず小説が生まれたほどである。
この店の担々麺はイカレている。黒い担々麺は黒いごまをすりおろしたものがかかっているのだが、何らかの機械で豪快にぶっ潰してでかいおたまでぶちまけました、というノリでぶっかかっている。スープは消化器官を消火器官にしなければならないほど辛く、一口で脳髄に響く。しかし飲み下した後、麻痺した口腔には複雑な香りが漂う。赤い担々麺はマグマのごとくドロドロで見た目がもう辛い。運ばれてきただけで脳にアラートが響くような見た目だ。白い担々麺は一見とんこつラーメンのようで、なんだこれなら平和に食べ終えられるんじゃないかと思わされるが全部フェイクであり、ものすごい辛さである。辛いものは赤いだろうという我々の先入観に思い切り揺さぶりをかけてくるのだ。
わたしはきわめて上品な中国料理店の担々麺を食べながら、あのピーキーでぶっ飛んだ担々麺を思い出していた。あれとこれとどちらがうまいのか。
わからない。答えは出せそうにない。不思議だ。担々麺と担々麺を比較しているはずなのに、どちらがうまいのか結論を出せないのである。比較できるようなものではない気がする。でも、また食べたいのはどちらか、と聞かれれば簡単だ。もちろんピーキーでぶっ飛んだ担々麺のほうだ。黒いのも赤いのも白いのも、また食べに行きたい。ついでにわけのわからない麻婆豆腐のかかった揚げ麺というあれもまた食べたい。
優れた技術。申し分ないバランス。きわめて高いクオリティ。そういったものが「好き!」や「うまい!」や「もう一度食べたい!」につながるとは限らない。
どんな人が、どんな場所で、どんなふうに食べるものを提供するのか。それによって目指すべき味は異なり、身につけるべき技術も異なる。向上するにはまず進むべき道の先に何を見据えるかということが重要なのであろう。
いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。