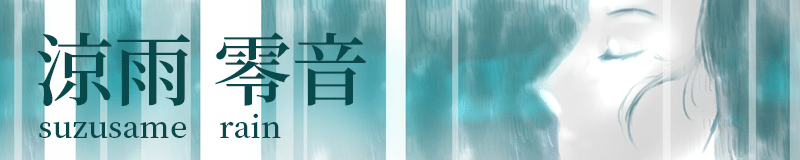[東京90's 下北沢編]まぼろしと生きる町
この町に目抜き通りなんてものはない。駅前から無秩序に伸びる道はどれも車がすれちがえないほどに細く、どの通りも似たような商店街だ。どれも少しずつカーブしていて、土地勘が無いと自分がどの辺を歩いているのかあっという間に見失う。そんな通りの一つに面した半地下の料理屋におれたちはよく集まっていた。まだ一度も注文されたことのないものもあるんじゃないかと思うほど大量の料理が並ぶメニュー。毎回初めてのものを注文した。
思えばおれたちは不思議な顔合わせだった。バンドをやっているおれ、劇団に所属しているカワバタ、アニメーターをやっているハヤシ、映像屋のコイズミ。普通に暮らしていたらなかなか接点がないはずの四人だ。新宿と渋谷からそれぞれ同じぐらい離れていて、中央線文化圏からも程よく離れている。下北沢はおれたちのような、渋谷とも新宿とも中央線とも違うなんらかの「表現者」が集まる不思議な町だった。他のどの町とも色が似ていない、そういう町だった。同じころ同じ町に引き寄せられたおれたちは、出会うべくして出会ったのかもしれない。
ハヤシとおれはこの町のゲームセンターで出会った。対戦型の格闘ゲームでよく技を競って、おれが勝つのとハヤシが勝つのと半々ぐらいだった。ハヤシは長髪に黒縁のめがねをかけていて、70年代のヒッピーみたいな雰囲気だった。あるとき、接戦を制してハヤシが勝ったあと、おれが立ち上がるとハヤシも立ち上がった。そのときおれは自分が何を思ったのかよく覚えていないんだが、ハヤシに声をかけた。
「なあ、このあと時間あるならメシでも食わないか」
ハヤシはわずかにまゆ毛を上げて、ほとんど誰も気づかない程度に驚いてみせてから「いいよ」と言った。
その日も半地下の料理屋へ行って、おれたちは大量のメニューの中のなにかを食いながらしゃべった。ゲームのことじゃなくて、お互いのことをしゃべった。ハヤシはアニメーターをしていると言った。いくつかのタイトルを挙げて、そういうので絵を描いてると言った。おれの知っているタイトルはなかった。アニメといえばドラえもんとかパーマンしか知らない。おれがそう言うと、ハヤシはドラえもんってのはごく限られたアニメーターしか描けないんだと言った。おれはドラえもんならおれでも描けると言ってテーブルにあった紙ナプキンにボールペンで描いて見せた。大昔に絵描き歌で覚えたやつだ。おれがそれを見せるとハヤシは上を向いたり下を向いたり振り返ったりしてるドラえもんをいくつか描いた。
「どんな向きでも誰が見てもドラえもんだとわかる絵を描けなきゃならない。ごく限られた認められたアニメーターだけがドラえもんを描かせてもらえるんだ」
「すっげえうまいなさすがに。この絵でもドラえもんはダメなのか」
「このぐらいじゃ話にならん」
おれはいっぺんにこのハヤシって男を気に入っちまった。
それからしばらく、ハヤシとは連絡先も交換せずに、ゲームセンターで会ったらメシを食う、という交流を続けていた。あるときおれが仕事を見せてほしいと言って、ハヤシの部屋へ遊びに行った。それからはメシを食ったあとハヤシの部屋へ流れて行き、缶チューハイなんかを飲んでそのまま泊り込んだりするようになった。
あるとき、ハヤシの部屋で二人で酒を飲んでいると、隣の部屋から奇妙な声が聞こえてきた。
「めぐる思考の果てに辿り着く境地。ああ。僕は希望を見つけているのか」
おれとハヤシは声を潜めて隣から聞こえてくる言葉を追っていた。
「なんだいありゃ」
「となりに住んでるやつ。よくわからない。ああいう感じでときどき大声で演説する。でもきっちり、9時には黙る」
「面白い野郎だな。会いに行こう」
おれが立ち上がって玄関まで行く間にハヤシは七回ぐらい「やめとけって」と言った。かまわず隣の部屋へ行ってドアを叩いた。演説野郎は即黙ってドアを細く開けた。出てきたのは鮫みたいな目をした尖った顔の男だった。
「ごめんなさい。うるさかったですか?」
「いや問題ない。面白いから会いに来たんだ。今隣で酒飲んでるんだけど来ないか」
おれが誘うと演説野郎はハヤシよりもはるかにわかりやすく大げさに驚いて見せてから、そのままサンダルをつっかけて出てきた。その晩おれたちはハヤシの部屋で朝までくっちゃべった。この演説野郎がカワバタだった。カワバタはアングラな劇団でちょっと前衛的な芝居をやっていると言った。ゼンエーテキってなんだと聞いたら、キテレツってことだと答えた。おれはハヤシと一緒にカワバタの芝居を見に行ったことがある。おれにはさっぱりわからなかったがハヤシは面白かったと言っていた。芝居の中でカワバタがとった奇妙なポーズを、ハヤシはあとで絵に描いて壁に貼った。
おれたちは三人で半地下の料理屋に集まるようになった。あるとき三人でメシを食っていたら少し離れた席で生姜焼き定食を食っていた男が、定食のトレーを持っておれたちのテーブルにやってきた。
「おれも仲間にいれてくれよ」
おれたちは誰も何も答えなかったけれど、そいつのために場所を空けた。いきなり定食のトレーごとやってくるのは普通じゃないし、おれたちに興味を持つ理由もわからない。おかしなやつであることは間違いないと思った。
「あんたら、表現者だろ」
生姜焼きが言った。表現者って言葉がおかしくておれは吹き出した。おれがバンドマンでハヤシがアニメーター、カワバタは俳優だと紹介すると、生姜焼きは映像屋のコイズミだと名乗った。
「映像屋ってなんだ。コマーシャルでも作るのか」
「コマーシャルなんかやらせてもらえるわけないだろ。ビデオだよ、ビデオ」
「ビデオ? ビデオをなにすんだよ」
おれが言うとカワバタが「Vシネか?」と聞いた。
「Vシネっぽいものをやることはあるけどもっとずっとアングラなやつだ。メインはエーブイだよエーブイ」
「AVってアダルトビデオか?」
「そう」
「おまえアダルトビデオ撮ってんの?」
「ちがう。撮ってんのは撮影のクルー。おれは編集だけ。撮影チームが撮ってきた映像を編集すんの」
「じゃあナニか。四六時中エロビデオ見てるわけか」
「それが仕事だからな」
アダルトビデオの編集をやっていると聞いて興味津々なのはおれだけだった。ハヤシはそもそもアダルトビデオなんてものを見そうになかったし、カワバタは前衛アートで全裸の男女が絡まって踊る、みたいなやつをやったりもしていて、普通の性欲みたいなものとは切り離されたところにいる感じだった。なんだかおれは自分だけが俗物のような気がした。
「羨ましいと思うのは浅いんだぞ」とコイズミがおれに言った。「仕事で四六時中見ててみろ。締切が迫ってくる中で編集するんだぞ。映っちゃいけない部分にモザイクかけたりするわけだ。漏れのないようにな。そんでカットをつなぐ。ここはもう0.5秒短い方がいいかな、とか考えながらだぞ。それを朝から晩までやるわけだ。次から次。楽しいと思うか」
「辛そうだな」
「あたりまえだ。続けてるとインポになるんだぞ。おれは本当はもっと観念的な映画を撮りたいんだ。でも仕事はしなきゃ食っていけない。だからやってるし、映像的には学ぶところもあるわけだ。要するにいかに盛り上げるかということだからな」
気付けばコイズミはすっかりおれたちに溶け込んでいて、いつしかおれたちはハヤシの部屋で飲み、カワバタの部屋と二人ずつに分かれて寝ることが増えた。
おれたちはいつかカワバタの芝居でハヤシの描いたアニメーションをコイズミが映像にしておれの音楽とともに上映するという作品をやろうと語らった。半地下の料理屋には永遠に夢を語れるほどのメニューがあった。
でもそのメニューを食いつくすよりも前に町は姿を変え、半地下の料理屋も無くなった。おれたちはいつしか町を離れ、夢は叶うことがないまま四人は散り散りになった。町が形を変えるたび、おれたちの記憶と現実をつなぐものが一つずつ失われていった。おれは表現者であることをやめ、今は妻子とともに郊外の住宅地に暮らしている。もう、あの仲間たちとの時間が本当に存在していたのかさえ、はっきりしない。ハヤシたちのアパートが無くなったとき、おれたちがあの場所にいた証も無くなった。おれたちは蜃気楼のような町に生きた蜃気楼のようなものだったのかもしれない。
いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。