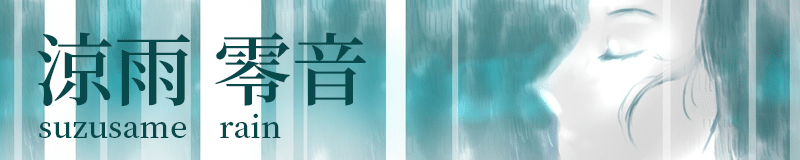なんども読みたくなるものを書きたい
「小説は一回読んだらいらないじゃないですか」
少し前のことになる。知人と、たしか電子書籍かなにかについて話していたときに、そう、言われた。この言葉は想像を超えてわたしを驚かせた。
「えっ?」
驚きすぎて声も出なかったのだけれど、相手は別にわたしを驚かせようとしたわけではなくて、わたしが驚いていることにすら気づかず、そのまま話は進んでいった。わたしはこの後なにを話したか覚えていない。そのぐらいびっくりした。
話の流れとしては、小説は一回読んだら終わりだから、別に買う必要が無い、というようなことであった。図書館で借りたらいい、というような。
わたしはこれを聞いてとてもびっくりしたのだけれど、同時に、どこかでもうだいぶ前から気づいていたような気もした。小説に限らず、なんらかの文章を読むという行為は長い年月をかけて少しずつ変容していて、何十年も前に固定されたわたしの読み方とは大きく異なるのではないかということ。そうであろうと思っていたのになぜ驚いたのか。それを考えてみて、いくつかの理由が思い当たった。
その言葉を放った人が、年齢的にそんなに大きく離れていない人であったこと
その言葉を放った人に対し、比較的本を読む人であるという印象を持っていたこと
そうなのだ。そういう読まれ方の変化には気づいていたのだけれど、おそらく自分の中のどこかで、対岸の火事ではないけれど、自分からは遠いところで起きている変化という印象を持っていたのだろう。それは知っていることではあったけれど、わかってはいなかった、ということではないだろうか。
もしかして、この状況は思ったよりも近くまで迫ってきているのではないか、という驚きが、きっとあったのだ。
それはもう、こういう人が増えれば、小説は売れなくなるに決まっている。一回読んで終わり、と考えると、今の本の値段は高い。文庫本でも千円を超えるものが多くなり、気軽には買いづらくなった。
わたしが中高生のころ、文庫は一冊500円前後だった。小遣いで買える値段だった。わたしは毎月最低でも一冊は文庫を買っていた。そんな風にして中学生で宇宙大作戦を全部、高校生でアガサ・クリスティを全部読んだ。
でも今の文庫はそのころの二倍ぐらいの値段になっている。一冊を何度も読むわたしでも欲しいものをかたっぱしからは買えないのだから、一度しか読まない人が買い渋るのは当然だと思った。特に中高生は自由になる少ないお金の中からスマホなどにもお金をかけていると考えると、それはもう本は売れないはずだ。
そうか。一回しか読まないのか。
小説は一回読めば終わりでいい、というような人に、「これは買ってでもほしい」と思わせるようなものを書くことができるだろうか。それはつまり、ストーリーがオチまで全部わかってしまったネタバレ状態であっても読みたいと思うもの、ということであろう。そういうものが書けるだろうか。
書架を眺めてみると、もっとも手に取りやすい場所に、わたしが「結末がわかっていても何度でも読みたいと思う作品」が並んでいる。背表紙を追うだけで好きな描写、好きな表現、好きな言葉が思い浮かぶ。すぐにでもページを開きたくなる。そのわずかなフレーズのために、作品全体をもう一度読みたいと思う。世界のどこかにいる誰かに、そんなことを思わせるようなものを書くことができるだろうか。
わたしはそういうものを書けるようになりたい。
いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。