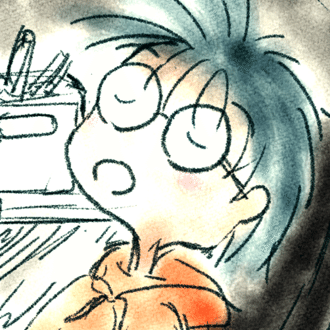[短編小説]路地裏の珈琲店
入り口のドアベルがキンキンと澄んだ音を奏で、来客を告げる。入ってきたのは細身で背の高い人だった。黒のスキニーパンツに黒のレザージャケット。レンズに薄く色の入った細身の眼鏡をかけ、左肩に肩紐をかけて小脇に抱えるように楽器ケースを持っている。絵に描いたようなバンドマンのスタイルだ。30年ほど前の。
ここはどことも知れない街の裏路地にある珈琲店、珈琲工房サカイ。店主の名前がサカイなのだろうけれど、聞いてみたことはない。聞いてもきっと微笑むだけだろう。
入ってきた客は店主に軽く会釈するとカウンターの隅に楽器を立て掛けた。
「マンデリンを」
品書きも見ずに注文すると、レザージャケットを脱いで楽器の上にかぶせてからカウンターの椅子に腰を下ろした。ジャケットの下からは黒地にプリズムの絵の書かれたTシャツを着ていた。ピンク・フロイドの「狂気」だったか。見覚えのあるアートワークだ。
その「狂気」が露になったとき、店内に低く流れていたのは「マイ・ロマンス」だった。ビル・エヴァンスではなくレッド・ガーランドの方の。ロマンスで包み込まれて狂気もおとなしくしているようだ。
熟年の店主は声もなく頷き、珈琲豆を取り出して挽き始める。
「よく出入りしてたハコがね」
そういって客は私のほうを見た。
「なくなっちゃったんですよ」
ぽつりぽつりと言葉をつなぎ、わずかに笑みを浮かべた。ファッションは古臭いけれど年は若いのかもしれない。
「ほら、そこの坂道。その坂を登っていくと右の方へカーブしているでしょう。そのちょうどカーブの真ん中ぐらいの右手にね、あったんですよ。マンションみたいな外観の建物でね、そこの地下に」
若者たちで賑わう目抜き通りから横へ逸れるとその坂道がある。坂道は別の世界へつながっているみたいで、一歩進むたびに街の喧騒が遠ざかり、それほど距離があるわけでもないのに、登りきると静かな住宅街だった。住宅街の中には著名人も来るような美容室などが点在していて、明らかにメインストリートとは違う世界の住人が暮らしている。
そのちょうど境界のあたりに、ライブハウスがある。ここにだけ、目抜き通りとも住宅街とも異なる異質な人種が集まっていた。
ハイソな住宅街を場違いな四輪駆動車が抜けてくる。搬入口の前に停まると時間の流れから途中下車したみたいな連中が降りてくる。
「おはようございます」
午後でも夜でも関係なく「おはようございます」と挨拶する世界の住人。その日初めて顔を合わせたら時刻がどうであれおはようなのだ。今からおまえとの時間が始まる。そういう意味だ。だいたいが、おはよう、こんにちは、こんばんは、と挨拶を配分すれば、どうしたってこんばんはの領域が多い。夕方以降翌朝まで全部こんばんはだからだ。バンドマンというのはだいたい午後から朝まで起きて昼間は寝ている人種だから、さっき起きて最初に会った人におはようと言っているに過ぎない。
だいぶガタの来ている四輪駆動車から降ろされた機材を、そんな連中が運び込む。坂の途中から建物の地下へ、急な階段を降りていく。一段降りるとわずかに気温が下がるように感じる。目覚めたばかりの搬入口は、数時間後にあふれるはずの熱気を受け止める準備をするように静かに冷えている。
「ヒ。ヒ。ヘイ。ワ。ワン。チ。チェ。ツ。ツェ。チー。チェ。チェック。ワン。ツー。ツ。ツゥー」
火を入れた音響システムでサウンドチェックが始まる。客席に届ける出音とステージ上に戻す返しをチェックする。いくつかの子音で特定の周波数の出方を確認し、イコライザーでバランスを調整する。無人のハコの中で、メンバーと客が入った状態を想像しながら音を作る。
「おはようございます。今日もよろしくおねがいします」
出演するメンバーは自ら機材を搬入し、スタッフに挨拶する。フロントも裏方もない。ライブハウスと出演バンドの関係は対等で、共にこの小さな世界を作り、守っている。
「どうっすか、今日は」
若い店長が声をかけてくる。ちょっとまえにこの若者が店長になった。出演する連中とほとんど同世代の店長だ。
「100ぐらいっすかね」
「おお。頑張ったね」
前売りのチケット。1600円とかそのあたりの金額。それを100枚。16万円。それだけ売れればまずまずだ。だいたい50枚ぐらいはライブハウスの使用料。残りは按分でバンド側に戻される。100枚売ったぐらいでは練習スタジオの代金分も元は取れない。それでも素人のバンドとしては上出来だった。
ステージでバンドのサウンドチェックをする。ドラムセットの一つ一つを確認する。ある程度まとまるとドラム全体で調整する。ドラムの音はマイクで拾うけれど、このぐらい小さいハコだと生の音も客席に届く。ライブハウスの音作りはステージから直接客席に届く音と、PAシステムを通して届けられる音のブレンドだ。バンドメンバーもこのことを頭に入れて音作りをする必要がある。なるべくPAに任せたほうが良い結果になりやすい。そういう意味でもバンドとライブハウスは二人三脚だった。
長い年月をかけて紫煙を吸い続けた楽屋の壁は、誰も喫煙しなくても煙草の匂いがする。床の白いタイルはあちこち割れてはがれ、七割方コンクリートの下地が見えている。足元がふらつく不安定なテーブルは薄っぺらい安物で、椅子はクッションのへたりきった丸椅子だ。多くのバンドマンたちの栄枯盛衰を見守ってきたであろうこの空間を、ヘタった蛍光灯の冷たい灯りが静かに撫でていた。
「思えばステージの本番よりもね」
客は掛け合いのフレーズを待つみたいに言葉を区切りながら話す。
「あの本番前の楽屋が好きだったんですよ」
私には縁遠い世界の話だったけれど、まるでそこに居合わせていたみたいに懐かしさを感じた。
「この腐りきった椅子は買い換えないのかよとかね」
客はマンデリンを舐めながら続ける。
「言ったもんです。すごく安いんだからってね。そしたらね。店長が言うんです」
そう言って客は私の方を向いた。
「新しいの入れてもすぐヘタるんだって。ときどき換えてるんですよこれでも、って」
客はカップの中を見下ろして黙った。私は次の言葉が届くまで待った。
「あそこはね。そういう場所なんですよ。あの楽屋、いや、あのハコ全体に、別の時間が流れてたんです。そこにあるものも、人も、みんなあの時間を生きていた。初めて出演するバンドも初々しいのは一曲目だけ。二曲目からはもうあの時間の中です。あそこはそういう場所だった」
客はマンデリンの残りを飲み干してカップをソーサーに置くと、立ち上がってジャケットのポケットから札を一枚取り出してカウンターに置いた。それを見て店主が黙礼する。
「ごちそうさま」
客は小さくそう言ってジャケットを羽織った。「狂気」が隠れた。店内に流れているのはオスカー・ピーターソンになっている。
立て掛けた楽器を肩に担いで客は言った。
「ね。そういう特別な時間の流れてるハコから出されちゃうと人はどうなると思います?」
私は答えなかった。
「竜宮から帰ってきた浦島太郎になるんです。この店は玉手箱なんだ。あのドアを出たらもう…。ね」
そう言って客は店から出て行った。
キンキンと、ドアベルが澄んだ音を響かせた。
いいなと思ったら応援しよう!