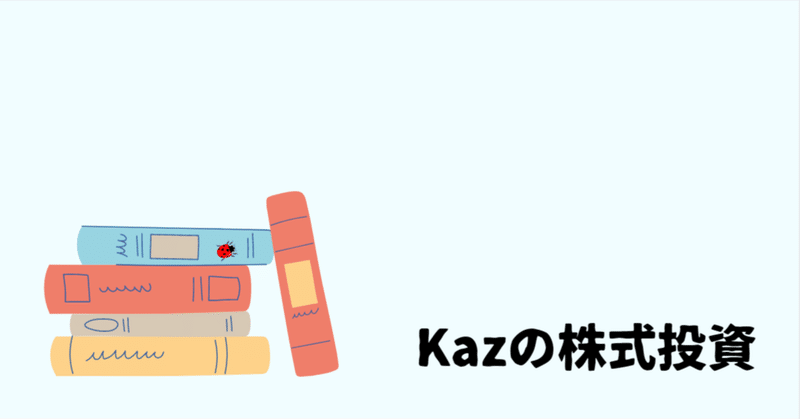
株式投資に簿記2級は役立つのか?実際に取得してみた。
世の中のほとんどの人は会計学のバックグラウンドを持っていないため、株式投資を始める際に簿記の勉強をした方がいいのかと悩んだ人も多いだろう。本稿ではそのような人たちに向け、労力に見合う対価が得られるかに焦点を当てて解説したい。
取得期間、労力
取り組んだ期間は8ヵ月であった。私はかなりマイペースに勉強を行ったので、このブログのために正確な勉強時間を測っておけば良かったと後悔している。内訳は日におよそ1-2時間だが、週に2-3日は全く手を付けなかったので合計250時間前後である。
ちなみに簿記3級の範囲の勉強は含まれていない。3級の試験を飛ばして2級を受けたため、3級範囲はテキストを数周読み込んだだけで終えている。勉強期間は1.5ヵ月、合計3-40時間くらいだろうか。
取得のコツ
なるべく楽して取得したい場合は、短期決戦で臨むのが間違いない。簿記2級は数年前に改訂されて以来、難易度が遥かに上がり範囲も広くなっている。私のようにマイペースにやっていると以前勉強したはずのことをすっかり忘れてしまい、復習に多くの時間を取られてしまう。
試験料金は5,200円と外国の試験に比べれば決して高額ではない上、かつネット試験(テストセンターのコンピュータを使う)は試験を受ける日程を自由に決められるため勉強計画は融通が利く。更にネット試験は過去の合格率が紙の試験よりも高かったため、受験の際はネット試験をお勧めする。
また、試験内容は論点の本質的な理解よりも問題を解くスピードと正確性を要求されていると感じた。制限時間の90分は、初めて演習問題に取り組んだ際にはまず間違いなく時間が足りなくなるほど問題量が多い。そのため、ひたすら演習問題を制限時間以内に解く練習が最も効果的である。試験はある程度パターン化されているため、機械的に仕訳問題を解けるようにして、残り時間に見直しの時間を作ると良い。試験では電卓の計算が必要なほど扱う数字の桁数が多く、計算ミスや数字の打ち間違いが頻繁に起こるためだ。どこかで間違えるとなし崩し的に失点してしまう場合も多い。
取得して良かったこと
最も重要だと感じているのは、財務諸表を読む精度が上がったことだ。例えば、商品を販売した等の日々の仕訳作業から財務諸表がどのように作成されるのかという流れが明確になったことで損益計算書や貸借対照表等それぞれの繋がりを実感できるようになった。更に財務諸表を眺めていて繰延税金資産や貸倒引当金、法人税等調整額など意味がわからなかった項目も理解できるようになった。
これまで我流で財務諸表を見てきて、そもそも複式簿記の概念すら知らない状態で勉強を始めた時に比べると、ようやく会計の入口に立つことができたと感じている。
ただし、私がそもそもの財務諸表の見方を覚えたのは初学者向けにそれのみを説明している本からである。株式投資を志す人には、簿記の前にこちらから入る方が役に立つし面白いだろうと思うので紹介しておく。
一方で、私が勉強している最中に疑問を持っていたことも確かである。ひたすらに仕訳の練習問題を解いたり、原価計算の種類を覚えることが直接株式投資に役立つとは思えなかったのである。実際に試験範囲のいくらかは全く無意味となるだろう。ただ、学校での勉強も同じで無意味だと思って勉強していたことの総体が重要であったりする。
簿記2級も勉強し終えてようやく全体の繋がりが見えてくるという点で、株式投資を理由に勉強を始めた人はモチベーションの維持も大変だろうが、この記事を見てやる気になってくれれば喜ばしい限りである。
私が勉強を始める前にネットで情報収集をしていた限りでは、株式投資のために簿記2級の勉強はやった方がいいけれどもやらなくてもいいという何とも曖昧な記事ばかりだった。私の結論は、本気で株式投資に向かい合うなら会計学の勉強は避けては通れないということだ。かのウォーレンバフェットも会計の勉強を勧めているので是非簿記に取り組んでほしいと思う。そのため、勉強を始めようと思うのなら3級で終えるのではなく2級も推奨する。2級は超高難易度試験ではない。諦めなければ必ず誰もが合格できる試験である。私は少なくとも1級レベルまで勉強は続けていくつもりである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
