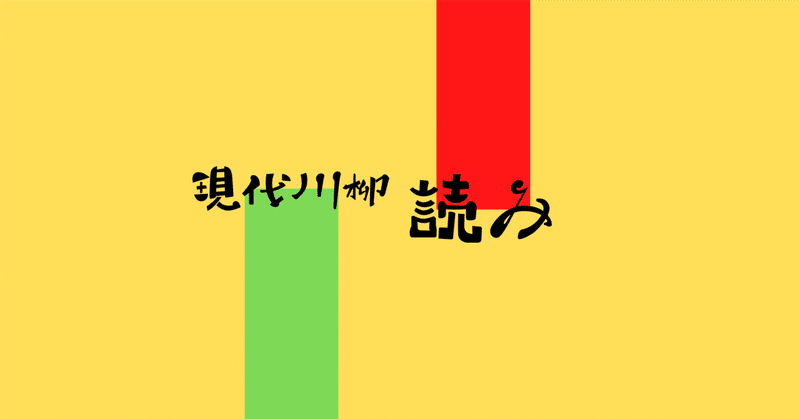
これも「読み」ですか? 15
おひさしぶりです現代川柳に「読み」をほどこすことで生計を立てています今田です。息つぎ無しの嘘からはじまりました。さて、今回は、先ごろ発表された海馬万句合第三回の入選句および軸吟(選者による句)に読みをほどこしてみます。
よろしくお願いしま~す。
選句結果は以下記事から引用しました。
① 題「くりかえし」
余熱から始める民の物語
/西脇祥貴
■題と句を交互に「くりかえし」眺めるうち、国や文化の栄枯盛衰があらわれる。終わりは始まりで始まりは終わり。エネルギー保存則は歴史や物語でも維持される。
吐きつ食いつポリエチレンの山河あり
/西脇祥貴
■吐きつ食いつ、の語順にくりかえし性をかんじた。食いつ吐きつ、では動きに区切りがつき、完結したムードが出る。そして、どこにも書かれていないが国が破れているようにかんじる不思議。
好きというきみが透明になるまで
/なかやまなな
■くりかえしの長い時が過ぎ、対象は透明になって消えたが、その空間に「好き」という概念だけが漂っている。時間と愛の組み合わせはうなぎと山椒くらい相性がいい。
スプーンを潰すスプーンを潰すスプーン
/栫伸太郎
■このような形の投稿は多かったのではと邪推するがはたして。さておき、スプーンがいくつも重ねられている光景だろうか。永遠に続く光景から575の型で抜いたようでもある。
右手からふだんづかいの花吹雪
/スズキ皐月
■マジシャンはつねに長そでを着ていて、ふだんからそこにネタを仕込んでいる。この句の花吹雪もつまりそういうことで、それなりに特別なものだが、とはいえふだんづかいレベルなのだ。
劇仕立てにした永久機関の輪
/成瀬悠
■完全なそれが存在しない以上、すべての永久機関はすくなからず創作を交えた劇仕立てで語られる。それにしても「輪」はいい。1文字1音で栄養(意味性)が豊富。短詩型にとってべんり。
馬小屋でゾエトロープが閉じている
/西沢葉火
■たしかにゾエトロープは今回の題である「くりかえし」そのものだ。馬の躍動感を描きがちなそれが実馬(じつば。実際の馬)たちの前に置かれている。くりかえしは現実を侵食するだろう。
我々がどこから来ても邪魔な犬
/スズキ皐月
■助詞「が」の使いようで意味を華麗に操っている。句の端にちょこんと座った犬は、スーパーやコンビニの出入口付近につながれて飼い主を待っている犬だ。
宇宙図書館に肉場と馬糞海胆
/川合大祐
■人間の存在感ゼロでいい。たとえるならダリのあの絵のような。ところで博士、霜降りの牛肉にウニを載せたお寿司っておぞましいですよね。映画『セブン』の最初の被害者は飽食でしたよね。
フィヨルドに針を落として手毬唄
/西沢葉火
■ある地形にレコードの針を落とすと、手毬唄が鳴った。このとき手毬唄は「音で聴く地図」である。ちなみに、リアス式海岸とフィヨルドはちがうものなんじゃ。えっ、そうなの博士。
ドンタコスじゃない「ったら」がスゴイんだ
/雪上牡丹餅
■くりかえしといえばCM(ソング)だが、それはそれとして、このCMのプランナーである佐藤雅彦で言えば、同じくスナック菓子「ジャガッツ」のCMのくりかえしの工夫がじつはスゴイんだ。
骨の模様になるまで言った
/雨月茄子春
■言葉を組み合わせるとそれなりに意味が出てしまうものだが、この句の場合、特定の意味に収斂しないのがいい。むろんなにもわからないが、わからないおまえが悪い、と罵られるのも愉楽。
また君の乳歯で橋が建っている
/城崎ララ
■はたして橋は「建つ」ものだろうか、という疑問に思考のリソースを奪われ、乳歯をほったらかしにしてしまった。まずい。きっとそのうちぐらぐらしてくるぞ。
<軸吟>
奇々怪々多士済々のマネキン忌
■々々々、とくりかえし性の畑を開墾したところに、人間の型のくりかえしであるマネキンがどーんとくる。マネキンの死を悼むのもマネキンだろう。くりかえしはくりかえしくりかえすのだ。
② 題「Straight, No Chaser (Live [Tokyo]) ―Thelonious Monk」
https://www.youtube.com/watch?v=S9QQbqupGe0&ab_channel=TheloniousMonk-Topic
そいつ、そいつがあの粗いアッシリア
/西脇祥貴
■三連符のようになめらかに鳴る三文字。たしかにモンクはかの帝国のごとき残虐性をもってピアノを蹂躙したとさえ言える。ほんとに?
ドライスキンに徹するべきだ
/朧
■円陣だ。いいかみんな、しっとりしちゃいけない。かさかさするぞ。過去を振り返るな。未来を臨むな。ドライスキンに徹するべきだ。
浮いたまま歩いて夢をおびきだす
/森砂季
■鮎の友釣りのように、自分自身が夢遊病患者になりきってべつの夢遊病患者を面白半分におびきだしているうち、気づけばその国の半数が夢遊病患者になってしまっていた。zzz…....…
水族館 歴史はいつもかわいそう
/スズキ皐月
■読んだ刹那、読む者の脳裏には合わせ鏡のごとく「◯◯館 歴史はいつもかわいそう」の句が無数に発生しだす。体育館、十角館、水車館、迷路館、時計館、黒猫館、暗黒館、立命館……
隕石の降らない大半の日々よ
/太代祐一
■直接なにも動かすことなく、しかし景色をがらっと変えるアプローチ。「見方を変える」とも、いわゆる「ただごと句」ともちがう。ただまあ、要するに「everyday」ではある。
A little deaf; 砲弾の聞き手は僕だ
/西脇祥貴
■英語で書かれたことじたいが、TOEIC2点のわたしにとって、なにかしら deaf 性をかんじるものだった。合衆国大統領がイスラエル支援の声明を出した数日後に記す。
天皇の街にひとつの零を弾く
/川合大祐
■そこは東京か。あるいは京都か。とまれ、弾かれたのは零である。それはジョン・ケージが「弾いた」無ともちがうなにかだろう。
ドラムドラムあなたのへその見せどころ
/水城鉄茶
■(披講を聴いて)なるほど〜、たしかにドラムではなく drum と1音節で発音したほうが打楽器っぽいし、(ビールを10杯飲んで)あと、へそに向けて収斂していくイメージも得られておもろ〜
瞼はふたつでもただ壊れてゆく
/藤井皐
■ふたつでも、とつなげて読むか、あるいは、ふたつ/でも、と読むか。意味はさほど変わらないかもしれないが、なんというか、迫力が変わるように思った。つまり、レンチキュラー句?
固唾もじじつ船酔いだとさ
/ササキリユウイチ
■人は酔う。酒に船に自分に。そして人は嘔吐する。その直前に口中に湧くあのいやな液体。あれが固唾である。そうだろう。
文字盤に耳で飛ぶ象死んでいる
/川合大祐
■ダンボをあしらった時計は何時を指して止まっているのだろう。いや、ダンボではない可能性もあるのか。耳で飛ぶ象、いっぱいいるし。「ピーナッツを機関銃みたいに撃つ象」ならダンボだ。
<軸吟>
チンピラのピアノが唄った遠いいくさ
■海外日本問わず、往年のジャズにはワルでカッコいいムードがある。ここで『嵐を呼ぶ男』を例に出すのはなんだかちがう気がするが、三度作り直されたその映画の三本目の設定が「ロックバンド」だったと知ったときは驚いた(さっき)。
③ 題「小町が行くぼくは一本の泡立つナイフ/石田柊馬」
ぼくたちはひとり切り裂きジャックたち
/今田健太郎
■ぼくたち、ひとり、ジャックたち。つまり、複数、単数、複数、というピストン運動である。この様子だとつぎは単数が来るぞ。
日本語のような日傘に目が泳ぐ
/ササキリユウイチ
■言葉遊びが不意に深めの意味性を獲得したような。そんなマザーグース感。たしかに「韻や文字で遊ぶ」のと「意味で遊ぶ」のは、けっきょく同じはたらきなのかもしれない。たしかに?
はしるからだ(背中に浮いている初稿)
/西脇祥貴
■なにを言ってるんだ、と思ったが初稿ならば仕方がない。2稿3稿と重ねるうち、だんだん地に足がついてくるのだろう。そしてその足は地面を蹴り、からだははしりだす。
I, Robot. My handcuffs ran away and got eaten by that dog.
/栫伸太郎
■独特な手ざわり。なつかしいような新鮮なような。または冷たいようなあたたかいような。もしくは英語のような日本語のような。あるいは英語のような英語のような。
モリブデン鋼の付け文 小町より
/石川聡
■語彙の選択も意味も構成も音数も、すべてがばっちりな575。刃物がごとき切れ味。しかしこれが題への呼応として生まれたことを思えば、たんに独立して存在する575ではないのだ。
舌下にとろけるHuman Behavior
/太代祐一
■すぱっと切れてはいるがなにで切ったのかがわからない、みたいな味わい。個人的には、食レポという行為ににじむ人間の業を思った。
カリメロの巣に現代詩文庫なしわれらの詩刑
/川合大祐
■題の句にある「定型を押さえながらも過剰に先へ伸びている」かんじにもっともうまく呼応していると思った。音数も意味も。
粘りつく夜霧を吐いておやすみなさい
/成瀬悠
■一読して、夜霧が「おやすみなさい」を呼びつけたような印象があったのが気になった。いいことなのか悪いことなのかはわからない。たぶんどっちでもない。
ソープカッティング(もいっかい言って)ソープカッティング
/城崎ララ
■当然せっけんは泡立つ。それをカットするのはナイフだろうか。単語の聴き慣れなさゆえ「もいっかい」言わざるえなかったものの、題への呼応の真摯ぶりはダントツ。
チェックメイトはニトロの小瓶
/西沢葉火
■ジャンル映画的な様式美、クリシェの美学のようなものをかんじた。こちらもまた題への呼応っぷりが見事だが、そうかんじるのは、つまり「石田柊馬っぽい句」ということなのだろうか。
石田さん、おれは一顆のライムです
/水城鉄茶
■そしてはっきり作者名を告げ、「これは呼応である」と宣言する句。句のなかに柑橘系をひとつ置くといい香りがしていい、と本気で思う。
はるか茜にうだるマチズモ
/高澤聡美
■題の句にあるマチズモを、題の句にあるナイフでもってひとくちサイズにすぱすぱとカットしなおしたような句。あえて難を言えば、そのようなある種の「要約性」が出すぎている気も。
<軸吟>
ジャズのいいとこは芋も剥けるとこ
■15年前に作った格言を披露するときがついに来た。「おもしろい支離滅裂を作るのとおもしろい理路整然を作るのは、同じくらい難しい」その難しさを理解している句だと思った。
④ 題「界」(川合大祐[第2回海馬万句合大賞受賞者]選)」
秋の単騎待ち@ふぢはらのかまたり界
/西脇祥貴
■ひとまず、単騎待ち、を調べたらそこにある説明に使われている単語がひとつもわからなくて詰んだ。あ、積んだわけじゃなくて。いやあの、だから、牌を積んだわけじゃなくて。
御託はJ・Bの金歯を引っこ抜いてから言え
/湊圭伍
■有無を言わせぬ迫力はむろん「御託」や「引っこ抜く」の力もあるが、やはりファンキー・プレジデントのそれをいただいてもいるだろう。句の中の力学みたいなものを考えた。
通り魔に名前をつけられちゃったから
/おかもとかも
■わたしのような名探偵コナンの原作をいちから読んでみるチャレンジ実行中の者には、ライバル警察官同士が、通り魔の通り名を我先につけようと争っているようにかんじられる句というか。
掛け声が似ている川に出てみたり
/城崎ララ
■題の「界」をほとんど「世界」の意味で捉えていたので、河川そばで繁栄したいくつかの文明のことが思い浮かんだ。
脱いできた毛皮とここですれ違う
/城崎ララ
■かつてのペットと古着屋で再会するシーンではありきたりだから、もっと抽象的な意味の毛皮と取りたい。ただ、それと同時にこの秋出没しまくっているクマ(の毛皮)の意味でも取りたい。
みてきてよ かわいい国のお湯加減
/高澤聡美
■難、というほどのことではないが、ここは「加減」より「かげん」のほうが、こう、句の鮮度が長持ちするような気がした。むろん長持ちさせないという選択肢もある。
泣かないでバブルスくんをつかまえて
/まつりぺきん
■チンパンジーは賢い。たぶんつかまえられないだろう。仮につかまえられたとして、それはきっとチンパンジーが「つかまえさせた」のだ。かれらの手のひらの上である。指が長い。
視界一面さだまさし
/小沢史
■さだまさしのコンサートの場内スタッフのアルバイトをしたことがある。あの歌声でわたしは眠った。業務中である。しかし「北の国から」である。睡魔はさだまさしの顔をしているのだ。
どらやきのかいわいなかだししちゅえいしょん
/藤井皐
■586、とふくらんだリズムがあんこをなかに含んだどらやきのふくらみにかんじられた。そこにひらがな特有のふくらみや、妊婦のお腹のふくらみがふくまれないわけがない。
ニラ あらゆる交点にいてますわ
/西脇祥貴
■おおげさにいえば、ニラを食べることはニラを歯間に詰めることだ。歯とニラの交点には「詰まり」がある。や、あるんですわ。西のイントネーションを耳にしたとき、遠い文化の交点イスタンブールの街並みを思い出していた。
<軸吟>
ごくせんの墓を月下に磨きだす
■世代を風靡したドラマ(原作は漫画)の墓を月明かりのもとで磨きだす。月光は陽光の反射だとか。アクションはリアクションを呼び、題は句を呼ぶ。なるほどたしかに、栄枯盛衰や温故知新など過去と現在と未来が「くりかえし」訪れるイメージが浮かんだ。
はいおわりで〜す。長〜い。長いよ。たぶん八千句はあった。しかし、世間にはもっと長くて真摯でおもしろい読み(というか選評)もありますよね。だから!そっちを!読もう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
