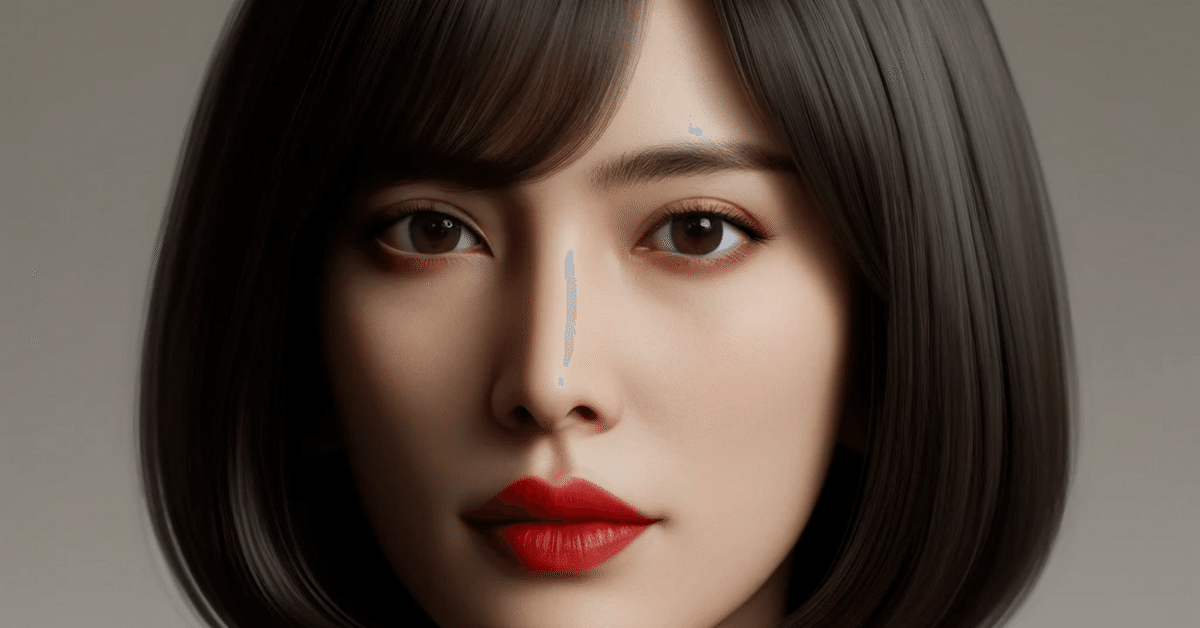
新世紀探偵(5:ミスター=イッセイ・スズキと話す必要がある)
ミスター=イッセイ・スズキと話す必要がある、と言い出したのは私の方だった。つぐ失踪の有効な手がかりがない現段階では、もっとも有力な情報源の一つと予想されるミスターに当たってみるのは当然のことだったし、気の合うことにミネコ・サカイのプランでもミスターとの面会は真っ先に組み込まれていたらしかった。そういうわけで、我々は「いとなみ」をチェックアウトして、ミスターが収監されている東京拘置所へと向かった(ミネコ・サカイは途中でマクドナルドのドライブスルーでビッグマックセットにさらにビッグマックを一個追加して朝食をとった。私はチーズバーガーセットを頼むだけにとどめた)。
ところで私はかねがね思っていたのだけれど、いくら何でも赤いBMWというのは目立ちすぎる。殺し屋に追われている現状でこの車に乗るという行為はほとんど自殺行為だろう。サングラスをかけながら車のエンジンを始動させているミネコ・サカイに対して、私はそのように異議申し立てをした。ミネコ・サカイはサングラスをわずかにずらしてから、私の目をまっすぐ見つめた。
「いまさらなんだけど、この車って色を変えられるのよね」
「冗談だろ?」
「ついでに言うと空も飛べるし、海にも潜れる」
「まさか」
助手席で声を上げて笑う私をよそに、ミネコ・サカイはインストルメントパネルの赤いLEDが光っているボタンを押しこんだ。すると、LEDの光が赤から青へとゆっくり変わっていった。まさかとは思ったが、私は一旦車の外に出て、本当に色が変わっているかどうか確かめてみた。そして、再び助手席に戻ってくると、今度は私がミネコ・サカイの顔をまっすぐ見つめる番だった。
「ミス・サカイ、もしかして君ってスーパーヒーローか何かなのか?」
「ふふふ」とミネコ・サカイは私のリアクションに満足したように微笑むと、再びサングラスをかけて「それじゃあ、出発しましょう」と言った。
ミネコ・サカイの運転する真っ青なBMWはまたしても唸りを上げながら、ラブホテルの駐車場から大通りへと出発していった。
*
東京拘置所へ到着すると、私たちはまず受付で身分証を確認された。ミネコ・サカイはiSeeを装着していたのでほとんど一瞬で認証が済んだが、私はマイナンバー・カードなどという時代遅れの遺物を出すのに手間取ったので、とことん守衛に怪しまれることになった。マイナンバーカードはコートのどちらのポケットを探してもなく、最終的にスラックスのポケットからぼろぼろになって出てきたのだった。守衛はまるできたない物でもさわるように(実際きたなかったと思うが)私のマイナンバーカードをつまむと、顔写真と私の実際の顔とを交互に眺めた。それから、不機嫌な表情を一切崩さず、投げ返すようにしてカードを返却した。
「どうもありがとう」と私はカードを受け取りながら言った。「東京拘置所のマニュアルには仏頂面で仕事をすることとでも書いてあるのかな?」
守衛は何か言いたそうに唇をひくつかせたが、結局は何も言わなかった。
「ごめんなさいね、この人、いちいちこういうことを言わずにはいられないの。そういう病気なの。ちょっと頭がおかしいのよ」とミネコ・サカイが守衛に向かってフォローになっていないフォローをした。守衛は呆れたように私たちを見送った。
イッセイ・スズキとの面会に関するその後の手続きは全てミネコ・サカイがiSeeを使って済ませてくれた。こういうときに自分がアナログであることの不便さを痛感する。しかし、だからと言って、二度とデバイスを自分の身体にコネクトするのはごめんこうむる。
ひと通りの手続きが済むと、これまた無愛想な拘置所の職員がやって来て、私たちを面会室まで案内した。面会室は昔から変わらない無機質な空間だった。チープなプラスチックのテーブルとパイプ椅子、天井から吊るされた裸電球、その他には何もない。職員は私とミネコ・サカイをパイプ椅子に座らせると「少々お待ちください」と事務的な声で言って、面会室を出て行った。あくまでもここは東京拘置所であって、ディズニー・リゾートではないのだ。職員にホスピタリティを期待する方が無駄というものだろう。私とミネコ・サカイは二人とも何を話すでもなく、腕を組んでいたずらに時間が過ぎるのを待った。
しばらくしてから面会室のドアが開いた。私とミネコ・サカイは同時にドアの方へ視線を移した。二人の職員に付きそわれてやって来たイッセイ・スズキは、数年前に私が逮捕したときとほとんど変わっていなかった。五分刈りにした坊主頭、ゲジゲジとした眉、よどんだ光をたたえた細い目、顔に対してやや大きすぎる耳、昔ひどく殴られたことがあるようにつぶれた団子鼻、いつもにやにやとした笑いを浮かべている薄い唇。どの年代にも見えると言ってもいい年齢不詳な雰囲気は相変わらずだった。ただ、数年の拘置所生活でさすがに多少やつれているようだったし、無精ひげもまばらに生えていた。イッセイ・スズキは手錠をしたまま向かいのパイプ椅子に腰かけると、まず私の顔をぼんやりと点検して、その次に隣のミネコ・サカイの顔を点検した。そして、すぐに我々に興味をなくしたようだった。
「面会時間は一時間以内とします」と職員は説明した。「我々はこの面会室のすぐ外に控えておりますので、お帰りになる際や何かあった際にはノックでお知らせください」
「それでは、カツ丼をお願いしてもいいでしょうか?」と私は言ってみたが、二人組の職員は何も聞こえなかったかのように面会室を出て行った。ドアの覗きガラスからは二人の職員の後頭部が見えた。どうやら東京拘置所では古きよき取り調べとカツ丼の伝統は消えてしまってひさしいみたいだ。
イッセイ・スズキはパイプ椅子に座らせられてからというもの、天井から吊るされた裸電球をずっと見つめていた。電球は古くなっているようで、ときどきいきなり光が明るくなったり、暗くなったりした。私とミネコ・サカイは顔を見合わせ、どちらが先に話し出すべきかをジェスチャーで相談していた。
「ボ、ボ、ボ、ボクはさァ」とイッセイ・スズキが電球を見ながら突然喋り始めた。「こ、こ、こ、この後予定があるんだよねェ」
私もミネコ・サカイも何も反応せずに沈黙をまもっていた。
「こ、こ、こ、この後、ヤ、ヤ、ヤ、ヤクルト・スワローズのデ、デ、デ、デイ・ゲームがあるんだよォ」とイッセイ・スズキはぼりぼりと坊主頭をかきながら言った。「ボ、ボ、ボ、ボクはヤ、ヤ、ヤ、ヤクルト・スワローズのだ、だ、だ、大ファンだから、ぜ、ぜ、ぜ、絶対に見なくちゃいけないんだよォ」
イッセイ・スズキはどうも私の顔を覚えていないようだった。先ほど私の顔を確認したときも何のリアクションも見せなかったし、何なら初対面のミネコ・サカイの方がまだしも興味を引いたようだった。ミネコ・サカイは咳払いをしてから「イッセイ・スズキさん、今日はあなたに聞きたいたいことがあってこちらを訪ねました」と話し始めた。
「な、な、な、何の話ィ?」とイッセイ・スズキはちかちかする電球から目を離して、ミネコ・サカイの顔を見た。「な、な、な、何の話だよォ?」
「この子に見覚えは?」と言ってミネコ・サカイはキタロー・ユカワ教授が私に見せたのと同じつぐの写真を机の上に置いた。ひまわり畑を背景に撮られたつぐのポートレート。イッセイ・スズキはミネコ・サカイの顔からつぐの写真に視線を落とした。それからだんだんと目がかっ開いてきて、鼻息もどんどん荒くなってきた。そのうちによだれも垂らしかねないくらい、イッセイ・スズキは性的に興奮しているようだった。私はイッセイ・スズキに対する嫌悪感を新たにした。
「その子の名前はつぐちゃん」とミネコ・サカイは説明した。「昨日から行方がわからなくなっています。そして、つぐちゃんの失踪と同時に、ダークウェブにおいてあなたがかつて使用していた『ミスター』というユーザーネームを騙る人物が再び現れたとの情報を得ています。ここまでの話に心当たりは?」
スペシャル・エージェントを名乗るだけあって、ミネコ・サカイはさすがにこういった尋問には慣れきっているようだった。何と言っても手際がいい。必要なことを必要なだけ最短距離で聞く。無駄な暴力や恫喝は一切なし。やっぱりプロフェッショナルだ、と私はあらためてミネコ・サカイの実力を認識した。どうやらC級探偵の私の出る幕はなさそうだ。
「ボ、ボ、ボ、ボクは知らないィ」とイッセイ・スズキはつぐの写真に視線を釘付けにしたまま答えた。「ボ、ボ、ボ、ボクは何も知らないィ」
やれやれ、というようにミネコ・サカイはため息をついた。しばらく中指でとんとんと机を叩いてから「わかったわ」と再び口を開いた。
「もし、あなたがいまから本当のことを話してくれるんだったら、それ相応の報酬はあげられるかもね」
「ほ、ほ、ほ、報酬ってェ?」
「そのつぐちゃんの写真をあげるわ」とミネコ・サカイは即答した。「つぐちゃんの写真、喉から手が出るほど欲しいんでしょう? こんなしみったれた拘置所では、あなたのお眼鏡にかなうような非合法のポルノは支給されないものね。もし、あなたが本当のことを話すんだったら、その写真を独房まで持ち帰りなさい。くれぐれもここの人たちには見つからないようにするのよ」とそこまで話したところですでに指を伸ばしていたイッセイ・スズキに警告するように、ミネコ・サカイは素早く片手をかぶせてつぐの写真を隠してしまった。「でも、あなたがこのまま嘘をつき続けるなら、この写真は没収する。そして、いますぐ外にいる職員さんに声をかけて、あなたは再び独房へと連れ戻されることになる。きっとあなたの頭の中はつぐちゃんのことでいっぱいでしょうね。そのころには私たちはさっさとここから出て、ほかのところを当たっているでしょう。あなたにはもう用はないから、ここには二度と戻ってこない。さて、あなたはどっちがいいのかしら?」
イッセイ・スズキはつぐの写真を隠しているミネコ・サカイの手と、ミネコ・サカイの顔とを交互に見比べて、頭の中で損得を計算したり、あるいはいくつかのファクターを並べて比較検討しているみたいだった。その顔つきは人間というより、ずる賢い悪魔のようだった。私はイッセイ・スズキの醜悪な姿を見て、ミスターを逮捕したときのことを思い出していた。
*
「ユリイカ!」というヤノの甲高い声が真夜中のオフィスに響きわたった。
ミスターについて話し合っていた私とドンは、声を上げた張本人であるヤノのデスクへ向かった。ホソノ、ハヤシ、サトウもマグカップを片手にヤノのデスクへと集まってきた。そのころはちょうど首相の暗殺未遂事件があったせいで、ミスター事件対策本部はほとんど機能不全に陥っており、いまここにいるメンバーは全員、非公式にドンが集めた人員だった。私を含めた全員がそれぞれの部署で厄介者扱いされている変わり者ばかりだったが、私もヤノもホソノもハヤシもサトウも、何かしらのつながりで一度はドンに世話になったことがあり、ドンをリスペクトしていたのだった。
「見てください!」とヤノはいささか興奮状態でパソコンの画面の一点を指差しながら叫んだ。
ヤノの人差し指が画面を指差し続ける中、私を含めた捜査本部の全員がモニターに現れている謎めいたコードの群れを眺めていた。しかし、クラッキングに関する専門的知識を持たないヤノ以外のメンバーにとっては、いったい何が何だかまったく理解できなかった。
「ヤノ、俺も含めてお前以外のメンバーにはこれだけ見ても何一つわからん。ちんぷんかんぷんだ」とドンはヤノのかたわらで難しそうな顔をしながら言った。「悪いが無学な俺たちにもわかるように説明してもらえるか?」
「ガッチャ!」とヤノはアッシュピンクの髪をかき上げながら言った。「結論から言うと、ミスターの個人情報を特定しました」
「本当か!?」とドンは天井が割れそうなほどの大声でいきなり叫んだ。「それは本当なのか!?」
「イッセイ・スズキ、34歳、埼玉県所沢市二山町9048在住、筑波大学理工学群工学システム学類卒業、現在は無職」とヤノはピンポイントで答えた。「一分前にこの住所にあるデバイスからダーク・ウェブのミスターのアカウントにアクセスした形跡があります。間違いありません」
「どうしてわかった?」
「ミスターがミスターらしからぬ初歩的なミスをしてくれたおかげです」とヤノは説明した。「ミスターっていつも複数のオニオンに動画をアップロードしているでしょう? あいつはいつも全てのオニオンで異なったTorを使っているんです。まあ、これ自体は珍しいことではありません。ただ、一分前に特定のオニオンにアップロードされてすぐ削除された動画があったんです。恐らくアップロード途中で何かしらのエラーが起きたんでしょう。当然その段階ではまだオニオンとTorの組み合わせはたった一つしかなかったわけです。偶然にもわたしは該当のオニオンを監視しているところだったので、まさにタマネギの皮でも剥くようにTorをすぐさま逆探知して、あいつのiSeeに登録されていた個人情報をごっそりひっこ抜いてやりました」
「なるほど、わかりやすい説明をありがとう」とドンはヤノの説明にもっともらしく頷きながら言った。「念のため確認しておくが、いまの説明を理解できたやつは?」
私、ホソノ、ハヤシ、サトウは黙ったまま頭を横に振った。
「まあ、いいか」とドンは頭をかきながら言った。「それにしてもよくやった、ヤノ。俺はお前を誇りに思う。しかし、祝賀ムードになるのはまだ早いぞ。いまからここにいるメンバーでミスターをとっ捕まえに行く。俺と**とヤノ、ホソノとハヤシとサトウに分かれてそれぞれ現地に向かう。そして、さっさとやつを捕まえて、ピザでも取り寄せてみんなで食べよう。もちろん俺のおごりでな」
私、ホソノ、ハヤシ、サトウ、ヤノの全員がそれを聞いて拍手喝采を送った。
「ヤノ、やつを逮捕したらすぐさまピザの手配を頼む。もちろんドミノ・ピザだ」
「オーケー、ドン」とヤノは米軍式に敬礼しながら言った。
そのようにして、ミスター事件対策本部(非公式)のメンバーたちはミスター=イッセイ・スズキ逮捕へと急きょ向かうことになったのだった。しかし、このときには誰も気がついていなかったのだが、これはミスター=イッセイ・スズキによる巧妙なワナだったのだ。
*
ヤノが特定した埼玉県の住所に着いたメンバーたちはそれぞれパトカーから降りながら、思わず呆気にとられることになった。ヤノによればミスターの現在地と目されたその場所は、郊外によくあるような普通の二階建て住宅だった。真夜中ということもあって明かりこそともっていなかったものの、表札には「スズキ」とあったし、実際に人が住んでいる気配もあった。
「ホシには俺と**で接触する。ホソノ、ハヤシ、サトウはバックアップの準備をして待機、ヤノはやつのクラッキングにそなえて全員のiSeeにファイアウォールを展開して待機」
「ラジャー!」とヤノはパトカーの上でラップトップを叩きながら言った。ホソノ、ハヤシ、サトウもそれぞれ短く頷いて、パトカーのそばで拳銃を低く構えて待機の姿勢をとった。ドンと私はスーツの襟を正し、ネクタイを締め直し、二人で顔を見合わせた。「行きましょう」と私は言った。
ドンは表札の隣にあるインターフォンのボタンを押した。真夜中に似つかわしくない「ピンポン」という音がして、直後に二階の窓に明かりがついた。そして、インターフォンから「はい」という声が聞こえた。年配の人物のようで、声にはいくらか緊張した響きがこもっていた。ドンは咳払いをしてから「夜分遅くに申し訳ありません。警視庁の者ですが、こちらはイッセイ・スズキさんのお住まいでお間違いないでしょうか?」と尋ねた。
「イッセイでしたら息子ですけど」と戸惑いぎみの声が言った。「警視庁の方がイッセイに何のご用です?」
「現在、捜索中の事件の被疑者として、署までご同行をお願いしたくお伺いしました」
「被疑者?」とインターフォンの声はさらに混乱したように繰り返した。「うちの息子が何の事件の被疑者になっているんです?」
「ひとまず顔を合わせてお話しましょう」とドンは言った。「話はそれからです」
それから少し経った後、年配の夫婦の姿が現れた。二人ともパジャマ姿のままだった。父親の方は禿げ上がった頭に銀縁の眼鏡をかけており、母親の方はパーマをあてた髪と肉づきのいい顔をしていた。
「夜分遅くに失礼します」とドンは警察手帳を見せながら言った。隣にいた私もスズキ夫婦に見えるように警察手帳を掲げた。「イッセイさんはいまどちらにいらっしゃいます?」
「二階の寝室で寝ています」とイッセイ・スズキの父親が我々のために門を開けながら言った。
「きっと何かの間違いでしょう?」とイッセイ・スズキの母親も門のところまで出てきて尋ねた。
「間違いかどうかはイッセイさんに会って話せばわかります。それではちょっとお邪魔します」とドンは両親にそれ以上有無を言わせず、門の先に伸びているポーチをずかずかと歩いていって、二階建て住宅の中へと踏み込んだ。私も後ろから早足で着いていった。
ドンはそのまま革靴を脱いで家に上がり、私もそれに続いた。リビングへと続く廊下を歩いていくと、つき当たりに折り返すような形で二階への階段があった。ドンと私は階段を上がり、二階の廊下へと出る。いちばん奥の開きっぱなしになっている扉は恐らく両親の寝室だろう。そうすると手前の扉がイッセイ・スズキの寝室のものということになる。ドンはiSeeを起動して、外で待機しているメンバーたちに「これよりホシに接触する。ホソノ、ハヤシ、サトウは指示があるまで引き続き待機。ヤノは引き続き全員のデバイスにファイアウォールを展開、異変があれば適宜対応してくれ」と指示を出した。「了解」と全員が返事をした。それからドンは私の顔を見て頷いた。私もドンの顔を見て頷いた。そして、ドンは拳銃を片手にイッセイ・スズキの寝室のドアノブに手を伸ばし、部屋の中へと乗り込んでいった。私も拳銃を構えて、後から続いた。
「何?」とドンは立ち止まった。私も思わず目を見張った。
イッセイ・スズキの寝室だと思った場所は寝室ではなく、一面の赤い空間だった。ミロのヴィーナスの彫像、緑の葉をつけた観葉植物、L字型に配置された二組の二人がけソファ、ガラス製のテーブル、その上に置かれたブルーローズの花束、ラッパ型蓄音機、暗幕のように周囲に垂らされている真っ赤なビロード。いつの間にかドンと私はソファに並んで座らせられていた。ここはいったいどこなんだ?
「ドンさん、**さん、聞こえますか!?」とヤノの声がiSeeを通して聞こえてくるが、その声は奇妙に歪んでいる。「ミスターにまんまとしてやられました! そこは危険です! いますぐこちらに──」
ヤノの通信はそこで途絶えてしまった。どうやらiSeeの通信機能が遮断されたらしい。ドンと私は不思議そうな表情で顔を見合わせた。私はソファから立ち上がろうとしたが、まるで夢の中でのようにうまく身体が動かなかった。恐らくドンも同じだっただろう。ここは子どもたちが殺され続けていた場所と同じだ、と私は気がついた。
巨大な目玉のマスクにシルクハットを被り、タキシードを着込んでステッキを持った人物がもう一方のソファに座ってこちらを見ていた。ミスター、と私は思う。私とドンは同時にミスターの方を見る。
「Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore(トト、どうやらここはカンザスじゃないみたいよ)」とミスターは合成音声のような声で言った。「お二人ともようこそいらっしゃいました」
私もドンも返事をしない。返事をしようとしても口が動かなかった。
「私はもう疲れてしまいました」とミスターはステッキで床をとんとんと叩きながら言った。「何故なら、あなたがたの仕事が遅すぎるから。子どもは何人も無駄死にしました。私はもうこのゲームに飽きてしまいました。何故なら、あなたがたが弱すぎたから」
ミスターはそれからステッキをてこにしてソファから立ち上がった。そして白い手袋をはめた手で親指を鳴らした。ラッパ型の蓄音機からシャンソンのような音楽が流れ始めた。
「私はもうこのゲームから降ります。こちらとしてもあなたがたの不戦勝ということで異存はありません」とミスターはソファに座っている私たちを見下ろしながら言った。「しかし、あなたがたにはそれ相応のペナルティを与えます。罪のない子どもたちを何人も無駄死にさせたことへの罰として」
ミスターはそれだけ言ってしまうと、はためいている赤いビロードの方へと歩いていった。そして、ビロードの向こうへ姿を消す直前、こちらを一瞬だけ振り向いた。
「There's no place like home!(やっぱりお家が一番ね!)」
その瞬間、赤い部屋の照明が激しく明滅し始めた。蓄音機から流れるシャンソンのボーカルがレコードの回転数を間違えたときのように極端に低くなり、断続的にしか聞こえなくなった。照明が明滅する中、私はすぐ隣にいたドンが目をつぶって激しくけいれんしているのを発見した。「ドン!」と私は叫びたかった。しかし、私は何も言うことができなかったし、何もすることもできなかった。ただ、すぐ隣でドンが激しくけいれんを繰り返すのを見ているほかなかった。
「あなたにも原因がある」という声が聞こえてくる。「私ばかりに非があるわけじゃない」
その声はどうやら先ほどまでミスターが座っていたソファから聞こえてくるようだった。私は照明が明滅を繰り返す中、目をこらしてソファに座っている人物の姿を確認した。そこには先だって離婚したばかりの元配偶者のMの姿があった。
「さびしかったのよ」とMは言う。「いつもあなたは仕事で外にいる。私は病気でずっと家にいる。たった一人でこんな場所に閉じこめられていると、本当に頭がおかしくなっちゃいそうだった。そんなとき、目の前に現れたのがWだったっていうそれだけ」
私はソファに座って喋り続けるMを見ていることしかできなかった。頷くことさえできなかった。
「ひさびさの再会だったのにも関わらず、Wはとっても優しかった。Wはちゃんと私の目を見て、私のとりとめのない話にも親切に耳を傾けてくれた。そして『Mの病気はいつかきっと治る。この暗闇がいつまでも続くわけじゃない。必ず明るい光がもたらされる』と慰めてくれた。全部あなたがしてくれなかったことよ」
もちろん、と私は声には出さずに言う。もちろん全部君の言う通りだと思う。
「そうやって、あなたはいつも私から逃げる」とMは言う。「全部君の言う通りだ、自分が悪かったからもうこの話はやめよう、ほかに何も言うべきことはないって、さっさと私とのコミュニケーションをシャットアウトしてどこかへ行ってしまう。私はあなたと結婚してからどれだけあなたと会話を交わしたのかわからないけど、こころの底からあなたと話し合えたと思ったことは一度もなかった。もっと言わせてもらえば、最初から私はあなたのことなんて好きじゃなかった。特に顔も好きじゃなければ、性格も好きじゃなかった。かたくななものの考え方も趣味の悪いところも全部嫌いだった。それでも結婚したら少しは好きになれるかもしれないと期待したけど、結局気持ちは変わらなかった。ただ、Wが近くにいてくれなかったときに、あなたがそばにいたというだけだったのに。どうして私はWと付き合い続けて結婚しなかったのかしら? どうしてあなたは私のことを好きになんかなったのかしら? あなたが私のことを好きになったせいで、私の人生は不幸になってしまったのよ」
赤い部屋の光が明滅し、シャンソンのレコードが断続的に流れる中、私はMの言ったことに対して何一つ返す言葉を持たなかった。本当に全部Mの言う通りだったからだ。言ってみれば私はWからMを盗んだようなものだった。MとWの関係が上手くいっていないとき、たまたま私が近くにいて、それで完璧な関係だったはずのMとWを損なってしまったのだ。そういう意味では私はMとWの両方を傷つけたのだということになる。私がそこにいなければ、Mの人生もWの人生も損なわれずに済んだかもしれなかったのだ。
「その通りよ」とMは言った。「だから、あなたはいまここで命を絶つことによって、その罪を償いなさい。そうすれば、あなたのけがれきった魂も救済されて、これ以上苦しまなくても済むのよ。さあ──」
「**さん!」というヤノの声が突然天井のあたりから聞こえた。「**さん、聞こえますか!?」
「聞こえる」と私は突然口を開けるようになってつぶやいた。「聞こえる!」と私は天井から聞こえるヤノの声に向かって繰り返し叫んだ。
「いまからドンと**さんをそこから強制的に排出します! ドンにも通信をこころみましたが応答ありません! **さんの許可でいっせいに強制排出を行います!」
「ドンと私の強制排出を許可する!」と私は叫んだ。「いますぐ強制排出してくれ!」
Mはソファから立ち上がって、私の方に近づいてこようとした。私は目をつぶって、ヤノが一刻も早くここから強制排出してくれるのを待った。その前に何かが私の頬にふれた。私は目を開けた。目の前にMの微笑んでいる顔があった。Mは私の頬を片手でさわっていた。
「また、そうやって逃げるのね」とMは私の顔の輪郭をなでながら言った。「いいわよ。いつまでも逃げ続けなさい。あなたが逃げ続けられる限り、いつまでも」
私はMに何かを言い返そうとした。それはとても大事なことだった。しかし、その前に意識が遠のき始めた。かつて口にしかけてできなかった言葉も、どこにも行くあてのない気持ちも、全ては暗黒の渦へと飲み込まれていった。M、と私は意識がブラックアウトする直前に思った。私の罪、相応の罰をもって贖われるべき罪、けがれきった魂の救済、それから。
*
次に意識を取り戻したとき、まず目の前にあったのはトラバーチン模様の天井だった。私はどうやら病室のベッドに寝かされているようだった。ゆっくりと身体を起こすと、まるで過剰に睡眠をとりすぎたときのような重苦しい頭痛がしていることに気がついた。それ以外には特に痛みはなかった。ベッドどうしを仕切る簡易カーテンに囲まれてはいたが、周りで誰かと誰かが一対一で囁き合っているような声が聞こえた。恐らくナースと患者とが話し合っている声だろう。通低音のように持続する囁きを聞いているうちに、私は意識がブラックアウトする前のことをだんだんと思い出していった。赤い部屋、ミロのヴィーナス、ブルーローズの花束、蓄音機から流れるシャンソン、そしてミスター(巨大な目玉の被り物にシルクハット、タキシードに黒いステッキ)。すぐ隣でけいれんしていたドンの姿。そしてM。「また、そうやって逃げるのね」。相応の罰をもって罪を贖うこと。けがれきった魂の救済。
頭がいくぶんかはっきりしてきた私は、ベッドにそなえつけられた緑色の呼び出しボタンを押した。しばらくしてナースがやって来た。私はナースにドンの本名を伝え、いまどこにいるのかと聞いた。ナースはドンに関する質問には何も答えずに「ドクターを呼んできます。それといま待合室に職場の方がいらっしゃいますから、**さんが意識を取り戻したとお伝えしてきます」とだけ言って、すぐにどこかへ行ってしまった。職場の方、と私はそれ以上でも以下でもなくただそれだけを思った。
しばらくしてから、ヤノが一人でカーテンの向こう側からこちらを覗いた。「ヤノ」と私は言った。「ドンはいまどこにいる? 私たちにいったい何が起こったんだ?」
「お体はもう大丈夫なんですか?」とヤノは私の質問を無視して聞いた。ヤノは疲れ切っている様子だった。アッシュピンクの髪はぼさぼさだったし、目も充血しきっていたし、声まで震えていた。私はヤノがそこまで憔悴している姿を初めて見た。
「うん、少し頭痛がするけど、それ以外は特に問題ないみたいだ」と私は答えた。「それでいったい何があったんだ?」
しかし、そこでヤノは突然泣き始めてしまった。「よかった」とヤノは両手で顔を覆いながら言った。「もう二人ともだめかと」
「私は全然大丈夫だよ」と私は言った。そして、ベッドサイドのボックスからティッシュを何枚か取り出して、ヤノに差し出した。
「ごめんなさい」とヤノはティッシュを受け取って涙を拭きながら言った。「それで何の話でしたっけ?」
「私とドンに何が起こったのかを知りたい」
「すいません、その話でした」とヤノはそう言ってようやく話し始めた。「ミスターの部屋にドンと**さんが到着した瞬間、わたしのモニターから二人の位置情報がロストしました。何かしらの異常があったことがすぐにわかって、わたしは慌てて外で待機していたホソノさんたちに声をかけました。急いで全員で家の中に上がっていって、ミスターの部屋まで行ってみると、床の上で倒れているドンと**さんの姿と、ベッドの中で眠っている様子のミスター=イッセイ・スズキの姿を視認しました。ミスターが何らかの方法でドンと**さんのチップをクラッキングしたことを把握したわたしは、ラップトップと二人の物理コネクタを接続して、二人のマインドデータを救出する作業を始めました。ホソノさんたちは眠っているイッセイ・スズキに近づいて起こそうとしましたが、どれだけ声をかけたり身体を揺さぶったりしてみても目覚める気配はなさそうでした。ホソノさんは何かに気がついたようにベッドサイドのゴミ箱を覗きこむと、すぐ『救急車!』と叫びました。イッセイ・スズキは睡眠薬を過剰摂取して自殺をはかったようでした。ハヤシさんは救急に、サトウさんは署に連絡をとって、それぞれ応援を要請しました。
一方、わたしはドンと**さんのマインドデータを探索するのに手間取っていました。全ての階層を自動解析しても見つからなかったんです。わたしはマインドデータの自動探索を早々に諦め、もう一度全ての階層を手動で解析していくことにしました。手動での解析が完了するまでには3分くらいかかりましたが、それはわたしにとってあまりにも長い3分間でした。
二人のマインドデータがなかなか見つからなかったのは、ミスターが仕掛けたトロイの木馬によって、二人の個体識別コードがでたらめに暗号化されてしまっていたからでした。わたしはまず暗号化されてしまった二人のマインドデータを解析して元に戻してから、直接発信をかけました。ドンからは応答がありませんでしたが、**さんからはすぐに反応がありました。ここからは**さんも記憶にあるお話でしょうけど、わたしは**さんの許可を得た後、二人をトロイの木馬から強制排出しました。しかし、マインドデータが復旧しても、二人はすぐに意識を取り戻しませんでした。それから少しして到着した救急車にドンと**さんとイッセイ・スズキが乗せられ、それぞれ病院へ運ばれていきました。イッセイ・スズキは病院に運ばれるとすぐに胃洗浄を施され、間もなく意識を取り戻したということでした」
ヤノはそこまで話すと一旦口を閉ざした。そこから先に起きたことを話したくないようだった。
「私はどれくらい意識がなかったんだ?」と私はひとまず聞いた。
「3日間です」とヤノは答えた。
「3日間」と私は繰り返した。鯨に飲み込まれていたヨナと同じだけの時間、私は生死をさまよっていたということになる。「それでドンは?」
「ドンは……」と言ってヤノは一瞬言葉を詰まらせた。「ドンはいまだに意識が戻っていません。ドクターの説明では**さんはマインドデータの損傷が軽微だったので一週間以内に意識を取り戻す可能性が高いとおっしゃっていましたが、ドンはすでに取り返しのつかないほどマインドデータが破壊されてしまっていて、この先意識を取り戻す可能性は限りなく低いそうです」
「要するに、ドンは一命はとりとめたが、この先ずっと……」
「そういうことです」とヤノは答えた。それから再び両手で顔を覆って、泣き始めた。
ドンが植物状態になったと聞いて、私は何も言うことができなかった。ドンはまだ新米刑事の私にいつも親切にしてくれた。刑事とはいかなる仕事なのかを一から教えてくれたのもドンなら、組織という巨大なシステムの中で働くということがどういうことなのかを教えてくれたのもドンだった。要するに私にとって全てを教えてくれた先輩がドンだったのだ。公私の別に関わらず、私が何かしらで悩んでいるときはいつも相談に乗ってくれたし、話しが長くなりそうなときは居酒屋に行って何時間でも話を聞いてくれた。ドンはそのアウトローな性格から、警視庁の上層部にはむしろ疎まれていたと言った方がよかったが、私を含めて部下からの信頼は非常に厚いものがあった。非公式の「ミスター事件対策本部」もドンが中心となって立ち上げたもので、私やホソノ、ハヤシ、サトウ、ヤノといった面々はドンを慕って集まったメンバーだった。私はあの「赤い部屋」でドンを助けることができなかった。すぐ隣にいて、ドンが洗脳されていくところを見ていることしかできなかった。さいわい、ヤノがレスキューしてくれたおかげで、最悪の事態こそ避けられたものの、ドンはもうこの先二度と(恐らくもう二度と)目を覚ますことがないだろう。
「もう少しだけ眠りたい」と私はベッドサイドで泣いているヤノに言った。
ヤノは何か返事をしたようだったが、私はそのときにはすでにまた眠りにつこうとしていた。私がMの幻影を見たように、ドンはあの赤い部屋でいったい何を見せられたのだろう? そして、どれだけの恐怖を体験したのだろう? あそこでドンが何を見たのかはもう誰にもわからない。再びドンが目を覚まさない限りは。もう二度と。
べえー、永遠に
こまの底にしがみついて
ぐるぐるまわる幽霊のように
ぼくは
きみなしで
生きる宇宙の
広さにおびえて
いる。
*
翌週、病院を退院した私は、ドンを含めた非公式の捜査本部のメンバーたちに重い制裁が科されたことを知った。私、ヤノ、ホソノ、ハヤシ、サトウは、上層部の許可を得ずミスター事件を捜査していたことによって、それぞれ降格処分と一ヶ月の停職を言い渡された。植物状態にあるドンについての処分は保留されていたが、仮に意識を取り戻してももう警視庁にはいられないだろうという話だった。恐らくメンバーのそれぞれにそれぞれの言い分があったはずだが、警視庁という巨大なシステムの中では個人がいくら声を上げても無駄だということもまた全員が知るところだった。私たちは甘んじてその処分を受け入れた。
「イッセイ・スズキとミスターの人格がどうしても結びつかない」というのが私の被疑者に対する第一印象だった。五分刈りにした坊主頭、ゲジゲジとした眉、よどんだ光をたたえた細い目、顔に対してやや大きすぎる耳、昔ひどく殴られたことがあるようにつぶれた団子鼻、いつもにやにやとした笑いを浮かべている薄い唇というその年齢不詳の外見から、ミスターのあのソフィスティケートされたビジュアルと犯罪の手口を思い起こすのは確かに難しかった。しかし、イッセイ・スズキは取り調べに対して「ボ、ボ、ボ、ボクがミスターですゥ。ま、ま、ま、間違いありませェん」と自供を繰り返していたとのことだったし、警視庁による個体識別コードの解析によってもミスターとイッセイ・スズキが同一人物であることは再三確認されていた。
正直、私はニュースで初めてイッセイ・スズキの顔を見たとき、こんなつまらない人間にドンは殺されたのだと思ってしまった(一命はとりとめたが殺されたと言っても過言ではないだろう)。別に思想信条があるからといってその犯罪が正当化されるわけではないが、イッセイ・スズキには思想も信条も何もなかった。筑波大学の理工学群工学システム学類を卒業した後、都内のIT企業に就職するも「上司からのハラスメントと労働基準法の規定をはるかに超過する時間の残業」を理由に退職、うつ病を発症してメンタルクリニックに通いながら、しばらくはハローワークなどにも通って次の就職先を探していたようだったが、次第に外に出ることもままならなくなりそのまま引きこもりになる。以来、10年以上をあの二階建て住宅の一室で過ごしていた。被害者の子どもたちにはメタバース上のソーシャルゲームを通して接触。同世代の子どもを装って、メッセージのやりとりなどを通じて被害者と親しくなる一方で、アカウントの情報から被害者の個体識別コードを特定し、マイクロチップとISeeをクラッキングする。そして、ターゲットを徹底的に洗脳し、特殊なコードによって生成された「ターゲットが深層意識においてもっとも恐怖している対象を顕現させる」というプログラムを流し込めば、後は自動的に被害者が自殺をしてくれるというからくりだった。恐らく被害者の子どもたちも私とドンが招かれたあの「赤い部屋」に誘い込まれ、自分がもっとも恐怖しているものを見せ続けられたのだろう。イッセイ・スズキは一連の犯行の動機について「ゲ、ゲ、ゲ、ゲームのつもりだったんだよォ」と笑いながら答えたということだった。
イッセイ・スズキはその後刑事裁判にかけられ、第一審、第二審のいずれも死刑判決を下された。最高裁でもその結果は変わらなかった。裁判長は「被告人の自己中心的かつ他人の痛みを顧みない著しく偏った人格傾向による犯罪であり、精神疾患や障害による影響は見られず、完全な責任能力が認められる」とし、「犯罪史上類を見ない凶悪事件であり、残虐非道な犯行に及んだ被告人の責任は重大で、科すべき刑は極刑以外にありえない」と結んだ。私は第一審からの全ての裁判を傍聴していたが、イッセイ・スズキはいずれの裁判においても反省の色を見せなかった。ずっと裁判所の天井の照明を見上げていた。死刑判決が下されたときにも全くのうわの空だった。
イッセイ・スズキの死刑判決によって、ミスター事件が一応の終結を見た後、私は真っ先に病院に行ってマイクロチップとiSeeを摘出してもらった。そして、誰にも相談することなく一方的に辞表を提出して警視庁を退職し、貯金がつきるまでしばらく何もせず過ごすことにした。毎日ウィスキーを一瓶飲み、煙草を一箱吸うという毎日が続いた。それ以外には何もしなかった(本当に何もしなかった)。インスタントラーメンやレトルトカレーなどの食品は全てアマゾンで買っていたので、外に出ることはなかった。シャワーもまともに浴びなかったし、髭も剃らずに伸びるままにしていた。そのときの私は本当に社会から隔絶されていると言っていい状況だった。
M、ドン、まるで私の人生は次々に大切な誰かが奪い取られていくようにできているみたいだった。Mの場合は私が家庭を顧みなかったことによって姿を消した。ドンの場合は(私がいちばん近くにいたのにも関わらず)助けられなかったことによって、やはり私のもとからいなくなった。私の人生とはいったい何なのだろう? 私がまだ生きている意味とはいったい何なのだろう? 彗星と見紛うほど燃え上がりながら空から落ちていく飛行機のように、私の人生はことごとく破壊されつつあるようだった。翼もエンジンももはや取り返しのつかないほど損傷してしまって、後は真っ逆さまに墜落していくほかどうしようもなかった。あるいは神様に全てを奪われつくしたヨブみたいだった。もう生きていたくない、と私は思った。こんなことならもういっそのこと死んでしまった方がましだ。
刑事を辞めてから一ヶ月後のクリスマスの朝、私は近所のスーパーで買ってきておいたロープをトイレのドアノブにくくりつけ、輪っかをつくって自分の首にはめた。それからいきおいをつけて上体を前に倒し、自分の体重で首を締めようとした。麻のロープがぎゅっと首を締め付け、喉元がはげしく圧迫された。頭から血の気が引いていくような感覚があり、このまま続ければもうすぐにでも事きれそうな感覚があった。
そのとき、インターフォンのチャイムが鳴った。私は思わず喉元のロープにかけていた自重をゆるめて、インターフォンの方を見た。何故かはわからないが、一瞬Mが戻ってきたのかもしれないと思った。ひとまずロープの輪っかを首元から外すと、私はインターフォンのもとまで行ってモニターを確認した。そこにはネイビーブルーに髪を染めた人物の姿があった。「はい」と私は通話ボタンを押しながら言った(それはひさびさに声を出した瞬間だった)。「ヤノです!」と相手は言った。私はモニターの中をよく見てみた。髪の色こそアッシュピンクからネイビーブルーになって、長さもいくぶんか短くなっているものの、確かにそれはヤノだった。
「悪いけど、いま誰かと会うような気分じゃないんだ」と私は言った。「申し訳ないけど、今日のところは帰ってほしい」
「恐らくそうだろうとは思ったんですけど、あえて来ました」とヤノは照れくさそうに笑いながら言った。「本当におせっかいでごめんなさい。でも、どうしても福島に帰る前に**さんの顔を見ておきたかったから」
「福島?」と私は思わず聞き返してしまった。「地元に帰るのか?」
「ビンゴ!」とヤノはモニターの向こうで笑った。「いま、私の話に興味を持ちましたね? 続きは家の中でお話しします!」
仕方なく私はドアの鍵を開けて、ヤノをマンションの部屋に上げることにした。ヤノはここに来る途中にスーパーに寄って買い物をしてきたらしく、ビニール袋を提げていた。ゴミが散らかって足の踏み場もない私の部屋を見ると、「想像以上にきたない」と正直に言った。それから髭だらけになっている私の顔を見て「**さん、いままで見たことがないくらいひどい顔です。シャワーでも浴びてきてください。ついでに髭も剃ってきちゃってください。ゴーゴーゴー!」とバスルームに追いやった。渋々ではあったけれど、私はヤノに言われた通り、シャワーを浴びることにした。前にシャワーを浴びたのがいつだったのかもう全然記憶になかった。
しかし、ひさびさに浴びる熱いシャワーは気持ちよかった。誇張ではなく本当に生き返ったようなここちだった。シャンプーで頭を洗い(二回も洗わなければいけなかった)、ボディソープで身体を洗い、洗顔剤をたっぷりと使って顔を洗った。顔に塗りたくった洗顔剤を熱いシャワーで洗い流したとき、私は先ほどまで首にロープをかけていたのが何だかばかばかしくなってきた。どうしてあれほどまで死に近づかなければならなかったのか、自分でもだんだんよくわからなくなってきた。洗面所に出て、バスタオルで頭と身体をしっかりと拭き、ドライヤーで髪を乾かした。そして、シェービングクリームを顔に塗って、新しい剃刀でていねいに髭を剃った。髭を剃り終わって、冷たい水道水で顔に残ったシェービングクリームを洗い流してみると、鏡の中の自分は先ほどまでとはまるで別人みたいに見えた。ついでに歯ブラシに歯磨き粉をペーストして、歯もしっかりと磨いておくことにした。そこまでやって、ようやく気持ちがすっきりした。ときとして、こういう馬鹿みたいな生活の細部を馬鹿みたいにしっかりやることが少し気持ちを持ち上げてくれたりもするのだ。それがたとえつい先ほどまで死のうとしていた人間であっても、だ。
リビングに戻ってみると、部屋は見違えたようにきれいになっていた。あれだけ散らかっていたゴミは一つの袋にまとめられ、床はワックスで磨き上げたみたいにぴかぴかになっていた。トイレのドアノブにかけっぱなしにしていた首吊り用のロープもいつの間にかなくなっていたが、ヤノはそれについては一言も言わなかった。ヤノはいまキッチンで大量にたまっていた洗い物を洗ってくれているところだった。
「**さん、ずいぶん顔がまともになりました!」とヤノは笑顔で言った。
「自分でもそう思う」と私も笑いながら言った。
キッチンまで行って、私はヤノが洗ってくれた食器を一枚一枚ふきんで拭いていった。そして全ての食器を元あった場所へと戻していった。その後で大量にたまっていた洗濯物も洗濯機に投げこみ、洗剤と柔軟剤を注いで、スイッチをオンにした。洗濯機は振動しながら回り始めた。
「ちょっと休憩」とヤノはリビングに戻ってソファに座り込みながら言った。私がやらなかった家事を全てやってくれたので、さすがに疲れてしまったようだった。
「ヤノ、今日はわざわざ来てくれて、本当にありがとう」と私もソファに座りながら礼を言った。
「いえいえ」とヤノは顔の前で手を振りながら言った。「私が勝手に来ただけですから、全然構わないんです。ところでハーゲンダッツを買ってきて冷凍庫にしまってあるんですけど、いまからちょっと食べません?」
「それは素晴らしいアイディアだ」と私は言ってキッチンへ行った。そして冷凍庫を開けて、ハーゲンダッツを二個とHäagen-Dazsと書かれた専用スプーンを取ってきた。クッキー&クリーム味とマカデミアナッツ味。「私、クッキー&クリーム食べてもいいですか?」とヤノが尋ねた。
「もちろんいいに決まっている」と私はクッキー&クリーム味のハーゲンダッツとスプーンをヤノに渡しながら言った。「君が買ってきてくれたんだから、君が好きな方を選ぶのは当然の権利だよ。それにこの二択だったら、私はマカデミアナッツの方が好きなんだ」
それから私たちはソファに並んで座ってハーゲンダッツを食べた。私もヤノもしばらく黙ってアイスクリームをすくっていたが、私はヤノが「福島に帰る」と言っていたことを思い出して「本当に福島に帰るのか?」と質問した。
「本当に福島に帰るんです」とヤノは私の顔を見て言った。「確か前にもお話ししたと思うんですけど、ずっと遠距離で付き合っていた福島の恋人と結婚することになりまして。ほら、福島で原発職員をやっているって話していたあの人です。まあ、それでこの間のこともあったし、いいきっかけかもしれないと思って、この際、警視庁を退職して郷里に帰ることにしました。元々警察って職業にも向いていなかったところもありましたし、ちょっと無理をしすぎていたみたいです」
「そうなんだ」と私は言った。「さみしくなるな」
「**さん、本当にそう思ってますか?」とヤノは私の顔を見ながら冗談めかして言った。「社交辞令じゃなくて?」
「社交辞令じゃなくて」と私は言った。「本当にさみしくなるよ。さよならだけが人生だ」
「さよならだけが人生ならば、また来る春は何だろう」とヤノは寺山修司の詩を引用した。「月並みなことを言うようですが、別れの数だけまた新しい出会いがあるって私は信じてます。まあ、それがいい出会いなのかよくない出会いなのかは出会ってみないとわからないんですけど」
「まあ、それもそうだな」と私は言った。「ちなみに福島での就職先はもう決まっているのか?」
「配偶者のつてでわたしも原発で働くことになっています」とヤノは言った。「いまだにあっちでは原発反対派の声も大きいし、人員はつねに不足しているんです。まあ、わたしたちの世代は歴史の教科書でしかあの震災のことを知らないですから、あんまり実感がないんですけど、やっぱりわたしたちのおじいちゃんやおばあちゃんの世代は子どものころに直に体験してますからね。現におじいちゃんとおばあちゃんはわたしが原発で働くことにも、原発職員と結婚することにも反対してます。そうは言ってもわたしたちにも生活がありますから。それでも、一方で後ろめたい気持ちもあるんです」
「それはそうだろうね」と私は言った。それ以上私には何も言えなかった。
「**さんの方はこれからどうするつもりなんですか?」と今度はヤノが私に質問してきた。「まさか、このままこのデカダンな生活を続けていくわけじゃないですよね?」
「そうだな」と私は言った。「正直なところを言うと、まだ何も考えていないんだ。あるいはギリシャあたりにでも引っ越して、余生を語学勉強に費やすのも悪くないと思っている」
「冗談ですよね?」とヤノは笑いながら言った。「まだまだ引退するような年齢じゃないでしょう。私とそんなに変わらないんだから」
「でも、本当に何のあてもないんだよ」
「いっそのこと『新世紀探偵』で探偵でもやったらどうですか?」とヤノは言った。「**さん、どっちかというと個人主義だし、刑事より探偵の方が向いていそうです」
「『新世紀探偵』」と私はヤノが口にした会社名を繰り返した。「確かにそれもありかもしれない。ギリシャに行くのはその後でも間に合うしな」
「その通りです」とヤノはハーゲンダッツを食べ終わって言った。「長い人生、まだまだこれからですよ。泣こうが笑おうが死ぬまで続いていくんです。どうせなら最後まで楽しんでやりましょう。ギリシャなんていつでも行けますから」
「ガッチャ」と私はヤノの口癖をまねた。そして我々は笑い合った。
それから、私たちはベランダに出て洗濯物を干した。外は気持ちがいいほど晴れわたっていて、何だかクリスマスという感じがしなかった。洗濯物を全て干してしまうと、「そろそろわたしは帰ります」とヤノは言った。私は駅まで送っていくと言ったが、ヤノは「ありがとうございます。でも、駅まで送って来られると、何だか未練がましくなっちゃいそうなので遠慮しておきます」と断った。
「わたし、**さんのこと、一人の人間として好きでした」とヤノは私の部屋を出て行く直前に振り返って言った。まるで突然思い出した言い方だったので、私は思わず笑ってしまった。
「私もヤノのことが好きだった。もちろん一人の人間として」と私は笑いがおさまった後で言った。「ここ一年で君には二回も命を救われた。本当に感謝してもしきれないくらい感謝している。あと、言うのが遅れたけど、ご結婚おめでとうございます。福島でもどうかお元気で」
「**さんもどうかお元気で。今後のますますのご活躍をお祈り申し上げます」とヤノは玄関先でかしこまったように礼をした。私も礼を返した。
私はヤノが出て行った後、ゆっくりとドアを閉めて鍵をかけた。「さよならだけが人生ならば、また来る春は何だろう」と私は一人で繰り返した。
それから、リビングのソファに座って、グーグルのAI「ジェミニ」のアプリを開いた。「『新世紀探偵』に転職しようと思っているんだけど、どうしたらいいんだろう?」。ジェミニはしばらく「……」と回答を考えたのち、「新世紀探偵」採用窓口の電話番号を送ってよこした。
そのようにして、私は『新世紀探偵』の探偵となったのだった。
*
「あ、あ、あァ、わ、わ、わ、わかったからァ!」とイッセイ・スズキは長い間悩んでようやく口を開いた。「ほ、ほ、ほ、本当のことを話すからァ!」
「ミスター、あなたって本当に話がわかる人ね」とミネコ・サカイは指を鳴らした。しかし、つぐの写真からはまだ手を離さなかった。「そういうことなら、ここからは録音させてもらうわよ」
ミネコ・サカイはそう言って、iSeeのボイスレコーダー機能を起動させた。イッセイ・スズキは唾を飲み込むと、唇をなめてから話し始めた。
「せ、せ、せ、政府の人間がァ、ボ、ボ、ボ、ボクのところに来たんだよォ」とイッセイ・スズキは言った。「そ、そ、そ、それでボ、ボ、ボ、ボクは、た、た、た、ただ、ミ、ミ、ミ、ミスターのことを聞かれたから、しょ、しょ、しょ、正直に答えただけェ。ど、ど、ど、どうやって子どもたちのチップをク、ク、ク、クラッキングしていたか、そ、そ、そ、そういう細かいことを答えただけェ。ほ、ほ、ほ、ほかには何も言っていないんだァ。ほ、ほ、ほ、本当の話だよォ。う、う、う、嘘じゃないよォ」
「なるほど」とミネコ・サカイはイッセイ・スズキがいま話したことを頭の中で検討しながら相づちを打った。「ちなみにそれはいつの話?」
「い、い、い、一ヶ月くらい前かなァ」とイッセイ・スズキは言った。「と、と、と、突然来たんだよォ」
「あなたはどうしてその人物が政府の人間だってわかったのかしら?」
「じ、じ、じ、自分で言ってたんだよォ。せ、せ、せ、政府の人間だって、ミ、ミ、ミ、ミスターの技術を教えたら、い、い、い、いいことがあるって言ってくれてさァ」
「いいこと?」
「し、し、し、死刑じゃなくて終身刑に減刑してくれるってェ」とイッセイ・スズキは唇に笑いを浮かべながら言った。「しゅ、しゅ、しゅ、終身刑にしてくれるってそう言ったんだァ」
「へえ、そういうことね」とミネコ・サカイは納得したように言った。「ほかにその人は何か言ってた?」
「そ、そ、そ、その人って、ひ、ひ、ひ、一人だけじゃないんだよォ」とイッセイ・スズキは言った。「ス、ス、ス、スーツを着た人と、も、も、も、もう一人いたァ」
「もう一人? もう一人はどんな人だった?」
「く、く、く、車椅子の、と、と、と、年寄りィ」とイッセイ・スズキは言った。「か、か、か、片方しかない、へ、へ、へ、変な眼鏡をかけてたァ」
ミネコ・サカイはその瞬間に私の顔を見た。私も訳がわからないという表情を浮かべて、ミネコ・サカイの顔を見返した。片眼鏡をかけて車椅子に乗っている老齢の人物と言えば、(私たちの知っている限り)キタロー・ユカワ教授をおいてほかにいなかったからだ。
「あ、あ、あ、熱海ィ」とイッセイ・スズキは続けて言った。「あ、あ、あ、熱海の、ラ、ラ、ラ、ラボォ」
「熱海のラボ?」とミネコ・サカイは再びイッセイ・スズキに視線を戻して確認した。「熱海のラボってその人たちがそう言っていたのね?」
「そ、そ、そ、そうゥ」とイッセイ・スズキは繰り返し頷いた。「あ、あ、あ、熱海の、ラ、ラ、ラ、ラボォ」
「イッセイ・スズキさん、どうもありがとう」とミネコ・サカイは言った。そして、つぐの写真をイッセイ・スズキの方にスライドさせた。「約束通り、それはあなたにあげます。さっきも言ったけど、くれぐれも職員さんに見つからないようにね」
それだけ言うと、ミネコ・サカイはさっさとパイプ椅子から立ち上がって、ドアの方まで靴音を響かせて行った。私もそれに続くことにした。ミネコ・サカイは扉をノックして、外で待っていた二人組の職員に「終わりました」と声をかけた。職員たちは面会室の中にいたイッセイ・スズキを立ち上がらせると、両脇から挟むようにして独房へ連れ帰ろうとした。
「そうそう、イッセイ・スズキさん」とミネコ・サカイは職員に両腕を拘束されたイッセイ・スズキに声をかけた。イッセイ・スズキは顔だけひねるようにして、後ろにいた私たちの方を見た。
「さっき言い忘れたけど、政府の人間の言うことなんて信用しない方がいいわよ」とミネコ・サカイはサングラスをかけながら言った。「あいつらって息を吐くように嘘をつくから。恐らくあなたは極刑のままでしょうね」
「う、う、う、嘘だよォ」
「嘘じゃないわよ」と言ってミネコ・サカイはiSeeで素早くイッセイ・スズキのデータを確認した。「やっぱり、あなたが減刑されたというデータはどこにも見当たらないわ。かわいそうに、元ミスターともあろう者が見事に一杯くわされたわね。ご愁傷様。やがて来る死刑の日まで、ずっとここで臭い飯でも食ってなさい。
それから、職員のお二人にも言っておくわね。その人、ポケットの中に何か隠し持っているみたいよ」
イッセイ・スズキの叫び声が響きわたる中、私とミネコ・サカイは東京拘置所を後にした。
(6へ続く)
ここから先は
¥ 500
thx :)
