
デザインの分業化とコラボレーション - Design Matters Tokyo 24で印象に残ったセッション -
おはようございます!こんにちは!こんばんは!
「家計簿プリカ B/43(ビーヨンサン)」を運営する株式会社スマートバンクでプロダクトデザイナーをしているputchomです。
先日、スマートバンクのデザイナー皆でDesign Matters Tokyo 24の1日目に参加して様々なセッションを聞いてきたので、今回はその中から自分も日々課題を感じている「デザインの分業化とコラボレーション」という切り口で、個人的に印象に残ったセッションをいくつか紹介しようと思います!
(※ リアルタイムな翻訳を書記していたため、意訳がある場合がありますのでご了承ください。)
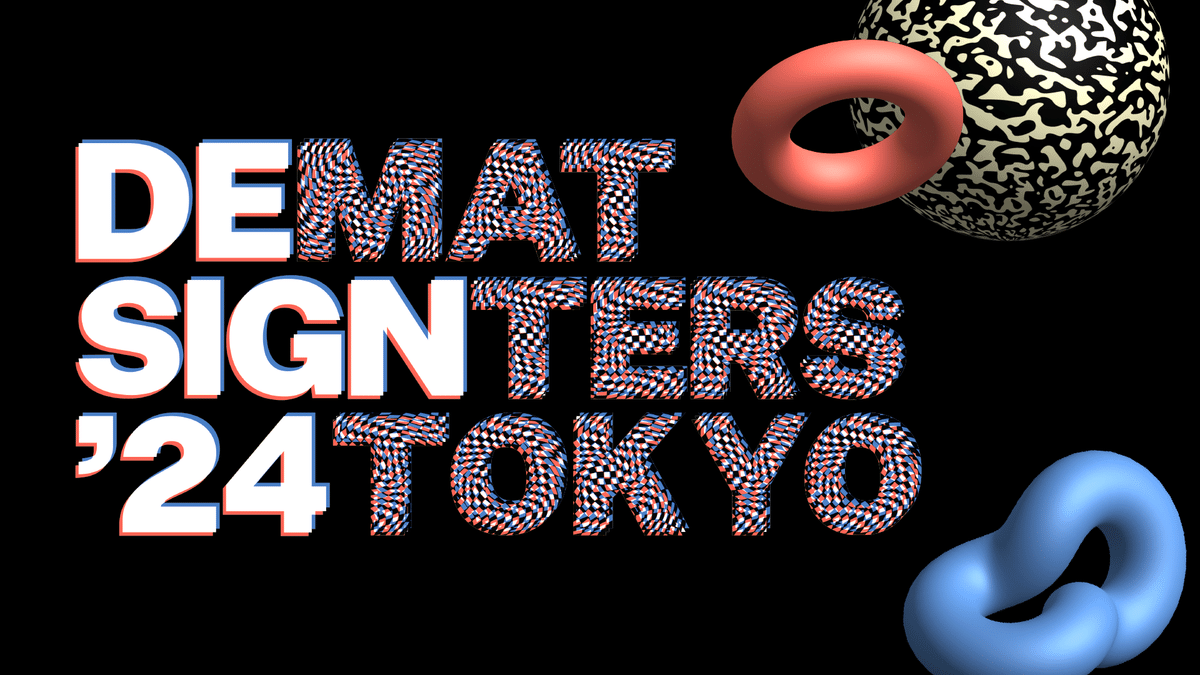
Design a better world with better writing

はじめに印象に残ったのはApple、Etsy、IKEAなどのライティングも手掛けるライターのNick DiLalloさんによる「Design a better world with better writing」というセッション。
良いデザインには良い文章が必要です。この講演では、私たちが生きていく上で、言葉がどのように私たちの考え方や行動を形作っているのかを探ります。どのように言葉を選べば、私たちが生きたい世界を反映できるのか。明瞭な文章は、世界をより公正に、より誠実に、より包括的にすることができるのでしょうか?
これらについて学べるでしょう:
・ブランドや商品のための語彙の定義
・言語がどのように理解と相互作用を形成するか
・視点を反映した適切な言葉の選択
・アクセシブルなインターフェイスにおける言語の役割
サービスデザインにおいてインターフェースやコンテンツのライティングは多くの部分を占めるわけですが、同時にその専門性も年々高まっていると感じています。
当セッションでは、実際の事例を参照しながら、専門スキルを持ったライターのライティングによってインターフェースから受ける印象がどのように変化するかわかりやすく解説されていました。



Q&Aではデザイナーとのコラボレーションについての質問があり、早めのタイミングでライターを巻き込むことが重要で、デザイナーだからデザインだけをして、ライターだからライティングだけを考えるのではなく、お互いコラボレーションすべきと述べられていたのが印象的でした。
また、最後のまとめで「ライターを採用しよう」とおっしゃっていて、日々デザインシステムを構築している身としては一度ライティングに専門性を持った方と一緒に働いて、専門的な知見を吸収する機会を持ちたいと感じました。
Navigating Design Success

次に印象に残ったのはMongo DBのメンバーであるRebecca Radparvarさん(デザイン戦略担当)、Lauren Foxさん(プロダクトデザイン担当)、 Sandy Nguyenさん(デザインシステム担当)による「Navigating Design Success」というセッション。
私たちの組織で初めて、分野横断的でデザイン戦略主導のイニシアチブを実施する際の課題と機会を探ります。
過去8年間、私たちの開発者データプラットフォームであるAtlasは、非常に機能豊富なプラットフォームへと発展してきました。私たちは、組織初のデザイン戦略主導のイニシアチブを実行する任務を与えられました。私たちのプレゼンテーションでは、戦略的・戦術的なデザイン成果物を提供するために、私たちの組織の中核となるデザイン分野(デザイン戦略、プロダクトデザイン、デザインシステム)の間で初めて新しいコラボレーションスタイルとパートナーシップで取り組むことから生まれた課題と機会について探求します。
私たちの目標は、構成可能で持続可能な情報アーキテクチャとナビゲーション・デザインを作成することでした。
私たちのプロセスや得られたもの、特にこれらの学習が今後のデザインやデザイン戦略主導のプロジェクトにどのように応用できるかについて掘り下げます。私たちのチームが直面した複雑な問題を明らかにし、継続的な前進を確保するために障害を克服するための戦略を共有します。
インパクトの推進におけるデザインのユニークな機会を照らし出す、組織的な葛藤を浮き彫りにすることで、デザインが製品戦略やデリバリーを推進するユニークな立場にあるとき、どのようにしてテーブルの席を確保するかだけでなく、どのようにして首座の席を獲得するかを示します。
内容としてはブランドの再編成に伴う管理画面のナビゲーションの情報設計を分業するデザイナーがどのようにコラボレーションしながら進めていったかというお話でした。




特に「コラボレーションに大事なのは関係するメンバーの言語を使うこと」という部分に共感しました。これは普段デザインシステムをどのように浸透させるかを考えるときに自分も意識していて、例えばスマートバンクではデザインシステムのユーザーはモバイルエンジニアが多いので、コンポーネントの命名をモバイルエンジニアに馴染みのある命名にしたりしています。
また、以前管理画面のナビゲーション改修をやったこともあり、それぞれの部門がサービスの一等地を手にしたい状況の中でステークホルダーの理解を得ながらナビゲーションを改修する難しさを思い出す内容でした。
Design by default - how societies are created by intentional and unintentional designers

最後に印象に残ったのはデンマークのFintech企業Pleoのプロダクトリサーチャー Adilice Sanches さんによる「Design by default - how societies are created by intentional and unintentional designers」というセッション。
社会をデザインすることを考えるとき、私たちはその責任をデザイナー、建築家、エンジニア、都市計画家、あるいはその他の「デザインの専門家」の役割と容易に結びつけることができます。しかし、歴史を振り返ると、社会は予想以上に複雑で有機的であることがわかります。その結果、社会は意図的なデザインと非意図的なデザインの両方によって定義されることになります。
非デザイナーは常に、意図的なデザインを鼓舞する上で重要な役割を果たし、意図的なデザインがどのように採用され、あるいは主流となったかを形成してきました。今日、テクノロジーはますますデザインを民主化し、ノンデザイナーがAIのようなツールを使ってデザインする力を与えています。しかし、その結果はどうなるのだろうか?すべてのCEOが自分の製品を作れるようになったら、社会は将来どうなるだろうか?あるいは、すべてのプロダクト・マネージャーが自分のアプリをコーディングできるようになったら、社会はどうなるのだろうか?
本講演では、デザイナーと非デザイナーがどのように重要な決定を下し、現代社会に影響を与えたか、また、意図的なデザインと非意図的なデザインのギャップを埋めるために、デザインの専門家がどのように大衆と関わることができるか、いくつかの事例を検証します。
Adiliceさんは元々建築が専門であり、このイベントのトピックを見た時に、建築とデジタル、リサーチの交差点について話をしたかったそうです。そこで、建築的な考え方を元にして、「デザインというのはneed、function、formをかけ合わせた問題解決の式であり、社会の中の様々な人々がこの公式を使って問題解決としている」と述べられていました。



プロダクトデザインの分業化が進んでいる中で、それぞれの職種がそれぞれの責任範囲でneed, function, formのバランスを考えながらデザインしていくことが重要というのは、なんとなく認識できていたものの、うまく言語化できていなかった部分なので良い頭の整理になったセッションでした。
ちなみに先日書いた記事で、スマートバンクのデザインプロセスも紹介しているのですが、今回の内容とシンクロする部分もあり、とても共感できる内容でした。
最後に
近年「デザイナー」と一口に言っても、専門とするスキルセットが違い職種も細分化されてきています。また、デザインのプロセスに関わるメンバーもデザイナーだけではなく多様化しています。
そういった中でお互いの専門性を活かしてチームとして最大のパフォーマンスを出すことはとても難しいです。
今回のセッションを聞いて、そんな中でも世界中の皆さんが様々な工夫をしながら分業化とコラボレーションの壁を乗り越えていることを学び、勇気をもらうことができました。
スマートバンクでもプロダクトデザイナーとコミュニケーションデザイナーはもちろん、リサーチャーやPMとも分業してデザインしています。まだまだデザイン組織も過渡期であり、パフォーマンスを最大化するようなコラボレーションをするためには、たくさんの課題があると感じています。
Design Matters 24で得た知見をもとに、さらに良いデザイン組織になるようにしていきたいと思える貴重な機会となりました。
採用情報
スマートバンクではプロダクトデザイナーやコミュニケーションデザイナーを積極採用中です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
