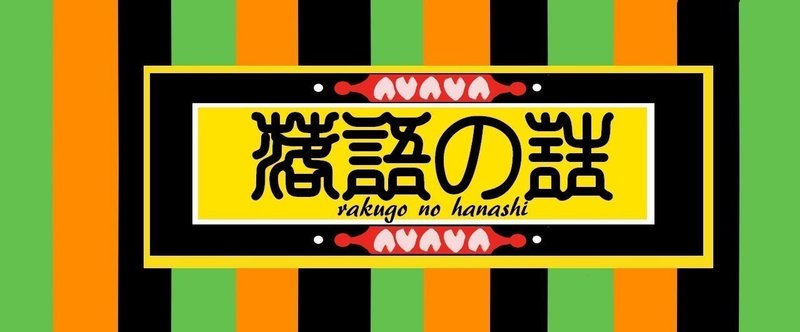
三代目 古今亭志ん朝と「文七元結」の噺
ぷらすです、こんばんは。
落語の人情噺はいくつもありますが、以前書いた「芝浜」と並んで有名なのが、今回の「文七元結(ぶんしちもっとい)」ではないかと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ストーリー
江戸の下町、本庄「だるま横丁」という裏長屋に、左官屋の長兵衛という腕の立つ職人がいました。
ところがこの長兵衛、悪い仲間に誘われてうっかり博打にのめり込み、左官は上手くても、博打は「下手の横好き」というやつで、ずっと負けっぱなし。
仕事道具や家具一式、終いには家族の着物まで質に入れる始末で、夫婦喧嘩が絶えない。
年の瀬も押し迫るある日、いつものように博打に負けた長兵衛が家に帰ると、明かりも点けずに奥さんがシクシク泣いている。
どうしたんだと聞くと、今年十七になるお久という娘が昨夜から帰ってこない。方々探してみても一向に見つからない。
父親は博打に明け暮れ貧乏暮らし、家では毎日のように喧嘩ばかりしているから、お久はすっかり嫌になって家出をしたか、世を儚んで自殺でもしたんじゃなかろうかと、奥さんはそう言います。
そんな話をしているうちに、長兵衛の家に吉原の大店「角海老(すみずし)」の使いの者がやってきて長兵衛に、「女将さんが今すぐ来て欲しいと言っている」と。長兵衛が今は娘のことで取り込み中だからと断ると「娘さんは昨夜からお店に来ている」という。
すぐに迎えに行こうとするけど、着物も質に入れてしまって着るものがないから、嫌がる奥さんの着物を無理やり剥ぎ取って、それを着込むと「角海老」に行きます。
「角海老」には女将さんとお久がいて、女将さん曰く、夕べお久がやってきて、自分が吉原で女郎として働くから自分を買ったお金を両親に渡し、女将さんから長兵衛に、もう博打は止めて真面目に働くよう言って欲しいと頼まれた。
そんなお久の健気さに心を打たれたので、長兵衛にお金を貸そうと言います。
いくら必要か聞かれ、諸々で五十両あればどうにかなると答える長兵衛。
そこで女将さんは、五十両を貸すから翌年の大晦日までに返すよう言います。それまでは、お店でお久を預かり花嫁修業もさせるしお店に(女郎として)出すような事もしない。その代わり、大晦日を一日でも過ぎたらお久を女郎にするから、そのつもりで今後一切博打を止め、一生懸命に働いて娘を迎えに来てやるよう、長兵衛を諭します。
この一件ですっかり改心した長兵衛が、家に戻ろうと吾妻橋にさしかかると、一人の若者が飛び降り自殺しようとしている。
慌てて止めた長兵衛がワケを聞くと「文七」と名乗る若者は、自分はある大店の者で、集金した五十両をスリに取られたので死んで詫びるのだと言う。
いくら説得しても死ぬと言ってきかない文七に、長兵衛は先ほど借りた五十両をやると言います。
粗末な身なりの自分がなぜ五十両という大金を持っているのか、ワケを話しますと、そんな大事な金は受け取れないという文七に、五十両を投げつけ逃げるように家に帰る長兵衛。
そのお金を持って文七がお店に帰ると、番頭さんと旦那さんが待っていて、集金はどうしたと聞きます。
文七が貰った五十両を差し出すと、二人はなぜお前が金を持っているのかと驚きます。
二人の話によれば、集金先で誘われた文七が、大好きな囲碁を打っているうちにすっかり遅くなり、慌てて帰る時に集金した五十両を置き忘れていたので、先方が届けてくれたのだと。
それなのに、お前が五十両を持っているのは一体どういうわけかと聞かれた文七は、吾妻橋での一部始終を話し、翌日、旦那さんと二人で長兵衛の家に行きます。
長兵衛にお金を返し(そこでも受け取る受け取らないとひと悶着ある)お礼のお酒を渡した旦那さん。貴方の心意気に感動したので、身寄りのない文七の親代わりとなり自分とも親戚として付き合って欲しいと頼みます。
そして、長兵衛の借金を代わりに払って「角海老」引き取ったお久を、長兵衛のもとに帰すのです。
その後、文七とお久は結婚し、二人で元結(髷(まげ)の根を結い束ねる紐)屋を開き、文七が考案した元結は、「文七元結」と呼ばれて人気を博し、二人は末永く幸せに暮らしたというお話。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この「文七元結」は、中国で伝承されてきた話をベースに、幕末から明治いかけて活躍した、初代 三遊亭圓朝が創作した人情噺で、枕も入れれば40分~一時間前後という長い噺なうえに登場人物も多く、人情の中にもおかしさを入れなくてはいけないので大変難しい演目と言われ、逆にこの噺が出来れば噺家として一人前と言われているんだそうです。
この噺が人気が高い理由は、噺の随所に江戸っ子の心意気が感じられるところではないかと思います。
主人公の長兵衛は本当にダメダメな親父だけど、どこか憎めないし、貧乏なくせに見栄っ張りで、カッコつけても全然キマらず、馬鹿がつくほどのお人好しと、オーバーなくらい江戸っ子の気質を体現するキャラクターだし、脇を固める吉原の女将さんや文七の働くお店の旦那さんもそれぞれに粋な人たちです。
「相手の面目を立ててやる」というのが江戸の武家文化で、女将さんも本気でお久を女郎にするつもりはなく、ただ長兵衛にお金を貸してもいいけれど、長兵衛がまたぞろ博打にお金を使わないように、また、『娘と引き換えにお金を貸す』という体裁をとることで、ただ恵んで貰ったのではない、その腕を活かして娘を取り返せばいいのだと長兵衛の面目を立ててやってるし、旦那さんも同様で、親戚付きあいという建前を用意して長兵衛の面目が立つように便宜を計ってお久を家に帰してあげてるわけですね。
きっと、そういう「江戸っ子の粋」が、寄席に来ている庶民のハートを掴んだんだと思います。ちなみに、この噺は『人情噺 文七元結』という題名で歌舞伎でも演じられています。
そんな風に、人気の高い演目だけに多くの名人の持ちネタになっているんですが、その中でも僕が特に好きなのが三代目 古今亭志ん朝さんの「文七元結」です。
志ん朝さんの「文七元結」は枕からオチまで、流れる水ようでまるで一本の映画を観ているような気持ちになるんですよ。
志ん朝さんは、昭和の大名人と言われた五代目 古今亭志ん生さんの次男で、立川談志、三遊亭圓楽、春風亭柳朝さんらとともに、「江戸落語四天王」に数えられ、また同世代の噺家では「西の枝雀(桂枝雀)、東の志ん朝」と称され、多くの人に愛された名人です。
ジブリのアニメ『平成狸合戦ぽんぽこ』のナレーションの人といえば、ピンとくる人もいるかもしれませんね。
とにかく、滑稽噺から人情噺まで、どんなネタでも出来るオールランダーで、その腕前は、めったに人を褒めない立川談志さんに「金を払って聞く価値のあるのは志ん朝だけだ」と言わしめたほどだったとか。
そんな志ん朝さんの落語の特徴を一言で言うなら、
「品がある」
だと思います。
「上品」なんじゃなくて「品がある」
僕の好きな小説家、池波正太郎さんが小説のあとがきだったか、エッセイだったかで書いていたんですが、「分かってない人の時代劇で、江戸っ子は常時べらんめぇ口調で喋るけれど、実際はそうじゃない」みたいな事を書いていたんですが、志ん朝さんの落語は、まさに池波さんの言葉を体現していると言えるでしょう。
江戸っ子と言っても、商家の人と職人や人足、目上の人への話し方と目下に対しての話し方、普通の時と怒っているとき。
当たり前ですが、育ちや状況、性格によって全部話し方は違います。
そのへんの演じ分けが志ん朝さんは絶妙なんですよね。
また、寄席でトリを務めるときの志ん朝さんのネタは一時間以上のものも珍しくありません。
舞台経験のある方ならわかると思いますが、舞台装置もなく、場面転換もなく、たった一人の演者の語りだけで一時間以上、お客さんをダレさせないで最後まで楽しませるのは至難の業です。
しかし、志ん朝さんの落語は、時間も忘れて聞き入ってしまうんですね。
いつのまにか江戸時代へタイムスリップしているような、そんな感覚です。
安易に使っていい表現でないのは重々承知ですが、ほんと「天才」というのは志ん朝さんのためにある言葉だと思います。
もし、機会があれば古今亭志ん朝さんの「文七元結」で、あなたもタイムスリップしてみてください。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
