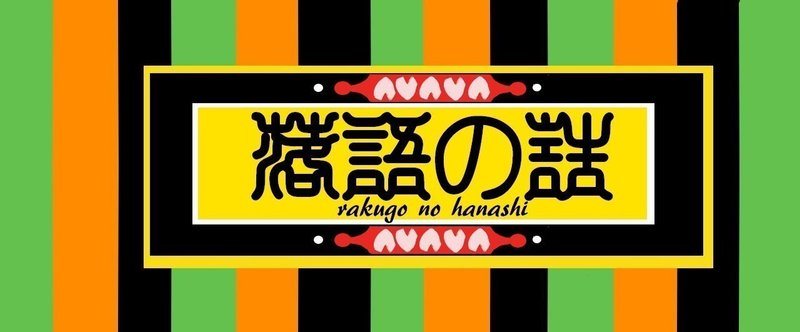
立川談志と「芝浜」の噺
ぷらすです、こんばんは。
例えば、落語を聞いたことがない人でも、落語に興味のない人でも、ある年齢より上の世代の人なら「立川談志」の名前を知らない人は、まずいないのではないでしょうか。
バラエティーやワイドショーで本人を見た人も多いと思いますし、ビートたけしさん、爆笑問題、伊集院光さんなど、芸能人の話を聞いて名前を知ったという人も多いと思います。
かくゆう、僕も最初はビートたけしさんのラジオで名前とエピソードを聞いて、談志さんの名前を知ったクチです。
芸能界(特にお笑い)の人が立川談志という人を語るとき、名前の枕につくのは大抵「天才」か「奇才」、とにかく凄い落語家だと誰もが口にします。
「落語の解釈がほかの落語家とは全然違う」ってのもよく言われてます。
ただ、素人の僕からすると、談志さんのどこが天才で「落語の解釈」というのが何を指しているのかは正直分からないんですけども。
落語というと普通、枕(ネタに入るまでの振りというか、ネタに入る前の軽いお喋り?)→ネタ→サゲ(オチ)という流れなんですけど、僕がテレビやDVDで観た、談志さんの落語は落語っていうか、例えば持ち時間が30分だとしたら15分は漫談や時事放談(というか政治への愚痴や皮肉?)みたいな感じで、肝心のネタはストーリーの途中から始めたり、始まったと思ってもネタの途中で脱線したりで、いわゆる「落語」を聞いてる感じがあまりしない印象です。
ただ、一旦ネタに入ったときの語りは、比喩ではなく本当に「流れるよう」で、観客は気が付けばストーリーの中に入っているんですよね。
枕とネタの境目がないというか、ちょっと前まで政治家や落語家の悪口を言ってハズたのに、気が付けば八っつぁんや熊さん「が」話をしてるみたいな。(分かり辛いですかね?)
もちろん、そこが天才ってわけじゃなく、天才の「片鱗」っていう事なんじゃないかと思うんですけども。
僕が見た談志さんっていうのは、とにかく自由奔放で偏屈で理屈っぽくて口が悪いオッサン。ただし、落語は大好きで、落語に対しては真摯に向き合っている人というイメージです。
本人曰く、終戦当時、談志さんはまだ小学生で、つい昨日まで鬼畜米兵だ一億総火の玉だと言っていた大人が手のひらを返したように、戦争は悪だ、平和が一番だ云々と言い出し、それまでの価値観が全部ひっくり返ったのを見て、「全部嘘っぱちじゃねーか!」と憤慨したそうです。
それで、寄席で古典落語を観て「古典落語にはずっと変わらない人情(と価値観)がある」(うろ覚え)と高校を中退して「5代目 柳家 小さん」に弟子入り。落語の世界に足を踏み入れたのだとか。
そんな談志さんが得意としていたのが人情噺で、特に「芝浜」は談志さんの十八番だったそうです。
「芝浜」というのは、多分、数ある古典落語の中でも一番有名な人情噺で、ざっくりあらすじを書くとこんな感じ。
天秤棒一本で行商をしている魚屋の勝は、腕は良いけど酒好きで怠け者。
何かと理由をつけては仕事をしないので家計はいつも火の車だけど本人はどこ吹く風。
いつものように酒を呑んで寝ていると、堪りかねた奥さんに頼むから仕事に行ってくれと起こされるところから話は始まります。
じゃぁ明日から仕事に行くから、今日は好きなだけ酒を呑ませてくれと約束し、翌日、奥さんに起こされて嫌々仕事に出かけます。
ところが、河岸に行ってもまだ誰もいない。おかしいなと思っていると時刻を知らせる鐘の音がなり、数えてみるとまだ時間が早い。
さては女房、時間を間違えて早く起こしたなと憤慨するも、一旦帰ってまた戻ってくるのも面倒なので浜に降りて煙草を吹かしていると、浜の波間に漂っている財布を見つけます。
それを拾ってみると中には十両の金が。(今で言うと80~100万円位)
勝は慌てて財布を懐に入れて家に持ち帰ると、「仕事なんかしなくても暫くは遊んで暮らせる。さぁ宴会だ酒と肴を買って来い」と奥さんに言います。
で、翌日起こされて、奥さんに仕事に行くように言われたので、昨日拾った金があるだろうと言うと、「何を夢みたいな事を」と奥さん。
明日から仕事に行く約束をして大酒を呑み、起きたと思ったら「さぁ宴会だ酒と肴を買って来い」と言われ、奥さんは訳も分からず近所中に借金をして言われた通りにすると、勝は近所の知り合いを呼んで大騒ぎした末に酔っ払って眠ってしまったのだと。
結局、財布を拾ったのは夢で、借金だけが残った事を知った勝はショックを受け、死のうと言うけど奥さんに諭されて改心し、その日以来、人が変わったように酒を断ち、真面目に働くようになります。
そして三年後、一所懸命に働いた結果、表通りに店を構えて人を雇えるまでになった大晦日。
仕事を終えた勝に奥さんは、金を拾ったのは夢ではなく、ネコババの罪で捕まったりしないよう、長屋の大家に相談のうえ、拾った金を番所(警察署みたいなところ)に届け、勝には(金を拾ったのは)夢だと嘘をついていたのだと告白します。
そして、落とし主が現れないまま三年が経ち、拾い主の勝が晴れて金を受け取れる事になったのだと。
奥さんは離婚されるのを覚悟で告白しましたが、勝は奥さんに感謝して一件落着。お祝いに大好きだった酒を呑もうと奥さんに勧められますが、「(今の幸せが)また、夢になるといけない」と呑むのを止めるのがオチになります。
この噺は本当に有名で、僕も子供の頃から色んな噺家さんの「芝浜」を観ました。
古典落語は、演者の年齢や流派?によって、同じ噺でも少しづつ脚色が違うんですが、それは「芝浜」も一緒で、大筋は一緒でも細かい部分は演者によって少しづつ違うので、通な人は誰々の「芝浜」が良いとかあるみたいです。
もちろん、談志さんの「芝浜」も以前DVDで観たことがあります。
普通、落語は登場人物+ナレーション(噺家さん自身)の三人称で語られるんですけど、談志さんの「芝浜」はナレーションが一切なくて、勝と奥さんのセリフだけで構成されてるんですね。つまり、説明の部分が一切ないんです。
もしかしたら、そういうやり方をしてる人が他にもいるのかもしれませんが、僕は談志さんが初めてだったので、これはかなり驚きました。
もう一つビックリしたのは、談志さんの「芝浜」が完全にお芝居だったことです。
前回も書きましたが、「落語」というのは基本「語り」の芸なので、登場人物のセリフに感情を込めて演じる=お芝居にしちゃうのは粋じゃないと言われてます。
ところが談志さんの場合、勝のときは勝に、奥さんの時は奥さんに成って、感情たっぷりに「お芝居」してるんですね。
つまり、一人で二人芝居を演じてるワケです。
ただ、それが凄く良いんですよ。落語だということを忘れちゃうくらい感情移入して、噺の中に入り込んじゃうんです。
子供の頃からいろんな落語を観てきましたが、落語で泣いたのはこの時が初めてでした。
まぁ、もしかしたら談志さんは普通に「落語」をしていて、その魔法みたいに巧みな話術で「お芝居のように」見せているだけなのかもしれませんが。
観客がそうと気がつかないうちに、落語の枠も飛び越えた「自分の世界」に巻き込んじゃう落語家。
立川談志という人が「天才」と評されているのは、もしかしたら、そういう部分なのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
