
俳句のいさらゐ ⋓◍⋓ 松尾芭蕉『奥の細道』その十七。「一家に遊女もねたり萩と月」
「一家に遊女もねたり萩と月」
芭蕉『奥の細道』より
省略が極みに達しているこの俳句の解釈は、むつかしい。しかし、解釈したい気持ちに誘われ続けていた俳句である。
この俳句の着想点は、作者のこういう感情に発するだろう。
■ 遊女のいる処と言えば、岡場所 ( 非公認の遊里 ) であって、こちらから
そこへ出向いて行って会うものが遊女と思ってきたが、長旅ゆえの、一所
不在の宿りを続けていると、自分と同じ旅客同士として遊女に出会い、色
里での痴話とは異なる、身の上話を交わすという珍しい経験もする。色事
も艶事もなく遊女といるというのは、得難い経験であることだ。こんなと
ころに旅の面白さはある。

仮にこういう類想句を考えてみよう。
「居合はせし旅の遊女や萩と月」
「旅の舎 ( や ) に遊女居合はす萩と月」
寝たり、と言わなくても、月があるので夜の時間であることはわかる。紀行文の中の俳句なので、当然月を見るのは一晩過ごす旅宿であることもわかる。しかし、仮に詠んだ上の俳句では、意だけは伝わっても、芭蕉の俳句の奥行きはまったくない。
上に述べた思いを、諧謔として「ねたり」という言葉に詠み、その諧謔が、境遇は違っても、浮き草の身過ぎをしている同士が、それぞれの思いで以て、この夜の萩と月を眺めることだ、というしみじみとした情を表現をもたらしている。
ふと、芭蕉の時代からは、遥か後年の三好達治の短詩「雪」の情緒を想起する。
太郎を眠らせ太郎の屋根に雪ふりつむ
次郎を眠らせ次郎の屋根に雪ふりつむ
達治の詩の屋根と雪が、芭蕉の俳句では萩と月である。
芭蕉を、遊女を眠らせるひと夜の宿の屋根の上に、月光は注いでいるのである。

そして「萩と月」の措辞である。「萩に月」あるいは「月に萩」ではないことに注目する。
なびく萩の穂越しに眺める月の美しさ、優美さ、あるいは寂寥感を讃えている吟ではないということを示すだろう。これは両者の対比である。つまり、それぞれに何ごとかを象徴させた詠みぶりである。
「萩」に象徴させたのは、限られた時間を生き、なびき、うつろいゆく運命の、芭蕉自身も遊女も含めた衆生ではないだろうか。たとえば『古事記』ではそういう人間の姿を「青人草」といっている。それと同じ感じ方、見方と言える。
「汝、吾を助けしがごとく、葦原中国にあらゆるうつしき青人草 ( あおひとくさ ) の、苦き瀬に落ちて患ひ、くるしむ時に、助くべし」
「古事記」より
吹きまよふ野風を寒み秋萩のうつりも行くか人の心の
雲林院親王 「古今和歌集」781
「月」はその対照として、俗世の時間の外の、不滅の、恒久の、遥遠の時間を言っている。
月山で芭蕉は、「雲の峯幾つ崩て月の山」と詠んだ。その月もまた、ひとときも休みことなく、生まれ、盛り、形を変え、果ててゆく夏の雲に対して、恒なるものとしてとらえられている。

たとえば、下に引く和歌などは、月に向かいもの思う心を示した典型である。
月見ればちぢに物こそ悲しけれわが身一つの秋にはあらねど
大江千里 「古今和歌集」秋上 193
今はただ強ひて忘るるいにしへを思ひいでよと澄める月影
建礼門院右京大夫集 323番
しかし芭蕉が『奥の細道』の旅で見ている月は、普段の暮らしの中で、住まいにいて眺めている月ではない。漂泊の旅人の見る月である。歩き通した、苦しい行路の一日がどうにか終わり、一日の辛苦から解放される時間が芭蕉の俳句の背景にはある。
私の経験に置き換えてそのことを考えてみたい。
あわただしかった日帰り登山の日の夕暮れ、あるいは人と深い会話を重ねた日が閉じゆく時間、夕空に昇った月を見て、その日の出来事が、いっきょに記憶に中に送り込まれて、ついさっきまでの濃密な時間が霧散してゆくような感覚を覚えたことが一度ならず私にはある。月光には、昂ぶりが生み出した残光を拭ってゆくイレーザー ( 消去器具 ) の機能があると、そんなとき感じたものだ。

芭蕉の「一家に」の前書きに、「今日は親知らず子知らず、犬戻し、駒返しなど云ふ北国一の難所を越えてつかれば」とある。
俳句の中には、難路のことを示す言辞はないが、この前文は、俳句に内包された一体のものに感じられる。厳しい行路を乗り越えてきて、その果てにまた、遊女に頼みごとをされるという思わぬ非日常の出来事があって、何とも彫りの深い一日であったが、月を眺めていると、それもこれも、瞬く間に過ぎた一閃の輝きと思えて来る。
芭蕉の胸中にあるのはそういう思いではないだろうか。
この境地は先に挙げた「雲の峯幾つ崩て月の山」の心情の、変奏曲にも見えて来る。

なお、この市振での一夜については、「曾良にかたれば、書とどめ侍る」と『奥の細道』にはあるが、曽良の随行日記に記述がないことから、創作上での、芭蕉の虚構の設定という説が有力であるように見える。
そうなのかもしれないが、芭蕉が同宿の者に語り掛けられたことのいちいちまでは、些末なこととして曽良が記録しなかったことも考えられる。師の思いの底の底までは、毎日行動を共にする門人といえども読み取ることはできないだろう。
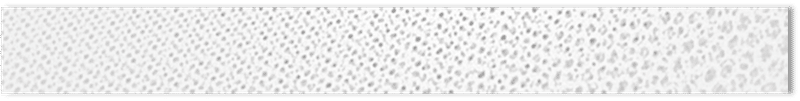
またこうは言えるだろう。遊女でなくとも、江戸の俳諧宗匠暮らしでは出会えない生業の人々と、宿で出会いその声を聞く経験は必ずあったはずだと。
『奥の細道』の旅以前にもさまざまな旅を重ねて、庶民の暮らしを間近に見て来た芭蕉だが、門人を中心に普段付き合う人は、裕福な商家の主人であったり、高位の武士であったり、俳諧師であったり、いわば上層階級の人たちなのだから、違う階級の人たちの言動からは、門人たちとの交際では感じ取れない、世に生きる現実をまざまざと感じ取っていたことだろう。
それが、「一家に遊女もねたり萩と月」の、遊女の苦労の身の上話として収斂されていて、要は力なき衆生に同情を覚えながらも、現実を動かすものとしては無為としか言いようのない俳諧の道を歩む者としての諦観、悪く言えば非情の思いに包まれているところに視点があると考えるのも、この俳句のひとつの読み取り方であろう。
令和6年6月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
