
ワタクシ流☆絵解き館その215 神社で見つけた明治時代の石版画
ある日、某所の神社にある奉納額の絵が、明治時代の石版画だと気づいた。
適切に管理された神社では、通常、奉納額が掲げられているのをまま目にするものだ。
今は衰えつつある習慣であろうが、昭和の戦前頃までは、旅をした氏子が土産に買って来た泥絵や浮世絵版画や稀には油彩画などを奉納する習いがあったという。
中には、氏子自身が描いた絵だったりもするし、またプロの画家に発注して描かせて奉納した場合もあったと記録されている。民俗文化のひとつとして見ると楽しい。
ともあれ、筆者が気づいた石版画を下に掲げる。一点目は、「石山寺秋月」とタイトルがある。二点目はタイトル部分は隠れているが、征韓論争図とすぐわかった。

「石山寺秋月」は額に明治廿拾年十月吉日の奉納とある。これは明治20年10月の吉日という読みになる。明治20年は1887年。2022年現在からは、135年前である。相当に古いものだ。それなのに石版画の色彩の残り具合から、いい質のものであることがわかる。しかし、調べてみた限りでは、作者がわからない。近江石山寺と月の組み合わせは、伝統的画題だ。
では明治20年がどういう時代かを見よう。日本と清国の間で行われた日清戦争が、1894年(明治27年)7月25日から1895年(明治28年)4月17日にかけてである。その戦争の7年も前である。当時石版画を売っていた処としては、最も可能性が高いのは、東京。さらに商都大阪か。
筆者の住む田舎町の神社の氏子となれば、明治20年当時の旅とは、ごく普通に考えれば、商売や丁稚奉公で行った旅としか思えない。
と考えれば、東京か、当時から船での行商先だった大阪だろう。故郷を出た一族の誰かが、里帰りで持ち帰ったことも考えらえれる。
奉納し、百年をはるかに超える今日まで伝わっているのは、石版画が、珍しく値の張るものという意識が、初めにあったからだろう。
明治時代の絵を見られる場所は、現在では、美術館、博物館になるから、何のもったいもつけず飾ってあるのを見れば、もうそろそろ貴重文化財として色褪せないようにすべきでは、という気持ちになる。
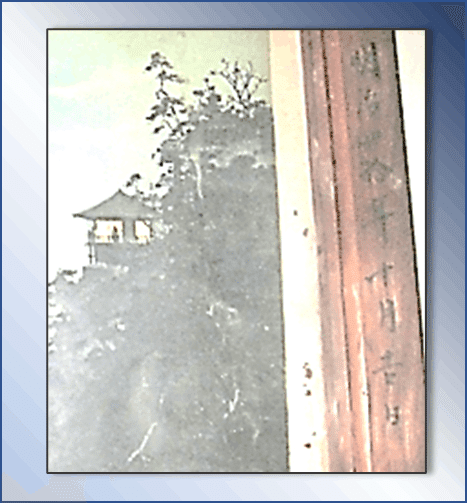
もう一点の征韓論争図。調べてみると、町田信次郎の「征韓論争 明治六年西郷江藤板垣等岩倉大久保木戸等と朝鮮を討たんことを議す」(明治37年)という石版画だった。
下に掲げた一枚目が奉納されているもの。フラッシュが写りこんだのは、ご容赦のほどを。二枚目以下が、「教育歴史画/第三輯の十一」の図版。同じ絵柄である。
石版画の奉納時期はわからないが、日露戦争終結が明治38年、韓国併合が明治43年の出来事なので、その当時と思われる。朝鮮半島から大陸へ勢力を張ろうとしていた時代の気分に沿ったものだろう。




町田信次郎は、歴史画を描いた石版画家。信次郎の別の作品を下に掲げる。日本各地、雛の町々には、町田信次郎の石版画が奉納してあるかもしれない。
note執筆者で、各地の田舎を巡っておられる方は、ぜひ気に止めておいてください。

令和4年12月 瀬戸風 凪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
