
【トークイベント】コロナと真実:「自粛」で見えてきた世界(6月27日)
ポスト研究会第7弾は、科学史家の塚原東吾さん、脳神経内科医師で医療社会学者の美馬達哉さん、感染症対策史研究の野坂しおりさんをお迎えして、美馬さんの近刊『感染症社会 アフターコロナの生政治』(人文書院)を囲みながら「コロナと真実:「自粛」で見えてきた世界」について討議しました。
ぽすけん企画 第7弾 トークイベント
「コロナと真実:「自粛」で見えてきた世界」
出演者:塚原東吾×美馬達哉×野坂しおり(司会・高原太一)
日時:2020年6月27日(土) 18:00〜20:00
場所:zoom(参加費500円)
【出演者プロフィール】

塚原東吾(つかはら・とうご)
神戸大学国際文化教授。専門は科学史。江戸時代の蘭学からオランダサッカー、原爆、水俣、フクシマにも関心があり、いうならば「蘭学者(なう)」。『反東京オリンピック宣言』にも寄稿していて、ナオミ・クラインの災害資本主義と「ノーマルシー(平常性)バイアス」をネタにしている。ポスト・ノーマル・サイエンスを提唱してきたので、ニュー・ノーマルには抵抗感がある。ポス研ではポストコロナ時代のノーマルとは何かを問い直してみたい。

美馬達哉(みま・たつや)
立命館大学先端総合学術研究科教授/脳神経内科医師。難病を扱う脳神経内科の臨床と共に、医療や生存に関わる人文学的研究を行う。研究は手広く、ウイルスからグローバリゼーションまで。フーコー論は『生を治める術としての近代医療』(現代書館、2015年)、リスク学は『リスク化される身体』(青土社、2012年)でいったんまとめて、次のテーマを模索中。コロナについては『感染症社会』(人文書院、2020年)。

野坂しおり(のさか・しおり)
フランス社会科学高等研究院博士課程在籍。専門は19世紀後半〜20世紀初頭の感染症対策史、細菌学研究史。科学技術が医療を通じて人間の身体や微生物に働きかけてきた過程、またその政治性に興味がある。同時に、現代の近代科学、環境問題、社会的不平等について考える可能性を模索中。翻訳書に『人新世とは何か』青土社(2018年)、論考に「人新世は誰のものか;環境危機をめぐる対話と合意の政治性」(『地質学史懇話会会報』、2020年)。

高原太一(たかはら・たいち)
東京外国語大学博士後期課程在籍。専門は砂川闘争を中心とする日本近現代史。基地やダム、高度経済成長期の開発によって「先祖伝来の土地」や生業を失った人びとの歴史を掘っている。「自粛」期間にジモトを歩いた記録を「ぽすけん」Noteで連載中(「ちいたら散歩 コロナ自粛下のジモトを歩く」)。論文に「『砂川問題』の同時代史―歴史教育家、高橋磌一の経験を中心に」(東京外国語大学海外事情研究所, Quadrante, No.21, 2019)。
【トークテーマ】
コロナ禍と呼ばれ、「自粛」が余儀なくされるなか、私たちはこれまで意識することがなかった、あるいは目にすることが少なかった(かも知れない)存在や仕組みに注意を払いはじめた。エッセンシャル・ワーカー、外国人技能実習生、ネットカフェ難民や夜の街、または医療崩壊、社会距離、家賃など、一見バラバラに立ち現れた存在や現象は、同時に私たちに「問い」としても迫ってくる。
自分だけが助かればいいのか(Uber Eatsを活用しながら)、この数値は「正しい」のか(テレビで報道される感染者数を眺めながら)、この国の政治はどうなってるんだ(届かない10万円と届いたアベノマスクを前に)。問いのレベルも、さまざまである。
今回のトークでは、コロナという出来事/危機を「歴史的」アプローチによって検証してゆく。バラバラに見える現象や問題に、連関性や同時代性を与えながら、問題の本質に迫っていきたいからである。
捉えたいのは同時代的なヨコの関係性だけではない。時空間を飛び越えて、過去の出来事、例えばペストやSARS、原発事故との関係性を見出しながら、私たち自身の存在自体も問われているかも知れない<いま・ここ>の危機=「自粛」で見えてきた世界を根源的に批判していく。
その一歩となる踏み台を、『感染症社会 アフターコロナの生政治』を近刊予定の美馬達哉さん、「コロナから発される問い」(現代思想 緊急特集「感染/パンデミック」所収)の筆者である塚原東吾さん、パリ在住で『人新世とは何か』の訳者でもある野坂しおりさんという3人の論者と共に作り上げていければと思う。司会は、民衆史研究者で「ちいたら散歩 コロナ自粛下のジモトを歩く」を連載中(ぽすけんnote)の高原太一です。
ーーー以下、トークの記録ーーー
<はじめに:コロンブス的交換とは?>

高原:本日の司会をつとめます高原太一です。東京外国語大学大学院で砂川闘争について研究しています、歴史研究者です。まずは本日の出発点となる本を紹介したく思います。2020年5月に発行された雑誌「現代思想」の緊急特集「感染/パンデミック」。

ここに本日お話頂きます、塚原東吾さんと美馬達哉さん、そして塚原さんの論考で引用されている野坂しおりさんが紙面上で一堂に会しています。ただし、今日は塚原さんが岡山、美馬さんが京都、野坂さんはパリ、私は川崎と昔風にいうなら四元放送で話をすすめていきます。
お一人お一人の紹介は短めになりますが、塚原さんは「現代の蘭学者」ということで、本日は科学史の視点からこのコロナという病いを病いたらしめているものはなにかについてお話し頂きます。美馬さんは脳神経内科の医師としてご活躍されながら、医療社会学の研究者でもあります。本日は美馬さんの近刊『感染症社会 アフターコロナの生政治』(人文書院、2020年7月出版予定)をご紹介頂きながら、私たちが向き合っている状況や世界をどのような枠組みで捉えればいいのかについてご提起頂きます。

そして、サマータイムで7時間の時差があるパリからご出演の野坂さんからは、パリにおいてどのようなコロナ禍の日常を過ごしたのか、そこで見えてきた問題はなんであるのかを野坂さんが訳された『人新世とは何か <地球と人類の時代>の思想史』(青土社、2018)の議論も参照して頂きながら論じるという予定です。
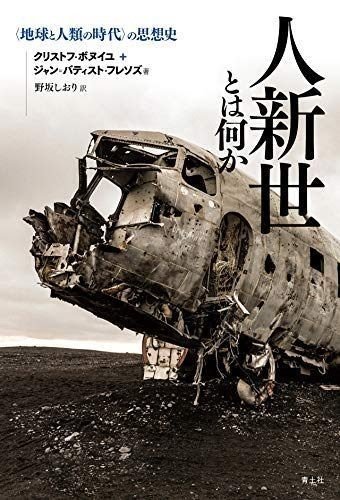
議論の取っ掛りとしては、まず塚原さんに「現代思想」に寄稿された「コロナから発される問い」についてお話頂きます。
今日(2020年6月27日)は、東京でも感染者がまた50人を超える状況で、一旦落ち着いたかと思えば、またぶり返しているような状況ですが、このCovid-19というウイルスは、いかなる「病い」なのか。それについて3人の論者が、歴史的アプローチを取りながら分析していくのが本日の課題となりそうです。
進行としては、1時間を経過したところで、すこし休憩を挟みまして、その間に美馬さんの新著『感染症社会』の目次をzoom画面で共有したいと思います。そのため、前半は先ほどから述べています塚原さんの論考を中心に、後半は美馬さんの新著を囲みながらという形で討議したいと思います。それでは、塚原さん、まずは今回の「コロナ禍」という状況に直面して、どのようなことをお考えになったのか教えて頂ければと思います。

塚原:このトークにお招き頂き、そしてご参加ありがとうございます。神戸大学の塚原です。初めましてよろしくお願いします。「ぽすけん」というのは小笠原博毅さんや山本敦久さんがやっているのは知ってましたけど、コロナというテーマでお座敷がかかりました。このことはちょっと色々考えるべきことがある。そこで何を考えたかと言うと「現代思想」の感染/パンデミック(実質はコロナ)特集に原稿を書いたときに、これは病気で、でも単なるウイルスが広がって人間が病んでいく生物医学的なものだけじゃないということが基本的な問いです。これを人間とウイルスの戦争だといって戦力を全面投入して町を閉鎖しろとか、本当にそうなのかとか、いろんな事が考えられる。専門家会議さえ、フッとなくなった。何が起こっているのだろう? そういうことを考える時に、医学だけじゃなく、社会、人文の知が必要なんじゃないか。我々の経験や過去の事例を丁寧に見ていかなければならない。
ここから少し飛ぶんですけど時間的・空間的に長く大きいスケールで、感染症を見て考える時に、僕たちはどういう時代、社会に生きてて、人間同士、もしくは動物と人間の関係を考えていかないといけない。僕は科学史が専門で、そこでスタンダードな理解となっているのは、アーノルドという人がいってる「コロンブス的交換」という概念です。そもそも病気というのは社会が変わる時に起こる。これは、コロンブスがアメリカ大陸を発見したというけど、支配の歴史であったり植民地や黒人奴隷のこと、そしてなんでインカ帝国やマヤ・アステカ文明というのが滅びたかと言うと、病気というのが大きな要因だったと言われています。トマトにせよジャガイモにせよ食品であっても、国民カルチャーにおけるイタリア料理のトマトはイタリアの原産ではない。南米大陸から持ってきたものです。朝鮮半島のキムチだって、コロンブス以前に唐辛子はなかった。すでにこのことは定説となっているんですけど、コロンブスが動物・植物そして細菌やウイルスを交換してきた大きな流れがある。コロナは二一世紀のコロンブス的交換の現れではないか、というのが1個目のテーゼです。
このコロンブスって誰の船できたのか、だれのお金で、グローバル時代のいま一時代のインフラを考えることが必要だ。あれ俺固まってる? 大丈夫?(ズームのトラブルによる)。要するにこの疾病は新たな人新世のパンデミックではなかろうか。そこで考えないといけないのは医学の知性もウイルスとの「戦争」に勝つという、そういうストーリーだけでいいのだろうかということです。
そこで思い浮かんだのは、実はさっき、司会の太一くんが紹介してくれた『人新世とは何か』です。そういう全く新しい概念が満載で、この本の翻訳は野坂しおりさんにお願いした。それで、「現代思想」のコロナ特集の後半はだいぶ野坂さんから入れ知恵してもらって、ブルーノ・ラトゥールやフーコーの薫陶を受けたフランスの科学史家、科学論者は何を言っているのかを教えてもらった。だいぶいろいろ情報を野坂さんからもらって、それでディスカッションしながらまとめた論考です。
そこでのまとめは、コロナは新たな環境変容のなかで生まれてきた疾病ではないかということです。この締切は(2020年)4月3日だったので、状況は進行中だったのですが、その状況のなかで科学史とか医学史とかに関係する人間は、この点、つまりコロナは人新世の疾病だということは言うべきかなと、小さな論考をつくったということです。これを提起として受け取って頂いて、ありがとうございます。
高原:いきなり本日の核心にあたるところをズバリとご指摘下さいました。もう一度、塚原さんの論点を整理しますと、1つめとして「コロンブス的交換」がコロナを含む感染症の根幹にある問題だと。そして、世界的な感染症の流行自体はコロンブスの時代に始まり、世界史において何度も巻き起こってきた出来事なんだけれども、このCovid-19について言えば、それは「コロンブス的交換の二一世紀的な新局面」という問題が加わっている。そして、二一世紀のコロンブス的交換という視点からコロナ禍を見直したとき、そこには国民国家への批判が内在されており、帝国主義や植民地主義、あるいはポスト・コロニアルの問題を避けて通ることは出来ないだろう、こういうことですね。
2つめとして、二一世紀的コロンブス的交換を考えるさいに欠かせない概念が「人新世」(じんしんせい)である。この概念がどのようなものであるかは、後ほど野坂さんからも説明があると思いますが、これは今日のキーワードの一つですよね。塚原さんの見立てによれば、このCovid-19というのは「人新世における疾病/パンデミック」なんだと捉えられている。それゆえ、今日のお話はコロナ/感染症だけでなく、いま取り沙汰されている環境問題、これについても論及せざる得ないことが分かりました。
このように、塚原さんからまず本日の議論の大きな見取り図を描いてもらったと思いますが、もう少し現状にも分け入りながら分析を進めていきたいと思います。野坂さん、先ほどの塚原さんのお話でも、また「現代思想」の特集においても、フランス系の哲学者や思想家が寄稿していますが、なぜフランス系であるのかは問うてもよい点だと思います。そこには、ある種の必然性というか、フランスやパリという都市自体が感染症/パンデミックにおいて象徴するものがあるのではないかと思います。
そこで、野坂さんからまずはこの間パリではなにが起きていたのか。日本の「自粛」とは様相が異なるロック・ダウンが実際どのようなものであったのか。そして、この間にどのような問題が見えてきたのか、あるいは見えてしまったのか、お話頂ければと思います。
<パリからの報告>
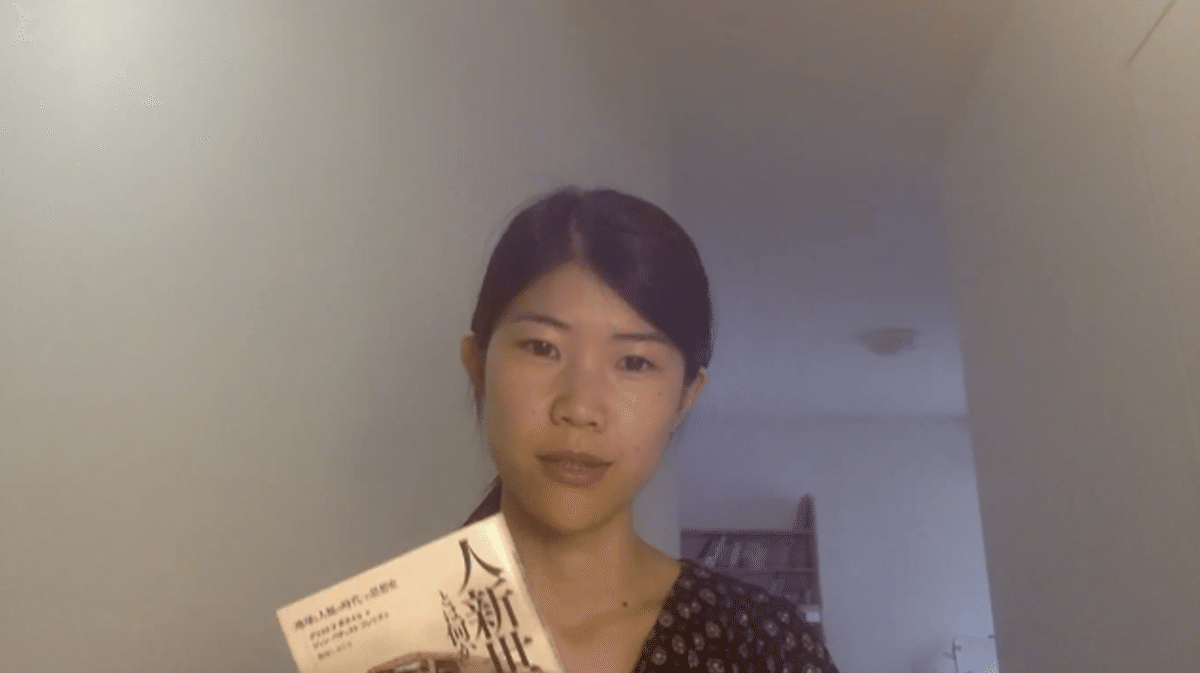
野坂:野坂です、よろしくおねがいします。私の観点としては、今パリに住んでいることから、Covid-19の感染拡大が始まる前からロックダウンに至るまで、そしてそこから今ロックダウンが解除されたフランスの状況について私の経験からお話したいと思います。
フランスの状況としては、中国でcovidが感染が拡大してロックダウンが始まった、という段階において、フランスでは対策が必要だ、水際対策が必要だと言われていましたが、一般的な感覚としてはまさかフランスにはこないだろうと、もちろんそれに関して警告を出している人はいたけれども、基本的には友達と会話してるときとかでも、まさかフランスにはこないだろうと多数の人が考えているという状況がまずありました。それが2月の段階で、いつごろだったかな、3月はじめくらいにマクロンが専門者会議を招集してコロナに対する対策の議論をはじめる。でも真剣には捉えられていなくて。マクロン政権がそこでメインに行った会議は年金対策でした。フランスでは当時、年金制度改革に対する批判とストライキが起きていたんですね、凄く。だからそのことをメインに会話をしていた。コロナの会議を使って年金改革の会議をしていたんです。だからコロナへの危機感は感じていなかった。
それが、イタリアでまず感染者数が増えてきて、3月10日くらいからフランスでも爆発的に感染者数が増えてきた。その段階で、3月17日からフランスはロックダウンということで、基本的に外出禁止になった。テレワークの推奨と、不要不急の外出意外は全部禁止で外出許可証というものがないと買い物にもいけない状況が5月10日まで続いた。その時に言われていたロジックが、ステイホーム。家にいることは私たちができる命を救うことだ、という言説が説得力を持つ。これは日本でも言われていたと思うけど、そういう状況があった。
フランスでは、結果として現段階(6月27日)の死者数が、3万人弱という結構多い数字になっているんですね。なので一時は医療崩壊がすごく目立っていて、患者がいても、医療施設が受け入れられないくらいだった。そこで始まった社会運動として、夜の8時になるとみんながベランダにでて医療従事者の人たちに拍手をするという状況がありました。そのなかでお医者さんや看護師だったり、医療従事者の人たちへの称賛の声がすごいあった。一方でエッセンシャルワーカーの人たち、スーパーでレジを打っている人だとか、掃除をする人だとか、そういう人たちへの視線もものすごく集まったんですね。普段は収入も少なくて、ほぼ目が向けられない人たちです。ゴミ収集をする人だとか、介護をする人、スーパーでレジに居る人たちっていうのが、このパンデミックを通じて私たちの生活に不可欠だということが明らかになった。だって彼らがいないと生活がまわらないから。ゴミが収集されないと不衛生な状況で生活することになるし。でも彼らは仕事をすることで感染リスクにさらされてしまう。中でも特に指摘されたのがエッセンシャルワーカーには移民系がとても多いということ。そこで問題になってくるのが、コロナだけじゃなくて、フランスに元々あった社会問題。人種差別だったり、表立ったりしてなくても、収入が少なくて社会から脚光を浴びないけど不可欠な存在としてのエッセンシャルワーカーは、移民系の人たちが多いということを可視化してきた。
高原:移民系というのは具体的にはどういう地域からの人が多いですか? そこに「人種」的な要素を見出すことは出来ますか?
野坂:基本的にはアフリカ系の黒人の人たちが多い。アラブ系、アジア系も多い。でも黒人系の人たちが多い、個人的な経験からいうと。私、一度だけロックダウン中に電車に乗ったんですね。その時に、誰がこのロックダウンの状況の中で電車に乗っているんだろうって電車の中を見回すと、黒人の人たちばっかりでした。私が住んでいるところが郊外ということもあるけれど、パリ郊外から市内に電車で出ていく人たちは黒人の人たち。着飾ってるわけでもなく、清掃業だったり警備業の人たちが仕事に行くために電車に乗っているという印象を受けました。
高原:なるほど。すこしフランスにおける移民の歴史を簡単に振り返りたいのですが、一般的にフランスにおける移民というのは、旧植民地やいまなお現存するフランスの海外領からが多いのか、その辺を教えて頂けますか。
野坂:旧植民地からの人が多いですね。フランスの植民地の歴史研究者によれば、アメリカでは三角貿易で連れてこられた人たちが多いのに対して、フランスでは、本国から離れた植民地で奴隷たちが使われていた。よって、植民地時代にフランスにつれてこられた人もいるけど、それ以外に脱植民地化したあとに自分たちで稼ぎに来た人たちもいる。このことが影響して、現代的な人種差別の扱い方の、若干のニュアンスがかわってくる。フランスで国として、人種とか旧植民地っていう言い方が好まれない所以です。
高原:フランス国旗の下では1つですもんね。
野坂:旧植民地からフランスに来た人たちの中には、自分たちの意思で経済的な出稼ぎのために来たっていう人たちも多かったりするので、そこで色んな意味合いはでてきますけど、基本的には旧植民地の負の遺産を持った人が多く移民系と呼ばれています。
高原:そうですか。この人種の問題も、先ほど塚原さんからご提起頂いた二一世紀的コロンブス的交換における人の流れだと思うのですが、この点については美馬さんもご著書のなかでコロンブス的交換についてのお話しがあったかと思います(第一章「感染症という妖怪」所収、「二一世紀のコロンブス的交換?」)。まずは、そのあたりを切り口に、ご著書についてもご紹介頂けますか。
<生態系という観点>

美馬:みなさん初めまして、美馬です。お二人のお話を聞きながら考えていたのですが、いまから3つのことを言いますね。
1つは21世紀のコロンブス的交換という時に、生態系という考え方を拡張するというか、本気で考えないといけないという点です。要するに、コロンブス時代のコロンブス的交換では、ヨーロッパ人が周囲の環境ごと新大陸にいくところが重要なわけです。羊をつれていって、そのへんの草をくいちらかすとか羊が食べやすい草を増やすとか、自分たちが食べ慣れた食べ物である小麦を栽培するとか、自分たちの慣れ親しんだ病原体も一緒にいってしまうとか。そうすると新大陸側での受け止めるインパクトは巨大なものになります。自然環境や景観まで変わってしまうわけです。さらに、麻疹や天然痘で人口の過半数や大多数が死滅することも起きる。つまり、交換されたものは、生態系そのものだったわけです。
今回の新型コロナウイルス感染症での特徴はそこに関わる新しさです。たとえば、クラスター発生ということが言われています。日本政府は夜の街うんぬんと言っているわけですが、見込み捜査ではなく数字を客観的に見れば、経路不明つまり昼の街でも広がっていることは明らかですし、初期には医療現場でのクラスターのほうが圧倒的に多かったですね。医療現場で広がるということを理解する鍵が、生態系という考え方です。つまり、近代医療によって人間が人間の身体内部つまり人間的自然に直接触れるようになったことで、体内のウイルスと病院環境との生態学的に一体化したのです。人工呼吸器で喉の奥にまでチューブを入れたり、痰を出しやすくするため霧のような薬物をすわせるネブライザーなどはその極端な例です。また、もっと一般的には医療のケアでは三密を避けられないし、防護措置が不十分だと医療従事者を介して感染が拡大するというパターンです。医師は複数の病院を掛け持ちすることが多いし、複数の病院にかかる患者もいる、そうやって病院から病院へ拡大していくわけです。2003年のSARSでは、そうやって拡大しました。今回の新型コロナでも同じようなことが起きていた可能性は高いです。
これは、コロンブスの時代とは異なる21世紀のコロンブス的交換の特徴とみていいと思います。たとえば、20世紀末のエイズがそうなんですね。血液を介して感染するので、輸血という医療技術で人間の体内環境に直接アクセスする技術ができたことで拡大しました。あとは、日本では社会運動や裁判でも有名になったB型肝炎やC型肝炎です。これは注射針とくに予防接種などで使い回しがあったことが感染拡大につながっています。人新世を地球全体での地質学的な変化としてみるだけではなく、人間の内部環境へのアクセスというミクロ面でも新たなステージだったとみることができると考えています。
もう1つは、さっきエッセンシャルワーカーの話が出ましたように、テレワーク不可能な仕事の存在が浮き彫りになったことです。それは労働集約性が高い部門や人間の対面的労働サービスで合理化が難しかった分野です。医療介護はもちろんですし、ヨーロッパでは食肉工場なども感染拡大の場になっています。日本は医療介護はまだ移民労働化あまりしていませんが、世界的には、低賃金の移民労働によって支えられている部門です。デジタル資本主義とか情報社会といくらきれい事を言っても、三密はなくならないことがはっきりした。そのなかで、テレワークできる人びとと、リアル三密労働し続けないといけなかったり、仕事がなく経済的に破綻する人びととの差も明確化した。このあたりが、野坂さんの話で重要な点だと思います。
それで三つ目は、前に言った二つの点と関わるのですが、三密は人間の条件であり、それが19〜20世紀的な近代化によって作られたタイプの三密がウイルスにとって絶好の増殖環境になったというところです。三密しないと生きていけない存在である人びとが社会にはいる。体の弱った高齢者とか認知症の重度の人、重度の介護の必要な障害者など、介護者が密着して食事介助しないと餓死しかねないわけです。フランスなどヨーロッパ諸国では、病院だけでなく介護施設でも大量死が起きました。ただ、ここで意識しないといけないのは、そうした弱者を社会からの逸脱者として、社会から排除しながら、一つの場所に集めて住まわせている施設収容というやり方が問われているということです。似たような病状を人を集めてまとめてケアすることは合理的です。でもそれは、たんに生き物を管理するという点では合理的というだけで、人間との関わり方として見れば、どうなのでしょうか。
高齢者の施設でウイルスによる大量死が起きた事実は、やまゆり園での障害者大量殺人ともつながって見えます。銃ならばともかく、たかが刃物で大量殺人できたのは、施設収容という背景があったからこそです。
高原:ありがとうございます。いまの美馬さんからの提起を受けて、またはフランスの野坂さんからのレポートを受けて、塚原さん、改めてコロンブス的交換について戻った時いかがですか?
<ポスト「病院化する社会」のテクノロジーと交換>
塚原:美馬さんのご指摘、丁寧に整理していただいと思います。コロンブス的なものと考えるというのは、広い意味でのインフラストラクチャーのことを検証する必要があるということだと思う。
美馬さんの述べたことに付け加えると、僕らの世代で、若い頃に流行ったイヴァン・イリッチは、これを「病院化する社会」と言ってます。ケアとか人間の自然治癒力というものを病院にあずけてしまったのではなかろうか、近代社会の名の下に我々は、伝統医療だったり受け継がれた知だったりをかなぐり捨てて、病院という近代社会を強制的に導入したのではないか。イリッチは、文明論的批判であり、そこにはさらにもう1つ、コマーシャリズムに対する批判、政治に対する批判、それは医療が近代合理性を体現するもので、これがいいのだということで医者に対して人体に介入する権限を独占化させたということに対する批判があった。
これは日本で明治になると、医学部を出た人だけが人体への介入の許可を与えられ、それに準ずる法制度が出来てきた。いまや、先ほど美馬さんが仰ったように身体に介入するテクノロジーが作られてきた。そして、これを支えるのは、幸か不幸か日本の場合は国民皆保険制度というのがある。これは必要だし、いい制度なんです。弱者のための制度だから。病院化しているから、必ずいかんとは言わないけれども、あるせめぎ合いの場になっている。
そういった形で地球上の広い地域で、病院化、医療の合理性主張が人口を包み込むようになってきてしまった。これはイヴァン・イリッチは70年代にこれを批判していたのです。この状況は加速していて、2010年代が終わりかけた頃に、より美馬さんがいっていた2番め、ケアの囲い込みみたいなものもどんどん進んできていて、これがコロナなどの流行の際、もっともヴァルネラブルな(傷づきやすい)ポイントになっている。
あと階級の問題もありますけど、本当はジェンダー、クラス、レースという微妙なひだがある。新自由主義的なアメリカのスタイルでは、国民皆保険が愁眉な課題である。ヨーロッパのように社民の政策が1980年代にはなんとかもっていて、その名残で生きてたわけですけど、それがこのコロナでどう持ちこたえるか。こういうところが新しい局面だと思っています。厳しいところです。
いま(チャットのコメントで)やまゆり事件のことを仰いましたけれど、たしかに弱者を集中化させることは必要なことである。これをどう考えるか。いわゆる発達補償論みたいな感じで、ケアを制度化していく努力は延々とされていた。ある意味で、近代的病院化を民主的にやろうという方向の努力で、ネオリベに抗う良心的な方策です。でもやはりそれは本当にそこだけでいいのかというところは考えなきゃいけない。これは21世紀で、「人新世」のエフェクトにより災害が増えるだろうし、国際的な流通への依存度は下げていかないといけないという時代に、資源大量消費型の近代医療システム、福祉国家型のケアの制度を、どう考えたら良いかということが課題として挙げられるのではないかと思っている。これは近代医療システムへの深い部分での疑義であり、伝統医療や在来型のケアへのまなざしであって、これを具体化するというのは、かなり難しいかも知れません。ですが、少なくともネオリベ的な再編とは一線を画しながら進めないといけないことだと考えているので、なかなか舵取りの難しい政策的課題となってくると思います。
あともう一つ、テクノロジーの問題があります。美馬さんが身体への医療的介入が深くなっていると仰っていましたが、たとえばネブライザーや粘膜への介入と言いましょうか、皮膚の下に入っていく技術です。さらにこの近年の医療テクノロジ―は、情報テクノロジーて合体してよりパワーアップしています。つまり、人体についての情報を、より広く、より深くカバーして、モニターすることが出来る。24時間モニターすることは簡単になっている。病院に行ったら機械をいっぱい繋げられてチューブだらけになることを「スパゲティ状態」と言われたりする。
そして、コロナの抑制で明らかになったことは、このようなモニターリングがある種の成功例と考えられている。コロナ患者を「追う」とか、行動を記録・監視するとか、通常のことになったと言える。そして、そのことで大規模な発生が抑えられた(ように見える)のです。監視社会の肯定というのが、コロナで一気に進んでいる。このことには危機感を覚えます。コロナそのものよりもはるかに恐ろしい。
いまのテクノロジーのレベルを考えれば、「つながった」ら、もうそこからは簡単な話です。時計1個つけて、ここで心拍数・血圧・体温測ってこれを携帯電話で、すべてモニターして、これで僕の携帯(スマホ)が全部ビッグデータを撮る社会になっちゃう。こうなったら、もうSFではない、それが具体的な現実なのです。中国ではそんなことも含めて、人間のからだそのものがテクノロジーの介入を受け、それがさらに電子ネットワークで、アルゴリズムを操作される可能性をもつ。
英語で電子的にネットワークにつながることをコネクテッドとか、ウェブに入ったとか言いますが、ワイアード(wired)という表現もある。ワイアーとは、電子のゲーブル、電線のことですが、細い針金、ハガネの線です。ちなみに鉄条網、あのトゲトゲでチクチクするやつはバーブド・ワイアーといいます。ですから、電子的なネットワークにつながるのは、どうにもハガネのワイアーで縛り上げられているような気がしてならない。それももしかしたら1960年代の感性の残滓がある、私の世代だからかも知れませんが。
こういう時代に生きているときのコロナの現象のインフラは「人新世」でしょう。ぽくの人新世という概念はデカ過ぎかなと思うけど、そのくらいの時代の転換と変容について考え、コロナというものをもう1回向き合っていくというのは必要だと思う。というようなのが、美馬さんへの付け足しです。
高原:塚原さん、ありがとうございます。とくに最後の人新世における「つながり」の話しは肝が冷えるような現実ですが、ここで美馬さんに少しお伺いしたいと思います。コロンブス的交換のときは、まさしく生態系とか生物との交換という言葉がふさわしかったと思うのですが、先ほど塚原さんがおっしゃったように、身体に直接介入するテクノロジーや監視社会、あるいは検温の時代でも、生態系という自然をイメージさせる言葉は有効ですか? あわせて、コロンブス的交換と二一世紀的のそれとの違いについてもう少し知りたいのですが。
美馬:生態系という言葉は、生物としての人間という面が強調されるので、生態系でいいんじゃないかと思います。生物とか物質としての人間と、主体ないし法的主体としての人間との前者に軸足を置いて考えていこうということです。監視社会や監視文化というときに、情報やデータとしての人間やプライバシーの権利という抽象的な話にいってしまいがちなので、そこで生物や具体的な物質としての人間、社会や自然のネットワークの中の人間というハブみたいな視点を忘れないようにしましょう、といいたいわけです。
くりかえしますが、20世紀までの近代社会の一つの特徴は、塚原さんの話にもあったとおりで、異物とされたマイノリティを施設に大量収容することで均質な括弧付き「近代市民社会」を安定させたところです。子どもは学校、高齢者は介護施設、肉体労働者は工場、病人は病院、障害者はコロニーのような考え方です。それは、近代的な効率化だったのですが、その限界がコロナウイルスでものすごくはっきり見えています。もちろん、20世紀末から、医療介護関連で言えば、地域包括医療のように施設への大量収容を見直して在宅中心にという方向はでてきていたのですが、それが加速されていくでしょう。
そのときに核になるのは、いい面も悪い面も含めてIT技術やモバイル技術になります。スマホのようなモバイル機器による監視ですね。今日はそこの話はいかないですが、本のほうでは基本的な図式を提出してます。ただ一点だけいうと、日本でも出てきているコロナウイルス監視アプリは、グーグルとアップルの協力でできたプラットホーム上で動いているはずです。これは、塚原さんも指摘されていた国民国家の役割の変化と関わっています。つまり、一国内で作ったように見せかけていますが、実際にはグローバル企業が蓄積したものをベースにしてるので、国家はグローバル企業の許可を得なければ何もできないわけです。
高原:なるほど。本日の美馬さんのズーム背景となっているパノプティコンが壊れかけている時代とも言えるかも知れませんね。
<「みんな」とは誰か?>
高原:ここで、一つ気になったニュースを紹介します。最近のビッグデータをフル活用したコロナ対策がニュースで語られるときに「みんなの技術」とか、この「技術はみんなに役立ちます」みたいな物言いがされるのを目にしました(“ビッグデータ”でコロナと闘う)。
しかし、「みんな」という言葉が使われるときに気をつけなければいけないのが、その「みんな」には意識的・無意識的に含まれない人が出てくることです。例えば、日本の首相は「国難」と連発して「みんな」を「日本国民」にすり替え、国民国家としての統合を図ろうとするのが見て取れるのですが、例えばフランスにおいても、そのような言説が見られるのか。そのあたりについて、野坂さんからフランスでの「みんな」のありかたや、その「みんな」が誰を包摂し排除していると考えられるのか教えてもらえますか。
野坂:フランスの文脈でいうと、共和制という理念はものすごく強いです。共和制のもとにはみんな一緒だから、ジェンダーもなくレースもない、クラスはあるかもしれないけど。少なくともレースはない。Covid-19の感染者数をみるとき、例えばフランスではアメリカでされているような人種別の統計は絶対とらないんですね。それは人種は「存在しない」から、なんですけども。フランスの共和制なりにいうと。そういった「みんな」の考え方は、私が翻訳した『人新世とは何か』(青土社、2018)の主張につながる。著者のフレソズとボヌイユが特に批判していることが、本の中では基本的に環境危機の話なんですけれども、環境危機があって、それに対して私たち人類がいるという考え方。人類対地球、人類対自然、という構図をもとに、人類がこの危機を救わなわなければならない、という言説が出てくる。著者たちが批判しているのが、いやそうじゃないでしょ、人類といっても環境破壊をもたらした人類はほんの一握りの人たちで、いまも森の中で生活してる人とか集団住宅で暮らす低所得の人とか、いわゆる環境負荷をほぼ出さない人たちは、自然破壊の責任を負うべきなのかっていう点。それをものすごく批判しているんですね。
今回のコロナの件でもそうですけど、仮想敵みたいなものが想定されると、じゃあその仮想敵に対する我々って誰なんだって話は絶対にでてくるんですね。美馬先生がおっしゃられたように近代という時代の批判もこの本(『人新世とは何か』)でされていますが、生物としての人間ではなくていかに文化としての人間というイメージを作り上げ、近代技術を使って自然を支配して、いかに自分たちの文化圏をつくりあげたのか、ということがポイントになる。弱者であったり、逸脱者に対しては、囲い込んで、近代の空間には入り込めないようにする。そういうなかで近代は成立してきた。その結果としてこの人新世という状況がおきている。生物としての人間、自然というものは(文化圏の中に)絶対にあって、コントロール出来ない面も絶対にあるのだけど、それをコントロールしてしまう。この本のなかでは脱抑制という言葉を使って説明しているんですが、いかにリスクがあったり、危険や自然災害があったり、パンデミックがあっても、それに対して抑制をかける。ワクチンを開発したり、あるいは森林に入っていけば、マラリアにかかる。蚊が襲ってくると、それに対して対策をして、近代のプロジェクトを進めてきた。その結果として環境問題が起こるほどの社会になってしまったということが述べられているんですね。
なので、我々というのは誰のことなのか。環境汚染を進めてきた、科学産業を進めてきた人たちは誰かっていう話につながって。ここでひとつまた宣伝させていただくと、私が最近書いた論考があって、そこでフランス語で出版された本なんですけども、デコロニアル・エコロジーっていう本(Seuil, 2019)に触れています。これに関しては、これも人新世の話なんですけど、そのなかで抑圧されてきた人たち、すなわち黒人の人達だったり、移民系の人たちあるいは、女性だったりっていう存在がどう政治ができるかって話をしているんですけれども、ポイントになってくるのは、人新世を生み出した近代社会の根っこは、この著者にとっては植民地主義ということです。
というのも植民地主義のなかでは、さきほど美馬先生がおっしゃったように、いかに例えば白人以外の奴隷を使って、囲い込んで、合理的にプランテーションするのか、そのなかでいかに経済的利をもたらすのか、ということに焦点があてられていて。たとえばフランス本土では人権って話がでてきたりとか共和制をつくりこんで「我々」の文化圏というものをつくりあげるんですけども、その外にはその文化圏を支える植民地があると。植民地の人たちは「我々」のなかには組み込まれない。その構造が今日まで続いてきたから、環境問題でも旧植民地に出自を持つ人たちがまず被害を受けて、パンデミックでいえば、彼らがケアワーカーになったりっていう状況がある。それは旧植民地の人たちだけじゃなく、いろいろな条件で囲い込まれる弱者たちがいる、その根っこに植民地主義がある、というのがマルコム・フェルディナンっていう人(デコロニアル・エコロジーの著者)が言ってることです。
高原:いまの野坂さんの話と、先ほどの塚原さん、美馬さんの話を統合して考えたときに、近代が生み出してきた問題の1つの答えとして、いま流行りの言葉でいえば「正解」として病院が誕生したと。病院においては、内と外をはっきり峻別すること、それは空間的にだけでなく、主体においても患者とそれ以外を分ける。そして、病いはあくまで病院の中で治療されるものであって、原則的には病院の外には病気がないような社会を作ろうとする。しかし、その過程のなかで、病院自体が社会になっていった。イリイチはそれを「医療化する社会」と呼んだわけですね。
ただし病院というのは、先ほど美馬さんから院内感染のメカニズムについて詳しくご説明頂きましたが、病院自体がじつは動くんだと。お医者さんもそうですし、患者も。そして、テクノロジーの面でいえば、もはやコロンブスの時代の話では全くなく、身体の中にまで医療技術が入ってくる。その内部も外部もないような社会になっているときに登場してきた「病い」がコロナであった。少々強引ですが、次に議論していく美馬さんのご著書のタイトルが「感染症社会」であるというのも、たんにコロナで苦しんでいる現状のみを指しているのではなくて、それこそイリイチの議論の延長線上にあるのだと、そんな気がしてきました。
それでは、それについては後半に、ここで一回休憩を取ったあとさらに深めていければと思います。
(休憩)
以下、前半のコメント
視聴者コメント:
いま、リベラルアーツを通じて、広くて深い教養が大事と思っています。
視聴者コメント:
コロンブス的交換コロナは21世紀的コロンブス的交換なのでは?
視聴者コメント:
コロンブス的交換→アルフレッド・W・クロスビー『ヨーロッパの帝国主義:生態学的視点から歴史を見る』
視聴者コメント:
新たな環境変容のなかで生まれてきた疾病人新世におけるパンデミック
視聴者コメント:
コロンブスは「カニバル」(食人種)を発見=捏造した。コロナは中国グローバリズムを発見=捏造した。どちらも「野蛮の言説」の永続化!
視聴者コメント:
野坂:フランスのロックダウン状況
視聴者コメント:
フランスにおける「エッセンシャル・ワーカー」
視聴者コメント:
エッセンシャルワーカーの不可欠性が可視化される
視聴者コメント:
そもそもの問題が可視化される。顕在化する。
視聴者コメント:
不可視化された存在の可視化。緊急事態下の権力とアイデンティティの問題。
視聴者コメント:
グローバリゼーションの二面性:階級・人種・ジェンダー的差異の可視化と隠蔽
視聴者コメント:
ケアワーカーも移民が多い
視聴者コメント:
美馬さん:1.生態系、人間、環境、病原菌ごと移動した
視聴者コメント:
コロンブス:サトウキビから奴隷へ、病原菌から土地奪取へ
視聴者コメント:
医療現場でのクラスター。これは生態系の問題。医療技術が身体に介入する
こと、内的環境に介入することがパンデミックを引き起こす
視聴者コメント:
免疫力を落とすような薬物管理も問題
視聴者コメント:
エイズ、B型肝炎など。内部環境への技術の介入。これもまた人新生のかたち。2.合理化できていないところ。それがエッセンシャルなところ。そこもまた生態系として考えることができる。3密:生存の条件。ここもまた生態系。弱者の囲い込み。それが介護施設や医療現場。そのマイナス面が見えてきた
視聴者コメント:
人間の「社会」を「生態系」として捉え直すことで見えてくる世界が多分にある。
視聴者コメント:
エッセンシャル=本質的=内面的=顕微鏡的…「必要」という名の「免除可能性」(dispensability)
視聴者コメント:
3.階級問題。食肉工場などの現場とテレワークできる人たちの格差。それがリスクをめぐる階級uberの宅配も生態系
視聴者コメント:
コロンブス的交換。インフラ。イリーチ。医療化する社会。
視聴者コメント:
コロンブスから始まる「ヨーロッパ的近代」は、移動(グローバリズム)と定着(コロニアリズム)のよって成立した。
視聴者コメント:
近代合理性のもとで、医者に人体への介入を独占させた。地球規模で、身体への高度技術の介入が進んできた。
視聴者コメント:
宮城まり子さん ねむの木学園の園長さんでしたが 2月後半に肺炎で近院に入院、一か月後都内の病院に転院されて3月21日93歳で死亡 その死因が悪性リンパ腫 ってちょっとおかしい 障碍児や若い人たちは 合併症がなければ重症化しなかったからクラスタ―ばれなかったかのかも
視聴者コメント:
新自由主義的な競争によって弱者を振り分け、集中化する仕組みが、コロナ以降どう持ちこたえられるのか?粘膜、皮膚下に入る技術。さらに端末の情報(データ)による管理。監視社会の成功なのか?
視聴者コメント:
コロンブス的交換;生態系→身体やデータによる監視を生態系として考えることは可能か?
視聴者コメント:
前近代のコロンブス的交換から、人新世のコウモリ的交換へ(?)
視聴者コメント:
生物としての人間:情報としての人間。こうした物質性は生態系として捉えることができるだろう。人間の集まりの仕組みや人を集める場所のあり方が問われている。
視聴者コメント:
ある種のSegregationになってしまいますね
視聴者コメント:
モバイルな監視はデータの集中(独占)か?そうではないものへといくのか?
視聴者コメント:
mobilityやITや監視社会が猖獗を極めると、一番先に滅びるのは、「演劇」ではないか…?「集まってはいけない…」?
視聴者コメント:
国民国家を超えたグローバルなエージェントがあってはじめて国民国家の監視が成立する。信彦の息子?太一:みんなの技術という言説が国家に結びつく?
視聴者コメント:
しかし「演劇」は2500年間、常に起きてきたパンデミックにも耐えて生き残ってきた。そうなると本当に恐ろしいのは病原菌ではなく、監視テクノロジーなのでは?
視聴者コメント:
監視テクノロジー、例えば37.5℃=発熱症状という指標は、医療への移動を禁止する、医療への自由を奪う医療化した監視テクノロジーか?
視聴者コメント:
デコロニアルエコロジー人新生は植民地主義が生み出した環境問題の犠牲者は旧植民地の人たち、社会的弱者、囲い込まれる人たち
視聴者コメント:
全くその通りで、だからこそ気候変動と感染症の問題は同時に対処しなくてはいけない。
視聴者コメント:
病院化する社会は移動する。支配的な技術は、外部と内部を貫通する。
<コロナを捉えるための時間軸:『感染症社会』を読み解く>
高原:それでは、美馬さんから新刊の目次をズーム画面で出して頂きながら、ご著書の紹介とさらなる論点をあげて頂き、討論したいと思います。
美馬:これ7月3日頃に書店に並ぶはずですが、リアルなブツとしての本はできています。
今回は宣伝も兼ねて、コロナウイルスという問題を、どんな時間軸で位置づけるかというところからみていきます。長い方からいくと、1つは数万年単位で位置づけるということです。これは本の第1章で論じています。
新型コロナウイルスは、もともとはコウモリで、何か別の動物に広がってから人間に感染するようになっています。じつは、こうしたタイプの病気は非常に多く、人間の文明の発生つまり定住や家畜の発明と関わっています。人獣共通感染症、英語ではズーノーシスと呼びます。人間が家畜を飼うようになって一緒に暮らすことで、コロンブス的交換ではないですが、人間と動物の間で病原菌の交換が起きるわけです。新型コロナウイルスもですが、伝染病とか疫病になる病気があるのは、社会的動物つまり集住する動物だけです。鳥とかコウモリとか牛とか人間とか、群れを作るから群れの中で伝染病が広がる、この生物学的な基本を押さえておきましょう。たとえば、麻疹であれば、牛の牛疫、犬のジステンパーとよく似たウイルスで、たぶん犬や牛を家畜化したことと関わっています。グローバル化のなかでコウモリの生態系と人間との接触がさまざまな面で密になったのが、今回の新型コロナの背景でしょう。
その次に数百年の単位で見れば、コロンブス的交換のように大陸間での病気の交換という現象の一つとなる。少し繰り返しになります、天然痘と麻疹がアジアやヨーロッパではたいした病気ではなかったのだけれども、新大陸では住民をばたばたとなぎ倒すように大殺戮する疫病となりました。いっぽう、アフリカ大陸はマラリアがあって、当初はヨーロッパ人が植民地化に苦労していたのが、特効薬のキニーネが発見されてからは一気に植民地化が進みます。コロナについても、死亡率などの重症度では大陸間の違いはかなり大きいです。これは原因不明ですが、有力な説の一つは、新型コロナウイルスと似たコロナウイルスの流行が東アジアではすでにあって、自然免疫が高かったのではないかという議論です。
次にもう少し100〜200年ぐらいの人新世のスケールに近づくと、植民地主義や帝国主義との関わりです。本では6章で論じました。ひとつは、コロナとコレラを比べてみようという話です。コレラというのは、もともとインドのベンガル地方の局地的な病気でしたが、19世紀にイギリスがインドを植民地にして鉄道で各地をつなぎ世界と貿易を始めたことでパンデミックになります。
もう一つは世界戦争の影響です。1918年のスペイン風邪というインフルエンザのパンデミックは第一次世界大戦によって世界に拡大しました。各地を移動する軍隊と復員兵が病気を拡大させたわけです。米国とヨーロッパの間の兵院輸送船の中で、患者が大発生したりしています。世界戦争と帝国主義という人間が意図的に起こした現象と感染症の拡大はセットになっています。新型コロナの場合であればグローバリゼーションですね。
飛行機による国際移動と経済的なグローバリゼーションを通じての病気の拡大がでてくるのはこの数十年のスケールでみえてきます。少し触れたエイズは80年代での血液製剤のグローバルな貿易によって拡大しました。あとは、ウイルスそのものはセキとともにせいぜい2mしか動けないので、ウイルスをもった生き物の移動による感染の拡大です。SARSだと香港から世界各地に飛行機乗客を通じて拡大します。これは、本の4章で論じました。
この20〜30年でのもう一つ重要なポイントは、人間の側でパンデミックを予防するための対策を事前に立てておくという機運がでてきたことです。リスクマネジメント体制の構築ですね。そうすると、鳥インフルエンザなり新型インフルエンザなり、感染症が感染症として問題化する前に持続的に世界を医学的に監視をする必要があるという話につながります。これが、国際保健の新たなステージつまり、ポストコロニアルな秩序と密接に関わるわけです。すごく単純化して言うと、1970年代くらいまでの国際保健は、貧困国の医療水準をどう上げるか、ワクチンをどう普及させるか、という問題なので、先進国から貧困国へと言う一方的なベクトルです。ただ、なぜ貧困国は貧困なのかといえば、先進国が一方的に収奪しているからなわけですから、まあ飴と鞭の飴のほうに相当します。けれども、90年代後半以降のパンデミック予防というシステムでは、ウイルスや生態系に関する情報や遺伝情報を先進国が吸い上げて、それを特許で囲い込んだ上で、治療薬やワクチンを生産してグローバルに売りつけるという仕組みになります。それ以前の国際保健とは異なった中身になっているということを押さえた上で、WHOをめぐる米中の綱引きを見る必要があります。これは、第7章で論じています。
ということで、今回は、数万年から数十年までのさまざまなタイムスケールで感染症と人間社会の関わりを考えて新型コロナウイルス感染症がどう見えるかを整理しておきました。文明と家畜化、コロンブス的交換、帝国主義、世界戦争、グローバリゼーション、リスク社会化などいろいろな視点があり得ることを紹介しました。
さいごに、塚原さんの論点に少し戻すと、こういうさまざまなタイムスケールの中で人新世はどう位置づけられるのか、ちょっと人新世という言葉が収まりが悪いな、という気はしています。だから、本のなかでは人新世という言葉は最後の校正段階で削除しました。そのあたり、人新世という概念の使い勝手としてどうなのでしょう。
高原:ぜひお読み下さい、というのはゲラをフライングで拝読しました私からも伝えたく思います。
<人新世と近代>
高原:次に、塚原さんに美馬さんが最後のところで出されたパスを受けて頂きたいのですが(笑)、塚原さん自身「蘭学者」であるということにある種の誇りというか、物事を思考するときのスタイルやスタンスとしてお持ちだと思いますが、蘭学というのは、間違いなく近代の学問ですよね。
そのときに「近代」という時間のスケールをはるかに超えていくような「人新世」という枠組みについて、どれくらいのタイム・スパンで考えているのか。もう一度、塚原さんの「人新世」理解について把握したいのですがいかがでしょうか。
塚原:はい、ありがとうございます。美馬さんのお話が面白かったので、どのへんから議論をしたらいいかと思っていて悩んでいるところなんだけれど、蘭学っていうことで言うなら、僕はやっぱり「日本人にとって近代とはなにか」ってところが初発の問題意識なので、まあせいぜい200年くらいのスパンでものを見てきました。もしくは、ヨーロッパの科学、つまり17世紀科学革命、ガリレオあたりで、近代科学が始まってからの人類の変容っていうのを主に扱ってきたので、せいぜい500年。1万年の話になるとそこまでいけるのかなっていうのが自分自身にクエスチョンマークを出します。でも、僕の人新世というのは、その程度の広がりで見ています。ガリレオのときをポイントとしてとるなら、コロンブスとか大航海時代、人類の大きな「近代ヨーロッパ」の発生です。
あと重要な環境変容をもたらしたのは、1つは毒ガス使ったり、戦車が出来たり、戦争の仕方が大きく変わった時代。これはイギリスの第一次産業革命でなく、第二次産業革命の成果です。アメリカ・ドイツ、日本は乗り遅れたけど電気と化学、石炭と蒸気機関ではなくて石油の内燃機関が出来たこと、これが人類史に及ぼした影響が大きいことに着目出来ます。もちろん日本は、というか蘭学者が熱中したのは大砲と「黒船」だから、第一次産業革命の成果なので、この辺はもう少し詳しく考えないといけない。
美馬さんのモデルとは違う気がするけど、もう1つ言えることは「大加速」と呼ばれるんだけれど、この定常状態から、突然ぴゅってあがる曲線、これはホッケースティック曲線ともいわれるんですが、どこで大きく状況が変わったかを横軸に時間、縦軸に量で取るグラフがあって、グレートアクセラレーションって呼んだりするけれど、大気中の二酸化炭素や、人類の鉄の生産量とか、定常状態が急な上昇に変わるというやつです。
これは窒素の量、大気の中にあるのですが、これは人工的に定着させられて、海中にものすごく増えている。なんでかというと、ハーバーが空中窒素の固定法を考え出して、工業的に肥料を作った。そして、そこから生まれたのが、第一次世界大戦で使われた毒ガスだった。だから、人間の科学技術と環境の関係はリンなんかもそうです、それから鉄の使用量も劇的に変わってきたし、硫黄酸化物の量も変わってくる。そのラインがきゅっと急上昇になるところが問題だと考えると、まあ20世紀だろうし、第二次世界大戦のあとは、まさに「大加速」している。もちろん原子爆弾とか宇宙ロケットとかも考えないといけない。
けれども、本当に簡単にポコっと変わったのかと言うと、そうでもない。そこには複雑な要因が絡んでいるから、一瞬にしてすべてが革命的に変わるというより、暫時的革命というか、重層的に、そしてそれらは相乗効果を生みながら、時代はときに緩やかに、そしてダイナミックに変容を遂げた。ここで小生が、それでも重要なことだと考えるのは、ヨーロッパが近代を迎えたことです。近代ヨーロッパこそが近代科学、科学は近代ヨーロッパが生み出したものだということです。科学は、ヨーロッパのものと、それ以外の知と分けて考えるほうがいい。
グローバル企業が国家をこえる時代になっているという点については、やっぱり、それでも、いろんな民族とか国民国家はGAFAが関わってるし、美馬さんが指摘しているように国民国家の力がなくなっているということは言えるし、テクノロジーの部分では確かにそうかも知れない。けれども、国民国家は強烈に残ってるところがあって、これは差別とかね強烈な、危機的局面になればなるほど、ジェンダー、レース、クラスは強烈に再現される場面がある。
アメリカでBlack Lives Matterって話が出ているけれど、確かにそもそも感染機会の危険度が違うわけです。感染後のケアも違う。アメリカはクラスの問題、レースの問題かも知れないジェンダー、今回コロナは男性の感染者が多いと言っているし、どういうメカニズムか分からないけれど、ケアワーカーは女性圧倒的に多い。メディカル・システムの上位職は男性が多くいるけれど、ケアでも介護職でも女性が多くて、いわば危険にさらされている。日本ではあまりリアルにいわれてないけれど、外国人労働者の人で死んでるかも知れない人もいると思う。でも、分からない。
そこで野坂さんに聞いておきたいのは、フランスはどうなんですかということです。アメリカのBLMがこんなにデカくなっちゃったのはコロナという背景があるからだと思います。これはフランスでもあるんじゃないでしょうか。
<コロナ禍における「階級」と差別の問題:フランスの事例から>
野坂:はい、フランスでもかなりあります。というのも、まずクラスの問題は出てくるんですけれども、あと感染した人たちの差異として前景化されるのは、高齢者であったり老人ホームにいる人たち。あとは、感染した後の人たち。集中治療室で治療されたあとの後遺症が人によってはすごいんですね、コロナって。例えば認識障害とか、結構大きい後遺症が残りやすくて、私の知り合いの知り合いにも退院後2週間歩けなかったとか、喋れなくなったっていう人もいるくらい。喋れないっていうのも、身体能力的にしゃべれなくなったのか、脳に以上があったのかはわからないんですけども、後遺症がすごいんです。なのでそのことも考えると、例えばアメリカの社会みたいに医療費が自己負担になってしまうと、後遺症に関してもかなり問題は出てくると思うんですね。
つまり、例えばフランスでも、まず感染してしまうことに対する不平等性があって、感染した後もいかに自分がケアされるかという不平等性はかなりでてくると思います。そもそもの問題として、やっぱり医療現場って身体に触れる行為なので、医者が白人で黒人女性に差別意識をもっている場合はバイオレンスな状況になりやすい。例えばアラブ系女性はヒジャブというベールをかぶっている、だからそういう人に対する医療現場での差別というものもあります。なので、あとはそうですね、医療現場でそういう差別が考えられるということと、ロックダウンで警察によるパトロールが増えるのですが、そのパトロールの巡回が主に行われているのは、もともと地域として危険視されていたところという問題もあります。なので結局何をコントロールしているのかって問われたときに、感染リスクを防ぐために警官は外出証明書をみせろって聞いているのか、それとも、もともと目をつけていたヤンキーとかがいたりして、その人に「おまえ何やってんねん、今外出たらあかんやろ」って言ってるのかが、外から判断できない。
高原:ということを、フランス語で言うのですよね?(笑)
野坂:関西弁ではないです(笑)。このような状況が繰り返されてしまうので、アメリカのBLMの話を聞いても、やっぱりなっていう印象を持つというか、それが暴力のひとつの口実になってしまうんですね。外出許可の理由にも曖昧なものがあるので。たとえば買い物はOKだけど、微妙な理由での外出、洗濯物を洗いに行きたい、不要不急じゃないかもしれないけど、掛かりつけのお医者さんに診察してほしいとか。微妙な理由のときに警官によっては、それは違う、お前は罰金払え、ってなったりっていういざこざが起きるという話はありますね。
高原:なるほど。
野坂:なのでコロナの中で、国民国家の影響は減っていると指摘されているけど、いざポリシングするとなると、国民国家の影響は強いと思います。というのも、ウイルスの感染が拡大しているなかで、アプリなんかを使った国際社会の監視団体だったり、GAFAとかの影響とかはあるんですけど、ロックダウンするって手段にいたったときとか、マスクを誰が購入するってなったときとかに、国民国家は強い。あとやっぱり警察を出動するのも国家のレベルなので。たとえば市町村の段階で決めても基本的には通らないので、国家のロジックは一番残っているなとは思いました。少なくともロックダウンが強くされている状況ではですけども。
塚原:フランスって、やっぱり、非常にけしからんところがあって、文明のロジックみたいな、私たちこそが文明だみたいなところがあるじゃないですか。それから中国人蔑視についても、こんな野蛮人とバカにしてたわけでしょう。そういうリプレゼンテーションの事例とか見せられますか?
野坂:まず動物の写真を見せていただければ(センザンコウの写真を見ながら)。これは日本語でセンザンコウっていう動物です。英語圏や、フランス語圏ではパンゴラン(pangolinのフランス語読み)ていって話題になってたんですけど。フランスのメディアでは、この動物がホストになってコロナが拡大したといわれている。2003年のSARSのときは、コウモリからハクビシンに、コウモリにもともと寄生していたウイルスがハクビシンを通じて、そのハクビシンが中国の市場に登場して、それを食べた人間から感染が広まったと言われているんですけども。今回は、コウモリにもともと寄生していた別のコロナウイルスが、このセンザンコウを通じて、spilloverっていうんですけど、別の動物にも病原性をもって、つまり人間に病原性を持ってしまったっていう現象から起きたと言われているんですね。
で、その、理由として、フランスではロックダウンが始まる前、なので2月末からこのセンザンコウっていう動物が原因だったんじゃないかって話がでてきてて。この動物がアフリカでそもそも、なんていうんだろう、まぁ森林で獲られて、それが中国に送られて。中国の市場で売られて、これを食べた人たちが、コロナウイルスの最初の感染者になったっていう説がある。例えば私が友達と話していても、これを食べるのか・・・って話になる。中国人は何なんだと。メディアでしきりに言われてたことは、中国でこの動物、センザンコウが売られている、市場は、冷蔵機能もないし衛生状態も悪いということ。だからウイルスが拡散するには格好の場所だって言われています。(例えば、イギリスのガーディアン紙でもこのことが取り上げられた。https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe)
その表象はものすごく強くて。もう1枚の写真、これは、フランスで数年前に話題になったシャルリー・エブドの最近の表紙です。中国の習近平と動物のセンザンコウがこういうことをしている(添い寝)。キャッチコピーには、中国は本当にすべて私たちに言ったのか、と書かれています。(シャルリー・エブドの写真を見ながら)その背景としては、中国が4月にコロナウイルスによる国内死者数を一気に上乗せした時があったんですね。そのときにフランス社会とかで、中国は情報を隠蔽している、していたという雰囲気が高まって(それに対する批判があった)。それプラス、このイメージでは、習近平ひとりが批判されているとはいえ、中国人に対する人種差別もあると思うんですね。私が思うに、フランスや近代西洋文明や社会と比べて考えてみると、野生動物を食べるっていうのは、(文明よりも)自然との距離が近いものとしてみられている。近代衛生技術である冷蔵庫や、抗生物質を使っていない、いわゆる不潔だと扱われる人たちに、他者の表象が加わっている。その不潔さが原因で、グローバルなエピデミックをひきおこしたんじゃないか。そういう考えがあって、スティグマがつけられていると思います。
<コロナ差別を生む「文明社会」の自負>
高原:差別的な発言やまなざしの裏で見え隠れするのが、文明社会・文明国家という自負をもつフランスですか。そのことをちょっと個人的な関心に引きつけて考えると、感染症とフランスの文明というのは、そもそも切っても切れない関係ですよね。むしろ、フランスの文明化のプロセス自体が、感染症への対策・防御として生まれてきた側面もありますよね。
例えば、村上陽一郎さんの『ペスト大流行-ヨーロッパ中世の崩壊-』(岩波新書、1983)、ちょうど塚原さんも手許にお持ちのようですがや、喜安朗さんの『パリの聖月曜日 19世紀都市騒乱の舞台裏』(平凡社、1982)が鮮やかに活写したように、フランスの「文明」が作り出される過程は同時に「病い」が誰に、どの街路に由来するのかという原因(犯人)探しであったと思います。ペストのときは魔女ですよね。そして、19世紀のコレラのときは、パリの貧民/民衆世界が病気の温床とされ、都市パリから徹底的に排除されていく。そのときはアルジェリアの植民地で武功をあげた将軍や軍隊が動員されていくのも象徴的ですが、そのような「前史」を起源に持ちながら、いまに続く「フランス」が生まれてきた。
ここで美馬さんにお尋ねしたいのですが、いま野坂さんから話にあった感染症の「人種化」やそれにともなう差別というのは、フランスに限った事例なのか、あるいは世界中で歴史的に繰り返されてきたのか、そのあたりを教えて頂けますか。
美馬:19世紀末から20世紀始まりにあった黄禍論の問題の繰り返しという面があります。中国のクーリーが労働者として米国に入り込んで、それ以前の移民世代とトラブルになるという背景でおきたものです。結局、米国やオーストラリアはレイシズムにもとづいて、市民権取得でアジア人を差別するという政策に至るわけです。
ここで、病気や感染症というイメージは重要です。天然痘やハンセン病を中国人移民が米国に持ち込むという言説が多く見られます。また、当時中国から実際に世界に拡大していたペストについても、激しいアジア人差別が起きます。西海岸で、チャイナタウンから白人を退去させた上でチャイナタウンをロックダウンするとか、ハワイではペストの出た家の家財道具を焼却処分していたらチャイナタウンと日本人町まで燃え広がった事件もありました。
人種差別を正当化するには、生まれつき劣っているとか変更不可能な優劣関係をいわなければなりません。そのとき、病気というのはすごくわかりやすい表象になります。病気だから移民させないようにする、あるいは排除する、というの自然なことのように聞こえてしまうからです。が、実際には、病気に罹っているかどうかを調べるよりも、アジア人みんなを排除する方向に進むわけです。もう一つ、例があったのですが失念したので後ほど。
高原:はい、思い出したらお願いします。
<差別するまなざしと「他者」>
高原:もう少し先ほどのことについて美馬さんにお伺いしたいのですが、今日の冒頭でも、ウイルスというのはくっつくだけのものなのに、それゆえとも言えるかも知れませんが、人種化や主体化、あるいは区域に、塊として存在しているように認識され、そう語られているのですよね。こういう認識の仕方というか、人びとが向けるまなざしというのは、近代の産物なのでしょうか。ウイルスを可視化していく力というのは、間違いなく科学のまなざしであり、医学のそれであると同時に統治者のまなざしでもあると思います。それと人種差別的なまなざしというのは、どこで交差したり重なりあうのか、そのメカニズムを教えて頂ければと思うのですが。
美馬:他者なるものが、そもそも生活習慣、つまり生きる社会のあり方や言語ゲームが違う存在なのです。ようするに、変わった生活習慣をもったり、へんな匂いがしたり、おかしな食べ物を好んだり、なんともいえず不快な存在なのです。その不快な差異をうまく分類できないと不安になるので、カテゴリー化というか人間をグループ分けするとき便利な分け方が、人種なのだろうと考えています。人種と病気というのもよく結び付けられます。それで、先ほど言おうとしていた例を思い出しました。
敗戦後の日本での朝鮮人差別と病気の関わりですね。敗戦直後に、日本政府は日本臣民だった朝鮮人について国籍を取りあげ、朝鮮半島に戻ることを推奨し始めます。けれど、すでに日本で定住していた朝鮮人も多かったので、何かと船での行き来が行われます。敗戦前までは国内移動だったのが、密航として取り締まりの対象となります。このとき、日本側は戦後の混乱した朝鮮半島でコレラ流行があったことを強調して、治安ではなく衛生や防疫の問題だと主張しつつ取り締まりを強化していきます。これは現在の新型コロナをめぐる嫌韓/中と重なってみえます。
高原:まさに、いまのお話は小池百合子都知事が連発する「夜の街」とも関わりますし、戦後でいえば「パンパン」と呼ばれた米兵相手の女性と名指された人びとが性病の温床として排除・差別された歴史と重なりますよね。そこにおいては「浄化」という言葉が使われたわけですが。
<質疑応答:コロナの「見える」化をめぐって>
高原:すこし時間も迫ってきましたので、チャットの方から頂いた質問にも応答したいと思います。まずは、小笠原博毅さん。「質問です。コロナウィルスのイメージはなんであんなにカラフルなんですか?」。これについてもう少し小笠原さんの方からご説明頂けますか?
小笠原:こんばんは、ありがとうございます。たまたま別の人と別の仕事のやり取りをしていた時に、その人がイギリスと中国と日本とで、コロナはなんであんなカラフルなのかというミニシンポをやっていたっていうんですよ。美大の先生なんですけどね。僕も実はそれをずっと考えていたので聞いてっました。ワンパターンじゃないんですよね、コロナのイメージの色付けって。あれなんでこんなことするのかなって
高原:実際に色を付けていくということですか?
小笠原:顕微鏡の写真に色をつけるじゃないですか。当然あんなちっぽけなものに色なんてないでしょう。それをあとから塗る。オレンジだったり紫だったり緑だったり、むちゃむちゃバラエティがあって、カラフルなんだけどあれはなんでか。視覚化ではあれど、あまりにも意図が見え見えすぎる。毒々しかったり不気味さを植え付けるという意味では、美馬さんの言葉で言うと、気持ち悪いもの? なんでしたっけ、要はユダヤ人このスパイスの匂いがするとか、アイリッシュはギネスの匂いがするとか、コロナウィルス自体が他者化を推し進める強烈な装置になっていると同時に、コロナウイルス自体が他者として顯れてきているのではないかと思いまして。そもそもなんであんな色をつけるのかというのを知りたいんです。
美馬:STS的にちょっとウンチクいうと、要はウイルスなので大きさからすると可視光線では見えない。人間の網膜では見えないので色もへったくれもない存在です。可視光線より小さいものなので。だから電子線で観てるわけです。だから、色のありえないものにカラフルに色を付けているので、インスタ映えですよね、それは。
野坂:科学史の観点からみると、最初に19世紀末に病原菌というものを、当時は電子じゃないので、旧型の顕微鏡で観始めた時に、そもそも大事だったのが、周りの組織だったりバクテリアに色付けすることだったんですね。塚原先生がおっしゃってたように、第二次科学革命で染色技術がでてきて、バクテリアを可視化することができるようになって、バクテアリアというものを表象できるようになった。当時の顕微鏡で見えたバクテリアの図を見ると、すでにカラフルなんです。ものにもよりますけど。紫で染色されていたり、赤で染色されていたり、見やすい。体細胞とかの組織は赤で、コレラ菌とかは紫みたいな。なのでそこから病原菌というものをアイデンティファイして、個別化してっていう技術と文化はそこからでてきている。それが他者化っていうような社会的なレベルへとつながっていったと考えられます。
塚原:これを再度、STS的に整理するなら、まず美馬さんが言ったように色という原理をこえた電子顕微鏡写真だから、そもそも可視光線のレベルではないという科学的事実。そして、歴史的な要因としては、しおりさんが指摘したように色素なんです。当時の研究者は色素でしめあげるって言ったといいます。顕微鏡で見ても、なかなか見えない。だけど、色素入れてやると、それで染まるやつと染まらないやつで差がついて、たとえば細胞膜だけとか、うまく枠組みが出来て、顕微鏡で見えるようになる。この色素というのが、まさにこの時代のミソで、ドイツの化学の一番大事なところです。そもそも染料を作るのが目的です、アニリンとか。そこで主に繊維産業で、洋服の色をつけたんですが、それだけじゃなくて、化学とか理化学とか医療でも使われて、なかでも細菌を見るとか、実験で抽出するとかで、この栄光のドイツ化学が作り出した合成染料をつける。そうすると、これをプレパラートにちょっと差し込んでやると、やっとこれで見えるようになったというのが1つめ。
それに視覚的なリプレゼンテーションについては、もう一つ、重要なSTS的要因があります。20世紀の後半から電子的画像技術の発達での人体の可視化にそれは現れています。CTスキャナや核磁気共鳴、それにソナーのようにお腹のなかの赤ちゃん見るやつでもいいです。あれをどんどん色を付けたり技術がすごいスピードで進んだ。要するに「見える化」が進みました。これこそが科学技術の成果ですみたいなインタープリテーションが生まれた。そこで喧伝されたのは「見えることが理解することです」という実に直感的なモデルです。じゃあ、いったい何が見えているといっても、それが問われることは少なくなる。SF的な視点なんだけれど、何億光年もいった先のハッブル望遠鏡とかでも、めっちゃ綺麗な宇宙の像を出したりする。このビジュアル優位性というのは「情動」によって、まさに即座に反応してロジカルに考えない、「いいね」を即答するっていうスタイルに適合性が高い。
今回のコロナのリプレゼンテーションにいっぱい使ってるし、個人的には好きなんだけど、キレウに図式化されている。科学雑誌でみると、直感的に、それは何かが分かる。そうすると化学者は反応のメカニズムについては「ああ、これは、こうくっついて」とか、それに色つけてもらうと分かりやすい。でも、そもそも分子に色なんてついてないって、みんな分かってやっているとは思う。これも現代科学の視角優先主義についてのSTS的説明ですが、こんなんでいいでしょうか。
高原:体温ですら、サーモグラフィーで赤くなったり青くなったり「見える化」されてますよね。あと東京アラート。危機感に色が付けられる。
塚原:ええ、だからね、ベイブリッジの虹の色が赤になったら怖いですねって、いやあ、すごい刷り込みだと思う。だからそういうところが、シンボリズムとか、情動によって巻き起こる共感をスティミュレートする。(チャットのコメントに対して)インスタ映えっていうのはそうですね。ポチって「いいね」が出れば、情動の喚起に答えることなり、一体感も確保出来る。そういう価値観が蔓延していることの原因であり帰結ではなかろうかと思います。
<生態系における「他者」とは>
高原:他にもご質問あればと思うのですが、すみません。すぐに出ないようでしたら、私の方から美馬さんに大きな質問をしたいと思います。他者という話が出たときに、今日のキーワードであります「生態系」と他者というのはどのような関係性で捉えればいいのか。生態系における他者とはなんだ? と思ったのですが。
美馬:他者として、社会学などは人間を想定しているんですね。人間と人間の間での他者っていう風に。だけど生態系や人新世の場合には人間ではない他者、つまりアクターですよね。人間じゃない他者も入ってくるっていうのが明示化されています。で、人間と非人間の他者をフラットに並べて論じることは可能か、というのが一つの探求の方向性で、それをどう社会理論に組み込んでいくかが試されているのが、現在の人文学や社会科学のホットトピックかと思います。
塚原:もう一つ付け足すとすれば、他者っていうことは、いま仰ったようにアクターってことで、非人間の存在はあるけれど「自然」だとも思います。生態系というより、人間が「自然」をどう観てきたか。それは絶え間ない外部化っていう言い方もされてきたものです。主体である人間は「自然」に対して、デカルト的で、人間中心主義的な差異化をしてきた。思考出来るかどうか、まさにデカルト的主体とそうでないもの「対象」に分けてきた。自然っていうのはなんなのか、デカルト的観念は結局のところヘーゲルみたいに逆立ちしちゃうわけで、それは近代哲学の宿病とも呼ぶべき問題だと思います。
だから、基本に返って、自然ってなんだったの、人間のなかに自然があったはずでは、ウイルスって今回のやつは皮をかぶったRNSウイルス、これは自然なのだろうかと問い直す必要がある。自然と共生するなんて生易しいことはいえない。だから ウイルスのことも含めてなんで人新世って言い出したかって言うと、そのレベルまで遡って考えていかないといけないっていうのが一つの結論です。
つまり、問うてるのは他者とはなにか。太一くんが指摘してくれたように、生態系に他者は入るのかどうかという問題でもあります。ウイルスは人間を宿主として、人間を殺してはいけないわけだから、やつらはやつらの戦略を持ってるわけで、「コロナとの戦争」とかそんな簡単なことじゃない。戦争して撲滅してというのは、新たな奴隷制度の提唱で、それは出来るものじゃないと考えられるのではないでしょうか。
野坂:他者と自然、あと人間を中心に据えたときに、他者の階級化という問題がでてくる。塚原先生がおっしゃったように、自然があっても野生の自然なのか、もしくは自分たちの生活圏に必要な家畜であったり、ウイルスとか微生物だったら善玉菌とかっていう、自分たちのための飼いならされた自然なのか。あるいは野生動物なのか、未開地の自然なのかっていう違いも出てくると思うんです。その中で、私たちが自然と呼ぶ時に、どういう自然なのかっていうこともそこから問い直さなければならない。それも植民地時代の話に戻ってくると、奴隷も自然に入るとか、いろんな位相があると思うんです。女性は自然なのかって話とかもよくありますけども。そのあたりの問題を全部違うレベルで、二項対立になっているものを観ていくべきだと思いました。
高原:ちょうど塚原さんと野坂さんから結論めいた話があったので、美馬さんからもなにかお話を頂けましたら。
美馬:もう1点足すと人間のなかに細菌がたくさんいるという話がこの20年くらいブームですね。ヒトゲノム計画の後は、そういう人間の皮膚や腸内そのほかに存在する細菌を徹底的に調べるヒトマイクロバイオーム計画が立ち上がっています。ウイルスとくにRNAについては、最新の生命科学でものすごく複雑な生態系があるようだと分かってきています。ウイルス対人間などという単純な考え方では捉えきれない状況が、生命科学の側から突きつけられてくる可能性もある。一種類の細菌やウイルスが病原体として病気を起こすという考え方そのものが、刷新されるかも知れない。まさに人新世という感じを持ってます。
高原:ありがとうございます。
<おわりに>
塚原:最後に一言。今回の美馬さんの本、すごく面白いから今日来てくれてる人(これを読んでくれている人)買ってください。実はこの本はいつもの美馬さんの本と比較して、売ることを意識して書いたんじゃないかって推測しています。この本は読みやすいんですよ、だけど、この『感染症社会』っていう本は人文書院の松岡さんって編集者がいいのかな。すごく砕いて書いてある。
美馬:じっくり書くと、色々書き足していくので難しい本になるのかも(笑)。
塚原:いやいや、読んでみて、そのスタイルに驚いた。だけど、ラトゥールも最近の『地球に降り立つ』っていう本、これも啓蒙書だよ。これは驚いちゃった。なんでこんな啓蒙主義になったかっていうことをまた聞かせてください。近代啓蒙主義者に美馬さんが「転身」した理由を。
美馬:わたしは骨の髄からの近代啓蒙主義者ですから(笑)。
塚原:それは次の話題ということで太一くんありがとう。
高原:それでは、これをもちまして今回のぽすけん企画「コロナと真実」を終わらせて頂きます。また本日の動画や加筆しnoteの原稿をご覧頂ければ幸いです。もう一度、それを読んで大いに啓蒙されましょう(笑)。ぽすけんは来週も続きます。宜しくお願い致します。
本日は改めまして、塚原さん、美馬さん、そしてパリから野坂さん、ご参加ありがとうございました。オーディエンスの皆さまも、活発なチャットでのコメントやご質問ありがとうございます。楽しかったです。
以下、後半のコメント
視聴者コメント:
人間が動物を飼いならしたのではなく、動物が人間を人畜化した。なるほど、グローバリズムは地域差を顕在化する。なるほど、感染症はエネルギー問題でもあるわけですね。人力⇒動物⇒風力⇒石炭⇒石油⇒原子力・・・つまり戦争の変化。
視聴者コメント:集密への警戒は、距離の尊重を生み、同時に相互の可傷性ヴァルネラヴィリティの認知を作り出す。なるほど「保険」も植民地主義による移動から生み出されましたね。ダニエル・デフォー!素晴らしい本です!
視聴者コメント:
7月3日に書店にならぶ『感染症社会』
コロナをどのような時間軸で引き受けるか?1万年単位で引き受けるとどうなるか?→第1章
生物学的な進化論。これは文明論でもある。
視聴者コメント:
乱学者!
視聴者コメント:
数百年単位。生態系の大陸間移動の始まり。天然痘、はしか、梅毒。コロナもこれに近いものなのかも。6章:植民地主義とコレラ。イギリスによるインドの植民地化と鉄道の発達
第一次世界大戦。インフルエンザ。兵士の移動。情報統制によって、感染症が見えない
視聴者コメント:
帝国主義と世界戦争と感染症の繋がり。人間(ウイルス)の移動。
1990年代以降。飛行機によるグローバルな移動。香港と鳥インフル。養鶏場という集団性。
21世紀:鳥インフルの耐性:コロナウイルス
視聴者コメント:
顕微鏡!
視聴者コメント:
リスク社会化。予防のテクノロジー。ウイルスのグローバルな監視システム。国際保健が先進国の問題として捉え返される。リスク監視、ゲノム、遺伝情報の知識の先進国への集中。
視聴者コメント:
ただ「見る」だけではなく、「名付ける」。
視聴者コメント:
質問:コロナウィルスのイメージはなんであんなにカラフルなんですか?それで作られるイメージだけじゃなくて、「思考」や「思想」があると思うのだけど。
視聴者コメント:
シニフィアンによるシニフィエに対する暴力、それとも抵抗?
視聴者コメント:
つかさんの蘭学:人類と化学物質、科学技術。「大加速」が起きるここ200年くらいで考えたい。ヨーロッパこそが近代。じゃあ、どうして日本人は受け入れたの?それが蘭学
視聴者コメント:
『解体新書』と江戸200年の平和が、現在の日本の「健康」を保っている?
視聴者コメント:
感染の危険度、感染後のケアが、階級や人種やジェンダーと結びついてる。社会の脆弱な部分と感染。
視聴者コメント:
第一次世界大戦の後1918~19年スペイン風邪 確かに面白い
視聴者コメント:
まったくそのとおり! BLMの敵はコロナではなく、WLMと宣う「白人社会」である。
視聴者コメント:
野坂:フランスの状況。感染とケアと重度な後遺症が、社会の分断面に問題として現れる。医療現場の差別
視聴者コメント:
シベリアの凍土が溶けると、スペイン風邪のウィルスが生き返るというのは本当ですか、美馬さん。1910年代だから私たちには免疫ないですよね。
視聴者コメント:
ポリシングと人種化された危険なローカル。
利佐子 黒野 から 皆様 : (7:29 午後)
犬の散歩もOK??DLM
視聴者コメント:
そもそも貧困家庭で庭がなければロックダウンで家に居続けられない。だから外に出る。黄色いベスト運動とロックダウンとの関係はどうですか、野坂さん?
視聴者コメント:
フランスの文明のロジック。
視聴者コメント:
wet market
視聴者コメント:
フランス人も野生動物食うのに。。
視聴者コメント:
「情報を隠蔽とか歪曲」とかよく言われますが、そもそも感染症に「情報」は無力なのではないですか?
視聴者コメント:
19世紀、移民に市民権を取らせない。国民国家。
視聴者コメント:
村上陽一郎「ペスト大流行」(岩波新書)
喜安朗「パリの聖月曜日」(平凡社)
視聴者コメント:
港とペスト
視聴者コメント:
中世の「魔女」は超優秀な医師でもありました、特に家父長ではなく母性を尊重する生殖技術において。その知恵と実践を奪ってきたのだ、近代的男性中心的医学・警察・法学・メディア・軍事・教育・工業の七位一体。
視聴者コメント:
検疫とチャイナタウン病気という建前で人種を隔離する。
視聴者コメント:
ウィルスによって、we lose!
視聴者コメント:
ウイルスが人種化されたり、場所区分されたり、特定の人に囲い込まれていくのは、近代の産物なのか?
視聴者コメント:
「他者」とは不快な生活習慣を持つもの。中韓への差別。敗戦後、第三国人として人種化し、帰国させる。
視聴者コメント:
中国に対する「人種差別」は中国主導のグローバリゼーションによって強化されたとすれば、コロンブス的な西洋植民地主義が新自由主義という形で、それに対抗しているのが現状ですか?
視聴者コメント:
彼らの日本への密航とコレラ問題、からのポリッシング
視聴者コメント:
中国、朝鮮、フィリピンと日本が連帯するチャンス?
視聴者コメント:
Q:Covid-19はなぜカラフルなのか?
視聴者コメント:
中国の花火のイメージ?新年だったしね。
視聴者コメント:
Q:Covid-19自体が他者化されている?
視聴者コメント:
あの絵を造ったのはWHOですか?
視聴者コメント:
A:想像/創造された形。インスタ映えwwwA:「他者」(バクテリア)を色付けする。他者の個別化・差別化・区別化。
視聴者コメント:
「見る」だけでなく、「色を付ける」ことが他者化と名付けのカギ。
視聴者コメント:
A:色付けすることで不可視なものを可視化する。
視聴者コメント:
なるほどオランダ絵画の世界ですか・・・グリーナウェイの『プロスペローの本』による世界の絵画化。
視聴者コメント:
医療=人体の見える化。他者創造のシステム。視覚優位の世界。
視聴者コメント:
皆さん丁寧な回答ありがとうございました
視聴者コメント:
Q:生態系と他者の関係性とはなにか?
視聴者コメント:
発症する2~3日前から感染のリスクがあるので体温だけ計ってても感染防げませんけど
視聴者コメント:
他者と生態系
視聴者コメント:
A:社会学=人間と人間の中での他者。生態系=人間とモノ(?)の関係における他者。
視聴者コメント:
例えば、観光産業からはマイクロツーリズムの推奨、需要の平準化、特定の場所への集中を避けるといった施策を、政府が観光喚起策の中で行ってほしい(=儲けたいが、何らかの移動の規制をしてほしい)、という声が出ているそうです。
コロナ禍が取りざたされた後では、国家が経済や産業の論理に沿う形で、市民に特定の消費、生活スタイルっを実践するように誘導していくのでしょうか。資本主義はどう、コロナ後の延命をはかるのか?
視聴者コメント:
生態系の移動が他者を作り出している?
視聴者コメント:
生態系には「他者」概念はないのでは? 人間だけが「自己」と「他者」と第三者「仲介者」で考えるのでは?
視聴者コメント:
絶え間ない外部化
視聴者コメント:
ワクチン接種が経済活動のフル活動再開の指標とされそう
視聴者コメント:
主体と外部。外部化される自然。
視聴者コメント:
ヴィヴェイロス・デ・カストロによるカニバリズム議論。
視聴者コメント:
自然という概念は、文明以前にあるのかな?
視聴者コメント:
ないでしょう。
視聴者コメント:
塚さん的人新世=人間にとっての自然、生態系を考える試み。
視聴者コメント:
近代の概念では。
視聴者コメント:
共生は自然科学の概念?そちらが人間社会に適応されたのかなあ。
視聴者コメント:
しおりさん:自然の階級化。
視聴者コメント:
もやしもん
視聴者コメント:
自然(他者)は味方か敵か。自然を二項対立化する人間社会。
視聴者コメント:
動物は細菌によって進化してきた。
視聴者コメント:
美馬さん:人間がもつ細菌。人間を「人間」にしているのは自己(?)だけか?
視聴者コメント:
「他者」によって作られる人間。
視聴者コメント:
塚原さんの『現代思想』論文は難しくなかったよ。
視聴者コメント:
肛門に水道突っ込んで浣腸したり、性病が映らないようにあらゆる抗生物質を常用して乱交していていた女性役の方は免疫力落として 後天的免疫不全になりました
視聴者コメント:
はい、皆さん、ご苦労様でした。今日も楽しかったねえ。
視聴者コメント:
塚崎さん、美馬さん、野坂さん、ぜひ週刊「金曜日」にも書いてください。自分の担当記事は、大学1年生が読んでも(それなりに)理解できる仕上げをモットーにしていますので。
視聴者コメント:
ありがとうございました
視聴者コメント:
太一の司会が良かった!バイバイ。
視聴者コメント:
太一おつかれ
視聴者コメント:
ありがとうございました。太一さんがわかりやすく問い直してくれて進行がわかりやすかったです。
視聴者コメント:
とても良かったです🎵
視聴者コメント:
チャットの書き込みも面白かったです
記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。
