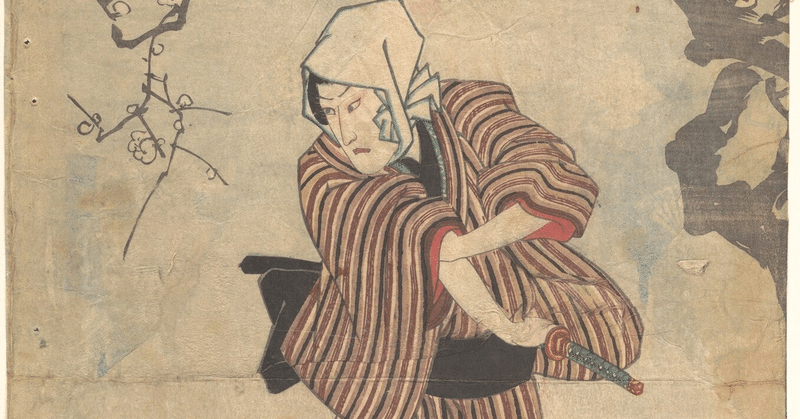
ウクライナへのロシア侵攻、 日本ができることは何だろう
ウクライナに関する直近の報道など
ロシアのフェイクニュース・・・の段階で止まってほしい。しかし侵攻が始まったというニュースに落胆している。2月24日夕方(JST)
ゼレンスキー大統領が国民へ向けて話した映像(2/24)
ロバートキャンベルさんのFacebookで観た、ゼレンスキー大統領の演説。上記より前のタイミングのようだ。(2/23)
ウクライナのゼレンスキー大統領は昨晩、国民に向けて演説を放送しました。途中で露語に切り替わり、ロシア国民に直接侵攻の非を訴えました。冷静な語りを英訳で読みながら、私は台湾の現状と重ねて考え、主権と戦争回避が対岸の火事じゃないなと痛感しました...
Posted by ロバート キャンベル on Wednesday, February 23, 2022
ゼレンスキー大統領は演説の大部分をロシア語で話した。彼は「多くのロシア人がウクライナを訪問し、ウクライナに親戚がいる。あるロシア人はウクライナ大学で学び、ウクライナの人たちと友達だ。ウクライナ国民と政府は平和を望む。ロシア人は戦争を望むのか。答はロシア市民にかかっている」と訴えた。
報道されている各国や機関の侵攻前の対応
米国はいつ戦争状態にいつ突入してもおかしくないという発言をこの数日発している。
ドイツ・フランスは、それぞれが話し合いの場で働きかけていたようだ。
日本は、22日、ロシアによるウクライナ親露派地域の独立承認と派兵決定を「強く批判する」と岸田首相が明言し、24日、制裁として①2地域の関係者の査証(ビザ)発給停止、資産凍結②2地域との輸出入禁止③ロシア政府による新規ソブリン債(国債、政府機関債など)の日本での発行・流通禁止――を実施すると発表した。
BBCでの外交専門家などのコメントからは(参照動画なし)、このままだとロシアが流すフェイク画像や偶発的な発砲を契機に、ウクライナ側が最初に手を出したというストーリーで戦争に至る可能性が高いと話している。その前段のウクライナのロシア側の地域の一方的な独立承認も予想されていた事柄だと論じていた。
専門家ならば、そういう事態があっても戦争に至らないような施策や外交を考えないのか?
個人として私が思っていること
日本人の端くれの私が、外交の専門家でもなく、コメンテーターでもジャーナリストでもなく、単なる一個人として、思うことを書いてみたい。ただ人が全うに生きられる世であってほしいと願う立場があるだけで、素人考え、口先だけなど批判の余地がたくさんあることは承知だ。
ロシアがやっていることは、正式には認められないような、あの手この手で自分達が被害を被っていると主張し自国防衛のための手を打っている(NATOが拡大しているとの訴え、ガスパイプラインを盾にとった交渉、サイバー攻撃等々)。たとえ、ウクライナを占領し、そこにいる人命を粗末に扱っても致し方ない=よい、という立場と行動をとっている。
これは、中国が香港・台湾に行っていることと同列だ。(少数民族に対する施策も、国内のこととはいえ同根だ。)
国際法に照らしても、いまの状況はウクライナに対する理不尽な侵攻だ。「力による現状変更」「「領土保全の原則」への違反」 これを日本は国として許容しない。そのことは岸田首相や林外務大臣が名言している。
日本はロシアが行っていることに対して、言葉で、そのような傲慢な態度は国として許さない、各国の主権を認めないことは許されないことだ、と明確に何度も伝えて日本のスタンスを明示する必要がある。それは、中国が香港の一国二制度を破壊し、台湾を支配しようとしていることと関係する。台湾の先にある、日本領域の島々や沖縄を中国から近いところから占領しかねないという可能性にも影響する。
またロシアに対して、ウクライナの新ロシア住民が住んでいて、昔はロシアであった場所に対してそのような主張をするならば、長年日本人が住んでいた北方領土についても同じように論を進めて「日本へ返しなさい」と伝うことが筋ではなかろうか。
つまり、この話は日本に通じる話なのだと私は思う。ロシアとウクライナのことは、ロシアと日本、中国と日本にも当てはまることであり、日本は自分事として捉える必要があるのではないだろうか。
日本がひとつの国として国際的に貢献する方法は、戦闘力をもって介入するのではなく、外交や平和堅持をもって関わる方策を打ち出して、複数展開できないだろうか。
プーチンは解釈を歪曲させたり、事実を捻じ曲げて無理難題を通そうとしている。その裏には、NATOに囲まれてロシアが損をしている、危険な状態にあるという認識を持っているようで、妄想に近いものがあるようだ。(詳細はメルケル元ドイツ首相の書籍(後述)に委ね、書籍記載内容より推論。)そうであれば、メルケルがこれまで会談するごとに、まず30分はプーチンの話を聞き、そのうえで手短に世界情勢を論理的に状況説明していったという関わりを、誰かが補完して行うニーズがあるのではないだろうか。
プーチンとの対話は、アメリカのように、自分が正義であると論を振りかざすこととは全く違う。アメリカのやり方は交渉としての効果を出せずにいる。持論を主張しているに過ぎず、その背後には軍需産業が手ぐすねを引いて、いまか今かと交渉決裂、そして出番を待っているという構図が透けて見えるようだ。
ゼレンスキー大統領は、演説の大部分をロシア語で話したそうだ。彼は「多くのロシア人がウクライナを訪問し、ウクライナに親戚がいる。あるロシア人はウクライナ大学で学び、ウクライナの人たちと友達だ。ウクライナ国民と政府は平和を望む。」これはロシアへ、世界へ伝えるべき重要なメッセージだ。全体としてウクライナがうまくやっているか、正しいかはわからないが、この主張・このスタンスを堅持することは重要だ。
国民は攻めてきたら自分が守るという気持ちを持っていて訓練も行っているらしい。そのうえで敵が攻撃してきても、決して手を出さない。「右のほほを打たれたら、左を出す」というような戦争回避策を、当事者と世界各国が協力して実現できないだろうか? 冒頭のゼレンスキー大統領のスマホ動画では「今日は家にいてほしい」つまり攻撃に加担しないように国民へ話しかけている。
日本が貢献できるかもしれない個人的な案
原則
・平和主義のスタンスを堅持する
・一国や民族の尊厳を守ることを重視するスタンスを打ち出す
・解決手段として戦闘を選ばず、あくまでも戦闘回避の話し合いを継続する
現状ウクライナの場合
・交渉の場に、一旦引退しているメルケルにも登場してもらうことを働きかける
257ページ プーチンとメルケルの会話が通常まずロシア語で始め、 細かいことまで伝えたいときはメルケルはドイツ語に切り替える。嘘をつくとどうなるかプーチンに教えるためにメルケルは次の電話会議をキャンセルする。 プーチンの虚勢の扱い方はメルケルの方が一枚上手だった。
彼女は相手が言ったことをその場でものすごく単純な子供っぽいと言えるほど無邪気な表現に言い換えて、おうむ返しにします。そうすることで相手の見せかけのポーズから劇的な要素を削ぎ落としてしまいます。例えばわが国の国家的利益とか歴史に刻み込まれた人などについて怒鳴り散らすと。ずっとシンプルな表現に要約して言い換えるのです。相手は自分の言い方がとても賢そうには思えないと感じます 。本来の狙いを明確にさせることを目指しました。そこから初めて本気の交渉ができるからだ。
・元KGBであるプーチンの話をきいて、紛争調整の対話の場をつくりだせる能力がある人(アーノルド・ミンデルやアダム・カヘンのような人材)が、話合いのテーブルにつく機会をつくる。
・前線に自衛隊がお風呂を準備する。敵・味方の戦士が、時間をわけて交互に身体を温める場を設ける(男湯・女湯と時間帯を分けるようなイメージ)。戦闘員の健康保持という名目での戦意喪失を狙う。(ヤマザキマリさんのローマ時代のテルマエ・ロマエの話) 民間人に提供することも可能。
・プーチン大統領に温泉につかってもらい、料理をふるまい、リラックスしてもらってから話し合いをする。良い状態で冷静に考えてもらうシチュエーションをつくる。
・チェコがソ連邦/ロシアに占領・解放に至った道から現在生かせる知見はないだろうか(1969年「プラハの春」が、ソビエト連邦を中心としたワルシャワ条約機構の軍事介入で潰された → 1989年「ビロード革命」)。
・エストニアなどバルト三国がソ連邦/ロシアに占領されたときの知見を、ウクライナの人と共有できないだろうか。
などなど。平和大国として、戦争回避と対話推進という面で貢献していくことが、将来的な日本の危機にも備えるものだと考えている。
以下、参考情報
メルケル 生い立ちや政治家としての成長・活躍を読み取れる本
アーノルド・ミンデルについて書籍紹介しているnoteブログ
アダム・カヘンについて紹介している記事
お読みいただいてありがとうございました。個人の妄想かもしれませんが、他人事でなく、このことを真剣に捉えることが、いまの解決や将来的なリスク低減につながると考えております。
なによりもウクライナの人々、逃げ出した人、国内にいる人、戦火に倒れた人、国外から見守っている人、すべての方々の平安を祈ります。早く戦争状態が集結しますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
