
【AI動画】「オリジナル」vs「コピー」 初心者はどちらを選ぶべき?【300万回再生の裏話】
皆さん、こんにちは。
実は1週間もたたず、私の動画が300万回再生を突破しました!ぱちぱち👏

300万回再生という数字は本当に嬉しい限りでこの動画1本で広告収益は6万円を超えるようです。

「これはシリーズ化して、まだまだ伸ばせる…!」
と、意気込んでいた矢先のこと。
「ん?あれ?この動画…どこかで…?」
今朝Tiktokをスワイプしていると流れてきたのは…
私の動画を模倣したと思われる作品が、オススメ表示に出てきました!
そっくりやんけ!

1本目の公開(6/15)からまだ2週間経っていない段階での出来事だったので、「もう模倣作品が出てくるなんて…」と、正直なところ、少しだけしんみりしてしまいました。
しかし、何かを作ってきたことがある人なら分かると思いますが、模倣し、模倣されるというのは、どんな業界、どんな世界でも日常です。
とはいえ、私のこのシリーズ動画は合計で700万回再生を超えていますし、注目度の高い動画だったということでしょう。これまで見たことのない構成や演出をしたAI動画だったので上手くハマりました。
…さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回はこの出来事を機に「初心者はオリジナルとコピーどっちを選ぶべきか」について、私の体験を踏まえて解説していきます。
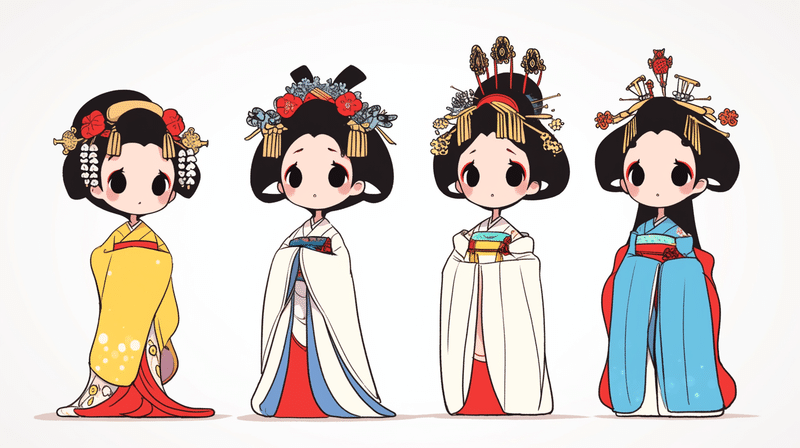
【結論】まずは「コピー」から。
結論から言うと、AI動画制作の初心者は「コピー」から始めることをおすすめします。
「え?パクっていいの…?」
そう思った人もいるかもしれません。
もちろん、著作権や肖像権を侵害してはいけませんし、
丸パクリを推奨するものではありません。
しかし、制作の基礎を学ぶためには、成功している作品を分析し、模倣することから始めるのが、近道です。
特に、構成や編集技術、効果音の使い方など、実際に手を動かして模倣してみることで、驚くほど効率的に学ぶことができます。
で、自分はというと、作りたいものを手当たり次第、自分の感覚で作っていました。アカウント設計とかありません。
おかげで遠回りをしました。

なぜ「コピー」が有効なのか?3つのメリット
「コピー」をおすすめする理由は、以下の3つのメリットがあるからです。
最速で技術を習得できる: 優れた作品の構成や技術を分析・模倣することで、遠回りせずに基礎を習得できます。
成功法則を学べる: なぜその動画が評価されているのか?構成、編集、効果音…要素ごとに分析することで、成功の秘訣が見えてきます。
モチベーション維持: 模倣でも、再生数が増えれば嬉しいもの。モチベーションを維持しながら、制作を継続できます。オリジナルで再生されないとダメージ大きいです!(もちろん喜びもひとしお)
ただし「コピー」だけで終わってはいけない理由
ただし、注意して欲しいのは、 「コピー」はあくまでもスタートライン ということ。
闇雲に模倣を続けるだけでは、ただの「二番煎じ」で終わってしまいます。
「コピー」を通して技術を磨いたら、
次は 「自分らしさ」 を追求し100万再生への道に進みましょう。
模倣から「オリジナル」を生み出すために
では、模倣から脱却し、「オリジナル」を生み出すにはどうすれば良いのでしょうか?
それは、 「なぜその動画を作りたいのか?」 という原点に立ち返ることです。模倣をして身につけた技術や経験を次は、
誰に、どんなメッセージを届けたいのか?
どんな感情を揺さぶりたいのか?
自分だからこそ表現できることは何か?
これらの問いと向き合い、昇華することで、模倣を超えたあなたの表現したいことが乗り移った”オリジナリティ”が生まれてくるはずです。模倣なきオリジナリティは型なし。型破り?どっちでもいいですけど。
歓喜の300万再生、そして悲劇の模倣。この経験を通して伝えたいこと
300万回再生という成功と、模倣されるという出来事。
この経験を通して、改めて「模倣とオリジナル」の関係について深く考えるようになりました。
そして、最終的にたどり着いたのは、 「模倣は、新たな創作を刺激する、共創のプロセス」 ではないかという考えです。
もちろん、ルールやマナーを守ること、そしてオリジナルへのリスペクトを忘れないことは大前提です。
しかし、そうした前提を守った上で、模倣とオリジナルが刺激し合い、新たなエンタメが生まれていくとおもいます。
パクられた直後にこれを書くのが、いいんですよねえ。
うだうだ言わずにどんどんアウトプットしていきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
